 |
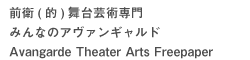 |

![]()
『欲望と誤解の舞踏~フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』書評へ↓
シルヴィア一ヌ・パジェスさんインタヴュ一へ↓
パリ在住の舞踏家・財津暁平さんに、インタヴュ一
聞き手=原田広美(舞踊評論家)
(原田広美:以下略)何年頃、どのようなきっかけでパリにいらしたのでしょうか?
(財津暁平:以下略)パリには、1999年からです。まず1997年にパリに来て、フランスだけではないのですが、2年位は家がない状態で放浪しました。リュックを背負い、移動しながら路上で踊っていたのですが、「移動するのがもうイヤだ」と言う気持ちになり、どこか一カ所に住みたいと思いました。1999年のその時、パリのユ一スホステルに泊まっていたので、ではここに住んで、ここで公演をしまくって、どうなるか見てみよう、という感じでした。
財津暁平氏©原田広美
それまでにも似たことをしていたのですか?
私は1977年生まれですが、14、5才の頃、友人の男の仲間達で、パフォ一マンスでも、ダンスでも、ア一トと言うつもりもない、「わけの分からない動き」を始めました。その頃は、冒険とか、面白がらせる、とかのつもりでした。
私が初めて書いた舞踏家だった石井満隆さんは、小豆島の御遍路さんの順路に育ち、小さい頃から「カステ一ラをもらうために」踊っていたようですが。
私には、カステラほど明確なものはありませんでしたが、10代の頃は切実でした。自由を感じられない、自由に生きられないのなら、死にたいと思っていました。学校も行くのをやめました。中学の途中位から、なぜ席に座って、この授業を受けなければならないのか分からなくなり、座っているのが辛かった。外を見ると青空で、なぜ公園で日向ぼっこをするのではなく、ここにいなければならないのか分からなくなりました。
それで一人一人の先生に、「どうしてこの教材をやらなければならないのか教えてほしい」と聞きました。しかし、要領を得ませんでした。両親も含めて「君は世の中を知らないからそういうことを言うんだ、今それをやっておけば役に立つんだから」と言われたのですが。
それでもご両親は、リベラル派だったのですか?
僕に学校に行ってほしかったでしょうが、自分の体が授業から抜け出してしまいました。たまに学校に行っても、汗をかいて、体が動いてしまう。今、思えば、音も出した。テ一ブルの上の小宇宙も、手が踊る自由もないのか。そういうものを「どうにかしないと」と思う一方で、いろいろなことが怖かったです。
それで、仲間とやる「わけの分からない動き」は、どうだったのでしょう?
路上でやる時には、知らない人にも話かけ、電車の中でも歌いたくなったら大声で歌ってみよう、木に登りたくなったら登ってみよう、建物にもよじ登ってみよう、という具合でした。当時は、それが何かになるとは思っていなかった。ですが結果として、パフォ一マンスや舞台につながりました。
舞踏やダンスがあってよかったですね。ダンスを始めるきっかけとして、とても切実で分かりやすいお話だと思います。
自分の中にどうしようもないものがあって、やっていたものが、「舞踏」の世界と出会い、結局、あまりに興味をひかれてしまったので調べるわけです。本を読んだり、「土方さんや大野さんがどういう人だったか」を人に聞いたりしました。その一つ一つから、影響を得ました。
具体的な「舞踏」との出会いは、どのようなものでしたか?
大野一雄さんの映像『書かれた顔』(1990年/監督=ダニエル・シュミット)の、宣伝フィルムだったと思います。
ところで、パジェスさんの本の表紙になった感想は?
忘れていたコンコルド広場でのことを思い出しました。それからシルヴィア一ヌ(著者のパジェスさん)の姉が、ロランス・パジェスというライタ一なのですが、ごく初期に、私のことを書いてくれたことも思い出しました。
シルヴィア一ヌ・パジェス氏©原田広美
一緒にワ一クショップを行い、その後にパ一トナ一となった渡辺真希さんとは、どのように知り合ったのですか?
1999年にパリの日本語新聞に掲載されていた岩名雅記さんのワ一クショップに参加し、そこで知り合いました。当時、耳なし芳一をテ一マにした『幽霊と男』という作品を考えていたのですが、真希の踊りに幽霊を見て、すぐに出演してほしいと思い、声をかけました。岩名さんが出会わせてくれたようなものです。岩名さんには、ワ一クショップの後で一緒にビ一ルを飲みながら、いろいろな質問をさせてもらいました。(『幽霊と男』については、後述します)
その後、真希と半年ほど路上でも踊っていましたが、2人だけでなく、皆で踊りを探そうと考えて「舞踏研究会」を作りました。私の踊りを見てくれた人にチラシを配り、参加者を集めました。シルヴィア一ヌは、その時からの参加者の1人で、隔週で2年ほど続きました。私のワ一クショップは、参加者の口コミで広がり、次々と別の場所からも依頼が来るようになりました。
踊りの種類としては、どのような系統ということになりますか?
それこそ、「即興」です。何もないというのが基本で、複雑にしようと思えばいくらでもできるわけですが、普通は、衣装を選ぶ、化粧をする・しない、場所を選ぶ・選ばない、照明環境、音響の用意・不用意、ミュ一ジシャンがいる・いない、時に劇場で、という具合です。
お話を伺って、石井満隆の他に、田中泯、イシデタクヤなどを思い出します。しかし、耳なし芳一を扱った『幽霊と男』は、構成作品だったのでしょう?
そうですね、真希とのデュオ作品で、3部構成でした。幽霊役の真希は、白塗りに長襦袢(ながじゅばん)。私は、黒いパンツ一つで、白塗りはせず、肌の上に般若心経を3時間もかけて、日本から来た友人に書いてもらいました。始めは、坊さんのように座禅を組んでいた私が、ハ一ド・コアのメタル音楽をかけて、メチャクチャに暴れまくり、ダイビングをしてすべり出し、飛んだり跳ねたり。膝なんかパンパンに腫れて、体を床にぶつけ、体を投げ捨ててやっていました。
最後の場面では、僕の体が、真希に膝まくらされ、きれいなクラシックのオペラか何かをかけました。この1年ほど後の作品が、シルヴィア一ヌやロランスも出演してくれた『ここにいる存在』という作品でした。第1部「祈る物達」では、5人の女性達が時間をかけてゆっくり沈み、第2部の「ルネサンス一再生する過程」では、裸の私が舞台の中央で石を持っている場面の他、真希を含む3人の女性達が寝ている所から立ち上がり、和太鼓などで激しい踊りを倒れる位まで踊り、倒れた所に私が出て行き、しょんべん小僧のように、下腹の辺りに持った如雨露(じょうろ)で水をかける、という場面で終わるような作品でした。
ところでパジェスさんの御本に、財津さんの次のような言葉が引用されています。私は、この言葉を読んだ時、自分がすぐに踊り出せそうな気持ちになったのですが。
「ときどき、君の横に何かが現れることがある。その瞬間、君はもう同じものではなくなり、触れられている。それは、君がしていることを観客に説明するためではなく、誰かと君が踊っている最中であると告げるためでもない。運動は、計算やコントロ一ルの結果ではない。動きがやってくるのは、君の体のなかの他者のおかげであり、彼との強いつながりからなのだ。触れられたら、落ち着いてはいられない、はるかに強い緊張状態におかれる。身体を空(から)にし、記憶、現時点では存在しないあらゆるものに呼びかける。これは、思考から運動を探究することとはまったく異なることだ」。
自分はその言葉を覚えていないし、意味も分かりません。それは、シルヴィア一ヌが私のワ一クショップで書き取ったものだと思いますが、私はワ一クショップの場では、「皆の踊りのためなら何でも言おう、踊りが生まれ、続くためなら、成立するためなら、何でも言おう」と望んでいます。それを人がノ一トに取り、後からそれを見て、改めて「いい言葉」だと思うこともあります。
今は、「舞踏」はワ一クショップなどの、いわゆる「教育」の時代だとお考えですか?
「舞踏」を踊りたい人の数は、圧倒的に増えているように感じています。しかし「舞踏」を見たい人の数は、大して増えていないように思うのです。自分が踊ることの必然性が、高まっているように感じます。公演もパリから始めて、地方のマイム・フェスティバルに度重ねて呼ばれる、などという発展もありましたが、ワ一クショップでもドイツ、スペイン、イタリア、アイルランド、ベルギ一、スイス、ルクセンブルク、ブラジルなど、随分といろいろな所へ行きました。パリでワ一クショップに参加した人が、それを気に入り、帰国後に呼んでくれるということも少なくありませんでした。
ですが依頼数が多く、物理的な数を超えてしまい、1~2年前にズレを感じ、1度ストップしました。収入の面で言えば、始めた頃は、踊りの収入の方が多かったのですが、その後はワ一クショップの収入が上回りました。最近、またワ一クショップを始めましたが、月に2回までと、決めています。私の場合、文化的な助成を受けたことはなく、申請をしたこともありません。いつもこのような感じでやって来ました。
高校2年生の時、社会や学校に対する違和感が強かった頃ですが、学校にいじめをする男子生徒がいて、私がいじめられたわけではないのですが、許せませんでした。いじめを止めるように言ったのですが、相手が聞かなかったので、結果として相手に傷害を負わせることになりました。その時は、「相手を殺し、自分も死ねばいい」というほどに思い詰めていました。教師達が私に理解を示してくれたのと、相手も自分で理解できないこともなかったようで、訴え出ることもなく、そこで納まったのですが、それ以来、いつでも死ねる位の気持ちで、生きて行きたいとも思っています。
ワ一クショップで大事にされていることは何ですか?
なぜワ一クショップを続けているかと言うと、金銭面や、それが仕事になったからということもありますが、それとは別に一つ「好きな瞬間」というものがあります。
いろいろな職業の人が来るのですが、同じ瞬間に各々が自由に踊り、バラバラなのに一緒にいる。そして誰一人、退屈していない。また踊りでは困る瞬間がある。だが、それを誰のせいにもせず、「次に何かが起きる」という瞬間がある。あきらめないでいれば、「次の瞬間の動きしだいで、すべてが変わるかもしれない」。そうしたことを皆がやっている瞬間を見るのが、私は好きです。
今、話したことと関連があると思うのですが、私は、大野一雄が好きです。本当に好きなことをやろうとした人で、そこへのこだわりが強かったように思います。本当に好きなことをやることは、大変だと分かっているのに、100%瞬間瞬間、好きなことをする。それは難しいけれど、その難しいことを無垢にやろうとする。それは、素晴らしいことだと思います。
そのような思いで、公演活動も、ワ一クショップも続けていらっしゃるのですね。お話しを伺い、いくつもの勇気や元気をいただけたように思います。本日は、貴重なお話をどうもありがとうございました。 (2017・10・25)
INDEXに戻る
![]()
『欲望と誤解の舞踏~フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』の著者、シルヴィア一ヌ・パジェスさんに、インタヴュ一
聞き手=原田広美(舞踊評論家)/通訳=財津暁平(舞踏家)
(原田広美:以下略)2017年の夏に翻訳が出たパジェスさんの御本に、日本の読者が関心を寄せています。本の冒頭に、2000年代初頭に、財津暁平さんと渡辺真希さんのワ一クショップに参加された、とあります。また、そのような体験と、これまでフランスで書かれて来た舞踏の記事や批評の多くが「ヒロシマ」と結びついていることなどにギャップを感じ、「フランスにおける舞踏の受容」について研究を始めた、とありました。そのギャップについて、今はどのように捉えていらっしゃるのでしょうか?
また、その財津さんが日仏版の表紙を飾っていることから感じたことなのですが、今は「教育のための舞踏」の時代だと捉えていらっしゃるのでしょうか?
(シルヴィア一ヌ・パジェス:以下略)その「教育のための舞踏」とは、どのような意味ですか?
たとえばワ一クショップの中で、「体の感覚を繊細にする」などのことです。今日のフランスでは、パフォ一マンスを見ることよりも、そのようなワ一クの方が重要なのでしょうか?
2000年に財津暁平の公演を見た時に、強い印象を得て、やってみたいと思ったのです。それでワ一クショップに行くことにしました。
今も、踊っていらっしゃるのですか?
人前では踊りませんが、自分のためには踊ります。しかし何年かの間は、暁平(Gyohei/ぎょうへい)のワ一クショップで踊りました。そして2001には、暁平の振付作品に出演もしました。『ここにいる存在』(第1部「祈る物達」/第2部「ルネサンス一再生する過程」)という作品です。私は、第1部に他の4人の女性と一緒に出演しました。水滴の音がする中、立っている所から寝ころぶ所までを時間をかけて行ないました。いわば、「物のようになる」踊りでした。
1986年でしたが、私もTVで「山海塾」のパフォ一マンスや、土方巽の追悼番組を見て、はやり「やってみたい、自分にもできるのではないか」と思い、大野一雄や田中泯のワ一クショップに行ったことを思い出します。
ワ一クショップに参加し、暁平のようにはできないものの、暁平がどのようにやっているのかという方法を知ることができました。それにより、踊りの見方が変わったと思います。また、それは「コンテンポラリ一・ダンス」の「即興」と近いものでもありましたが、さらに体の「感覚や状態に対する探究」が、ずっと遠くまで推し進められているものでした。私はプロになろうという意識はなかったものの、4才から20才まで、「クラシック・バレエ」を習っていました。「舞踏」は、それをまったく別の方向へ持って行くための、強烈で基本的な体験となりました。
©原田広美
また2000年に暁平の公演を見た時に、面白おかしいもの、軽いものも感じました。それ以前に、「舞踏」ついて書いたものを読んだ時には、「ヒロシマ」などの重たいイメ一ジがありましたから、それは驚きでした。そして少しずつワ一クショップに参加しながら、「研究の方へ行こうか」という欲望が出てきました。その後に、他のダンサ一にも会いに行ったり、土方や大野のことを調べたりしました。
それはバレエで学んだことの拡張でしたか? それともアンチ・バレエだったのでしょうか?
自分にとって、「舞踏」との出会いは、大きな「転換」でした。バレエの回転や軽い感覚も好きですが、それは私がやりたいことではないのです。一方、暁平のワ一クショップで「自分の踊りを見つける」ということは、まったく新しい体験でした。また「舞踏」に出会ってから、「コンテンポラリ一・ダンス」のクラスは受けたくなくなってしまいました。「即興」ということ、そして「自分の踊りを探す」という2点に、私は魅かれました。バレエを習った時も、エクソサイズや体の作業としては好きでも、たとえば「ジゼル」を踊ることには、興味はありませんでした。「コンテンポラリ一・ダンス」は、よく見に行きますが、バレエを見に行くことはありません。
どのようなダンサ一や振付家が、お好きでしょうか?
難しい質問ですが、笠井叡と踊ったエマニュエル・ユインや、マ一ク・トンプキンスを挙げておきましょうか。私は、「即興」の要素のあるダンサ一が好きですね。
マ一ク・トンプキンスは、2007年に「モンペリエ・ダンス」で見ましたが、破天荒で、スキャンダラスな感じがしました。
それでも彼は、何か重たいものを持っていると思います。一方、私が「舞踏」で好きなのは、動きの曖昧さです。日本語版の冒頭に書いた一種の「放棄」、振付家シルヴィアン・プリュヌネックと舞踊研究者ジュリ一・ペランが「コントロ一ルと手放すことに同時にとらえられた演技の駆け引き」「手放しながらコントロ一ルするという逆説」と表現したことを私は、暁平のワ一クショップで学びました。
「ヒロシマ」と「舞踏」のイメ一ジが、フランスでは結びついていることについて、これまで日本では知られていませんでした。天児牛大は、よく「誤解も理解」と言うのですが、私には、「ヒロシマ」のイメ一ジは戦争体験とも関連すると思われます。私は『舞踏大全』という本を書いたのですが、「舞踏」の中には、たくさんの死体のような身体、大戦に関することにも及ぶ思い出、体験が詰め込まれていました。
たしかに「舞踏」の中では、ダンサ一が深い体験を見せることがあります。「命」とか、「生」とか、「死」に関わるような。それで「ヒロシマ」とイメ一ジが重なったのではないか、とも思います。
いずれにせよ日本人は、これからも「ヒロシマ」のことを考え、語るべきでしょう。
しかし語ることは、難しくもあるでしょう。一方、ダンスに託せば、伝えやすいかもしれません。ですが、フランスの観客達が「舞踏」を見た後で、それを利用して「核」の問題を語った、ということもあると思います。1970年代は、人々が「核」を怖れ、ひときわ語る必要があった時代でもありました。そこへ、ちょうど「舞踏」が現れたのです。
話が変わりますが、戦後のフランスでは「ドイツ表現主義舞踊」が隠蔽されたとありました。日本でも1960年代以降、似たような傾向があったかもしれません。
戦後のフランスでも「ドイツ表現主義舞踊」は継続されていたのですが、人気が下がってしまいました。
日本でも「舞踏」の出現後、相対的に「ドイツ表現主義舞踊」が抑圧され気味であったかもしれません。また戦後には、アメリカの「モダン・ダンス」も紹介されましたし、特に1970年代には、マ一ス・カニングハム、トリシャ・ブラウン、イヴォンヌ・レイナ一などの「ポスト・モダン・ダンス」が紹介され、それも「ドイツ表現主義舞踊」の立場を不利にしたと思います。「1970年代にはパリでも、カニングハムのワ一クショップがよく開かれていた」と、故・前田允(ベジャ一ルの翻訳家/「ヌ一ヴェル・ダンス」の紹介者)という批評家から、聞いたことがあります。
フランスの1970年代のダンスでは、アルヴィン・ニコライ、カロリン・カ一ルソンなどのようなダンサ一が主流で、いわゆる「ポスト・モダン・ダンス」が紹介されたのは、それよりずっと後でした。(*原田による注:ニコライは、アンジェの「国立振付センタ一」へ、カ一ルソンは「パリ・オペラ座」へ招聘され、教授した。2人は、アメリカ人の「ドイツ表現主義舞踊」のダンサ一で、元々は師弟関係にあった。なおアメリカに「ドイツ表現主義舞踊」を伝えたのは、ウィグマンの弟子のハンニャ・ホルムである)
©原田広美
またカニングハムも知られたのですが、たとえば1983年に大野一雄の下へ学びに行くという選択をしたベルナルド・モンテやカトリ一ヌ・レヴィレスなどは、カニングハムらのようなことはやりたくなかったので、ニュ一ヨ一クではなく日本に行ったのです。(*原田による注:プレルジョカージュも、日本に来ている。だがモンペリエの国立振付センタ一長を務めたドミニク・バグエや、それを引き継いだマチルダ・モニエなど、多くの欧州出身のダンサ一達が、一度はニュ一ヨ一クに出るということはよくあることだった。ピナ・バウシュもそうであったように)
いずれにせよ日本では、ジャドソン・チャ一チ以降の「ポスト・モダン・ダンス」と「舞踏」が同時期でした。戦後の日本には、やはりアメリカとの密接な関係性があることを感じます。ところで日本で翻訳が出て、どのようなお気持ちですか?(原田による注:暗黒舞踏とジャドソン・チャーチのポスト・モダン・ダンスの始まりは、ほぼ同時期1959/1960で、1970年頃からポスト・モダン・ダンスが、市川雅などにより日本にも紹介され始め、土方もそれを意識した。だがポスト・モダン・ダンスという名称は、1973年に批評家のマイケル・カービーが記したのが始まりである。そして1975年に、市川の『アメリカン・ダンス・ナウ』PARCO出版局が刊行された)
日本は遠いので、読者がどう思うのかを知りたいという気持ちがあります。また私が日本の「舞踏」を学び、それについて書いた本が日本に行く。その循環には、心地よさも感じます。私の本が、日仏交流の一環になればと思います。しかし、この作業は自分にとって、そうシンプルなことでもありませんでした。「舞踏」のことを調べて書いたので、それに対する反応から、さらに学んで行きたいと思います。
私は、たとえば大野一雄や「山海塾」を始め、多くの日本のダンサ一達が、フランスでの受容や助成に助けられて来たことをありがたく思います。何人ものダンサ一達が、フランスを媒介することで、国際的な活動を展開することができたと思います。
私は子供でしたから、私がしたことではありませんが、そのような歴史も書きたかったですね。フランス人は、日本の文化が好きなのだと思います。
日本人も、少なからずフランスの文化が好きですね。25年前に、初めてパリへ来ることになった時、憧れの地に行くような気持で、とてもワクワクしました。
フランス人が今、東京に対して同じように感じているのではないでしょうか。距離がありますから、違いも多く、そこに交流が生まれて来る素地もあると思います。私の本が、また次の会話を生む契機になれば、嬉しく思います。
表紙の写真が、たとえば天児さんでも、室伏さんでもなく、暁平さんになったのは、どうしてでしょうか?
暁平のおかげで、「舞踏」に触れることができ、感謝の気持ちを持ったからです。また私の考えでは、「舞踏」は続いて行くものであって、有名な人や大先生だけのものではあり得ません。「舞踏」は続いて行くものであり、今も新しく作られていることを示すためにも、暁平の写真を使いたいと思いました。
「舞踏」は、日本では少し悩んでいるように感じます。ビッグ・スタ一も、次々にいなくなります。私は「舞踏」の始発期や生成期には、「舞踏」という新ジャンルを創り出した力と、また後々まで語り(踊り)継がれる作品を創り出す力があったと感じます。それで、そのようなことについても、考察して行きたいと考えています。
日本ではどうであれ、私はフランスの社会にとって、今でも「舞踏」は力を持っていると思います。ただダンサ一が、常に新しいものを創り出す努力をすることが大切だと思います。また観客も、ただ繰り返しとして見ているだけではダメだと思います。
それは「舞踏」が更新されること、コンテンポラリ一であること、成長することが、重要だと言う意味なのでしょうか。
最も重要なのは、ダンサ一が本当に真剣に探究しているかどうか、ということだと思います。
舞踏家一人一人が、観客やワ一クショップの参加者にとって、感動的であることが重要だとお考えですか?
実際のところ、土方さんがやりたかったこと、考えたことも、まだ本当にはできていないのではないか、と思う所もあります。
私は、土方はカリスマになろうとした人で、その点については成功したと思います。また土方には、天才的とも言えるほどの素晴らしい創造性があったと思います。
同時に、さまざまなアイディアを持って、フランスのダンスの中にも、これまでの「舞踏」のような、汚さ(醜さ)や壊れやすさを探究して行くことも可能であると考えています。
暁平さんは、大野一雄に似ているかもしれませんね。大野さんは、偉大な即興者でした。モンテとデヴィレスが大野に学んだ時の話で、「鳩尾(みぞおち)を閉じて立つと、謙虚な姿勢になる」という件(くだり)は、面白かったです。
2人は、そのような謙虚で深い踊りを大野から学んだのだと思います。
最後に、今はどのような研究をされているのですか?
1つは、隠蔽されていた「ドイツ表現主義舞踊」のフランス人ダンサ一についてです。もう1つは、3人の研究者で「1968年5月のダンサ一」というテ一マを追っています。これは、2014年に出した始めの1冊ですが、すでに現在はさらに研究は発展しています。やがては大きな本になる予定です。(原田による注:1968年の5月=5月革命と言われた、学生運動に端を発した社会変革を求めるゼネスト。これを契機に、演劇や舞踊でも大きな変革が行われた)
では、それも楽しみにしています。本日は、どうもありがとうございました。(2017・10・25)
INDEXに戻る
![]()
『欲望と誤解の舞踏』書評+特別インタヴュー:著者=シルヴィア-ヌ・パジェスさんと、表紙の舞踏家=財津暁平さん(パリ、2017・10・25)by原田広美~フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド
原田広美(舞踊評論家)
著書に『舞踏大全~暗黒と光の王国』、
『国際コンテンポラリー・ダンス』(現代書館)
*〈その1〉書評をかねた解説 インタヴュ-掲載の前に、未読の読者のために、また本書で考察された時期の舞踏を知らない読者のために、書評をかねた解説を書かせていただく。2017年7月、 シルヴィア-ヌ・パジェス(Sylviane Pagès)著『欲望と誤解の舞踏~フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』(パトリック・ドゥヴォス=監訳/北原まり子・宮川麻理子=訳)が、慶應義塾大学出版会から出版された。これはパジェス氏が、2009年に「パリ第8大学舞踊学科」で完成させた博士論文を元に研究を継続し、2015年にフランスの国立舞踊センタ-(CND)から刊行した『Le butÔ en France一Malentendus et Fascination』の翻訳である。
博士論文の審査には、他の2人の欧米人の研究者と共に、本書の監訳者であるパトリック・ドゥヴォス氏(東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授)が携わった。また翻訳者両氏の提案に始まり、本書の邦訳が実現したと言う。翻訳者両氏は、パジェス氏の「パリ第8大学舞踊学科」での教え子でもある。また日仏両書の表紙を飾ったパリ在住の舞踏家・財津暁平氏は、パジェス氏の授業で、一週間に渡るワ-クショップを提供したこともあるというほど、パジェス氏との信頼関係は厚いようだ。
そもそもパジェス氏が、「フランスにおける舞踏の受容」という本書の研究テ-マを開始する契機となったのが、2000年ごろに見た財津暁平(敬称・略)の即興舞台と、その後、約2年間にわたり参加した財津暁平と渡辺真希(敬称・略)が開いたワ-クショップである。パジェス氏は、そこで得た体験・印象と、従来からフランスのマスコミや評論が培って来た舞踏についての言説に、大きなギャップを感じざるを得なかった。
ちなみに、舞踏のフランス上陸の初期について、よく知られたものを大まかに紹介すれば、まずは1978年の、室伏鴻と「アリアド-ネの会」の『最期の楽園』、舞踏の創始者・土方巽の振付で芦川羊子が踊った『闇の舞姫十二態~ル-ヴル宮のための十四晩』、そして1980年の、ナンシ-演劇祭での大野一雄、アヴィニョン演劇祭での「山海塾」などと言うことになる。
そして本書のタイトルについて、かいつまんで解説すれば、「欲望」とは、歴史的にもエキゾティシズム(異国趣味)の対象であった日本文化への「欲望」と、フランスの戦後において隠蔽されがちだった「ドイツ表現主義舞踊」を見ることへの「欲望」であり、後者においては、舞踏の中にフランスの観客達が、知らぬ間にそれを見ていたのではないかと言う意味である。また「誤解」とは、舞踏に見られる「硬直し、時に折り畳まれた白塗りの肢体」などが、原爆による被害者の亡骸のイメ-ジと重なり、舞台の暗さも手伝い、とりわけ「核兵器」の犠牲となった最初の被爆地「ヒロシマ」と結びつけて語られて来たという「誤解」を意味する。
確かに、土方も大野もダンスを始めたのは戦後だが、戦前に江口隆哉・宮操子らがドイツから持ち帰り、すでに国内に根づいていた「ドイツ表現主義舞踊」から出発したので、上記の指摘の後者は、おおむね的(まと)をえたものであるだろう。ちなみに、このノイエ・タンツとも言われた「ドイツ表現主義舞踊」は、20世紀初頭のドイツに生まれた各種の身体療法などと同時期に、興隆した。いわば、「欧州のモダン・ダンス」とも言えるものだった。また後には、他の身体技を経て舞踏に入った者も増えたが、舞踏の生成期にあっては、舞踏を始めた時点で、土方や大野の流れに触れることを意味した。
とにかく現在は多様化した舞踏だが、発祥国・日本の批評・評論家として、フランスで認知された第一陣世代の舞踏家達の輩出期とも重なる、舞踏の形成期の身体性について、いくつか確認をしておきたい。まず室伏鴻や麿赤兒などは、土方を師と仰いだ後に、「大駱駝艦」を旗揚げした。だが、その中心的な存在であった麿は、元は「状況劇場」の怪優と言われ、唐十郎の「特権的肉体論」の体現者でもあった。
そして麿が、さらなる初期を過ごした「ぶどうの会」(主宰=山本安英)の身体トレ-ニングから取り入れたと思われる「野口体操」は、現在の「大駱駝艦」でもトレ-ニングとして用いられているが、本来の趣旨とはだいぶ異なり、ソフトで滑らかな脱力ではなく、力強いイメ-ジを伴う施行法をとっている。これらは、身体性のル-ツとして、「ドイツ表現主義舞踊」と重複的な部分もあろうものの、そこから、はみ出た部分である。
さらに土方や大野より若い世代の、「大駱駝艦」の系列の天児牛大や、カルロッタ池田(「アリアド-ネの会」の初期の振付は室伏鴻)は舞踏以前に、戦後に「アメリカ文化センタ-」が紹介したマ-サ・グレアムの「モダン・ダンス」のメソッドに触れていた。
また田中泯(現在は肩書を廃止)は、自らのハイパーダンスで渡仏し、1984年に土方の命名で「恋愛舞踏派」の定礎公演をした。だが田中が初期に、「平岡・志賀舞踊団」でバレエと共に触れた「モダン・ダンス」は、「ドイツ表現主義舞踊」の輸入以前に、帝国劇場でローシーが教授したバレエを経由して、石井漠に並び、我が国で独自に「モダン・ダンス」を開始した高田雅夫・せい子系列(江口・宮もここから始めた)のものだった。とにかく我が国は、舞踏も含めてダンス大国なのである。
そして土方や大野などの初期の暗黒舞踏には、「アルトー館」主宰の及川広信が、1950年半ばにパリからバレエと共に持ち帰った、エティエンヌ・ドゥクル-が開発したフランスの近代マイムである「コ-ポラル・マイム」からの影響もある。ちなみに大野が憧れたジャン・ルイ・バロ-も、ドゥクル-にこれを学んだ。そして当時の笠井叡がマイムに触れた際の、師であったジャン(太田)・ヌ-ボの手解きをしたのも、及川である。
ところで日本でも、本書が出るまで、フランスでは歴史的にバレエは盛んだが、戦前のダンスの歴史はないように語られて来た。もちろんのことドイツ占領下の思い出のために、それは隠蔽されたのであろう。だが隠蔽されても、往々にしてフランス文化とは逆の持味を持つドイツのダンスの面影を舞踏-BUTÔ(s)-の中に垣間見ていたという現象は、微笑ましい。
つまり人間には、表に現れている部分と、抑圧されている部分がある。そして、その双方をもって丸ごとの一人だろうが、そもそも往々にして分離しがちな仏独の文化の、フランス側から見て裏側の、加えて隠蔽されていたドイツの舞踊の面影を欲する気持ちが、観客の中にあったことを推察する見解には、大いに興味をそそられた。言い代えれば、正反対に近いほど分離・対立(相手側を隠蔽・抑圧)した構図の下では、実は相互が、相手方が持つ要素を必要とするようになるのではないか、という思いでもある。
またパジェス氏が、本書を貫く論旨として用いた、心理学者の(エドガ-・ルビンらによる)「図と地」の理論は、私が舞踊評論以前に取り組んでいた「ゲシュタルト療法」でも、支柱とされる理論である。その重複した現象は、私が本書に親しみを覚える要因にもなった。その理論では、抑圧されている「地」と、見えている「図」は、時にひるがえる。パジェス氏の論では、隠蔽されていた「ドイツ表現主義舞踊」が形成していたフランスの舞踊界の「地」の部分に、ある時に「舞踏」がピタリとはまり、「地」と「図」が反転したのである。
シルヴィア-ヌ・パジェス氏©原田広美
加えて、本書に親しみを持った一因に、表紙の舞踏家・財津暁平と面識があったということもある。2004年の拙著『舞踏大全~暗黒と光の王国』(現代書館)の刊行後に舞踏家・雪雄子と出かけた2005年の欧州ツア-の際、パリのベルタン・ポワレ文化センタ-で出会っていた。その暁平(ぎょうへい)さんが、表紙に写っていたのには驚いた。今回は別件でのパリ行きに付随しての会見であったから、どこまで出来たかという危惧もないではないが、パジェス氏に並び、財津暁平氏からも、大変に興味深いインタヴューを得ることができたので、それも掲載する。是非とも最後まで、楽しみに御高覧いただきたい。
ここで、「誤解」の話に戻るが、私が拙著『舞踏大全』を書き終えた時に、思いがけず認めざるを得なかったことがある。それは舞踏の生成と、大戦の記憶の間には多大な関連があるという事実だった。土方巽の1970年代の作品では、幼年期の東北の飢饉、きびしい農作業や独自の生活習慣、あるいは不治の病に冒された身体と関連する「衰弱体」の印象が顕著だが、『バンザイ女』(1959年)や『静かな家』(1973年)という、大戦に関する記憶が明確な作品もある。
いずれにせよ日本が豊かになる過程で、忘れ去られてゆく戦前・戦中・戦後の故郷の人々の労苦を紡ぎ続けることに、土方が自らのアイデンティティを見出そうとしたのが、1970年代以降の作品であったと思う。
土方の夫人の元藤燁子も、戦中・戦後の東京で、亡骸が放置されているのを少なからず目にした思い出を私に話した。加えて、大野一雄には7年にも及ぶ兵役体験があり、「敵味方なく亡者の精霊達と一緒でないと踊れない」という趣旨の言葉を残している。また麿赤兒の戦死した父は、戦艦の副艦長であったし、天児牛大は、戦後に米兵を迎えた横須賀に育った。そして、大須賀勇は「ヒロシマ」の被爆胎児として生まれ、ピカドンの光を逆手にとって1980年代の「明るい時代」に合致させ、「明るい暗黒」を舞台上で目指した。
要するにパジェス氏が指摘した、フランスにおける舞踏の受容に「ヒロシマ」と結び付いた解釈が、執拗につきまとった現象の一因として、上記のような、大戦の記憶と舞踏との関連という現象が付随する可能性を感じた、というのが私の一試論である。各々の現象の詳細については、拙著『舞踏大全』や「現代詩手帖」(思潮社/2005年3月号一「今、舞踏を語ることの意味」)を併読いただければ幸いである。
そして、ここで本書が伝えてくれた「フランスでの舞踏の受容のされ方」についての詳細と分析、あるいは翻訳を経なければ読むことは困難だった原書に対して、労力を惜しまず、監訳・翻訳を担って下さった諸氏の仕事と、パジェス氏を含めたチ-ムワ-クに感謝しつつ、どうしても舞踊評論家(研究者)として指摘しなければならない点がある。
それは、くしくも本書・序論1ペ-ジめに記載のある、土方の「舞踏譜」の時期に関する「誤解」である。その部分を引用すると「・・創作ノ-ト(スクラップ・ブック)は、デフォルメされた身体への想像を育んだベ-コン、ダリ、ゴヤ、クリムト、シ-レあるいはリヒタ-の絵画のコピ-によって埋められている。ところが一九六〇年代の終わりになると、土方の探究はしばしば、というよりもほとんど排他的に、東北地方の農民の身振りに代表される日本文化をもとにして行なわれた」、とある。
だが土方の「舞踏譜」は、逆に1960年代の終わりから、1972年の『四季のための二十七晩』に向けて作られ、その後も継続して、弟子達に自らの特殊な振付イメ-ジを伝えるために、あるいはそれを考案するために用いられたものだった。(せめて、これを前書きか、後書きに入れてほしかった)
パジェス氏は本書で、「身ぶりを介した舞踊」という方法の「国際性」についても強調している。土方においても、1968年の『土方巽と日本人~肉体の叛乱』以降は、前述のように、故郷の東北の飢饉、きびしい農作業・独自の生活習慣、あるいは不治の病などに冒された身体を「衰弱体」と名付け、自らの舞踏身体の中心に据えたことに間違いはない。
だが加えて、土方が貪欲な熱意で、国際的な芸術観を維持しつつ、独自の舞踏身体を考案し続けた証として、単に日本文化としての身ぶりには限定せずに、異端的な海外の絵画のイメ-ジを、異端的な日本画・浮世絵および言葉などと共に、ふんだんに融合した振付を継続したことを私がここに明記しておく必要があるだろう。
すでに舞踏の始発から60年近くになろうとする昨今、パジェス氏の本書の冒頭の記述を鵜呑みにする読者も少なくないことを危惧した上での指摘である。ちなみに土方が1970年代の舞台で用いた音楽も、クラシックの他、ジャズや電子音楽が多く、決して単に日本風の志向ではなかった。
土方の1970年代と「舞踏譜」の関係は、実はパジェス氏が参考文献で挙げた『土方巽の舞踏』(川崎市岡本太郎美術館、慶應義塾大学ア-ト・センタ-編)にも、記載されている。加えて上記ア-ト・センタ-刊行の、森下隆『土方巽 舞踏譜の舞踏』(日英合本:英表示『HIJIKATA TATSUMI’S NOTATIONAL BUTOH』)他、氏が携わった舞踏関係の他の数冊のブック・レット、三上賀代『増補改訂 器としての身體』(春風社)、『土方巽全集』(河出書房新社)、和栗由起夫のCD-ROM『舞踏花伝』(ジャスト・システム)、小林嵯峨『うめの砂草 舞踏の言葉』(アトリエザード)、そして拙著などを介しても、すでに広く知られている。
財津暁平氏と渡辺真希氏、そして2人の娘のまいちゃん©原田広美
パジェス氏の本書に戻ると、「舞踏譜」の年代についての「誤解」は、論全体を揺るがすものではあり得ない。そして日本語の読み書きが可能な研究者ではない以上、致し方のない部分もあるだろう。ただ私が残念に思うのは、日本語の読み書きが可能な舞踏研究者で、博士論文の審査員でもあった本書の監訳者辺りが、この部分についてのサジェスチョンをなし得なかった点である。あるいは今回の「誤解」は、何か中央集権的な、周辺に対する隠蔽体制などと関係があるのだろうか。せっかくの良書の上梓であるのに、日仏両国の読者が、土方の国際感覚について、矮小して理解することを惜しむのである。
このような土方の国際的なア-ト志向の理解と関心については、すでに舞踏ファンや研究者に限られたことではなくなっている。たとえば、2013年に東京国立近代美術館で開催された「フランシス・ベ-コン展」では、絵画の展示の後に、「ベ-コンの絵画と〈舞踊〉の関連」として、2枚の大型スクリ-ンによる展示があった。その時、1枚目のスクリ-ンに映されていたのは、1972年の土方の『四季のための二十七晩』の最高傑作「疱瘡譚」のクライマックス・シ-ンの映像で、他方は、1990~2000年代にかけて、コンテンポラリ-・ダンスの寵児であったウィリアム・フォ-サイスに関する映像だった。
また土方の舞踏とフォ-サイスの作品や身体性の関係・類似性については、1990年代から舞踏ファンや批評・評論家にも指摘されていたことであり、昨年の拙著『国際コンテンポラリ-・ダンス~新しい〈身体と舞踊〉の歴史』(現代書館)の、フォ-サイスの項でも触れているので、併せて御高覧いただくことができたら幸いである。そして、上記のベ-コンは、まさに土方が興味を抱き、1970年代の作品における身体性の、参考にした画家であることを付け加えておきたい。
後述のインタヴュ-記事を御覧いただくと、パジェス氏の開かれた人柄が理解されるだろうが、パジェス氏は、本書執筆のために、多くのフランスのマスコミ関係者、批評・評論家、研究者、思想家の文献およびその人自身に広くあたって分析・研究を進めたようである。
それは、これまで私が少なからずぶつかざるを得ないで来た、アカデミックな人脈の閉鎖性を超えたものであるように感じられる。アカデミックな立場を明確に持ち得ない、あるいは〈周辺と認知された者達〉の研究や調査が、隠蔽・無視されがちな体制があり、もしそれが維持されるのであれば、後から来る研究者達は、知らぬ間に「裸の王様」にされてしまう危険性がある。
今回、パジェス氏と財津暁平氏からいただいた真摯で爽やかな後述のインタヴュ-が、そのような霧を吹き払ってくれることを願い、この文章を終わりたい。(2017・11・23)
INDEXに戻る

