 |
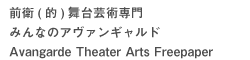 |

![]()
唐十郎の繋ぎ方—『ビンローの封印』『腰巻おぼろ』二つの公演を巡って
石倉和真 演劇研究
劇団唐組『ビンローの封印』
2017年4月28日(金) ~ 30日(日) 会場 南天満公園
2017年5月6日(土) & 7日(日) / 12日(金) ~ 14日(日) / 6月3日(土) & 4日(日) / 9日(金) ~ 11日(日) 会場 新宿・花園神社
2017年5月20日(土) & 21日(日) / 26日(金) ~ 28日(日) 会場 雑司ヶ谷・鬼子母神
2017年6月17日(土) & 18日(日) 会場 長野市城山公園・ふれあい広場
2017年6月23日(土) & 24日(日) 会場 甲府市歴史公園・山手御門前
新宿梁山泊『腰巻おぼろ 妖鯨篇』
2017年6月17日(土) ~ 26日(月) 会場 新宿・花園神社境内 特設紫テント
今年三月に『唐十郎特別講義 演劇・芸術・文学クロストーク』(唐十郎著 西堂行人編 国書刊行会)という本が発売された。これは二◯◯五年、六年当時、近畿大学の客員教授だった唐十郎の授業を活字化して集録したものだ。唐の創作プロセスや「状況劇場」を巡る貴重な証言が、同じく近畿大学教授(当時)で演劇評論家の西堂行人氏のインタビューによって引き出される。詳細な説明はここでは避けるが、唐十郎の脳内に広がる幼少期の原風景から、縦横無尽に展開する創作の秘密を垣間見ることができる内容となっている。
「生きる伝説・唐十郎」は病に倒れた今もなお、現在進行形で語られ続けている存在だ。
今年は本家ともいえる「劇団唐組」が四月末から六月にかけて『ビンローの封印』を二十五年振りに再演して、大阪、東京、長野、山梨を回った。唐と縁のある「新宿梁山泊」も主宰・金守珍の演出で同じく四月末に唐作品『風のほこり』、『紙芝居』を芝居砦・満天星で立て続けに上演した後、六月には新宿・花園神社でテント公演『腰巻おぼろ-妖鯨篇』を上演した。また金守珍といえば、記憶に新しいところでは昨年(二◯一六年)、シアターコクーンで故蜷川幸雄の追悼公演で同じく唐の『ビニールの城』を演出している。
このように現在でも定期的に過去作品の再演が続く唐十郎の「魅力」(魔力と言った方が適切か)とは何なのだろうか。
「状況劇場」が新宿・花園神社で最初のテント公演「腰巻お仙・義理人情いろはにほへと篇」を行ったのは一九六七年(昭和四十二年)。そこから数えて今年はちょうど五十年目の節目の年にあたる。その半世紀の総決算(というと少し大袈裟な気もするが)として、前述の「劇団唐組」の『ビンローの封印』と、「新宿梁山泊」の『腰巻おぼろ』の上演が花園神社で行われたことは感慨深い。
一時の中断はあったとしても、半世紀に渡り「テント」という非日常空間が新宿の真ん中に立ち続けたことの意義は、日本の現代演劇を考える上で重要であろう。安保闘争に揺れた六十年代〜七十年代から、八十年代の大量消費社会とバブル景気、そしてその崩壊を経て、九十年代以降現在まで続く大不景気時代。様々な時代のそれぞれの空気を吸いながら、それでも「テント」は依然そこに立ち続けた。忙しなく変化を続ける社会を底辺から見上げるように。
劇団唐組『ビンローの封印』©唐組
劇団唐組『ビンロー封印』の初演は一九九二年(平成四年)。
その前年の一九九一年に、東シナ海で操業中の日本漁船が外国船に襲撃を受けた実際の事件を元に、唐十郎が独自の解釈を加えて創作した。日本統治時代の台湾、そして今日へと続く尖閣諸島を巡る歴史的問題、そこに偽ブランド業者や、マフィア、カラオケ教室などの現代的要素、果ては実在の哲学者「和辻哲郎」までも登場し、それらがすべて唐式迷宮回路に組み込まれていく。
お馴染みの唐組メンバーに加え、若手俳優も積極的に起用した。中でも唐組初出演の全原徳和は独特の存在感を放ち、舞台に新しい風を吹き込んでいたのが印象的だ。劇団全体に若い力が戻ってきた。
この劇の中でも印象的なのがタイトルにもなった台湾のヤシ科の植物「ビンロー」(檳榔=びんろう)だ。日本では馴染みのない、台湾の嗜好品である檳榔は、石灰を混ぜて噛むと唾液が化学反応を起こして赤く染まる。それを飲まずに吐き出すと鮮血が飛び散ったような跡が残る。そして軽い酩酊と興奮状態が訪れるという。本作ではヒロインの女海賊を演じた赤松由美が檳榔の実を齧り実際に吐き出すが、赤い鮮血のような唾液を吹く彼女の姿は非常に妖艶であり、同時に他者を拒絶するような攻撃的な身体を見せつける。この辺りの人物造形には唐十郎のフェティシズムを感じる。
唐十郎と檳榔といえば、私は一九九六年の映画『海ほおずき』(監督:林海象)を思い出す。この映画で唐は脚本と主演を務めた。そして劇中には檳榔がやはり重要なアイテムの一つとして出てくる。台湾で起きた女子大生失踪事件の謎を追うこの探偵映画には、檳榔の他にも、海上で襲われた元・漁船の無線航海士(原田芳雄が好演)とその手に巻きついたコードという設定など、『ビンローの封印』と共通した要素が多い。またこの映画はほぼ全編台湾で撮影が行われている(『ビンローの封印』の初演時も唐組台湾公演を行っている)。
劇団唐組『ビンローの封印』©唐組
九十年代の唐十郎は台湾海峡や尖閣諸島、そしてその狭間で生きる特定の国家に所属しない海賊のような人間たちなどに関心を寄せていたことが分かる。唐作品には「水」にまつわるイメージが多く登場するが、「水」のイメージが「海」に繋がり、現実の事件を織り込みながら海路で結ばれた東アジアの近代史を巡る物語に展開していったと言える。
唐十郎はこのように独創的なイマジネーションを広げながらも、実在の人物や実際の事件を創作の出発点に使うなど、ある意味では常に時代を意識してきた作家と言える。
私が観劇した回の終演後には唐十郎が自ら舞台に上がり、観客に挨拶をした。その際唐は「久しぶりに久保井のにおいを嗅いだ気がしました」と語った。この発言にはどのような意図があるのだろうか。
久保井研は唐十郎が二◯一二年に病に倒れてから劇団をリードしてきた。現在は役者として舞台に立ち続け、さらに唐に代わり「演出」という重責も担っている。この演出という部分について、おそらく久保井は唐十郎の単なるコピーアンドペーストではなく、独自のアプローチで「久保井色」を出そうとしているのではないだろうか(公演前のインタビューからも久保井は「唐組」作品の選定と演出に当たり「ウェルメイド」を意識しているように思われる)。それを実際の上演から読み取った唐は「久保井のにおい」と表現したともいえる。
あくまで戯曲は戯曲として、演出についてはこれまで唐十郎の元で得た経験を活用しながら、最終的には久保井の解釈に基づいた演出を施していく。もちろん、“本家”「唐組」であればこそ、これまで唐十郎と「劇団唐組」を応援してきた観客のことを意識する必要もあろう。独自の演出、言うなれば唐十郎の演出からの脱却ともなれば、これは劇団としてもリスクも背負うということでもある。おそらく観客の多くは「唐十郎のにおい」を求めて来場している。そこにどのように久保井流の「におい」を加えていくのか。これは今後も続く課題となりそうだが、少なくとも演出家=久保井研の決意のようなものが表れた公演となった。
新宿梁山泊『腰巻おぼろ 妖鯨篇』©大須賀博
水や海のイメージがより鮮明に打ち出されていたのは、同じく新宿・花園神社にて上演された「新宿梁山泊」の『腰巻おぼろ-妖鯨篇』だ。これは一九七五年に「状況劇場」が上野不忍池で上演した伝説的な作品である。そして初演以来再演されてこなかったこの作品を、「新宿梁山泊」は見事に現在に蘇らせた。休憩を挟んで上演時間三時間半に及ぶ大作であるにも関わらず、終始疾走感とエネルギーに溢れ、観客を飽きさせない展開はさすが老練の劇団と言える。そして唐作品の魅力を理解し尽くした演出・金守珍と役者のそれぞれの技が光る。前述の「劇団唐組」が新しい方向性を模索しているなら、こちらは、ある意味正攻法で唐作品にぶつかっていったと言えよう。
ただし、正攻法と見せかけながらも、元々上演時間が五時間を超えたと言われるオリジナルの戯曲から、ディティールを壊さないようにセリフを少しずつ削ったことは今回功を奏したと言える。破天荒なストーリーでありながら、舞台全体のリズムが整っていた。
本作を象徴する仕掛けとして捕鯨船が登場する。ここには一九七◯年代の反捕鯨運動の影響が見られる。一九六◯年代末ごろから国際的な海洋生物資源保護の動きが出始め、一九七二年にはアメリカ合衆国は海洋哺乳類保護法を可決。過激な反捕鯨活動で知られるグリーンピースが初めての大々的な反捕鯨キャンペーンを展開したのもこの作品が上演されたのと同じ一九七五年である。『腰巻おぼろ』はこのような時代を背景として生まれた作品である。前述のように、唐十郎は七十年代においても最新の時事を自作にうまく取り入れながら、作品世界を膨らましていたことが分かる。
新宿梁山泊『腰巻おぼろ 妖鯨篇』©大須賀博
残念ながら私はこの初演については、数点の写真を見た限りであるが、唐十郎が演じた元捕鯨船の船長、千里眼のインパクトは強烈だ。肩をすぼめて目を見開いた異様な立ち姿、クライマックスの立ち回りの舞台写真からは、俳優・唐十郎ここにありという迫力が伝わってくる。今回、その千里眼役を唐十郎の長男である大鶴義丹が務めたことが話題になった。
大鶴義丹は近年「新宿梁山泊」の客演として過去の唐十郎作品の上演に参加していて、直近では『二都物語』、『新・二都物語』でも舞台に立つなど精力的だ。
客席からは大鶴が登場するや否や「義丹!」という声が掛かる。演技も堂々たるもので、父の演じた役を見事に演じてみせたといえるだろう。
また同じく今回客演で、「状況劇場」を代表する俳優の一人だった大久保鷹の「怪演」も健在だった。こちらも四十二年前と全く同じ役を演じたということで話題になった。
女優陣の美しい舞と可動式の舞台美術と映像のコラボレーションも印象的だ。しかし圧巻なのは舞台で惜しみなく本水を使ったラストシーンである。客席まで押し寄せるほどの大量の水、さらに巨大な捕鯨用の銛はクライマックスに相応しい圧倒的なカタルシスをもたらした。
しかしここまで書いて私はふと思う。これではまるで下手な歌舞伎のレビューのようである。
新宿梁山泊『腰巻おぼろ 妖鯨篇』©大須賀博
そもそも大向こうから声がかかる時点で、これは「現代演劇」ではなく、ある種の伝統芸能のようにも思える。私は先ほど大鶴義丹を唐十郎の長男、と書いたがおそらく客席のほとんどがそのことを承知のはずである。そして父と同じ役を演じていることも。最初からそのようなフィルターを通して彼を見ている。カーテンコールでも演出の金守珍が大鶴義丹を紹介する際、「唐十郎のDNAを継ぐ男」と紹介していた。
我々は大鶴義丹の中に、父である唐十郎を見ている。どこかで比較している。
これは何なのだろう。唐十郎は既に「伝統芸能」になってしまったのか。
もちろん大鶴義丹の演技は唐のそれとは全く違う。
しかし、客席にいながら我々はどうしても唐十郎をそこに重ねながら見てしまう。
『特権的肉体論』の「バリッと揃った役者体」と、実際の親子の「血脈」はどのように繋がっていくのだろうか。
前述のように今回の公演では大久保鷹がゲスト出演していたわけだが、初演と同じ役ということもあって、我々は現在の大久保鷹の肉体を通して一九七五年の上野に立っていた大久保鷹をも見ていたと言える。ある瞬間に、四十年前の上演と現在とが二重になって見えてくる。そのような意味では、唐十郎の「血」が流れる大鶴義丹の肉体を、我々はある種のメディアとして捉えて見ている。現在の上演を見ながら過去を、大鶴義丹を見ながら父・唐十郎の演じた一九七五年の上野不忍池の景色を見ているとも言える。そのためには赤の他人よりも「血」を継いだ肉体のほうが現在と過去とを繋ぐ媒介としての強度がより強いと思われる。しかもその肉体には唐十郎だけでなく「おぼろ」を演じた李麗仙の血も流れている。伝統芸能は「血」と「型」で継がれるが、少なくとも「血」の部分については、唐十郎の伝統芸能化が進んでいると言えのかもしれない。
唐十郎の継承を考えた時に、もう一つの問題は、「言葉」、戯曲の問題がある。唐十郎が「状況劇場」の役者に当て書きで書いた作品群、あるいは蜷川幸雄などの演出家に「当てた」書き下ろしの作品をどのように継承していけば良いのだろうか。正に「伝統芸能」よろしく「型」を作れば良いのだろうか。しかし、唐十郎の戯曲を上演するにあたり「型」で演じるのは作品としての強度を弱めてしまう気がしてならない。唐の戯曲は常に新しい演出、そのときの新鮮な「肉体」(年齢が若いという意味ではない。その時代を生々しく生きている身体)で戯曲世界を生き直す必要があるように思う。
それにしても唐式迷宮は複雑である。読み直す度、上演を重ねる度に発見がある。生易しい肉体ではこの戯曲の言葉に蹴散らされてしまう。何故なら前述のように唐十郎は時代と並走し、時代と格闘しながら作品を作ってきた。役者もまた同じように格闘することを求められる。そこにはどのような役者の肉体が必要であろうか。唐十郎の作品に応じられる俳優は今後生まれていくのか。突き詰めると現代日本において「唐十郎(の上演)は可能か」などとも思ってしまう。
しかし、戯曲が書かれた時代の「熱」を内包しているなら、同じような「熱」の中を生きているバリッとした役者の肉体を揃えるのも一つの手だ。例えば、日本という国籍にこだわらず、海外出身の俳優が唐十郎作品を演じるのも面白い。上演場所にしても、政治に対する若者の熱量と発展途中の経済の熱量が現在進行形で高い地域ほど唐十郎の言葉は映えるのではないかと思ってしまう。特に東アジアの経済発展の最中にある地域、新旧の価値観が衝突している場所ほど、唐の世界観が合うのではないだろうか。翻訳の問題はもちろんあるだろうが、唐十郎自身が長年東アジア(時には中東までも)に目を向けながら創作をしてきたのなら、唐十郎は日本だけの作家ではなく、そのような東アジア全体の作家という位置づけがあっても良いのではなかろうか。今後アジアの国々の俳優が集まって唐作品を上演する機会があれば面白いものになるだろうと密かに思ってしまう。
INDEXに戻る
全力!大人の文化祭!!
〜すこやかクラブ『真夏のたちかわ怪奇クラブ』体験談〜
宮川麻理子 ダンス研究家
すこやかクラブ『真夏のたちかわ怪奇クラブ』
2017年7月28日(金) & 29日(土) 会場 たちかわ創造舎
大人の本気は怖い。しかも、くだらないことに全力を傾ける、そのエネルギーが尋常ではないとなると、なおのことである。すこやかクラブ主宰のうえもとしほは、そんな大人の本気を引き出して、廃校となった小学校の校舎を丸ごと使ってこの『真夏のたちかわ怪奇クラブ』というイベントを行なった。廃校というと、打ち捨てられてうらぶれ、いかにも「出そう」なイメージだが、普段はそんなことはない。立川南エリアの文化拠点として注目を集める「たちかわ創造舎」として再活用されており、サイクリング拠点、数多くの映画撮影が行なわれている校舎、スポーツに使用されるグラウンド、誰もが立ち寄れる休憩所などが整備され、また複数の演劇団体やアーティストが拠点として活動を行っているのだ。すこやかクラブもここを拠点とする団体の一つであり、去年に引き続き二度目となるこのイベントを7月28、29日に開催した。28日は前夜祭、29日がメインイベントの日となっている。なお筆者は、このイベントの2日目にいわば「裏方」として関わっていた者であり、この文章は一般的な意味での「劇評」ではなく、部分的に参加した者が体感したその記録であることを明記しておく。
さて、このイベント、イメージとして一番近いのは文化祭のお化け屋敷だろうか。だがそこはプロ。とりわけ各種展開されるパフォーマンスのクオリティは高い。その割に、イベント全体はそれほどかっちりとオーガナイズされておらず、そこはかとない緩さが「文化祭」感を醸し出している。古い教室、そして夏の暑さも相まって、大人にとってはどこか郷愁も感じられる。
懐かしい下駄箱が迎えてくれる受付に立ち寄った途端、そこからすでに異様な光景が眼の前に現れてくる。白塗り、ざんばら髪になぜか矢が数本頭に刺さった上半身裸の男が闊歩し、大きなヤカンを頭にすっぽりとかぶった男はうろうろして時おり自分の頭から茶碗にお茶を注いでいる。平然と、しかしお化けの三角巾を付けてにこやかに受付するスタッフとのギャップ。最初からシュールすぎて笑えてくる。受付横にある待合室に案内されると、今度はネオンの飾りのついたケバケバしさ全開の白衣を着た養護教諭ふうの女と、ゾンビが登場する。このゾンビ、やたらに怖いのだ。まるで映画のようにリアルな特殊メイクもさることながら、折れ曲がったように動く体、やたら大きな叫び声など、集まっていた子供達はぎゃんぎゃん泣きわめく。大人でもちょっと怖い。しかも、ゾンビは、増える・・・。ゾンビたちに追われながら、白衣の女に「結界が張ってある」という校庭に案内され、そこでゾンビたちの踊りを見るという展開。どうやらプログラムによれば、これが「ゾンビの開会式」らしい。怪奇クラブの始まりというわけだ。以降は、30分に一度ほど開催される教室でのパフォーマンスと、常駐のインスタレーションなどを主軸として展開していく。
校舎の二階にある職員室と教室で繰り広げられるパフォーマンスは、例えば次のようなものだ。「ゾンビ女子会」では、ゾンビになってしまった3人の女の子たちが、生前のことを夢想しながらダンスを踊る。変な角度に曲がった手足や不気味なメイクを施しているにも関わらず、元気よく踊る姿にギャップを感じ、この女の子たちはどこか愛らしくもある。あるいは「弾丸小学校」では、観客が席につき、先生役のパフォーマーによる授業6年間分が十数分の間に展開される。名簿での点呼や黒板を使った授業、そして席替えと修学旅行の枕投げなど、誰もがかつて経験したような懐かしさを秒速の展開と笑いで追体験していく。この他「地獄甲子園」や「給食おばさん」なども交互に上演された。懐かしいのに、すべてがどこかズレていて、そのズレが笑いを生む、そんなパフォーマンスだ。それを大人になってしまった私たちが、かつて実際に小学校であった場所で体験するということ。私たちの記憶と校舎の記憶が重なり合い、しかしうえもとの演出によってそれらはエネルギー溢れる「くだらない笑い」へと転化されていく。
同じフロアの別教室はゾンビメイク体験コーナーになっており、写真による図解付きで誰もがゾンビメイクにチャレンジできる。その横では、オリジナルのゾンビ盆踊りの振付を解説するレクチャービデオが流れている。音楽室では竹を使ったインスタレーションの中、尺八奏者がセーラームンのテーマらしきものを演奏していたり、やたらテンションの高い校長先生が校長室を訪問した観客を相手にお話をしたりお菓子をまき散らしたり、スピリチュアル保健室なるものがあったりと、観客は自由に回遊してこれらを見ることが出来る。さらに、おばけの寄合所ではピアノの妖怪(?)が、「ピアノを弾いていかないか」と声をかけ、手を入れたところで「今だー!」と叫んで蓋を閉じ手を挟もうとする、お決まりのギャグで盛り上げ、廊下にはヤカン頭の男がただしゃがみ込み、あるいはカオナシのような司祭を連れたシスターがうろうろやってきて「あなたに霊が付いている」と迫ってきたり、単発的なパフォーマンスもちらほら見られた。オバケの「カオハメ」コーナーで写真撮影し、トイレに飾られたインスタレーション「うんこすごろく」や「うんこを題材にした俳句」でそのバカバカしさに笑い、「ジブリみたいなへや」で廃品を利用した立体彫刻オブジェの森に迷い込み(なおこの部屋は、普段からたちかわ創造舎に多くの立体彫刻オブジェを展示している作家の作品が陳列されている。それを「ジブリみたいなへや」としてイベントに組み込んだ格好だ)、大人が全力で悪ふざけをしているとしか言えないような気もするのだが、その全力加減が清々しく、体験型のイベント、そしてパフォーマンスとして楽しめるものに仕上がっている。
最後はあいにくの雨ながら、校舎の屋上で盆踊り大会が行なわれた。観客は傘をさしながらもかなりの参加者がおり、ゾンビも人も関係なく輪になって踊って終了となった。(晴れていれば昭和記念公園の花火が望めたというから残念!)
元は学校であったという場を最大限に生かしながら、「ゾンビ」「怪奇」というキーワードを見事に当てはめ、さらに様々な笑える演出・パフォーマンス、参加型の盆踊りと、そこに集う人々・老若男女が楽しめるプログラムになったのではないかと思う。
課題としては、パフォーマンスの更なる充実があげられる。開会式から盆踊りの終わりまで4時間あり、同じパフォーマンスが交互に上演されるため、最初から来た人はやや時間を持て余すことになる。むしろここは、すべてのパフォーマンスを見て回るのが不可能なくらい、数が多い方が良いのではないだろうか。
毎年開催され、立川の夏の一つの風物詩になるくらいにまでこのイベントが成長してくれることを願っている。
INDEXに戻る
劇に幻想が立ち上がる瞬間
藤原央登 劇評家
燐光群『くじらの墓標 2017』
2017年3月18日(土) ~ 31日(金) 会場 吉祥寺シアター
1
元は漁業倉庫だった何もない場所。薄暗くなったその空間を赤や青、オレンジの照明が斜めに切り取る。日常がにわかに変容し、切羽詰まった雰囲気が空間に漂う。その緊張感をぶち破るように、シャッターが半分開いた外から突如として幻想が雪崩を打って劇空間に押し寄せる。打ちつける幻想の力に現実が取り込まれ、壮大な虚構が一挙に立ち上がる。そんな、久しく経験していなかった瞬間を目にした私はくらくらとした。現実を食い破る幻想の渦が「動」であるならば、繊細でエロティックな「静」の描写も対比的に置かれる。これらが渾然一体となり、劇の細部までは理解できなくとも、身体感覚で何事かを知覚し感応するという、劇のダイナミズムを味わった。これこそ、演劇を観ることの醍醐味であると確信させられる思いだった。 本作は1993年に初演。翌年には関西、名古屋などのツアー公演を行い、その後はロンドン(97年)とニューヨーク(99年)で外国人キャストでも上演された。後に坂手洋二はくじらを題材にした作品を数多く生み出してゆく。その原点ともなる本作が坂手の代表作のひとつであることが、初演から24年の時を経ての上演で納得させられた。
事故で入院していたイッカク(HiRO)は療養がてら、管理人のような立場でこの倉庫に住み込んでいる。イッカクは、倉庫を所有する漁業関連会社の課長・シュウゾウ(鴨川てんし)の姪・チサ(宗像祥子)と婚約している。そんなイッカクを訪ねて次男から6男までの5人の兄弟がやってくる。厳かでゆっくりとした足取りから、彼らは死者のようにも思える。イッカクと20年ぶりに再会した彼らは、自分たちの出自を語る。代々続く捕鯨の家系であること、捕鯨してはならないと伝えられてきた子持ちのセミクジラを殺してしまったこと。その際に悪天候に見舞われて船が転覆した。禁を犯した家は末っ子を恵比寿(くじら)様に捧げることで、神の怒りを沈めてもらう必要があった。しかし、漁に出ていなかったイッカクを差し出すことは忍びなくてできない。そこで彼らは村を去って全滅したことにし、残されたイッカクを末っ子ではなく一人っ子の長男と見なすことで、難が及ばないようにしたこと。そしてこの度、イッカクはチサと婚約をした。結婚は新たに家を形成することである。すなわち、イッカクは末っ子ではなく家長である。村の因習には縛られない。ようやく、兄弟たちは顔を合わせることができたのである。
2
虚構と現実をない交ぜにすることは演劇にし得る大きな魅力である。嘘の力があまりにも強く出来させることができれば、そこに立ち会った者の現実認識が根底から変更する。嘘に基いた「本当」が現実となり、世界や人間の見方への新たな発見が与えられるのだ。とはいえ、そのように劇をつらえることは簡単ではない。強大な嘘は荒唐無稽さと裏腹でもあるし、それを支える細かな嘘を丁寧に説得力を持って用意しなければならない。舞台上で提示される嘘が、演劇ならではの虚構を成立させるための構成要素なのか、はたまた単なる無茶なのか。観客は鋭く見抜いてしまう。演劇は虚構ではあるが、だからといって観客は全てを「虚構だから」で片付けてはくれない。虚構を起こそうとする空間とさまざまな事物は実在のものであり、目の前の俳優は観客と同じ時代を生きる人間であるこをは忘れてはいなのだ。虚構を成立させる全ての要素が、強固な現実原則に支配されているものから成っていること。そのことを頭の片隅に置きながらも、なおかつ現実原則を覆す虚構を目撃すべく、観客は舞台に対峙している。
©姫田蘭
虚構を成立させるのはそれほどまでに困難なのだが、本作がそのための条件をクリアーして幻惑空間を作りえたのはなぜか。それは、くじらと人間を中心とする、2項関係の対比と同質性との絶妙なバランス感覚にある。くじら=人間と明確に記されているわけではない。両者の境界線は曖昧である。だが、代々捕鯨を生業とする家系に生まれ、くじらの種別から名付けられた7人の兄弟たちが、くじらの生を背負っていることは想像がつく。だから観客は、時々のシーンでくじらと人間どちらの立場が強いのか、両者の関係を巡らせる。そしてそこに、一個の生物が存在する意味を思索する。つまり、俳優たちの存在は単なる人間ではなく、その彼方にはるかに大きく、同じ哺乳類のくじらを見るのである。したがって本作は、大海原を回遊するくじらと、世界内存在である人間を同時に浮かび上がらせることに成功しているのである。そのことは、半ば閉ざされた倉庫に大自然を呼び込むことにもなる。そんな劇世界で主眼となるのは、イッカクの存在の不確かさについてである。
さらにはくじらと人間との対比と同質的が、つかず離れずの緊張感をはらみながら他の2項関係にも波及し、劇全体が円環をなしている。どこまでも続く合わせ鏡の像のように、自己像を巡る想念が拡散しながら累乗的に膨れ上がることで、どちらが自己なのかが判然としない領域へと進み出る。くらくらとする幻惑効果は、周到に構築されたこのような劇構造がもたらすものだ。それは結局、自己対話的だと言えなくはない。しかし、膨れ上がりながら最終的には円環をなす自己対話の巨大な渦を出来させたことによって、自然と人間とが不即不離な関係にあるようなイメージを想起させられた。それによって、世界は自分であるという壮大さと、それを裏返しにした世界にぽつねんと置かれた人間の寂しさを感得したのである。
3
2項の対比と同質性がくじらと人間だけでなく、広がりを伴って舞台全体に及んでいると感じさせる大きな要素を具体的に見てみよう。鍵はチサとクニコ(都築香弥子)の存在である。劇後半、チサが妊娠していることが発覚する。かねてよりシュウゾウとチサのただならぬ関係を知っていたらしいクニコの口ぶりから、2人の間の子どもではないかと思わされる。そういえば舞台が始まってしばらくして、イッカクとチサを交えて会話をしていた際、シュウゾウはチサを「ちょっと相談だ。」「すぐすむ話だから。」と言って、舞台上手の事務所へと誘っていた。実際にそこで何が行われたのかは分からないが、クニコの言葉によって点と点がつながり、チサとシュウゾウの不義密通を想像してしまう。その後、クニコはシュウゾウに離婚届に押印するように告げて去る。チサとシュウゾウの関係をいよいよ確信的に想像した私は、シュウゾウが封筒の中の用紙を取り出したところでその思いが裏切られる。そこには、水道料金の振替口座の変更届が入っていた。シュウゾウは言う、「私とチサは本当に何もない……。だけど、あいつの思い込みに合わせないと、あいつは本当に、おかしくなってしまう……。」と。ではチサの子どもの父親は誰なのか。イッカクは事故に遭った関係でチサとセックスをしていなかった。イッカクは後にチサから「気にしないで。あなたの知らない人だから」と言われる。ますます不安が募るイッカクは、「……俺は、ここにいちゃ、いけない。」と自己肯定感をなくしてゆく。兄弟が久しぶりに訪ねてきて、血縁関係が強固な捕鯨一家であることが判明したイッカクと、両親がおらずしかも親戚との不貞が疑われるチサは対比をなす。だが、婚約者ではない男の子どもを身ごもっているらしいチサと、リハビリ中でかつチサとの関係性が不安定になって孤独を感じつつあるイッカクは、それぞれに位相が異なるかもしれないが闇を抱える者という意味では同質的でもある。
舞台は、机につっぷして寝ているイッカクにチサが語りかける静かなシーンで始まり、同様のシチュエーションを役割を交代して会話をするシーンで終わる。また、6男のサチオ(山村秀勝)がクニコの膝に頭を乗せて耳かきされている様子を見て、次男のサトオ(川中健次郎)がクニコに死んだ母親の影を見て抱きつくシーンが2回挿入される。こういったことを併せて考えると、この舞台には人間とくじらに代表される対比と同質性を、どちらが正解かを確定させない曖昧な領域が保たれている。さらには答えを出さない曖昧さを、微妙にズラしつつ円環させる構造となっている。それゆえに、観る者に舞台の緻密な読解を誘発して止まないが、そう試みようとすると虚空を掴むような捉えどころがないもどかしい感覚に陥る。しかしその感覚が人間存在の不確かさへと通じていることは、身体的な実感として確実に感じられる。この辺の絶妙な加減が、本作の秀逸な点であり魅力となっている。
4
続いて冒頭に記した、劇的な幻惑を強烈に感じさせるシーンについて触れよう。かつて捕鯨をしていた際、見張り役だったサトオが東京湾の海面がかすみはじめたことを確認する。3男のゴンゾウ(杉山英之)は気のせいだと取り合わないが、シャッターの外からロープをひっぱってきた叔母のタツエ(中山マリ)がサチオを伴ってやってきて、倉庫内の机の脚にロープをくくりつける。ロープの先が引いていることを目の当たりにして、彼らは本腰を入れて捕鯨に取り掛かる。すっかり夜になった外は、突然の風雨。ロープの先に食らいついた獲物が引く力はかなり強い。ロープを必死に引っぱる兄弟たちも大きく左右に揺られる。くじら唄を歌い、祈りを捧げながら、あらん限りの力で引き続ける。その果てに登場したのは、これまで姿を見せなかった長男・ナガス(大西孝洋)である。ナガスとの会話の中で、彼はセミクジラの親子を殺しただけではないことが語られる。悪天候のためにくじらの追跡を止めるよう間に入った船に向って機関銃を撃ち、沈没させたのだ。そんなナガスを他の兄弟たちは海に沈め、乗っていた船を難破させて全滅を装ったのである。掟を破って強行したセミクジラ獲りに対する罪滅ぼしの意味だったのだろうか。そしてナガスに誘われるように、6兄弟はガレージの外へ消えてゆく。彼らはやはり死者であり、海に還ったのか。ここで対比と同質性は、生と死の要素をも含み始める。なお、イッカクが妊婦姿のチサを刺殺するという、イメージのようなシーンがこの後にある。これも、ナガスがくじらの親子を殺したこととの対比である。くじらと人間が別々に刺殺されることにより、くじら=人間の同質性と円環が観客の脳内で成立する。
©姫田蘭
さて、兄弟たちが再びイッカクの前に姿を現すのは、兄弟たちが海に去り、チサとの関係性にも自信が持てなくなり、「……なぜ俺だけ、生きてる。」と陸に打ち上げられたくじらのようにたった一人きりで絶望の淵に立っているような状態の時である。自殺をするのは人間とくじらだけだという。くじらは陸上でも呼吸はできるが、自重で内臓がつぶれ、皮膚が炎症を起こしてやがて死んでしまう。陸にくじらが打ち上げられるのは事故という説もあるが、たとえ海に戻したとしても、また陸に上がってきてしまう。したがって、自殺ではないという科学的な証拠はまだないのだという。呆けたようにそのようにつぶやいて包丁を手にするイッカクは、死の念に取り憑かれている様子。陸に上がって死にそうなくじらのようにイッカクはボロボロだ。そんなイッカクの背後から、鞄を手にしコートを着込んで外出姿の兄弟たちがやってくる。陸には限りがあるが海は広い。その海はどこかでひとつにつながっている。我々は別々の人生を歩むが、またいつか出会う時がくるだろう。兄弟たちはそうイッカクに語りかける。イッカクはこのまま自殺するのか否かは分からない。ただ、ひ弱なイッカクが、身体の何倍もある瀕死のくじらのように寂しく見えた。
ここまで自分なりに本作を読み解いてきたように、現実と虚構、どちらでもありどちらでもないような不思議な舞台である。そんな中で、死に行く一人の青年の身体感覚だけは確かなものとして感じられる。この世界でただ一人であることの不安感を、個人の狭い世界に閉じ込めるのではなく、文字通り大海に広げる手つきに、本作が射程に収める世界の広さがある。そこに、世界とのつながりを切実に求める意志を感じた。そこに私は端的に感動したのである。本作には、劇を生む詩の感覚が溢れている。
くじらの生態や伝統的な捕鯨の説明が散りばめられているにもかかわらず、行間が豊穣な文体。劇中で実際に鯨肉を焼いて試食するシーンもある。鯨肉の独特の匂いを初めて体感した。そんな劇世界を成り立たせる俳優たちは全員健闘している。初演時の俳優が数人出演しているが、そこには継続した活動を続けてきた劇団にしかできない共同作業の底力を感じた。若手ではチサを演じた宗像祥子が目を惹いた。宗像は昨年の『カムアウト2016←→1989』(下北沢ザ・スズナリ)でも要となる役を演じた。子どもっぽさを残しながらも肉感的なエロスが、ロマンス溢れる坂手の幻想劇にぴったりで、たっぷりとした芝居が良く活きていた。イッカク役の客演・HiROは中世的な立ち振る舞い。始まってしばらくはナイーブすぎると思ったが、過剰な繊細さとでもいう演技がしだいに迫力を持ち、生と死の間でなんとか踏みとどまる青年の苦しみを体現した。テーブルの上で行われるイッカクとチサの情交は、陸に打ち上げられた鯨のように、苦しくもエロティックな情感が匂い立っていた。
戯曲引用︰坂手洋二『くじらの墓標』而立書房,1998年
INDEXに戻る


