 |
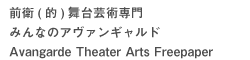 |

![]()
はめられたフレームのシアトリカリティを暴く
−akakilike『家族写真』
宮川麻理子(ダンス研究者)
akakilike『家族写真』
2018年6月22日(金)~24日(日) 会場 d-倉庫
©平澤直幸
公演のタイトルになっている「家族写真」-これがほぼ唯一の舞台を見る手がかりとなる枠組みで、事前に観客に与えられた情報である。お父さん、お母さん、お姉さん、お兄さん、妹、撮影のカメラマン、そして他人(?)。舞台上に出て来た彼らの容貌や言葉、ぼんやりと紡ぎ出される関係性などから、おそらくそう読み解くことは可能である。しかしここで展開されるのは、「家族写真」を撮影するシアワセな家族の物語ではない。このフレームはフレームとして淡々と、時にドラマチックに提示されるのだが、奇妙にフレームだけが浮かび上がり、場面ごとの連結やストーリー、登場人物同士の関係性は断定されることを巧妙に避けるのである。さらに出演者は、役を演じているようで演じていない。タスク、あるいは行為とでも言えるような動作を、またある時はバレエの振りを、舞台上に体を晒しながら「こなしていく」のである。そこから立ち上がる情景、うっすらと隆起するイメージは、どれも確定し得ないものである。これらの場面は、観客の中でだけ、例えば筒井が「お父さん」と自らを呼ぶことでのみ家族の物語として結晶するものであり、作品から明示されるものではない。
©平澤直幸
何もない舞台に客電も明るいなか出演者が登場し、中央に机を並べる。会議室によくあるような長机である。三脚を設置するカメラマン(前谷開)の姿も見える。そんな中で客席後方から水着の男(佐藤健太郎)が、イヤフォンで聞いている音楽をハミングしながら登場する。舞台上で机を挟んで女の子(迫沼莉子)と寺田みさこ、筒井潤(女、男という以外に役名を当てることができないので、出演者の名前とする)は下を向いている。水着の男は舞台後方まで行くと、床をクロールで泳ぐようにして進んで行く。暗転ののち明るくなると、霊安室のような感じで、2人(倉田翠、竹内英明)が机上に倒れており、やがてわずかに足を持ち上げたかと思うとズリズリとそこから落ちるように動いていく。そうして始まるのは、筒井のモノローグである。「もし、もしもやで、お父さんが死んだらやけどな、みんな考えたことある?」。このセリフから、おそらく筒井は「お父さん」なのであろうと想像される。しかし周りの「家族」たちはこのモノローグに反応することなく、例えば寺田みさこは明らかに振付らしい=日常の身振りではない手の動きを見せたり、そうかと思えば、他の出演者はガムを食べたりしている。「もしもお父さんが死んだら」というモノローグは目の前に家族「らしき」人がいるにも関わらず、誰に対して発せられる訳でもなく繰り返される。むしろ机の方へ目を向けたまま喋り続ける筒井は、死者に向かってこのセリフを語りかけているようにすら聞こえる。筒井のこのモノローグはやがて、「保険」という不思議な商品を売る話に接続される。つまり「保険」という商品は、筒井のこの「もしもお父さんが死んだら」というようなことを前提として売れるのである。やがて登場するネクタイの男(佐藤健太郎)は、そこで語られるセリフからどうやら「お父さん」のライフプランナーであったと想像されるのだが、彼がトライアスロンの話をし(健康でなければできない)、寺田とデュエットを踊り、「お父さん」と対照的なハツラツさを見せるのは「家族」という枠組み自体のもろさを露呈させる。「お父さん」かもしれなかった筒井の「家族」は、もしかしたら筒井のそれではなく、このネクタイの男の家族なのかもしれない。つまり見ている私たちにとっても絶対ではなかったこの「家族」は、演劇というレベルにおいても解体される。あるいは別の家族に変容する、と言ってもいいかもしれない。それは、実際のリアルな「家族」というレベルにおいても起こりうる、その脆弱さを開示しているのである。「お父さん」の家族かもしれなかった人たちは、なんらかの繋がりを再接続することによって(平たく言えば離婚とか、死別なのだが)別の家族を形成してしまうのだ。もちろんそれはなんら批判の対象となることでもなく(もちろん、「お父さん」のセリフに込められる怒りのエネルギーから彼の感情は押して図るべしだが)、本作においてもある種残酷に、粛々と進んで行く。ある瞬間の「家族」の集合写真は、次の瞬間に「他人たち」の写真になるのかもしれない。あるいはその「家族写真」は、家族写真という文脈を与えられることで「家族写真」になるのだろう。
©前谷開
バレリーナの身体もまた、文脈から剥ぎ取られて舞台上に晒される。劇中で繰り返し使用される曲は、バレエ『くるみ割り人形』の「雪片のワルツ」である。だがもちろんバレエ作品を踊るわけではない。バレリーナの身体(演出家でもある倉田翠、子役の迫沼莉子)もまた、バレエという文脈を欠くと、奇妙に爪先立ちをしてポーズをする、エキセントリックなものとなりうる。とりわけ倉田の奇妙な(カット)→危ういバランスをとりながらトウで立ち上がるポーズは、痙攣する身体を思わせた。例えば優美な曲線を描くポール・ド・ブラにしろ、バレエでは美しく立ち上がるポーズが、その物語(『くるみ割り人形』)という文脈が欠落することで、捩れた体、捻られ引きつった身体として提示される。この公演を見ている私の頭の片隅になぜかずっとあったのは、シャルコーが行ったヒステリーの研究、すなわちサルペトリエール病院の教室という舞台で、学生という観客の目の前にさらされた女性の身体であった。『シアターアーツ5』(1996年2月号)に掲載された座談会ⅰを参照するならば、ヒステリーというのは「人が見ていないとその症状は出てこないという特性があって、カメラを向けると突然発作が起こるⅱ」(鈴木晶)のであり、それは紛れもなく、この舞台の構造(前谷開というカメラマンが舞台上で写真を撮る)と無関係ではない。とりわけ長机の上に横たえられた倉田の身体は、教室で学生の目に晒されるヒステリー患者の身体を想起させた。また、そもそもバレエそのものが、石光泰夫によれば、「型の創出はまさに異常な身体の表現そのものだったⅲ」のであり、「無理にポワントで立つとか、あんなふうに高くジャンプするというのは単に重力に抵抗するということだけでなく、まさにカラダをぐっと反らせるというようなヒステリー的身体が起こす異常の反映ⅳ」なのである。その倉田が長机の上に横たわっていると、いつの間にか首回りに血だまりができている。ヒステリーの抑圧としてのエレガントなバレエの型、そしてそこから逃れようとする生の身体を意味する血。もしかしたら先に死ぬのはこの倉田なのではないかということを思わせる「もし、お父さんが1人残ったら」という筒井のモノローグが後に続く。今はたおやかに子供らしいバレエを踊っている女の子も、もしかしたらそのバレエという装置の抑圧を、後々その身体で感じ取ることになるのかもしれない。これはバレエという型への、冷静で批判的な眼差しである。
家族、バレエ、そして舞台。当たり前のように与えられたこれらのフレームの裏に見え隠れする、真実らしきもの。それすらも虚構なのかもしれないが、倉田が提示した複雑かつ重層的なこの作品は、外枠を少しずつ剥ぎ取って、漂う世界の内奥に迫ろうとしているように思えた。
------------
ⅰ豊島重之、石光泰夫、山崎哲、鈴木晶、鴻英良「座談会・精神分析と演劇のエクリチュール」『シアターアーツ5』、1996年2月号、pp.26-50。
ⅱ上述書、p.36。
ⅲ上述書、p.37。
ⅳ上述書、p.38。
INDEXに戻る
![]()
衰退する世界における人間の「グッド・デス」
藤原央登(劇評家)
サンプル『グッド・デス・バイブレーション考』
2018年5月05日(土)~15日(火) 会場 KAAT 神奈川芸術劇場 中スタジオ
©前澤秀登
『ブリッジ』(2017年6月)をもって劇団としての活動を終えたサンプル。サンプルの公式ツイッターでは、これを「第一形態」の終了と位置づけていた(→Twitter)。それから約1年。サンプルは松井周による「一人のユニットに『変態』」して再始動した(→Website)。KAAT 神奈川芸術劇場との共同制作によるその第一作は、深沢七郎の小説『楢山節考』(1956年)が題材となっている。
信州の山間にある貧しい村。そこの因習「おばすて」にしたがって母を捨てる息子。母子の絆を描くのが『楢山節考』だ。松井周の劇世界にはかねてより、独特の習慣や因習を持つ不思議な共同体が描かれる。そういう意味では、『楢山節考』との親和性は非常に高いといえよう。とはいえ本作における因習は、『楢山節考』のようなおよそ現代ではありえない、古くて非人道的なものではない。むしろ、現代日本の寓意の側面を強く感じさせる。それは、超高齢化社会と少子化である。
厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所のレポートによると、2025年に団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる。さらに団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年頃には高齢化率がピークに達すると予測されている。生産年齢人口が減少し高齢者が増えるといういびつな人口構成がこのまま進めば、2053年の総人口は1億人を割る見通しだという(「日本の将来推計人口」(平成29年推計))。山間で暮らす貧しい棄民の集落では、国の制度によって65歳以上の者は海に「船出」して「安楽死」しなければならない。これが、本作における『楢山節考』の因習に相当する決まりである。該当者であるツルオ(戸川純)が、「船出」の追い風となる台風の日に備えて暮らしている。現在の日本は、所得格差によって結婚・出産はおろか、人ひとりが生きるのにやっとである。低成長による国家財政の逼迫、社会保障費の増大とそれによる財政悪化はこの先、ますます深刻化することだろう。老人を役に立たない存在だとして容赦なく切り捨てる。一方で、優生人種を増産するべく厳しい人口統制を強いる。本作で展開される国家による措置に、深刻化した少子高齢化社会を無理矢理克服しようとした結果が読み取れる。だからこそ『楢山節考』的な因習に、古さではなく日本の未来の光景を見てしまう。本作には人口構成比率的には間違いなく衰退してゆくだろう、日本の現状を敷衍した世界が展開されているのだ。
松井作品で印象深いのは、KAATのプロデュース公演『ルーツ』(2016年、KAAT 神奈川芸術劇場 大スタジオ。拙稿の劇評はこちら)だ。これまでに抱いていた松井作品とは異なり、独特の因習を持つ共同体に自閉するのではなく、新たな創世神話を紡ごうとする意志を感じさせた。棄民の行く末を描く本作は、『ルーツ』のように共同体から飛び出るといった明確な進路を取ることはない。その点については、松井の態度が留保されているように見える。そのため、作品の主題は『ルーツ』より分かり難く、後退しているようにすら思える。この分かり難さはどこから来ているのか。先述したように本作の劇世界は、日本の現状を敷衍した未来の寓意のように感じられる。したがって、その萌芽は現在にもすでに散見されるはずだ。しかし、それがどこにあってどうするべきなのか。日本が今後進むべき方策を簡単に見出すことは難しい。約20年も諸課題に対する明確な処方箋を示すことができず、しかも今後も悪い見通しが予測されている現状がその証左である。とはいえ、何らかの対策をしなければ悪化に加速度がついてしまう。現在とは、今後の日本をどうグランドデザインするかについての、まさに最後のチャンスとも言えないか。そういう意味で現在は、国の針路をどう取るのかについて、過渡期/岐路に直面していることは確かなのである。そう考えれば、本作の分かり難さが見えてくる。つまり、未来につながる社会に対する2つの態度、すなわちそこに留まるのか出るのかを選択する前に、現状の社会をいかに認識するか。今一度、そのことを松井は考え、そして観客にも問いかけているのではないか。演劇は政治ではない。したがって、ここでの社会認識は個人がどう生きるのかにかかわる。ゆるやかに死を迎えつつあるとしか思えない日本を、いかに受け止めるか。そのことによって、因習という名の制度にしばられた共同体=国家の中でいかに生きるのかという選択が見えてくる。場合によっては、どうしようもないのであれば国と共に滅んだ方が良いという答えになるかもしれない。『ルーツ』より作品の雰囲気が後ろ向きに感じられる面があるのは、生と死の間を逡巡する両義的なあいまいさを含み込んでいるからである。
©前澤秀登
作品の大枠となる国家統制について詳述しておこう。老人を海に流すだけでなく、それは生まれてくる子供や個人の人格にまで及ぶ。だからこそ、そのような社会を未来に孕んでいるかもしれない現在をどのように捉えるのか。最終的には、個人の生き方へと問いが差し返されるのである。さて、国家統制である。恋愛結婚はモテる者とそうでない者を生み出すために禁止。男女はゲノムチェックを受けており、その上で国家が選んだマッチングパートナーと結婚しなければならない。もしそれに違反し「野良交尾」で子供が産まれた場合は、殺さなければならない。マッチングパートナー同士ではない子供には、遺伝子異常の懸念があるからだ。隣りの村からザラメ(野津あおい)がやってきたのも、集落に住む一家の子供・バイパス(板橋駿谷)と結婚するためであった。彼らはまだ10代前半の子供であるにもかかわらず、筋肉増強剤によって生殖ができる大人の身体にさせられている(マッチョな板谷に合致した設定である)。この措置は、少しでも健康で優秀な子供を多産させるためであろう。親は産まれた子供を国に売り、その対価で生活をする。その子供もやがてマッチングパートナーで結婚し、子供を産む。そのまた子供が……。高齢者を少なくする一方、国力の基となる子供を国家を挙げて増産しているわけである。国家はさらに、「超日本人」を生むための実験も行っているようだ。
集落に暮らすのは他に、ツルオの娘であるヌルミ(稲継美保)、隣の家の主婦・クッコ(椎橋綾那)である。劇途中にタップ(松井周)が体制側の人間としてやって来る。実は彼、ヌルミの子供である。かつて、謎の男(松井周)と「野良交尾」をして妊娠・出産したヌルミは、国の制度にしたがって海に流して殺したはずであった。だが、タップはすんでのところで他者に拾われて生き延びたのである。今や「中央」で勤務するタップは、ザラメがかつて産んだ子供が「超日本人」を生む遺伝子実験の末に死亡したことを報告しに来たのだ。
本作で展開される国家によるトップダウンの人口統制は、旧優生保護法(1948~1996)の下での強制不妊手術の問題を想起させた。今年1月、宮城県の60代の女性が、知的障害が理由の不妊手術は憲法違反であるとして、国家賠償請求を起こした。このことをきっかけに大きく報道され、厚生労働省による全国調査が始まった。本人の同意がない強制不妊手術を受けた人数は、約1万6500人いるとされている。かつて、女性を「産む機械」と発言した厚生労働大臣がいたが、人間をモノのように扱う劇世界は決してありえないものではなく、日本の歴史上において、負の側面として存在しているのである。
©前澤秀登
さらに、人々を陶酔させ扇動する恐れがあるとして歌や音楽が禁止されている他、個人の思想を披瀝し語ることも禁じられている。違反した場合は思想警察によって処罰される。かつて歌手だったツルオは、自由恋愛が可能な時代を生きていた。やがて、国家があらゆる面で締め付けを強めるようになったことに反発し、ゲリラライブを敢行。警察から歌手を辞めるか陰茎を切り落とすかを迫られ、ツルオは後者を選択した。ツルオと初対面したザラメが勘違いするほど、女性化してしまう。禁止されている歌を突然歌い出したりする暴走老人・ツルオを、戸川純は白髪のカツラを着用し低くしわがれた声で演じる。見るからに老人にしか見えない演技が目を惹いた。そんな陰茎を失って性が揺らいでいるツルオは、もはや男性としても女性としても機能しない、アイデンティティクライシスに陥った人間の象徴である。美術家・カミイケタクヤが手がけた舞台空間には、傘やラジカセ、トタンにタイヤといった、ゴミやガラクタが散乱する。ゴミ溜めのような空間の真ん中には、骨組みを組み合わせた球体の小さな構造物がある。椅子とテーブルしかなく、外にいるのと変わらないこの空間を住居にして、家族は暮らしている。過度な生殖行為によってもはや妊娠できない身体なのに、そのことを隠して嫁いで来たザラメ。そのことにショックを受けてクッコと不倫するバイパス。空腹のあまり他人の家から食物を盗んで集落の人間たちから制裁を受けるクッコ。野良交尾で子供を産んだことのあるヌルミと、「正常」な出自を持たないタップ。集落にいる者は皆、国家に貢献できなくなった者たちだ。まさに彼らは、周りのゴミやガラクタと同じく廃棄された存在なのである。
ツルオが「船出」した後、タップが家族の新たな一員に加わる。それを受けてヌルミが「ひどいところだけどすぐに慣れるよ」と発して舞台は終わる。本作の主眼は、この言葉の受け取り方にかかわる。国家統制から外れて棄民された共同体が、その状況を唯々諾々と受け入れるのか、それとも“あえて”追認する身振りをするのか。ヌルミの言葉を、食卓を囲んだ家族はどちらの意味で受け取ったのだろうか。両者の態度は同じようでいて、微妙だが決定的な違いがある。前者は、無抵抗に自分たちが置かれた状況をなすがままに受け入れることだ。それは、次第に先細りする国家と運命を共にすることである。しかし後者の“あえて”の身振りには、国家の針路とはまた別の生き方を模索する意志を感じさせる。貧しい小さな棄民の共同体のまま、オルタナティブな生を歩むこと。そのために、現状をそれとして正しく受け止める言葉として聞くことも可能だ。果たしてどちらの言葉として受け取るべきか。ここに、日本の行く末を占う岐路に立つ我々の問題が孕んでいる。
後者に対してのかすかな希望を感じさせるのは、ザラメがたびたび語る夢のエピソードだ。ザラメは、王=ツルオの后としてたくさんの子供を出産することを夢に見る。マリーアントワネットよろしく、国家を逼迫させた責任を追求され、断頭台で処刑される。その瞬間、彼女は自由に解き放たれ、鳥になってどこまでも飛翔する。家々の屋根を越えて果ては太陽に向かって進むが、首がないためにそのまま突っ込み、羽が焼けて墜落する……。内容的には、どこにも行けないことを再確認するような、救いのない夢だ。ここで重要なのはその内容ではなく、夢を見て語ることそのものにある。先述したように、劇世界の住人は機械のごとく子供を産むことだけを強制されている。そのことを阻害するあらゆるものは不必要なものとして禁じられている。そこには夢を語ることも含まれる。夢とは、睡眠中に見るものだけではない。広く大衆に現状変革を促し、反権力思想を醸成するものも含まれるからだ。だが考えることを止めよと強制されても、人間は簡単にはそのことを止められない。たとえ思い描く夢の結末がハッピーエンドでなくとも、それを目指してまた考えれば良い。ザラメが語る夢のエピソードに、考え夢想するという行為に、消えることのない人間性の残滓が示されている。それは後ろ向きではあるが、人間的理性をギリギリのところで死守していると言える。縮小する日本社会への処方箋はそう簡単ではない。そのような現実の中では、一人ひとりの人間にできる能動的な行為はこれくらいしかないのかもしれない。松井作品の特徴のひとつは、妄想の世界が現実を侵食するといった、様々な境界線を溶解させることにある。そのような劇世界は、身勝手な個人の世界に居直る現実逃避のように私には思えていた。しかし、考えることそのものを重視するザラメの夢のエピソードを踏まえると、別の見方もできる。それは、世界の見方の変革である。妄想することでは世界に直接的な影響は与えられない。だが、妄想を現実に重ねることは、AR(拡張現実)のように世界を違ったものとして見ることにはつながる。そこで得られる認識によって、もしかしたら次に起こす行動は変えることはできかもしれない。そのことは、その者による直接的な世界へのアクションにはつながるだろう。ザラメの夢のエピソードは、ささやかかもしれないが、誰にでも可能な、考えるという試みに意義を見出し、そこに賭けようとすることのように感じられた。
©前澤秀登
ツルオの「船出」も、ザラメの夢に近い理由が考えられるのではないか。『楢山節考』と異なり、ツルオが山ではなく海へ流される点に、その答えがあるように思う。嵐の夜、ツルオはいよいよ出発という時になって、突然抵抗し始める。そんなツルオを、バイパスは家族全員で出帆することを提案してなだめる。実は可動式であった家を船に見立てて出帆する様は、さながらノアの箱舟だ。しかし、洋上の船からひとり、またひとりと家族が去り、ツルオだけが残されてしまう。そしてツルオは、人がいるらしい島を見つける。そこは死を前にした者がたどり着く最果ての地か。たとえそうだとしても、山ではなく海に出ることに開放感を抱かせられる。山で死ぬことは、文字通り空間に散在するゴミと同じ立場になることである。対して、広い海は生命の源だ。棄民の民が住まう山間の集落を、中上健次が言うところの「路地」であるとすれば、海への「船出」はそこからの脱出を感じさせられるからである。国境などなく地球全体に広がり、そして循環する海。山と対比的に描かれる海に含まれる動的なイメージが、かすかな希望を感じさせる。だから、ツルオが死んでからタップが家族に迎えられることに、循環する海のように共同体が連鎖する様がそっと託されている。タップを演じた松井周の演技も印象的で、歯切れ良く冷静な台詞回しだからこそか、住人に対するツッコミが妙なおかしみを生んでいた。彼が入ったことで、家族はこれからも楽しく過ごしていけるかもしれない。
ここまで書き継いだことで、私はラストのヌルミの言葉を、積極的な意思を孕んだものとして受け取ることにする。世界にただ諦念することなく、状況を冷静に受け入れる。その上で、思考に代表される人間的な行動をできる範囲で起こしてみること。そうしながら死の時を待つ。今後、衰退する世界における人間の「グッド・デス」とは、このような生の在り方にあるのかもしれない。
INDEXに戻る
![]()
やさしい初夏のこぼれ日の中で、あなたは何を考えるのかな?
(批評文体ラボ1)
原田広美(舞踊評論家)
HEAD プレゼンツ『スワン666』
2018年6月19日(火)~7月1日(日) 会場 北千住BUoY
もう僕もだいぶ大人になったのだから、(実は僕は男ではないけれど)そうカチカチでなくても良いのではないか、と思った。飴屋さんが劇の中で演じた役の男も、メキシコの娼婦の前で立たなかったし。その前の場面が酷いよねぇと言っても、70年代では案外、刑事物のTV番組のソデなんかにも、そういう場面があったような気がする・・。その頃は、そういう性を怪しく扱う場面づくりが、きっとカッコいい時代だったんだ!(興奮するしネ、まだ子供だったから刺激が強くて。 まだ80年代の熟れ線に至る前でしょう。)――つまり女が番号札を下げて、男の前を廻ります。どの子がいい? 80年代は、東南アジアで、そういうのやってたっけ?(その後、地球規模でエイズがあったんだ)
絵:中原昌也
今回の劇、チリのロベルト・ボラーニョ(1953~2003)の『2666』から想を得たようだけど、これは死後出版だそう。ではいつ頃、書いたんだろう? チリやメキシコでは、そのような娼婦選び、今もよくあるのか分からないけれど、2666だから未来小説なの? だけどメキシコとアメリカの〈国境〉のトンネル、トランプのせいで注目されたから(トランプの発案は壁だったけど)、コンテンポラリーな話題ですね。
そして「2」は「鳥」みたいだから、それを「スワン」にしたのが飴屋さんのアイディアなんでしょう? とてもお洒落。それと関連するように、劇の始めと終わりで、鳥の声が問題になっていた。どうも水鳥よりも、高い声で小鳥みたい・・、と。そしてセックスが「おセックス」になっていたのも、飴屋さんのお洒落感覚だったのでしょう。それは、もう最後辺りの場面でしたが・・。
出演者は、4名。その中で黒い服の飴屋さんは、以下の3人を迎える教授のイメージか? また原作では、実在しないドイツの作家アルチンボルデイを追う4人だが(男3人、女1人の四角関係)、飴屋さんの他は3人で、今回のために集まった出演者と聞きました。始めに膝をついてニジリ歩くように登場したのは、緑の半袖上衣のサッカー・ウェアの男(山縣太一)。もう1人の男は、白Yシャツに白タイツ、つまりスワンだろうという男(小田尚稔)。そして首に番号札をかけた若い女性(加藤麻季-MARK)の、計3人。彼女は赤い上衣に白いスカート、サンダルにはセクシャル感があったけど、素朴な感じでした。そしてウクレレみたいな大きさの楽器も奏でた。いつもは音楽畑の人を女優さんにしたわけだ。だから全体に、いわゆる演技力で見せる劇とは違います。出演者達は、ピンマイクを使用。
ここでちょっと閑話休題、ねぇ「疲れたよ、カチカチは」とは言うものの、あの原田広美の、いつもの内容が詰まった上に、気品があって慎ましく?、シリウスみたいに輝きながら、どこかでフワリと愛がこぼれるような文章、大好きじゃん、やっぱりあれがいいねぇ、と誰か言ってくれますか? 誰かが『ぼくと観光バスに乗ってみませんか?』(4月に逝去した森田童子の曲です、気づいてネ)、と僕(私)を誘うなら、今です! 36歳以降の僕は、博覧強記で突っ走って来た! その理由は、僕の筆歴をよく知っている人だけが、気づけるのかな~♬?
そして話は変わりますが、批評も、大学の先生とか、博士とか、修士とか、男がいいとか、いつまで続くのでしょう、もう終わりそうな平成のこぼれ日の中で・・。僕は、時代と寝るような思想はそう好きでなく(それに真剣に取り組んできた人達、許してネ。僕も、ソコソコは押さえてマス!)、総合力のある本(これまでは3冊)で勝負して来たのだけれど。でも、もっと評判が立たなければ、やはり何とも言えないね。
ただし、たとえば坂口安吾は、東洋大学卒である! しかし新潮文庫でよく売れた太宰治と夏目漱石は、やっぱり東京大学卒(太宰は中途で除籍)である。くやしいな~。だけど、そういう勉強っていつのこと? それに親の平均年収と子供の学歴は、ほぼ正比例するんだって。この前も放送大学のテレビ授業で、そのことをやってたヨ! それに何十年も(20年とか30年とか)前に、少し余分に勉強したからって、それが何だって言うんだろう? 中身のある本は少ないのに、著者の肩書の権威で選ぶ人も多いし(難解で下手な翻訳ほど、日本ではよく売れるとも言うしね)、肩書が弱いと中味が良くても無視かぁ。あるいは読む以前に無視でしょう? いいと思っても自分より学歴が下のヤツを褒めたくないし、でしょう? くだらないのよね、専門性や、それをやる感性や才能は、そういうこととは別なんですけどね~。それで世の中、進まないわけでしょう。得してる人達だけが集まって、絡み合って、停滞です。
ただし僕がこの文章で、飴屋さんの『スワン666』について何が書けるだろうか。本来は演劇ではなく、舞踊評論家だし(OM-2は、けっこう書いて来ましたが)。だがダンスを経由しても、元々は舞踏Butohから来た批評家だし、暴力やセックス(セックスなんて言葉、この文章で初めて書いたヨ。これまではエロティシズムと書いて来たけれど、それは美学だったんだネ。)の問題なら、まあ何とかなるさ。「何だかんだ」で僕は、フロイトが源泉にあたる「心理療法家」でもあるし。とにかく飴屋さんのこと、ずっとどこかで尊敬して来たから、少し甘えさせてもらおう!
上演場所のこと、書くの忘れてた。北千住のBUoYの地下、もともと雑多な感じがたまらないですね。奥の奥に、銭湯だった名残の浴槽、水色のタイル張りだったっけ。今回は、入口側の三方に客席を作っていました。客席途切れた下手側に水槽がある。後で、飴屋さんがそこに落っこちて苦しむのですが・・。水槽の向こうの陰の音響コーナーでは、中原昌也の生演奏。舞台として使用されている床面はやや縦長で広く、全体に大変に雑多です。
まず沢山集められたマネキンが解体されて、ここかしこにある。下手一番奥には、脚ばかりが集めて立ててある。またマネキンのトルソの上の頭部に布がかかっていたり、それから鉄筋の大きな柱に絵(by中原昌也:この批評文に添えられている絵です)が貼ってあり、床面にある2つのマンホールも開かれている。そして観客席の脇のベッドの上に椅子が上げてあり、そこにまず赤い服の女の子、次にスワンが現れた! 誰かが「うるめ?マラソン」を走り(ヤン・ファーブルにも似たのあったけど、アングラでよくある〈走る〉演出だね、スワンが走ったんだっけ?)
また緑の男がボールを蹴ったり、飴屋さんは銀色のバットで、そこかしこを殴打し、最後には羽枕に向かって殴打に次ぐ殴打! そして『スワン666』だからこそ? 羽枕の布地が打ち破られ、白い細やかな羽がドドッ~と飛び散る! これについては、後でも触れたい!!
全体では、最後の方の「女だからと連続的に殺害されて行った300余人」と、「ひよこを雄雌でより分けて、卵産めない雄という理由で殺される話」が、互いにリバース。それから「立たなかった飴屋さんが演じる男」と、「発情するのは対象となる女のせいではなく、自分の中に充満していたエネルギーのせいなんだ、という男」が、リバース。舞台の中に設定された場所は、メキシコのサンタテレサ。アメリカへのトンネルがあるという国境の町、「命が軽い」町なんだって!! メキシコに行ったことのある知人によると、警察官さえ信用できないようなことも本当のようで・・。
でもメキシコっていえば、アルトーを思い出す。しかしトンネルで王子様と御姫様が出会う話は、よくは分からない。国交や両国の関係性にかかわる問題なのかな? おセックスをしなければならないらしいのに、ペニスを切ってしまって・・、それはもう大変なことになるわけでしょう。こういうのって悪趣味的に際立つための手口にも、僕には思えてしまうのだけど・・。マジでね、性転換とかと関係あるなら、それもそれでしょうが・・。しかし山場の印象が強いほど劇全体(元は小説でも同じ内容なのか)の印象も際立つのだから、これもいいか? この行為自体に託された比喩は、僕にはよく分からなかったけれど(トランプの言動にメキシコ側は怒っていて、もう繋がりたくないです、とか?)、その「破壊的な衝動」自体については、下記で触れることができると思う。
では最後の、僕の批評文のツメにゆきましょうか? これは、やはり劇全体で、「エロス(性の欲動)とタナトス(死と攻撃の欲動)」という、「リビドー・レベルの本能的な欲望と〈衝動〉」を扱っているようだ。それで見ていて、ズッシリ来るんだね。「欲望と〈衝動〉」と書いたのは、命の根源に交わるエネルギーとしての衝動に、「欲望や欲動」よりも、「もっと〈純潔なイメージ〉」を与えてあげてもいいんじゃないか、って思うからなんだ。でも「エロスとタナトス」が大枠のテーマだというのは、舞踊に近い。筋立てというより、コラージュ的な展開だから? 最近は、批評におけるジャンル分けって、ダサいんじゃないの? の声もあるけど、まあポスト・モダン以降の作風なんだネ。前衛的です!
また、もう一つ内容の奥に入ると、まず雄のひよこの圧殺と、サドの『ソドム百二十日』のような残酷極まる女性達の殺害。この女性達は、始めの娼婦のイメージとも隣り合わせになっていた。だからその殺害は、「エロスとタナトス」が〈混濁したままの発情〉だ! またペニスの切り落としは、「タナトス(死の欲動)」としての〈自傷〉だろう。
そして、「あらかじめ渦巻いている欲望(欲動)を持つ男」は、それをエロスとして発情させるつもりのようだけど、「カチカチでない場合」も、飴屋さんが演じた男は、あれだけの「強い衝動」でバットを振り回した! その攻撃の欲動は「暴力的」で、羽枕の殴打から溢れる羽は「美的」だった! それはアウト・プットされた暴力的なセックスみたいでもあったけど、とにかく飴屋さんの演出には美学がある。それで、やっぱり「暴力(タナトスの攻撃性)とエロティシズム」になったんだネ!
それから最後になるけれど、「(対象に関わらず)、あらかじめ渦巻いている欲望・欲動、そしてそれをさし止めているもの・・」というような、分析チックなセリフには痺れた。でも僕は、「エロスとタナトス」の強い「欲動」(やはり僕は、それを「衝動」とも書く)が、目を覆いたくなるような結果ばかりを作らないことを願いたい。それはともかく、「根源的な命のエネルギーのあり方の問題」なのだから・・。やさしい初夏のこぼれ日の中で、あなたは何を考えるのかな?
(2018年6月20日、北千住BUoY)
INDEXに戻る







