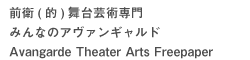©Jean Couturier(写真はケ・ブランリー美術館での上演)
1. レヴィ=ストロースの仮説
SPAC[静岡県舞台芸術センター]による『イナバとナバホの白兎』(構成・演出=宮城聰/台本=久保田梓美&出演者一同による共同創作)は、フランス国立ケ・ブランリー美術館より開館10周年記念として委嘱された作品である。非西洋的な芸術に光をあてるケ・ブランリー美術館の、文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースの名を冠した劇場は、2006年に宮城聰が『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』でこけら落としを行った劇場だ。この劇場での上演に先駆け、ふじのくに⇔せかい演劇祭のプログラムとして、静岡・駿府城公園の特設会場にて『イナバとナバホの白兎』のプレ上演が行われた。
本作は、「因幡の白兎」の類話がアメリカ先住民の神話に見られることから、アジアの大陸部に起源をもつ神話の一体系があり、それがまず日本に、続いてアメリカへと伝わったのではないか、というレヴィ=ストロースの仮説に基づき、そのいまだに発見されていない起源となる物語を創作するという試みである。演出の宮城聰はこの作品を、第一部・イナバ編(因幡の白兎)、第二部・ナバホ編(アメリカ先住民・ナバホ族の神話)、第三部・SPAC創作による物語という三部構造にし、さらに、台詞づくりも含めて出演者たちが稽古を重ねながら作っていく集団創作の手法をとった。
2. イナバの白兎――双子なのか?
駿府城公園に設置された特設舞台は鉄骨の骨組みがむき出しのシンプルなものだが、そのために緋毛氈を敷いたような床一面の赤さが目に入る。赤土にも血にも似た赤。舞台後方には楽器類が弓なりに並び、中央をカーブした綱が横断する。まず宮城が客席の前に現れ、レヴィ=ストロースの仮説と三部構成について観客に説明している間に、舞台には6人の俳優が横2列に座り低い声を立てている。下手の黒い台には客席を見回す男。宮城が去ると、棒を持つ4人の俳優に囲まれて兎が登場し、祭囃子のような音楽が始まる。
音楽は生演奏で、演奏するのも俳優。本作では、役の動きと台詞を別々の俳優が行う、いわゆるムーバー(動き手)/スピーカー(語り手)の手法が用いられているので、俳優は場面によって演奏者にもムーバーにもスピーカーにもなる。特に今回は、俳優たちが同じ赤の衣装で、しかも第一部と第二部ではムーバーは仮面を付けているため、誰が何役であるといった役柄と俳優の関係を固定して認識することは難しい。しかし、生演奏・仮面・語りということだけなら、神楽となんら変わらないだろう。実際にイナバ編は表面的には神楽のようにも見える。けれどこれが神楽でないのは、ムーバー/スピーカーの手法が、物語が含んでいる社会構造やそれを支える文化の力学をあぶりだすために使われているからだ。
たとえば、まず兎が海を渡るためにワニを騙して並ばせる。作り物のワニを背負った俳優たちが腹ばいでぞろぞろと横一列に並び、囃子の音に合わせて兎が渡り終わったところで騙されたことを知ったワニは兎の皮を剥ぐ。すると八十神(数多くの神。複数の俳優によって演じられる)と弟オオナムチが一列に並んで兎の脇を通りながら、一人ずつ「海の水を浴びて乾かすといいよ」と同じ言葉を投げかけ、オオナムチだけが「真水で洗ってガマの花粉をはたくといいよ」と別の言葉をかける。この一連の場面では、兎とオオナムチの台詞は演じ手(ムーバー)とは別の俳優(スピーカー)によって語られるが、ワニと八十神の台詞は、演じ手自身が語るというように、役におけるムーバー/スピーカーの関係を物語の中で転調させていくことで、人物の社会的地位や相互関係を表していく。つまり、ワニや八十神においてムーバー(身体)とスピーカー(言葉)を分けずに演じるのは、彼らが身体と言葉のズレ、すなわち自分の行動や発言の矛盾を自覚しなくてよい者――マジョリティであるという現れであり、一方、兎やオオナムチは身体と言葉のズレを常に自覚せざるを得ない者――マイノリティであるがためにムーバーとスピーカーとに分かれて演じられているといえよう。このようにムーバー/スピーカーの手法は、言葉と身体、意味を無自覚に一致させている言語/身体感覚を揺さぶることでで、その状況を作り出す社会の構造そのものを明らかにする。
この後、八十神とオオナムチが再び一列で歩きながら、ヤガミヒメに次々と花束を渡していく場面が続く。本作では動きや仕草が様式化されているため、観客は八十神+オオナムチの人数分、同じ動作を繰り返し見ることになる。しかも個々の動作だけではなく、一列に並び同じ動作を繰り返すというシチュエーションそのものが繰り返されることで、行為の反復が強調される。これらの反復に加え、オオナムチ役は舞台上で別の俳優に仮面を渡すというリレー形式で複数の俳優によって演じられることから、オオナムチ役の反復性も読み取れるだろう。そもそもオオナムチの仮面は八十神とは造形が異なるが、動作において際立った違いは見せない。だとすると、宮城がこれらの反復によって示すのは、わかりやすい異同ではなく、むしろ同質に見えるものの中にある差異なのではないだろうか。
この反復性は音楽においても顕著である。たとえばナレーション部分では、高い囃子の音色が一転して声明のような低いトーンに変わる。この囃子と声明が交互に繰り返される音とリズムの反復は、常にストーリーのその先を欲望する心理を抑え、目の前の舞台で起きている一つ一つの出来事に観客の意識を立ち戻らせる。そして物語とは一つの塊ではなく、出来事という要素の連なり、要素が組み立てられることによってできているという物語の構造そのものを示唆するのである。この反復とともに欠かせない要素に笑いがある。次にオオナムチは八十神に騙されて楔(くさび)に挟まれ死ぬことになるが、その場面は上半身裸の俳優がガシっと抱き合うことで楔を表して観客の笑いを誘う。イナバ・ナバホ編ではこのような笑いを随所に入れることで、劇的な場面を脱力させて、神話が英雄譚となることを避けるのだ。笑いはオオナムチを英雄には変えない。このように宮城は神話をさまざまな旋律が反響しあう協奏的な交響曲ではなく、同じ旋律が転調しながら反復していく対位法的なカノンとして描くのである。
さて、死んだオオナムチは母親の助けにより生き返り、根の国へ行くように言われ、根の国でスサノオから娘を娶らす条件として試練を受ける。一つ目は蛇の室に閉じ込められること、二つ目は草原に放った矢を取ってくること。前者はスサノオの娘に助けられ、後者は草原に火をつけられるも2匹のネズミに救われる。こうして試練を乗り越え、スサノオからオオクニヌシという新しい名前をもらい、弓矢と琴と娘とともに地上に戻り、スクナビコナに会い国造りを始める。これで第一部は終わる。
ここで一つの疑問が残る。それは第一部では時折、台の上の男が「兎」「気位の高い渡し手」「くさびの試練」など、そのとき舞台で起きている出来事のキーワードを半紙に書いて掲げていたことだ。このキーワードはレヴィ=ストロースの著作の中の言葉でもあり、ある神話の素材――「神話素」を提示しているようだが、その中にあった「双子なのか?」という疑問形の言葉。それからオオナムチと兎が向かい合い「ぼくたちって双子?」という『古事記』にない場面の挿入。これらは何を意味しているのだろうか?
3. ナバホの神話――旅する双子
ナバホ編になると太陽が沈んだかのごとく舞台は一気に暗くなる。イナバ編では綱の手前がムーバー、奥がスピーカーだった配置が反対に入れ替わる。綱一本で反転する世界。そしてナバホの歌――それが言葉なのかもわからない耳なじみのない歌声が物語の言語性を超えて闇とともに迫ってくる。その闇の中から浮かび上がるのは大きな丸い仮面の双子。他の登場人物もアメリカ先住民の仮面を連想させる大きな仮面を付けている。
双子は父親探しの旅の途中で、蜘蛛女に出会い身を守る呪文と太陽が父親であることを教えられ、呪文によって海を渡り、太陽の家に行き、太陽から自分の子か確かめるための試練を与えられる。この呪文というのが「…花粉になる」という歌で、すでに水と花粉という兎との類似点が見られるが、イナバ編とナバホ編ではその表現方法が正反対といえる。ナバホ編の登場人物たちの動作は、その場での足踏みや身振り・手振りなどが主で、空間的な移動があまりない。たとえば、太陽が双子を放り投げるときには、太陽はその場で何かを放る仕草をし、双子はその場で体を傾けるといった具合だ。しかしその代わり、語り手による類まれな歌声が、旅する双子の空間の変容を現していく。旋律が反復し転調していく歌声――ナバホ編でも宮城によるカノンは通底しており、行為もまた反復する。試練は反復の連続だ。まず山の棘に東西南北4回投げられ、次に海で凍えるところを前歯が目立つ大きな仮面のビーバーが繰り返しこすって温め助ける。最後は蒸し風呂で熱せられるが太陽の娘によって助けられ、太陽が「参ったか?」と言う度に、双子が「あーうん、いえ」と真っ直ぐ縦に出した掌を返して答える、というやり取りが繰り返され客席から笑いがこぼれる。そもそも掌を返すという動作は反復そのものではないだろうか。こうして試練をクリアした双子は、太陽から地上で怪物を倒すための弓矢と、「水から生まれしもの」「もののけを倒すもの」という名前と、太陽の息子に相応しい新しい顔(仮面)を授かり、ナバホの物語は終わる。

©Jean Couturier(写真はケ・ブランリー美術館での上演)
かくしてナバホの物語を見終えた観客は、宮城が最初に説明した二つの神話の類似性を思い浮かべ、イナバの物語を頭の中で反復することになるだろう。どちらの神話も、旅をし、途中で導き手となる女性に出会い、水を渡る困難を経て、太陽(または、それに準ずる人物)に会う。太陽から試練を与えられ、娘とネズミ(または、それに準ずる動物)に助けられ、武器と名前をもらい、地上の平定に向かう。しかし両者には、それを行うのが双子か否かという決定的な違いがある。先ほどの「双子なのか?」という疑問はここに結び付くのだ。レヴィ=ストロースの仮説によれば、元となる神話が遅く着いたアメリカの方が日本よりも神話の要素間の結びつきが認めやすいという。つまり、日本では時間の経過とともに、双子とその試練という要素の組み合わせがバラバラとなり、水を渡る困難は兎、試練はオオクニヌシ(オオナムチ)、地上の平定はオオクニヌシとスクナビコナに分かれてしまったということではないか。遡れば、兎・オオクニヌシ・スクナビコナは双子であった、のかもしれない。
だからイナバ編とナバホ編をそれぞれ独立させ上演したのは、二つの文化圏の表象イメージの違いを印象づけるというより、この二つの神話が同じ要素でできていながら配列が異なることでストーリーの表層が違って見えてくる――あえて言うなら平行構造と垂直構造――という物語の構造を見せるためだったといえよう。しかも二つの神話を綱により対称関係に置くことで、対比させるだけではなく、二つの物語によって生み出される一つの循環、太陽の運行による昼と夜という一日のサイクルも作り出し、人間の営みの絶えざる反復と再創造をも表すのである。
「神話」にはイデオロギーの道具として利用される側面がある。レヴィ=ストロースは「神話とは何でしょうか?」と尋ねられ、次のように答えている。「もしあなたがアメリカ大陸先住民の誰かに尋ねたとしましょう。そうすると彼はきっとこう答えるでしょう。それは人間と動物がまだ区別されていなかった頃の物語である、とね。この神話の定義は、私には、なかなか興味深いものに思えます。」(クロード・レヴィ=ストロース、ディディエ・エリボン『遠近の回想』竹内信夫、みすず書房、1991年、248頁)つまりこういうことではないだろうか――神話とは唯一無二の歴史を証明したり、血統の純粋性を担保したりするものではなく、ましてやナショナリズムを補完するための道具でもない。私たちがある神話を知っている時点で、その神話は何らかの方法で記録された、その偶然の一つに過ぎない。その記録にいたるまでに、イナバとナバホの途中の物語もあっただろう。イナバの物語も、起源の物語が「因幡の白兎」になるまでにいくつもの反復と転調があったはずだ。しかし、その途中の物語を知ることは不可能である。だから宮城は、イナバとナバホというベクトルの異なる二つの物語の反復と転調を示すことで、その構造を生み出す要素をつまびらかにし、神話の構造を開示する。宮城が描く神話は、英雄神話や建国神話ではない。要素によって配列された物語――詩と身体の組み合わせによって転調し得る多様性に開かれた物語――それが二つの神話の起源に迫る、SPACにより再創造された神話なのだ。
4. 普遍の神話―― 一人になる双子
第三部の前に、レヴィ=ストロースの顔写真を貼った人形が現れ、舞台上にいる俳優たちに向けて『月の裏側――日本文化への視角』(レヴィ=ストロース、川田順造訳、中央公論新社、2014年)の「因幡の白兎」の一節が読み上げられる。内容は冒頭で宮城が語ったことと同じだが、今回の作品の一番外枠にいた仮説の主であるレヴィ=ストロース本人が作品内部に入り込み、レヴィ=ストロースの仮説を反復した宮城聰の仮説をさらに反復するという、裏と表、外と内とがわからない構造へと導かれていく。
第三部は柔らかな打楽器の音から始まる。ムーバーは簡素な生成りの服で仮面も付けない。舞台上の綱もなくなり空間の基軸が一気に開かれ、ムーバーとスピーカーの位置も流動的になる。スピーカーは「ぼくたち」と語るが、双子のムーバーは女性で、栗毛のおかっぱ頭に表情のない二人はどこか無性的な雰囲気を醸し出す。これまでの仮面姿から一転した装飾のない容姿がかえって抽象性を強め、地域や時代に限定されない人物像を可能にしたのだ。双子は片手に棒を持ち、父親探しの旅をしていて、「けっして死なない老婆」に会い、そこで「昼と夜とがちょうど同じ長さ」の日から一年間、穀物の育て方、狩り、木の実を採ることを学ぶ。農耕と狩猟採集を学ぶというエピソードは、それが人間の営みの基本的な技術で、かつ太陽の運行とともにあるということを物語るものだろう。しかし双子は「退屈」を覚え、父である太陽に戦いを教わるために旅に出る。途中で「大きな水」に阻まれるが、「大きなケモノ」(俳優はヒトの姿のままで手に目玉を持つ)を騙して渡ったため、双子の片方はケモノに連れ去られ、残った一人で太陽のところへ行く。SPAC編の試練は、太陽の妻に殺されかけ、木の股に挟まれ、雪を取ってくるという三つで、いずれも太陽の娘によって助けられる。特に二つ目の試練では娘が小さなケモノに頼み木を齧って救い出す。この小さなケモノも大きなケモノ同様、ヒトの姿に前歯がついただけのもの。このように第三部でヒトとヒト以外の生き物の姿に明確な違いがないのは、多様な「人間(ヒト)」のあり方を表すためではないだろうか。第一部、第二部、第三部と物語を反復することで見えてくる差異。この差異を多様性ということもできよう。だからこそ第三部では歌と演奏はより一層複雑なパターンをもって反復と転調のカノンを奏でるのだ――一つの物語では埋没してしまう小さな差異、老婆や娘、ケモノというマージナルな存在を見逃さないために。
さて、太陽に認められた若者(双子の片割れ)は、太陽から弓矢と火を司る太陽の娘を与えられ地上に戻る。ここまではイナバ・ナバホ編と同じだが、ここから柔らかな衝撃が訪れる。――弓を手にした若者は、なぜかわずかに不安と戸惑いをみせ、捧げ持つ弓の弦を何気なく指で弾くとパッと目を輝かせる。そうして太陽に「戦(いくさ)の道具を歌と踊りに用います」と宣言し、弓で大きく弧を描き静かに舞う。武器が楽器となる瞬間――武器を捨てるのではなく、ヒトやケモノを殺す道具が美しい音を奏でる道具であったということに気づく瞬間――戦いは祭りに転調する。しかも指先がただ弓の弦に触れるという、目的なき動作が意志を芽生えさせる、ささやかでありながら大いなる転換。物語を振り返ってみれば、繰り返し出てくる棒も、楔も、太い綱も、すべては楽器となる可能性を秘めていた。一本の棒、一本の糸で音は生まれる。演劇的表現では、棒はいろいろなモノに見立てられる。しかし宮城がここで行ったのは棒や糸を見立てることではない。モノはモノそのままで、人の手の動きによって目的が変わるということだろう。触れるわずかな指先が変えるのだ、戦争を音楽に。

SPAC『イナバとナバホの白兎』第三部
5. 宮城聰の実験――出会う双子
若者による悠久とも思える静かで美しい弓の舞に、これまでの登場人物たちが舞台に現れ「天の弓矢を手に取りて、燃える火のなか舞い踊る。天の弓矢を手に取りて、弦を弾けばたえなる楽の音」と、一緒に歌い出す。太陽の娘がもたらす火は野原を焼かず、舞い踊る者を照らすだろう。弓も火も、戦争という暴力ではなく踊り歌うためにあるということに気づいたとき、第三部は神話の起源の創作という枠組みを遥かに超えて、神話をさらに反復させる終わりのない始まりの物語、あらゆる可能性に開かれた普遍の物語となるのである。
そしてもう一つの衝撃。他の登場人物とともに連れ去られた双子が戻ってきて、若者との再会が果たされる。しかし若者は喜ぶ前に戸惑いにも似た不思議な表情を浮かべる。それは初めて鏡を見たときの表情――双子とは、互いが互いの反復だったのかもしれない。失い、反復し、再創造される世界。弓を楽器に変えた指先から、双子の再会から、若者は初めて自分自身と出会うのだ。
宮城作品とは、常に「「自然や他者をコントロールしたい、支配下に置きたい」という欲望のもとに研ぎ澄まされてきた」2500年間の西洋の強い演劇を解体する試みである。だから20名以上の俳優が出演する大規模な舞台でありながら、スペクタクルに溺れることがないのは、表現方法それ自体が暴力や力を欲望することに対しても絶えず自覚的であるからだろう。集団創作がどれほどの時間と労力を費やすものであったかは想像に難くない。しかし、神話を西洋個人主義的な単一体の物語ではなく、大勢の名前を与えられないもの、小さなもの、失ったものの集合体の物語とするために、集団創作(プリコラージュ)が必要だったのではないか。それは長年同じ俳優やスタッフと、「反復」してきた集団にのみ可能なことである。宮城は、言葉を意味の奴隷にしない。身体を力に回収させない。しかも『イナバとナバホの白兎』では、モノさえも人間に隷属させないのだ。宮城聰が描く神話は、「人間と動物がまだ区別されていなかった頃の物語」からさらに深化した「人間とモノとがまだ区別されていなかった頃の物語」と言えるのではないだろうか。『イナバとナバホの白兎』は、レヴィ=ストロースの仮説に対する応答であると同時に、レヴィ=ストロースの仮説を使った宮城聰による演劇的な実験である。その実験において宮城は、観念ではなく、身体を通じて、モノを通じて――武器を楽器に、戦争を音楽へと転調する、その可能性を証明したのだ。
『イナバとナバホの白兎』演出=宮城聰/台本=久保田梓美 & 出演者一同による共同創作/音楽=棚川寛子/空間構成=木津潤平/照明デザイン=大迫浩二/衣裳デザイン=高橋佳代/音響デザイン=加藤久直/美術デザイン=深沢襟/出演=赤松直美、阿部一徳、石井萠水、大内米治、大高浩一、加藤幸夫、榊原有美、桜内結う、佐藤ゆず、鈴木真理子、大道無門優也、武石守正、舘野百代、保可南、寺内亜矢子、野口俊丞、本多麻紀、牧山祐大、美加理、三島景太、森山冬子、山本実幸、横山央、吉植荘一郎、吉見亮、渡辺敬彦
|