 |
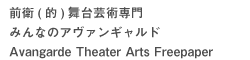 |

![]()
仮象としての山羊——akakilike『捌く』公演評
呉宮 百合香(ダンス研究)
akakilike『捌く』
2018年5月01日(火) 会場 d-倉庫
©Kai Maetani
何かの拍子に均衡が崩れかねないような、そこはかとない“やばさ”が立ち込める。 京都を拠点に活動するakakilike(主宰 倉田翠)の初東京公演がd-倉庫で行われた。1日のみ3回公演という、ハードなスケジュールだ。1987年生まれと比較的若手でありながら、年齢もバックグラウンドも多種多様な男性10名を巧みに統率し、さらにベテラン寺田みさこを大胆な形で使う振付家倉田の構成力と度胸には目を瞠る。
舞台中央奥、縦に置かれた長机の上で、6kgの肉塊を枕に横たわる山羊頭の女。そしてそれを取り巻く10人の男、彼らもまた一様ではない。ある者は舞台の外周を歩き続け、ある者は群をなして机を囲み、またある者は常に孤立してゆるい調子で喋り続けながら時折野球バットを振るう。複数の実在の事件を元にしているとあるが、その詳細が明かされることはなく、決して説明的ではない演者間の関係性は観客のうちに様々な連想を呼び起こす。
随所にユーモアも効いているが、作品全体の通奏低音は不穏さであり、えもいわれぬ暴力の気配だ。なにか暴力沙汰が繰り広げられるわけではない。しかし低く設定された入り口をくぐって舞台空間に集まってくる彼らが、何を背景に抱えているか——“外”で何をしてきたか——わからないような得体の知れなさをまとっている。
「みんな一緒で、どうやってソロになるか。男性10人のソロダンス作品。」という惹句が示唆するとおり、この作品の軸となるのは個と群の関係性である。男たちは皆ゴツゴツと歪で、群像にこそなりはすれ、均質的な集団にはなりえない。皆で机を囲んで佇む、そんな静かな場面でも、音に合わせて微かに体でリズムを刻んでいる者がいる。彼らは「演技」では語らない。所々に挿入される台詞も、その台詞自体は固有名を含む具体的なものだが、断片的で文脈を欠いているため、物語の構築には寄与せず、ただ特定の雰囲気を作り出すのみである。彼らをキャラクターづけるのは、演劇的な言動ではなく、その身体存在そのものだ。過呼吸、足音、震え、唐突な大声などが肉体を際立たせ、さらに彼らが観客に向ける眼差しが、彼らひとりひとりを浮き彫りにし、印象づける効果を生む。
そんなノイズを含んだ彼らの身体は、紅一点の寺田みさこの端正な身体性とは対照的で、更に言えば『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』『白鳥の湖』といった作中の随所に挿入されるクラシック・バレエの名曲が作り出す極度に非日常的な雰囲気とは全く性質を異にする(使われる楽曲が、観客が振付を想起するようなダンス曲ではなく、各幕の序曲や特定のキャラクターの登場曲など物語の情景を描き出す曲ばかりという点は、ポイントかもしれない)。どうにも似合わない音楽をバックに彼らが客席を見据える姿は、非常にシュールである。
そもそも彼らの見た目からして、ロードレースでも始めるかのようなスポーツウェアから、休日のお父さんのようなリラックスウェアまで、複数のトーンが入り混じっており、どのような集団なのかは判然としない。しかし演者間の組み合わせには法則があることが、特定のシーケンスの反復からうかがえる。互いに呼応し合うようにふっと関係が立ち上がっては、またさっと解消されて……そこに過剰なドラマ性や意味付けはなく、あくまで関係のみが浮き彫りとなる。
近年、演者個々人の“顔”が見えるグループ作品が少ないように感じる。イリュージョンを基本とする舞台芸術の魅力は——仮面の例えが示すとおり——リアル(現前)とフィクション(不在)の重なり合いにあるが、ある種の同質性や匿名性に回収されてしまい、演者の人となりのようなものが透けて見えてこない作品があまりに多い。影のない人物のように、浮ついているのだ。その点この『捌く』の演者たちは、作品世界の一部をなしながらも各々が際立っており、背景を持つ地に足のついた存在であることを感じさせる。
©Kai Maetani
ところで、彼らの中心にただ静かに存在し続ける「山羊」は何者なのだろうか。寺田みさこ演じる山羊頭の女は、時にゆっくりと体を起こしては横たわる体勢を変え、時に緊張をみなぎらせていた肢体を一気にだらんと弛緩させる。顔全体を仮面で覆った彼女は、男たちとは反対に、“匿名的”で“抽象的”な役割を意図的に演じている。
男の集団に囲まれて台の上にひとり横たわる女という構図は、性的暴行を連想させるかもしれない。しかし他方でこの山羊の面は「スケープゴート」、つまり特定の人間に罪を負わせて犠牲にするというもうひとつの見方を提示しているようにも思える。
やばいことは1人でやる。
誰が悪いかがはっきりしない「悪い」が1番悪い。
みんないつから、「大人」みたいになっちゃうの。
ユダヤ教では屠られる生贄の山羊と荒野に放たれる贖罪の山羊をそれぞれ選び出すが、さてこの山羊はどちらだったのか。最終場面、舞台上にひとり残った男が肉塊にナイフを突き立てるその瞬間、山羊頭の女はもうそこにはいない。それとも山羊は、悪魔の象徴か。
カーテンコールで、作中ではほとんど動かなかった寺田と振付家の倉田が、最後にナイフを振り上げた男に成り代わって、壁に手をついて踊り出す。そしてもうひとり、作品世界を持続させるかのように、客調が上がるまでバットの素振りをし続ける若い男。手を下すという決定的な場面で“終わらせない”——落着させない——ところに、良い意味の毒が効いている。
akakilikeは、来月6月22日から24日に再びd-倉庫で別作品『家族写真』(2016)を上演する。次回はどのような世界を携えて登場するのか、非常に楽しみだ。
INDEXに戻る
初体験
下島礼紗(ダンサー・振付家・「ケダゴロ」主宰)
ダンスの世界にいると、たくさんの「初体験」がある。当然、人生そのものが「初体験」の連続で構成されているのだと思うが、なかなかそれを日常から感じることは難しい。ゲームとか、ハロウィンとか、それぞれ様々な物事を用いて、刺激のある経験や非日常的体験を求めている。私にとってダンスや舞台(またはそこから生まれた新たなジャンル)は、そういう経験や体験に出会うことのできる手段である、と近頃は考えている。
「初体験」というのは、とても貴重なもので、同じ経験を積み重ねていくと、時に「マンネリ化」や「倦怠期」などというものを起こす。だから、風化してしまわぬよう、私にとって大切な「初体験」の一つとなった海外公演について、未熟な言葉ではあるが、ここに記させていただきたい。
昨年、 ハンガリーのブタペストとペーチで開催された「第5回ボディラディカル国際舞台芸術ビエンナーレ(5./BODY RADICAL International Performing Arts Biennial)」に参加させていただき、ソロ作品の発表と即興パフォーマンスを行った。私にとっては、これが初の海外公演であった。このフェスティバルへの参加のキッカケとなったのは、2017年2月に開催された「横浜ダンスコレクション2017」コンペティションIIにて、作品を発表し、「タッチポイントアートファウンデーション賞」をいただき、このフェスティバルへの参加の切符を得た。このチャンスを下さった、フェスティバルディレクターのBataritaさんに感謝の思いである。
今回、私が発表した作品は「オムツをはいたサル(Monkey in a diaper)」という作品である。この作品は、日本の著者、栗本慎一郎氏の著作「パンツをはいたサル〜人間とは、どういう生き物か〜」からインスピレーションを受け、創作したものである。この著書には、ヒトは裸のサルが余分にパンツをはいた生き物だと書いてある。ヒトはサルが裸になっただけだけではなく、パンツを履いてそれを脱いだり、脱ぐ素振りで雄を誘ったり、おかしな行動をシステマティックにとっている。そのことから、性行動・法律・道徳・宗教などを「パンツ」という表現に置き換えてヒトの行動を説明しているのだ。ソロ作品「オムツをはいたサル」は、この中の「宗教」の部分に主に着眼点を置き、1995年3月に日本の宗教団体「オウム真理教」が起こしたテロ事件「地下鉄サリン事件」とコネクトさせて創作した作品である。(2018年3月現在、オウム事件の死刑囚が東京拘置所から移送されたことにより、またもや世間を騒がせている) だが、海外での作品発表となるとここで大きな問題が生じる。そもそも「オウム真理教」や「地下鉄サリン事件」というワードは日本人なら多くの人が聞いたことのあるもので、内容についてもある程度のことは知っているだろう。しかし、海外の人々にこれがどれほど認知されているかわからない上、宗教への考えた方も日本人とは大きく異なることが想定される。であるならば、この作品をどう見せるか、ということがハンガリー出発前の大きな課題となった。作中に、プロジェクターでオウム真理教についての解説文を投影することも考えたが、それでは作品の本質よりもオウム事件の内容が先行してしまうようであまり良い方法ではないと思った。そこで、今回は作品をそのまま(海外仕様にはせず)持っていき、発表することを決意した。それによって、私の『身体と作品』の本質が見えてくるのではないかと考えたからだ。日本でこの作品を発表した際、『身体』よりもオウム真理教を取り扱ったことに対する反響が多かったように思えた。この機会に作品の内容(コンセプト的な部分)ではなく、下島礼紗という人間の身体をダイレクトにぶつけてみようという試みであった。そして、この試みは、私にとっての大きな発見や課題を得ることができた。
作品上演後、フェスティバル関係者や観客、共に出演したアジアのアーティストから様々な意見をいただいた。その意見は、私が踊る上で、大切にしたいと感じていることや、私の作品の全てに通ずるコンセプトなどに気づかせてくれた。例えば「ジェンダー」や「幼児性」、「母性」などだ。作品を通じて、私自身を見てもらえたように思い、このことは素直に嬉しかった。客席から、「作品を感じようとする力」を強く感じ、とても感動した。フェスティバルの関係者から聞いた話によると、ハンガリー人は、あまり作品のコンセプトを知ろうとはしないということだった。つまり、作者が考えたコンセプトや作品の正解よりも、作品を見て、その瞬間に自分が感じたことや考えたことを大切にするようだ。私はこれを聞いて、とても素敵なことだと感じた。観客として作品を観ることが、受動的ではなく、その作品に自分の意思を投じ、それも含めて作品として受け取るということは、コンテンポラリーダンスのような不確かなジャンルが今後普及していくために、とても大切なことだと思う。もちろんアーティスト達が高質な作品を世の中に提示することが大前提だが、観る側の意識が豊かになっていくこともとても重要なことだと思う。それを含めて言えば、今回の私の作品にはまだまだ未熟な部分がたくさんあった。観客がどの視座から作品を観るかわからないからこそ、油断はゆるされない。作者自身が一筋縄で作品を完結させてしまってはいけないのだ。作者は、様々な角度から切り込み、疑いをかけていかなければならない。例えば、コンセプト・身体性・必然性・意外性・全体のリズムなど、より自分のダンスを疑いながら進化させていかなければ、観客は退屈してしまう。言葉や文化の違う異国の地での発表だったからこそ、このことの気づくことができた。だが、これは、海外だろうが日本だろうが、変わらないだろう。そもそも人はそれぞれ違う感覚や考え方の中で生きている。だからこそ、より視野を広げて創作していかなければいけないという、大切なことを今回の経験から得ることができた。初の海外公演を経て、国によって言葉や文化は違うけれど、作品は国境を越えて舞台に曝け出されるものなのだと強く感じた。曝け出されることは、怖いことだが、同時にとても平等だ。だからこそ、国境を越えて、興味を持ってもらえる作品を創作していきたいと思った。どこまでも不確かなこのジャンルの中で、どう生きてどう楽しむか。今回の経験を経て、今後の活動に武者震いする思いである。夢はたくさんあるが、次なる目標は、私の主宰する〈ケダゴロ〉というダンスカンパニーの群舞作品を海外で発表する事だ。
余談だが、2016年頃から、私は、作品のテーマ(というか創作の軸に置くもの)に、政治・宗教・事件などをピックアップするようになった(上記で述べたオウム事件や、連合赤軍事件など…)。これにはちょっとした訳がある。2015年の終わり頃、急性肝炎になり、突然吐血。肝臓数値が8000まで上がっていたらしい(通常30〜40)。肝硬変になる寸前で緊急入院することになった。つまり何が言いたいかというと、すこ〜しだけ死際を経験して「死」という言葉を意識するようなった。人はそう簡単には死なないだろうが、簡単にも死ぬなと。そして何よりキツかったのは、入院中の絶食。もう家に帰ってご飯を食べれたらそれだけで幸せだー、と。テレビに映る美味しそうなハンバーグを見ていたら、一瞬ダンスのことを忘れた。と同時に、やっぱりダンスって生きていく上では不必要なものなのかな、と悲しくなった。そんな経験を経て、私は、世の中をもっと知りたいと思った。人生長くても80年前後、全ての事はわからないが、せめて自分の生きてる世界で起こっている事・起きた事は、なるべく多く知りたいと。突然終わりが来ても、後悔しないように。その為の手段が、私にとっては、ダンスや舞台なんだと思う。そして、これからも、世の中を知る為にダンスを続けていきたいと思っている。その中で、良い事でも悪い事でも、多くの「初体験」に出会い、常に生きている実感を持ち、ドキドキしながら活動していきたい。そんなスリルをたくさんの人と共有できたら幸せだ。
INDEXに戻る
天下泰平という夢の途中
藤原央登(劇評家)
流山児★事務所『オケハザマ』
2018年1月24日(土) ~ 2月4日(日) 会場 下北沢ザ・スズナリ
駿河の戦国大名・今川義元は2万5千人の軍勢を率いて、織田信長が治める尾張に侵攻した。迎え撃つ織田軍は5千人程度で、数の上では圧倒的な差があった。しかし織田軍の奇襲によって、今川軍は返り討ちに遭ってしまう。これが桶狭間の戦い(1560年)である。この戦いで、それまで東海道で広く影響力を及ぼしていた今川氏は凋落し、織田信長にとってはその後の戦国時代で存在感を高める転換点となった。
本作は漫画家・しりあがり寿の書き下ろし初戯曲である(脚本協力=竹内佑(デス電所))。静岡県出身のしりあがりは、信長に注目されがちな桶狭間の戦いを、同郷の義元の視点から描いた。とはいえシュールなギャグ漫画で知られるしりあがりである。忠実な歴史劇ではない。武将が群雄割拠する戦国時代は、劇半ばからテレビゲームに移行してしまう。これが劇の大枠であり最大のギャグなのだが、ほかにもあちこちに現代の社会・風俗ネタが盛り込まれる。加えて自由な歴史の見方に拍車をかけるのが、流山児祥による演出である(演出協力=林周一(風煉ダンス))。暗転と明転を何度も繰り返して行われるスピーディーな場転、舞台背景全体に投影される暗示的な映像、幾何学的なダンス。天野天街(少年王者舘)の方法にインスパイアされたような演出を駆使して、総勢29名の俳優を整然と動かし、劇にテンポを生み出す。そのような劇世界の中、役柄とコロスを兼ねる俳優たちは、大人数での活劇やダンス、さらには歌まで歌う。劇空間を俳優の数とパワーで埋め尽くす賑やかさで、まさに新春に相応しい娯楽作品に仕立てた。俳優、戯曲、演出が三位一体になって、混沌でかつ奇想天外な劇世界を一気に駆け抜けた。そうでありながらも、本作には劇の骨子がしっかりとある。一見すると史実とは関係のない劇世界は、現代の位置から戦国時代を見ることを強調する。そのことが最終的に、我々が生きる現代を批評する眼となって差し返されるからである。ハチャメチャな中から顕在化する知的な企みが、本作を高みへと押し上げたのである。 義元(井村タカオ)は権力と名誉欲に憑かれ、絶対権力によって天下の統一を目指そうとする人物ではない。天下泰平を夢見る理想主義者として描かれる。しりあがりはそのような人柄の表れを、義元が1554年に甲斐の武田氏、相模の北条氏と結んだ甲相駿三国同盟に見る。この同盟を東海地方全域に広げれば、東海道と中山道をぐるりと輪を描くようにつなぐことができる。劇中で「東海流通共栄圏」と名付けられた広域の経済圏が築かれると、そこをそれぞれの国の特産物や人が自由に往来することが可能となる。一国で経済を完結させようとすれば、天候不順などで作物が不足した場合に立ちゆかなくなる。その打開策として、最悪の場合は隣国との戦争につながる。恒常的に互いが互いの足らざる部分を補い合うことで、流血をもたらす戦を回避できる。まるでTPPのような経済圏を作った義元の狙いはここにあった。義元は「東海流通共栄圏」を完成させるため、尾張を攻略する必要があったのだ。義元が射程におさめる泰平の世は、日本国内のしかも東海地方であった。だが信長(水谷悟)が目指す射程はもっと大きく、世界各国と対等に渡り合うことによる日本全体の泰平を意味していた。この泰平を巡る弐人の認識の差が、本作では重要な意味を持つ。
義元の天下泰平の夢は、挫折するという悪夢となって彼を悩ませる。義元は連日の悪夢に襲われ、果ては信長に首を討ち取られる予知夢まで見てしまう(劇中、巨大な義元の人形が登場し、首が飛ぶシーンはスペクタクル的だった)。米をたくさん育ててそれを金に代え、そして多くの物品を買って民が豊かになること。武力に頼らない太平の世は、このような人間の在り方を、一国のみならず徐々に拡大させた時に実現される。これが義元の「東海流通共栄圏」思想であった。「文化的」に生きることを民にきちんと理解させ、忠実にその目的にまい進させる。切った張ったの世の中でそれを実現するには、義元自身の名声をより高めて、民から忠誠を尽くされねばならない。義元は「名声レベル」を上げようと努める。その努力はいつしか、ゲームの世界へと接続される。そのゲームは『信長の野望』(1983年~、コーエーテクモゲームス)ならぬ「義元の野望」。義元はゲーム内でのキャラクターのステータスを上げることに躍起になる。子供の教育方針を巡る場面で義元は、子供に懸命に歌を詠ませ、蹴鞠をさせ、自身の思想に基いて文化レベルを上げようとする。しかし戦国時代を生き抜くには強い身体が必要だと主張する妻・定恵院(坂井香奈美)は、剣術を習わせて武力レベルを上げようとする。手元のコントローラーでボタンを連打する両親に振り回され、子どもがせわしなく道具を持ち代える様子が可笑しい。桶狭間の戦いに備えた軍議においても、敵がこちらに寝返ろうとしている時は指が光るとか、相手のパラメーターが画面の右上に出る、あるいは噴き出しのように内心が頭から出るから、相手の作戦が丸分かりだと義元は発言する。それを聞いた側近たちからは、義元が異常者になったと見られる始末。義元の現実はゲームの世界にすっかり侵食され、それをクリアすることだけに執着してしまうのだ。ここにおいて劇の幕開けが、布団を被ってゲームに没頭する男の光景だったことは意味深である。これは何を意味するのか。まずは、義元がゲームのように戦を考えているということが指摘できよう。戦を嫌う平和主義者の義元が、現代の引きこもりの男と重ね合わされているということだ。1991年の湾岸戦争時、ミサイルが飛び交う戦火の映像が、まるでテレビゲームのようだと指摘されたことを思い出す。見方によれば、ロケット花火が飛んでいるような暗視カメラの映像を受容することは、同時代の世界で今まさに起こっている事柄との距離の遠さを強調する。そのことが、戦争という現実の虚構化や非実在性を抱かせると共に、そのようにしか受容できない身体とは何なのか。身体感覚のリアリティのなさとしても語られたのではなかったか。
では、本作は戦争のリアリティのなさを現代に重ねて描いた舞台だったのか。もちろんそうではない。むしろ、ゲームのように戦争を捉える感覚を徹底させ、そのまま突っ切ったところにこの舞台の真骨頂がある。そこに、ギャグ漫画家・しりあがり寿の独自性があり、ゲーム=現実世界の不条理なまでの徹底の果てに、現実への批評性が貌を出すのだ。本作を一段押し上げるのは、まさにこの点にある。劇にドライブ感を与えるのは、後半において信長もまたゲームをプレイしているという展開が見えてからだ。しかも信長は、義元よりも最新の攻略法を見出していた。義元は武力ではなく文化レベルを上げることが、この世界=ゲームをクリアする攻略法だと思っていた。しかし信長がプレイする最新の作品では、日本国内の小さな領主争いではなく、世界を視野に収める必要があった。そのことを表現するように、信長の陣にはクレオパトラ(竹本優希)やジャンヌダルク(橋口佳奈)といった世界の著名人と交流するシーンがある。子供の育て方を巡って妻とゲームのアプローチが違ったように、信長は世界を別の角度から捉え、その攻略法を見出していたのだ。義元がそんな信長に勝つためには、より最新の攻略法を見つけなければならない。義元はPCのアプリケーションを最新版にするごとく、ゲームのアップデートを試みる。しかし、99パーセントまではダウンロードできたものの、あと1%のところでフリーズしてしまう。それによって生じたバグの世界に義元は突入してしまう。バグの世界を抜け出そうと試みて、何度も義元は電脳空間からの着地を試みる。ところが突入した世界はことごとく、登場人物や場の状況がおかしな、バグが生じた世界である。パラレルワールドのような世界を、明転と暗転を繰り返しながらテンポ良く次々に切り返して見せるこのシーンは、本作のギャグ要素のハイライトだった。 義元は信長に首をはねられるという敗北の悪夢から何とか逃れようとして、ゲームの最新の攻略法を見出そうと奮闘した。それは、確定した自身の未来を何とか変えようとする必至の足掻きである。客演の井村(オペラシアターこんにゃく座)の演技がそのキャラクターに説得力を持たせる。ソフトながら確かな声量で歌を聞かせる一方で、いかにもお公家然とした優柔不断な義元を見事に造形した。そこからは、非武力による平和主義者として在ろうとする、貴族的な人間の悩みがにじみ出ていた。しかし運命は変えられなかった。先述したように、天下泰平という目指すゴールは同じでも、義元とは別の攻略法で世界を変えようとした信長に敗れる。井村が演じた義元像もあって、信長とラストシーンで対峙した時、私は義元=ハムレット、信長=フォーティンブラスに見えた。王家を巡る復讐譚に巻き込まれて最後に命を落とすハムレットは、ノルウェーの王子・フォーティンブラスに次のデンマーク国王の座を託す。その構図に、戦国時代における主役の交代が重なったからである。加えてこの覇者の交代劇は、現在に至るまで繰り返されてきたことに思い至らされる。時代が経るにつれて、天下泰平に至る攻略法は更新され続けてきた。と同時に、ソフトのインストールはいつも99%のところでフリーズし、失敗し続けてきた歴史でもあった。つまり天下泰平の解は21世紀の現在においても未だ見出せておらず、ソフトをアップデートしている途中なのだ。ここにおいて本作は、世界平和のために繰り返されてきた、攻略法のアップデートと失敗を巡る、人類の歴史を射程に収めることになった。ゲームのような混沌でかつ奇想天外な劇世界にリアリティを付与することで、現代に至るまでの歴史の重層性を想像させた。そして、いかに世界平和が困難であるかを、今を生きる我々を批評すると共に突きつけたのである。
INDEXに戻る








