 |
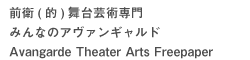 |

芝居を観る愉悦を与えたProject Nyxの代表作
藤原央登(劇評家)
Project Nyx『新雪之丞変化』
2020年3月19日(木)~29日(日) 会場 下北沢ザ・スズナリ
Project Nyxが女歌舞伎として上演した本作は、これまでになく俳優の演技で魅せるしっかりとした「芝居」に仕上がっていた。密輸の一大組織を作り、幕府とは距離を置いて独自の利権を確立した和蘭屋清左衛門。奉行役人である土部三斎(小谷佳加)はその利権に預かった挙句、清左衛門を罠に嵌めて死に追いやり、彼の妻を寝取った。15年前に両親を死へ追いやった三斎へ復讐するべく、女形の役者として中村座に潜り込んだ雪之丞(寺田結美)は、初の江戸公演で上方から上京する。三斎の娘・浪路(田上唯)と女盗賊・お初(加藤忍)の双方から好かれるという、雪之丞を巡る恋の鞘当てが絡まりながら、「長崎の敵を江戸で討つ」物語である。
©大須賀博
本作のひな型は、1934年から朝日新聞に連載された三上於菟吉の小説『雪之丞変化』。その後、多くの映画やテレビドラマ版が生まれた。2019年には、坂東玉三郎主演の『新版 雪之丞変化』で歌舞伎化もされた。派生作品の一つが、1988年に劇団め組プロデュースで上演された『新雪之丞変化-暗殺のオペラ-』(原作=三上於菟吉、作・演出=白石征)。本作はこれを下敷きにしている。め組の舞台では、花形女形の雪之丞を花組芝居の加納幸和が演じた。浪路も、当時は花組芝居に所属していた篠井英介が演じた。現代歌舞伎として創作されたわけだが、Project Nyxはこれを反転させて、女性が男性を演じる趣向になっている。もとよりProject Nyxの劇世界では、すべての役柄を女性が演じてきた。女性の華麗さと妖艶さを、メルヘンな非日常で包み込むエンターテインメント作品である。『雪之丞変化』という題材が義理人情に根差した時代物であるせいか、これまでとは異なって観る者の生理に響くエロスが感じられた。
©大須賀博
もちろんザ・スズナリ全体を使った、ショーアップされた演出がこれまで通りに踏襲されてはいる。中村座の大衆演劇の楽屋、マッドサイエンティスト風の土部三斎が住む欧風的な屋敷。そして中村座が上演する心中物(『曾根崎心中』『宇田川心中』)の劇中劇が演じられる場。これらを、大掛かりな3つのボックス装置を移動&反転させることで転換する。一旦、幕を引いて転換する間は、狂言回しやソロダンスで繋いで客を飽きさせない。さらにBUCK-TICKのロック曲をバックにした群舞が、カッコ良くてエロティックな和洋混交の世界へと誘う。今回はそういったエンターテインメント要素に芝居の内容がかき消されるのではなく、両者が補完しあっていた。それはまず親の仇を討つ孤高のヒーローという、日本人の深層に訴える優れた作品があってのことだろう。その底流に流れているのは、雪之丞を突き動かす原動力になっている愛情である。それは雪之丞への愛をまっすぐに向け続けた浪路と、雪之丞と浪路の間を取り持つような役回りを果たす男前なお初にも当てはまる。浪路に至ってはマクベス夫人のごとく、誤って毒の入った酒を飲んで死んでしまう。そういった愛の深さやもつれという本作のエッセンスを抜き取り、濃密な恋愛=心中物語を要所要所に散りばめている点は、白石征の戯曲にはない本作ならではの読みである。中村座の座員による、今にも心中せんとする鬼気迫る男女の光景。これに、雪之丞にすがり付く浪路の光景が連なるように対応させる。劇中、胡蝶の夢が引き合いに出されるように、恋愛とは虚構のような現実であり、その渦中にいる者にしか味わえない「夢」である。愛をフックに、虚構と現実の区別が付かず入れ子になった世界を生きる人間の行く末。心中シーンと雪之丞・浪路が地続きに見せることで、芝居もまたひと時の「夢」であることを追加的に意識させる。そのことによって、虚構と現実が互いに果てしなく映し合うという本作の核心を、強調して提示することに成功しているのである。
この入れ子構造が引き起こす非情な運命に、雪之丞はさらされてしまう。物語のラストで、三斎こそが雪之丞の父・和蘭屋清左衛門であったという真実が発覚するからだ。自分を罠に嵌めた小役人を殺害した清左衛門は、硝酸で顔を焼いてから顔相を三斎に似せる手術を施して逃亡。あたかも清左衛門が死んだように見せかけることで、家族の身に危険が及ばないようにしたのである。雪之丞が陥る運命は、ギリシャ悲劇に通じる。許されざる恋の「夢」から覚めるには、命を投げ出さなければならないほど深い代償をもたらす。それと同じように雪之丞は、愛と復讐心を一身に受け止める父親を殺すことと引き換えに、ようやく本懐を遂げるのだ。三斎に成りすましていた清左衛門は、どういう人格を生きていたのか。雪之丞は一体、誰を探し求めていたのか。雪之丞と三斎の関係性は、役を演じることやアイデンティティにまつわる巡る問題を含んでいる。そういった意味でも、舞台表象と作品内容とが合致して虚構と現実の入れ子構造を描く本作は、演劇を観ることの愉悦を改めて感じさせたのである。
©大須賀博
そこに芝居のできる俳優の魅力が、第三のピースとして全面に押し出されている。本作の最大の見どころは、ショーアップされたエンターテインメントに作品が紛れさせることなく、きちんと屹立させた芝居心のある俳優である。雪之丞を演じた寺田結美は、背が高く貫禄があるために着物が良く似合い、立ち姿だけで画になる。劇中劇である冒頭の心中シーンでは、男を一途に慕うけなげな女性を演じる。上方から江戸に鳴り物入りで殴り込み、瞬く間に一座の評判を江戸中に轟かせた女形、という役柄にまさに沿う。かと思えば、『宇田川心中』の主人公を演じた際には、打って変わって低く野太い声と恰幅の良い身体を活かして、見事な男っぷりを見せる。まさに変幻自在。宝塚で言えば男役と女役を一人でこなすような活躍で、作品を芯から支えた。そしてもう一人、盗みが手につかなくなるほど雪之丞に惚れ込む、お初を演じた加藤忍の芸達者ぶりも目を見張るものがあった。小柄ながらも空間に響き渡る力強い声を武器に、歌って踊って幕間を一人で持たせる。左の顎につけたホクロが、マリリンモンローのように妖艶でエロティック。雪之丞の心を奪おうとアプローチして袖にされ続けるが、それでも盗んだ彼の財布を後生大事に持ち続ける辺りには可愛らしさも覗かせた。
他にも、米問屋の広海屋を演じたもりちえも印象に残る。広海屋は、自分の米を出し抜けに市場に流通させて米価を暴落させる人物。利得を得ようとずる賢く立ち回る悪代官っぷりと共に、湯呑の熱い茶をそれらしく飲むしぐさなど、細かい芝居を大事にするところにも好感を持った。佐藤梟による「恋愛していますか」といったおなじみの客いじりでは、思わぬ形で現下の状況を突く。最前列のプレミアムシートの客席だけに、宇野亜喜良デザインのオリジナル巾着がプレゼントされた。それを紹介する際、佐藤は巾着の中に「愛を入れておきました」と言う。その上で「見えないものが一番怖いのよね」と佐藤が言ったことで、客席は沸いた。それは、蔓延しつつあった新型コロナウイルスに掛けた言葉である。盲目的な恋や復讐心が引き起こす悲劇と、ウイルスに対する漠然とした恐怖にさらされている現状がどことなく見合う。本作を観劇した際は、しばらくしてかつて経験したことのない非日常の日常を生きることになるとは思いもしなかった。
©大須賀博
最後に、視覚的な演出の妙について改めて触れておきたい。雪之丞には誰もが見惚れる女形だが仇討ちにまい進する非情な人格と、真っ黒のほっかむり姿だがほがらかで人懐っこい闇太郎という2つの人格がある。雪之丞自身も、虚構と現実の鏡像関係を往還する役柄なのだが、初演では加納幸和が双方を演じた。だが本作では、闇太郎は水嶋カンナが演じて人格を完全に切り分けた。そのことで原作の役どころとは違い、雪之丞の復讐心が凝縮して分離したかのような印象を与える。そんな闇太郎の性格を良く表現するのが、月夜の晩に街並みを走るシーンである。降りた黒幕に投影された大きな月をバックに、闇太郎がその場で足踏み。そしてしだいに月が小さくなることで闇太郎が街を走っていることを表現しつつ、そのまま幕が上がると、そこは浪路が眠る屋形船に到達するという演出であった。テンポが良く流れるようなシーン処理は、映像的で巧みであった。なおかつ無表情で駆ける闇太郎は、雪之丞の負の人格が夜道を滑っているような印象を与えた。また父を殺してしまった雪之丞が、在りし日の和蘭丸を幻視するラスト。左右から舞台面の中央に向けて、勢い良く引いた白い幕を合わせて一挙に船を表現する。舞台を前後に使って立体的に見せる視覚面と、手早の良さが相まった良い演出であった。
演技と演出の総合力で作品の魅力を引き出した本作は、Project Nyxの代表作になった。
INDEXに戻る
過激思想に通じる、日本人の潜在意識に巣くう差別意識
藤原央登(劇評家)
流山児★事務所『コタン虐殺』
2020年2月1日(土)~9日(日) 会場 下北沢ザ・スズナリ
倭人(日本人)に搾取され続けた末、1669年のシャクシャインの戦いで蜂起するも敗北するアイヌの歴史。そして1974年に起きた、アイヌの独立を訴えて町長を襲撃した北海道白老町長襲撃事件。2つの時空間を往還することで浮かび上がるのはもちろん、日本人によるアイヌ民族への根深い差別である。だが本作は、過去の歴史的な差別を追うだけで終止しない。現在に至るまで差別が残っており、時にそれが過激思想へと高進すること。加えて過激思想の持ち主は決して特異な人間だけが有するのではなく、我々にもその可能性があること。そのことを突きつける、非常に射程の広い作品なのである。
本作は、公演前に体調不良で2人が降板。公演中にも1人が急病で降板した。これを受けて2月6日の昼公演は休演。しかし私が観劇する予定だった、同日の夜から早くも公演は再開した。降板した俳優の役とを兼務することになった俳優が、手持ちの台本を朗読するなどで対応した。もともと幾人かの俳優は、2つの時代で役を兼ねる。また降板した俳優は、ストーリーテラーを担う新人刑事役であったため、手持ちの台本を日記のように朗読することは、役柄と合致していた。急遽の対応ではあったが、作品に沿うよう配慮がなされていた。劇団の対応力の高さを、ここに付記しておきたい。
©横田敦史
アイヌには諸地域に数々のコタン(部族)があった。その中で、北海道の静内から釧路や厚岸に至る太平洋沿岸を拠点にするメナシクルと、胆振から日高北部に至る太平洋沿岸を拠点にするシュムクルは、漁猟権などを巡って対立していた。シュムクルの酋長・オニビシ(イワヲ)の跡継ぎとなる甥のツカコボシ(上田和弘)が誕生した祝いの席で、メナシクルの酋長・カモクタインの代理で訪れたシャクシャイン(杉木隆幸)が、オニビシの部下を殺害したことがきっかけであった。その報復として、シュクムクル側がカモクタインを殺害。松前藩が両者を仲裁することで一旦は争いが収まるものの、今度はシャクシャインがオニビシを殺害する。仲裁以来、シュムクルは松前藩に食い込んでいた。そのため、オニビシの姉婿であるウタフ(上田和弘)が、メナシクルに反撃するべく松前藩に武器と兵の貸与を願い出る。しかし、ウタフは松前藩からその要請を断られた上、帰宅途上に死亡する。その死因が、流行り病に見せかけた松前藩による毒殺という風聞が流れた。そのことがきっかけとなり、シャクシャインの呼びかけでアイヌの部族たちは団結し、松前藩に争いを挑む。これがシャクシャインの戦いである。戦いが長期戦になる中、アイヌ民族は劣勢となる。そして松前藩の計略によって持たれた見せかけの和睦で、シャクシャインが殺害されてこの戦いは終わった。
上記を含めた1648年~1669年までのアイヌの歴史が展開される中、途中で21世紀のすすきののキャバクラ場面が挟み込まれる。様々な楽器を一人で生演奏する鈴木光介の劇伴と併せて、アイヌの言葉や習慣・世界観を歌いながら解説する幕間狂言は、作品にエンターテインメント要素を添える。しかしここでの歌を含めて、本作を貫くのは倭人がいかにアイヌを搾取してきたかを描くことにある。例えばアイヌとの交易を独占した松前藩が、米一俵のサイズを小さくすることでアイヌから蝦夷錦を安く買い叩いた。シュムクルとメナシクルの仲介を担った松前藩は、その度に調停料を課して借金漬けにしていた。そして借金のカタといっては、オットセイ50頭やオスのペニス5本などを要求するシーンもある。倭人は金に汚く、強欲であることが強調されるのである。
©横田敦史
そんな倭人のイメージを最も強調するのは、先述したアイヌの殺害に、全て倭人が関与しているという詩森ろばによる〈フィクション〉であろう。シュムクルとメナシクルが対立するきっかけとなった最初の殺害こそ、シュムクルの男が倭人の刀をシャクシャインに見せびらかしているうちに小競り合いとなった拍子に、シャクシャインが構えた刀の上にシュムクルの男がバランスを崩して倒れた事故死として描かれる。しかしそれ以後は、倭人の暗躍によってアイヌたちは殺害されてゆくのだ。シャクシャインの息子・カンリリカとオニビシの甥・ツカコボシが友情を育み、子の世代では両部族の争いを亡くそうと誓う。しかしそのツカコボシが殺害されたことで、アイヌの苦境を打破する未来への希望も絶たれてしまう。犯人である「静かに忍び寄る影」は、松前藩の指揮官・佐藤権左衛門(流山寺祥)の腹心の部下・文四郎(田島亮)であった。彼らは松前藩の支配権を拡大するために、アイヌの滅亡を目論んでいた。松前藩は甘言を弄してオニビシを取り込み、交易による利益をより効率良く搾取する。その一方で2つのコタンが互いに殺し合い、報復の連鎖が起こっているように仕向ける。本来は信頼が厚いアイヌ民族の信義を失わせることで、アイヌの滅亡も効率良く運ぶように企むのだ。また文四郎は、シャクシャインの娘・チャレンカ(山丸莉菜)に粉をかけてコタンに出入りし、スパイ活動も行う。文四郎に片思いを抱くようになったチャレンカもまた、彼の正体を知ってオフィーリアよろしく身投げしてしまう。
舞台美術には、あらゆるものに神が宿ると説明されるアイヌの思想、そして自然と共生する生き方を反映するように、切り出した樹木を全面に使っている。背景には、木を梯子のように組み合わせた装置がある。争いのシーンでは、ここを人が激しく昇り降りして躍動感があった。そして床板は、持ち上げるとテーブルになる仕掛けになっていた。そのことによってアイヌの歴史物語から、白老町長襲撃事件の犯人・八木原(田島亮)を刑事・佐久(杉木隆幸)が取り調べるシーンへと素早く切り替わる。時々に差し挟まれる取り調べで、白老町長を襲撃した八木原の動機と人間性がしだいに明らかになってゆく。古くから白老町のポロト湖畔に、アイヌは集落を形成していた。それを受けて白老町は1965年に、集落付近に観光施設「ポロトアイヌコタン」(現アイヌ民族博物館)を建設する。アイヌ文化の保護と観光振興が目的であった。これに反発したのが、新左翼の活動家たちであった。日本人のアイヌへの差別意識と、人目に晒して金儲けをする卑しい資本主義社会の打倒。その果てにアイヌ民族の独立を目指すアイヌ独立論を掲げて、1970年代に北海道を中心にテロ事件が頻発していた。ノンセクト・ラジカル(無党派活動家)である八木原が起こした事件は、そのひとつであった。
©横田敦史
取り調べを進めるうちに、佐久はアイヌの血を引いていることが分かる。シャクシャインと佐久を杉木隆幸が演じている。そのため佐久は、アイヌの英雄と目されたシャクシャインの末裔のように見える。また八木原と文四郎も、田島亮が演じる。つまりアイヌの英雄とテロリストが、時と場所を隔てて再び対峙する構図になっているのだ。佐久はこれまでの人生の中で、少なからず差別を受けてきたため、自らがアイヌの血を引いていることを表立っては公言してこなかった。対して八木原は当初、自分はアイヌだと佐久に言う。しかし実は広島出身の日本人であり、アイヌでないことが発覚する。佐久からすれば、当事者でもない倭人がアイヌの独立を唱えてテロ活動することの方が、無神経でかつ迷惑である。佐久はささやかな自分の人生を、自らの手で自由に選択して生きることが望みだと語る。その言葉の裏側には、弱者救済や社会正義と称した運動の影で、救われるべき人々が置いてけぼりになり、かえって居場所が奪われてしまう問題を衝いている。その要因のひとつは、運動の担い手が自らの身勝手やエゴを押し付けたり、自尊心を満たすために運動が自己目的化して本来の狙いから外れることにあろう。活動の空転化によって、活動家同士のエゴがぶつかり合い、内ゲバの末に瓦解したのが1973年に終焉を迎える新左翼運動だったのではなかったか。八木原もまた、そのような当時の社会情勢の中で活動を行っていた。資本主義の道具になったアイヌを救い独立を支援するとは言うものの、八木原の成した行動が犯罪である以上、所詮は社会不安を与えるテロリストでしかない。それでも佐久はかつての英雄のように、時に諫めながらも深い懐で包み込むように八木原を受け止めようとする。ヒゲ面でクマのような体格の杉木と、線が細く切れ長の目が印象的な田島。配役の妙もあって、倭人がアイヌの生活を脅かす構造が、20世紀に至っても残っていることを強く印象付けた。
ここまでの物語は、差別の根深さをアイヌに焦点を絞るものであった。だが本作はこれで終わりではない。詩森はもう一つの〈フィクション〉を施して、差別の問題をもう一段階引き上げる。八木原はその後、1987年に朝日新聞阪神支局襲撃事件を起こした赤報隊の一人になったという点がそれに当たる。ラストシーン近く、八木原からそのことを告白する手紙が届いたと佐久が語る。極左と極右、振り子のように両極端の過激思想に染まった彼の心性はいかほどか。最後まで佐久と八木原は噛み合うことはなく、分かり合えない。それでも語り合おうと呼びかける佐久の姿で本作は終わる。佐久が呼びかけているのは、八木原という特異なテロリストではない。両極端の過激思想を一人の人物が背負うがゆえに、八木原はあらゆる排外主義者を集約した姿に見える。その時に私は八木原に、相模原障害者施設殺傷事件を引き起こした植松聖被告を重ねた。2016年7月に入所者19人を刺殺、入所者・職員計26人に重軽傷を負わせた植松被告。彼の裁判員裁判が年明けから横浜地裁で行われており、3月16日に死刑判決が下された。観劇日の前日である2月5日の第10回公判では被害者参加制度に基いて、殺害された利用者の遺族や負傷者の家族が植松被告に直接質問した。遺族に「なぜ殺したのか」と問われると、植松被告はかねてからの障害者への差別的な持論を展開した上で「社会の迷惑になっているから」「殺した方が社会の役に立つと思った」などと述べた。極端な差別意識と力ずくの排除は、21世紀の今日に至ってもなお根強く残っている。本作における八木原の存在は、そのことを告げているのだ。
©横田敦史
さらに八木原や植松被告が特別で特殊な人間であると思えないのは、彼らの過激思想の源流に、本作で言えばアイヌ差別があるからだ。倭人によるアイヌ差別は彼らの過激思想に比べれば、程度の差こそあれ広く多くの日本人が抱いていたのではないか。むしろ程度の差があるからこそ、当たり前のように差別が広まっていたともいえる。そういう風にアイヌを差別してきた倭人の末裔が、八木原であるという劇構造は何を意味するか。それはすなわち、日本人全体が持っている差別の根が、八木原=赤報隊=植松聖といった過激思想に辿り着くということであり、そういう意味で我々は彼らとは無縁ではないということなのだ。日本人がアイヌを差別してきた過去が、そっくり現代の様々な差別感情として現代にも生きていること。極端な差別感情は特異な人間が有するものではなく、誰しもがその貌を覗かせる可能性があること。本作は日本人の潜在意識下に巣くう根深い差別意識の在り処を、歴史を踏まえた上で我々に突きつけたのである。
どうすれば根深い差別意識を払拭して、分かり合い共生できるのか。そのためには、それでもなお語ろうと呼びかける佐久に、どのように我々が応えるかにかかっているのだろう。
INDEXに戻る
より良い世界を創る一員となるよう観客を鼓舞
藤原央登(劇評家)
世田谷パブリックシアター+エッチビイ『終わりのない』
2019年10月29日(火)~11月17日(日) 会場 世田谷パブリックシアター
地球温暖化や紛争、他国を無視した大国の自国第一主義と独善主義によって、世界は混沌としている。この情勢が高進した先に待っているのは、地球の崩壊。現在とは、未来に地球が消滅するか否かの転換点である。このような現状認識の下、散見される懸念を解消して地球の未来を救うべく、一人ひとりがより良く生きよ。そう直截にエールを送る作品であった。地球を守るための努力や活動を促す極大のメッセージが、18歳の少年の生き方と交叉する貴種流離譚に落とし込まれている。未来を想像して現在を律して生きることが、結果的に世界を救うことにつながる。極大と極小が合致した、観る者の肺腑を衝く物語だ。
本作は、ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』が下敷きとなっている。トロイア戦争に勝利したオデュッセウスが、トロイアから故郷のイタケに戻るまで実に10年を要した。その漂流の間に経験した様々な試練を描く作品である。この長大な苦難の旅が、川端悠理(山田裕貴)が経験するタイムトラベルへと重ね合わされる。悠理はエッセイストでもあるプロダイバーの父・山鳥士郎(仲村トオル)、物理学者の母・川端楊(村岡希美)に加え、幼なじみの色川りさ(清水葉月)、戸田春喜(大窪人衛)と共に、湖畔のキャンプに訪れる。幼なじみたちが高校卒業後の針路をそれぞれに定める中、高校受験に失敗しフリースクールに通う悠理は、自分は何がしたいのかが分からなくなっている。その上、両親からは互いに仕事に打ち込むという理由で、突然に離婚を告げられる。
ひとり取り残された気分に陥った悠理は、遊泳しに行った海で溺れてしまう。それが引き金となり、悠理は3つの時空を旅することになる。すなわち、中学校時代の同級生・能海杏(奈緒)も交えてキャンプに来ている別の2020年8月現在。環境汚染と戦争によって人類が絶滅した地球を脱して、リヒト(安井順平)、ゼン(盛隆二)、アン(奈緒)と共に新たな惑星を探索する3185年の宇宙船内。そしてイプノスという、地球によく似た惑星である。頭から濃紺の一枚布を被ったイプノス人たちのいるこの惑星は、未来のようでもあり古代の神話世界のようにも見える。円形の八百屋舞台と、円形のスクーンを背景にしつらえた簡素な舞台。床面に照らされた真っ赤な明かりが宇宙船内の異常を表現したり、スクリーンに水中を思わせる映像などが投影される。どこにでも変化する抽象空間に、目を惹く照明と映像が鮮やか。
©田中亜紀
劇のはじまりも鮮烈だ。水中で息を吐くようなゴボゴボという音が流れた後、一気に明転。すると背中を丸めてゆっくりと手足を動かす悠理が、中空に浮かぶ。悠理は9歳の時にも一度、ダイビングで溺れた経験がある。中空でもがく悠理の姿は、9歳の頃か18歳の頃か、はたまた酸素のない宇宙空間に放り出された3185年のユーリか。悠理のタイムトラベルを集約しつつ予告する、強烈なイメージであった。
悠理が時空を行き来する過程で浮かび上がる本作のキーワードは、無意識が引き起こす「ひらめき」と、量子力学の解釈のひとつである「多世界解釈」だ。この2つの要素は舞台が進むにしたがって「想像力」の謂いとなって結実する。そのことが、SF要素を加味した劇世界に説得力を与えている。その辺の筆致は、前川知大の得意とするところが発揮されている。
人間は個人として存在していると同時に、人類が誕生してから今日に至るまでの記憶を有している。デジャヴ(既視感)は、この集団的無意識が不意に蘇った証であるといった旨のやりとりが劇中にある。そのことを敷衍すれば、現在を生きる自分の意志が、未来の誰かに影響を与えるかもしれない。連綿と続く人類の集団的無意識は、過去から受け継ぎ、そしてまだ見ぬ未来に生を受ける者に引き継いでいくものである。とするならば、未来の生が受け取る予定の記憶を、現在に生きる者たちが先取りして捉える必要があるのではないか。未来の人類に伝えたい記憶が失われないように、現代人がそれを自覚して生きるために。未来と過去は、現在を律するという意味で同義なのだ。そして過去・未来を問わず他者の無意識としての声を、自身の身体で受け止めて納得することこそ、ひらめきや直感、神の啓示と言ったりするのだろう。それは人間特有の現象である。だが本作ではこれら無意識の力を、AI(人工知能)のディープラーニング(深層学習)に見られる発展・進化、あるいは多数のコンピューターがサーバにつながれ統御されているシステムとパラレルなものとして説明される。人間とロボットの相似性を含み込みながら、人間の「発展」の余地や可能性を思わせて興味深い。
©田中亜紀
3185年を生きる18歳のユーリは、3人の調査員と共に果てしのない旅を続ける中で、ある惑星に降り立つ。そこの調査をする際に、ユーリはヘルメットを外したためにウイルスを吸い込んで即死する。乗組員たちはユーリを蘇生させるべく、無傷で残ったユーリの脳から身体のバックアップデータを取り出して12体を復元した。その後、脳データを戻してユーリを無事に再生させた。しかしそのユーリの意識は、なぜか1000年前の悠理のものであった。彼らは同じ失敗を繰り返す度に、ユーリを宇宙空間に放出して(殺して)はやり直している。
ユーリの身体に悠理の意識が入り込む不可思議が、アンドロイドのダン(浜田信也)とのやりとりを通して理由付けされる。ダンによれば宇宙船内は20のユニットに分かれおり、それぞれにダンと同様のアンドロイドが1体ずつ存在しているという。そして個別のアンドロイドたちはシステムによって統合され、ひとつの人格としても機能するのだという。3185年のユーリと2020年の悠理は、姿形が同じである。いわば20体のダンと同じく、12体のユーリは悠理のクローンである。それは複数のPCにアプリケーションをインストールするように、ひとつの意識をクローンに移すことに近い。そして意識を器としての身体に飛ばしインストールさせる力こそ、無意識の働きなのである。
加えて他者との邂逅によって、無意識がひらめきへと昇華される。宇宙船から放り出されたユーリは宇宙空間で死んだと思いきや、彼はイプノスという星に飛ぶ。そこでエイ(森下創)という人物と出会う。31世紀の月で生まれた彼もまた、別の惑星を目指す船団の一員であった。船が故障しながらもエイは、もうひとつの宇宙である地球にそっくりなイプノスの星に漂着した。宇宙はひとつではなく多元に、無限に広がっている。生き残ったのはエイひとりであるため、そのことを誰にも伝えられなかった。そんな折、不意にユーリが現れた。エイはユーリに、21世紀の地球人に自分が体験したことを伝えて欲しいと託す。
©田中亜紀
2つ目のキーワードである多世界解釈とは何か。劇中ではシュレディンガーの猫に通じるコインの例で解説される。1枚のコインを両手の内、どちらかの手に隠して相手に提示する。右手と左手、どちらの手にコインがあるかを予想して選択する前は、コインは両手に存在していると考える。そこから人はコインの在り処を予想して、どちらかの手を選択する。選択によって当然、コインがある場合とない場合のどちらかの結果が明らかになるだろう。コインが両方の手にある世界から、選択によってコインがある世界orコインがない世界のどちらかへと分岐するのだ。そのようにして人は、常に選択することで次々に分岐する世界を歩み続けている。その一方で、選ばれなかった世界も無数に存在するのである。後戻りして選択し直すことができないため、別の世界は決して知ることはできない。だから、世界はひとつのように感じる。しかし選ばれなかった世界は消滅することなく、平行世界として決して交わることなく存在している。つまり我々の目の前には、見えないまでも事前にあらゆる選択肢が提示されており、そこから意識的/無意識的に逐次選択することで、無限の選択肢の海をフローチャートのように歩んでいるのである。
現在、未来の世界を垣間見るタイムトラベルは不可能だ。かつて流産させたきり会っていない杏とキャンプするもうひとつの現在のように、タイムパラドックスも経験することはできない。しかし、他者の声を聞くことをひらめきと多世界解釈に代えることで、多元的な世界を思考することはできる。人間に備わる無意識の力によって、意識は時空を超えてアクセスすることができるのだった。そっくり同じ姿の自分がいると想定して、過去や未来を見ようとする。それはまさに想像力のことにほかならない。そしてエイに言葉を託されたように、過去であれば死者の声、未来であれば未だ産まれていない人類の声を先取りして聞くこと。その声は遠い時空から自らに呼びかけられた、神の啓示かもしれない。そのような声を聞き留めることで、現在を客観的に見返すことになり、次なる行動をより良きものへと促すことにつながる。そう促すものこそ、連綿と続く人類の集団的無意識である。そしてそれはひらめきとして、自己を越えた力となるのだ。2つのキーワードを合致させて見えてくる本作の核はここに集約されている。
悠理は時空を遍歴することで、物理学者である母親が関わる量子コンピューターの開発プロジェクトが、ダンが生まれるきっかけになっていたことを知る。そして環境問題に取り組むために政治家になるという父親の行動が、1000年後に訪れる人類の滅亡を食い止めることになるかもしれないと思い至る。だから悠理は、互いの仕事に傾注するために離婚すると話す両親の意向を受け入れ、応援する。そして悠理自身も、自分の道をしっかりと歩むことへの強い決意をする。より良い人生を送るべく自立する自分がいる世界を、悠理は選択するのである。最後に悠理は、他の登場人物たちから「ユーリ、ユーリ」と彼に寄り添うように呼び掛ける声を聞く。俳優たちはイプノス人をも兼ねる。したがってその呼びかけは現世の人たちの声であると同時に、個を越えた未来人からの無意識の声でもある。それを自分のものとして受け止め、より良い生の選択のために生かす。悠理の決意は我々の問題でもある。終わりのない人類の選択の積み重ねが、良い未来へとつながると信じて生きること。本作は観客をそのように鼓舞するのだ。
イキウメの劇団員に加えて仲村トオルと村岡希美といった実力俳優たちが、自然体で苦悩する山田裕貴を全力で支える。ダンを演じた浜田信也が、悠理との出会いによって揺らぎが生じ、無感情で機械的な演技に人間味が差し込む。その微妙な変化の表現力が印象深かった。
INDEXに戻る








