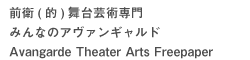論考
柴田恵美のダンス哲学
ダンス批評家 坂口勝彦
ダンス批評、思想史。雑誌およびウェブマガジン「シアターアーツ」編集委員。『江口隆哉・宮操子 前線舞踊慰問の軌跡』(共著、かんた)、
ジョン・ディーの「数学への序説」の翻訳(『原典ルネサンス自然学』(名古屋大学出版会)所収)等。 |
柴田恵美に瞠目させられたのは、2009年の『biyori』だったと思う。神楽坂にあったdie pratze で行われた「ダンスがみたい! 新人シリーズ 6」で、新人賞を取ったときだ。冒頭から驚かされた。薄闇でうごめいている2本の触覚のようなものが、前方に突き出された足だということはわかるのだけれど、異様なほどのけぞっている上体は、足についている付属物にしか見えず、まるで足が意志を持って動いているようにしか見えなかった。柴田恵美の身体はそれからも、普通の人間の身体の構造になかなか戻ることはなかった。もちろんダンスやバレエの既存の形にもならない。それがとても驚きであり新鮮だった。
いわゆる異形の身体を具現するようなダンスは、しばしばみられる。特に10年前にはそういうダンスは今よりも多かったように思う。とりわけ舞踏系がそれを得意としていた。『biyori』も一見すると異形のダンスに見えたけれど、安易に異形とは言えないものがあった。舞踏などでの異形の形態が、物と化す身体を目指しているとしたら、柴田恵美はことさらそうした異形のものを意図しているわけではないように見えたからだ。既存のダンスの形や意味のまとまりでは捉えがたいから異様なものに見えるのかもしれないけれど、それは新しいダンスに思えた。
異様な外観に比べて、身体のひとつひとつの動きそれ自体はしなやかで力強い。バレエやダンスのリリックな美しさとは違い、硬質で無機質なのだけれど、決して無意味な動きであるはずはないと思わせるほどに力強く、饒舌だった。
10年前の傑作『biyori』には、柴田恵美のエッセンスが詰め込まれていたと思う。そして、10年後の今年2019年の初頭に上演された『行進曲』と、夏に上演された『三道農楽カラク』では、『biyori』とのつながりを強く意識させながら、柴田恵美の求めるものが驚くほどほど純化されていた。
渋谷Bunkamuraの裏にあったライブハウス「SARAVAH渋谷」で1月に上演された『行進曲』では、7人のダンサーが踊った。でも、踊ったと言うよりは、動いたと言いたくなるほど、通常の踊りと呼べるような動きはほとんどない。その動きは、『biyori』での動きをはるかに先鋭にし、あるいは単純にすることで強調されていた。手足を後ろや横や前に、めいっぱい曲げて投げ出すような動きが随所に現れる。そうした動きで一連の流れを作るのだから、ダンサーへの負荷はそうとうなものだろうが、見ている方としても、あと一歩でバラバラになってしまうのではないかとハラハラしてしまうほどだった。それほどに、柴田恵美は思いきってやりたいことをやっている感がした。
 ©大洞博靖
©大洞博靖
そして、『三道農楽カラク』。これは、d-倉庫の夏の企画「ダンスがみたい!」の参加作品。今年の課題曲が韓国のパーカッションアンサンブル「サムルノリ」の代表的な曲『三道農楽カラク』。朝鮮半島に古くからある農楽を元にして、1970年代に作られたという。「農楽」という呼び方は、日本統治時代に雅楽と区別するために作られたもので、もともとは「プンムルノリ」と言うらしい。特有のリズムパターンからなるフレーズを「カラク」といい、半島の中・南部の慶尚道などのいくつかの道をあわせて「三道農楽カラク」と呼ぶという。日本の植民地時代に破壊された伝承の再構築という側面があるのだろう。
この課題曲は30分弱で、打楽器の強烈なリズムが延々と続く。ポリリズムのように聞こえる所もあり、少しずつリズムが変化していく様子はミニマルミュージックのようでもある。再構築された70年代は、ちょうどミニマルミュージックがあちこちでブームになっていた頃。アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルがライヒの曲でダンス作品を最初に作ったのもあの頃なので、影響関係もあるのだろうか。この一種のミニマルミュージックに、柴田恵美はフルに振付をした。
前半20分余りは無音で、後半30分にサムルノリの音楽が流れる。前半では薄闇の中で6人のダンサーが離散と融合を繰り返しながらゆっくりと形を変えていく。ダンサーは全体としての形を構成する要素になり、ひとりひとりはほとんど区別ができないが、大きなかたまりが得体の知れない強さで迫ってくる。
後半は『三道農楽カラク』の音楽で踊る。鼓の打音に合わせて足踏みする所など、いかにも音楽に合わせている所もありながら、次第に音楽とダンスが独立して進むように感じられる瞬間が多くなる。腰に手を当てながら、足を突然後方に振り上げたり、横に振り払ったり、相撲の動きの変形かと思う動きが組み合わされるときなどは、その動きの奇抜さに目を奪われる。何の前ぶれもなくグニャリと体が歪むなど、そのアクセントが音楽のリズムを上回るようにも見える。中ほどで、音楽がリズムを早めて突っ走りはじめても、安易に着いていくことはせずに、寝っ転がったりしながらじっくりと待ち、そうして最後に爆発する。音楽は最初から最後まで盛り上がりっぱなしで、最後に特別なクライマックスを迎えるわけではないので、ダンスのタメが最後に効いてくる。
ダンスは音楽に沿いながらも、単純に音楽のリズムや流れに合わせて振り付けるのではなくて、音楽と平行しながらも自律的な流れを作っている。
このように、この作品にも柴田恵美の強烈な美意識あるいは哲学が貫かれていて、それがそうとうなレベルで具体化してきているように思えた。そこに見えて来た要素をいくつか列挙してみよう。
まずは、個性ないしは個の消去。この作品では、ダンサーたちが正面を向いて顔をはっきりと見せることはほとんどない。踊っているときはたいてい下を向いていているか、天井をまっすぐ見詰める無理な体勢であることが多い。これは『biyori』でも『行進曲』でもそうだった。顔を伏せるのは、観客の視線を身体の動きに集中させるという意図もあるだろうが、顔の表情によって伝わってしまいそうになるものを遮断する意図も大きいと思う。表情がダンスの情緒を決めることを避けるのは難しいだろうから。そうすると、踊る側の意識も変わるだろう。

©大洞博靖
何らか情緒の表出としてのダンスというものから、柴田恵美は距離を置こうとしているようにも見える。個の表現としてのダンスではなく、もっと硬質で無機質なダンスを求めているのではないか。だから、情緒を伝えがちな顔をできるだけ隠すのではないかと思う。
それと同じ理由からだろうが、幾何学的な動きを多用することになり、身体も幾何的な運動態となる。とりわけ『行進曲』では、身体をできるだけ直線的に使おうとしているように見えた。中途半端に関節を曲げて曖昧な曲線が現れるのを極力避けるため、手足は可動領域ギリギリまでめいっぱい曲げられたり広げられたりする。『三道農楽カラク』では、柔らかな線も現れたが、やはり手足は曖昧に曲げられることなく直線的なことが多かった。
その極端な直線性は、通常のダンスからはあまりにもかけ離れている。柴田恵美が求めているのがそうした直線性であり、そこから生まれるダンスは、通常の柔らかな曲線的なダンスとはまったく異なる表情を見せる。そもそも表情豊かな動きと言われるような動きは、けっこうステレオタイプなものが多くて、個の内面の表出というよりはただ単にそのような形を情感の表現と見る習慣に依存しているだけのことが多い。柴田恵美が距離を置こうとしているのはそのような表象の習慣でもあるだろう。そしてそういうステレオタイプではない、別の新しいダンスの意味を作ろうとしているのだと思う。
音楽とダンスの関係も新たにされようとしている。ソロの『biyori』は音楽で踊ることはないし、群舞であっても『行進曲』はほとんどが無音で、幾度か唐突に鳴る騒がしい音楽も、勝手に鳴っているという感じだ。柴田にとっては、踊る際に必ずしも音楽は必要ないのだろう。あくまでも身体から生まれるリズムが優先され、音楽に身体を従属させる必要はないのかもしれない。
考えてみれば、なぜダンスは音楽に合わせて踊るものと決まっているのだろう。ダンスが音楽に従属せずに対等な立場にあることはできないのか。おそらくこの問いは、ローザスのアンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルが既に40年ほど前に提示している問いだろう。アンヌ・テレサは、スコアを綿密に分析し、ひとつひとつの音と動きとの関係を緻密に考察し、音楽を越えるほどの精緻な構造を持つダンスを作り出した。柴田恵美のやろうとしていることも、音楽を越える運動態としてのダンスを目指すという意味でそれに近いところがあるように見える。音楽とは独立に自律的な運動態となるダンスが目指されるのだろう。そして、その意図は『三道農楽カラク』で、そうとうなレベルで達成されていたと思う。
課題曲の『三道農楽カラク』となんらかの形で関係を提示しなくてはならない。だからこそ、音楽と共にありつつ、音楽と独立にあるという、きわどい存立状態が生まれたのかもしれない。音楽にピッタリ合わせた動きは足踏みぐらいで、ほとんどの動きは音楽に反応した動きではなくて、音楽とは別の流れを作っている。もちろん音をきっかけにして動くので、ある意味では音楽に合わせて動いているとは言えるが、音楽に体を合わせるわけではなく、音楽とはリズムを共有しつつも、音楽の方向とは別の独立した律動がダンスで作られる。
そういう柴田恵美のダンスは、音楽に合わせてリリカルに美しく踊るモダンダンスとはかなり異なるものになる。音楽に合わせて体を気持ちよく動かすようなダンスではないし、曖昧な曲線に満ちたダンスでもない。でもそこには別種の力と美しさがあるし、別の心地よさもある。柴田恵美は、こういう強靱な哲学を備えてダンスを作り続けている。
|