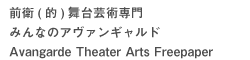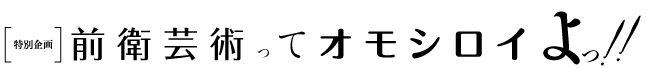知り合い同士である二人のパフォーマーに話して頂きました。まずは、パフォーマンスをやり始めた経緯から聞いてみました。
林( H )―――僕はもともと美大志望で、浪人して予備校に行ってたんですけど…嫌になって逃げちゃったんですよね。当時は自分の才能とか能力とかいったものを中心に物事を考えていたから。その辺の過信が崩されたことに耐えられなくなって、絵を続けることにまるで興味が持てなくなって…。その後、何もしてなかったんだけど10代から20代へという時期だから月並みに色々苦しい経験をして、それから劇場にスタッフとして加わりました。パフォーマンスを始めたのはもう少し前だけどそれは絵をやっていた時の延長線上でやっていて、今のような取り組みを始めるのは劇場でいろんな人に出会ってからです。
佐々木さんは劇団に入って何年目ですか。
佐々木( S )―えーと20年です。
俳優として始めたのは?
S―――――それはもっと後です。99年だから、13~14年前です。
H―――――それは1998年の「K氏の痙攣」の頃?
S―――――いや、その後の「Circulate-1」という作品の時。
H―――――「Circulate」が演者としては初めてだったんだね。
S―――――そう、初めて出た。でもOM-2ってもともとスタッフと黒衣と演者の垣根が無かったので…。それまでも僕は黒衣(スタッフ)だったけど、ちょこっとワンシーンに出るとか、そういうことはやっていた。 今のOM-2は俳優が創ってきたシーンがまずあって、基本的には演出家の真壁さんがそれを作品の形にしていくんですよね。当時はもっと台本の役割が大きかったのでしょうか。
S―――――そうですね。真壁さんの台本があって、ちゃんとだれだれが何の役柄っていうのもあって…。
「Nocturnal Architecture」の「視線のシーン」は有名ですが、そういう大掛かりな仕掛けも「Circulate」の頃はまだあったのですか。
S―――――いいえ、「Circulate」からやってないです。 「Circulate」はどういう作品だったのですか。
S―――――「Circulate」では仕掛けは勿論あったんだけれど「Nocturnal Architecture」より、もうちょっと役者の身体に眼が向いたっていうか…。その前までは役者も装置も同列にあって、身体の足りなさを装置が補うって感じで…
H―――――そうすると当時は今のように俳優が個々でシーンを創るわけじゃなく、台本があって、というやり方?
S―――――うん、役柄とは言わないけれどもとりあえずこのシーンにはこの人が必要で、こういうセリフを喋って、大体こういうことをやるっていう台本めいたものはあった。けれども、その内容を創っていくのは個人ではなくそのシーンに関わる人達が一緒に創っていくというもの。
H―――――シーン毎でいくつかの班に分かれているってこと?
S―――――そう、そんな感じ。
H―――――現在の創り方にシフトしていったのはいつ頃なの?
S―――――「K氏の痙攣」以降に集団で創るやり方に真壁さんが飽きたんだと思う、きっと。その辺をもうちょっと個人に焦点を当てていこうっていうか、個人から何が出るだろうっていう実験をみんなでし始めた、稽古場で。それはお題目っていうか…。例えば最初だったら真壁さんが「椅子を使って10分間のシーンを創って来て」ってみんなに言って、後は自分たち演者が創るっていうのが始まり。
H―――――でも、台本があってやるのと、自分で創るっていうのは全く違うことでしょう?
S―――――僕は比べようがないの。というのは、僕がちゃんと演者として関わったのは「Circulate」からだから…。その時も同じように台本が椅子に代わってあったというだけでシーン自体は集団とはいえ個々で創っていく部分が多かった。だからそんなに突拍子もない転換の仕方っていう感じはしなかった。でも言葉や音楽、照明も自分で工夫して創るなり選択し決定していくっていうことを全部自分でやるっていうことだから、それは初めてといえば初めての経験。
同じ流れの中にある取り組みだったと。
S―――――そうそう、それを個人でやってみたということ。

佐々木敦|©前澤秀登
H―――――自分で舞台に立つようになってからの13~14年で舞台への意識に変化はあるの?
S―――――どうなんだろう。多分、変化が無いはずはないんだけど、それをどう言っていいのか…。例えば僕が一番最初にパフォーマンスを意識するっていうか、自分の身体が舞台に転がり出すっていうか、そういう体験をしたのが95年の法政大学でやった「Nocturnal Architecture」っていう作品で、さっき出てきた「視線のシーン」。
「視線のシーン」というのはどのようなものですか。
S―――――その作品自体が変わった芝居ではあったんだけれど、演技のシーンらしきものが続いている中で突然、30~40分間お客さんを演者が見つめる。台本もなくなって、ただお客さんと見つめ合うってだけのシーン、それが「視線のシーン」。ちょっと話が前後するけど、その前年のシンガポール公演の時に同じシーンに僕は黒衣として出ていたんだけれど、それでそのシーンはやっぱり特別に見えたの。それは僕が今まで見てきたいわゆる演劇というか、身体でこう何かやることが…。う~ん(笑)、何ていうか、こういうモノだろうって思ってきたものがことごとく壊されるというか…。それまでは僕としては黒衣で十分なことをやっていて、それは大変だけど面白いと感じていたんだけど、その「視線のシーン」だけはそこに入っていきたい、その中にいたいって強く思ったの。
で、その翌年、凱旋公演を法政大学でやって、その時も黒衣として観ていたんだけどその「視線のシーン」が、どうしても…「このシーンはこうではないはずだ」って思えて…。僕はこのシ-ンを真壁さんの意図として、役者がそれまで与えられてきた役割なり言葉なりをその30分のシーンの中で「脱いでいく」というか、「捨てていく」というか…そしてその役割を脱ぎ捨てた演者が「一人の人間」として立ち始めるシーンだろうというふうに捉えたのね。
H―――――与えられたものを脱ぐって言ったけど、それはモノの見方や記憶、社会的約束や考え方のパターンみたいなものまで、自分を自分足らしめている条件付けのすべてのことでしょう。そういうものに自分の身体が支配され何かを演じている。そのような無意識に束縛された身体の状態を脱することが意図されたシーンだったと。
S―――――うん、そう。でもそのはずなのに、演者がその役割を「演技」していて、その役割に入り込んでいくようなものに見えちゃったんだよね。例えばある感情の振幅、悲しみや高揚であるとか、そういうものが一層「演じている」シーンのように見えてきて…。で、僕はそうじゃないだろうって思ったの。演じるとか与えられた役柄そのものをやめていくことをしなければ、このシーンは始まらないんだって…そう思った時にどうしても僕は、何だろう…「僕がやればいいんだ」って思った。
そもそも、二人にとって「演技をする」というのはどういうことなんでしょうか。
H―――――舞台で演技するってこと以前に、ただ日常で生きているだけでもそれが何かを演じているという状態に近いわけでしょ。自分が自分に課しているアイデンティティを現実の生活において背負うということ自体が…。良い悪いは別にして、それ自体が巧妙な演技だと思うんです。一般的にはお芝居では台本があって、役柄の人格やストーリーの中での意味を解釈し、それを表現するわけだけど、それは現実社会で生きるという手続きと違うことなんだろうか、と思ってしまうんです。現実社会でもそれが上手な人と下手な人がいて優劣を比較されながらやっているんだと。「演技」することを前提とした演劇はその事が分かり易いというだけで、ダンスでも音楽でもそれ以外でも全てではないにせよ大抵根低にあるものは同じく見えてしまう。少なくとも僕が思う芸術の在り方とは大分違うなって思います
日常生活上での演技があって、またそれとは別に他の役をやるわけだからより複雑になるわけで、複雑になる分、面白いのかもしれませんが。
H―――――うーん…どうなのかな。面白くはないと思う。
人は洋服の衣替えをするように、もしくは飽きた服を捨てて買い替えるように、自分の役柄を変え続けながら生きている。「新しい自分になりたい」とか「本当の自分」とか、よく聞くけどそれは今の日常の役柄に不平を言っているわけだよね。相手や状況に応じて違う役柄を演じ分けるよう求められることなんていくらでもありうる。そういったことが普通に生きる中に含まれている。程度の差こそあれ、自分というものを演じずに生きている人なんて僕は見たことが無い。現実社会でただ生きているだけでも十分に複雑でこんがらがっている。その上に舞台でも演じる。フィクションの上にフィクションを重ねるようなものだと思う。
現実での演技でさえ複雑だから、演技の構造を簡素にして、演技はやめるべきだということ…?
H―――――「演技をしない」っていうのはどういうことか。日常で意図もなくただぼうっとしている間も、この身体は「私」で一杯に満たされている。それを「自我」とでもいうべきか。この自我というものについて僕たちは分かっているつもりで何も知らないと思う。知的な了解はあるかもしれないけど、それは身体の在り方に関わるような了解だろうかと。説明が難しいけど…そのことが様々な混乱の根っこにあるんじゃないかと思っている。
「演技をやめる」というのは、自分が自分である根拠まで遡って、身体の在り方を顧みるということ。それは「自分以外の何か」になろうとする試みとは勿論違う。その身体を問うという過程で人間としての在り方に触れるような「体験」を重ねていく。「私」中心の在り方から飛び出し、また「私」に戻る……行きつ戻りつを繰り返す。「私」というものから身体が完全に自由になることはないんです。けれど、少しずつ身体に影響が現れる。
価値観などについて考え方が変わるということですか。
H―――――結果的にはそういうこともあるかもしれませんが、部分的な変化ではなくて、つまり思考などの身体の一部に関わる変化ではなく全体の変化です。オカルティックに思うかもしれませんが、それは身体の変容と言えるかもしれません。僕はただ、その後の身体の行き先へ自分を投げ出すだけ。つまり、僕がやっていることは自らの身体を実験することです。その先はどうなるか分からないし、知的に共有することが目的じゃない。体現できないのなら思想として説明が出来ても仕方がないんです。
話を聞いているとなんだか宗教のようですが…。
H―――――宗教も色々あるので一概に言えないけど、例えば仏教の禅宗で示されることなどはかなり近しいものがあります。やり方は違いますが取り組みの内実としては芸術の本質にも迫るものだと思う。

林慶一|©大久保由利子
二人ともいわゆる「演劇」というジャンルに属してないのかもしれないですが、「パフォーマンス(?)」の良し悪しをどう捉えているのでしょうか。
S―――――たぶん、身体が選んでいくんだと思う。その辺の良し悪しっていうのはこうだからこれは良い、これは駄目っていうのを頭では判断してないんじゃないか。頭でこうだって考えるより、より速く強く「身体」の方が判断する…。
H―――――その「身体」って言うとき何を指しているの?
S―――――うーん…「思考が手放す身体」っていうかなあ。僕が「Nocturnal Architecture」で体験した時に感じたような「僕の先に身体がある」という感じ。それがどういうことでそうなっているのか分からないけど「こうじゃないんじゃないか」とか「これはおかしいんじゃないか」とか。これは正しくない美しくないでもいいけど、そういうことを頭で考えるものとまったく違う感覚というか。僕が自分だと思っていた自分、思い込まされてきた自分、そこから離れた「身体」がそういうことを判断しているんだと思う。それはたぶん、僕が音楽はこういうモノだろうとか演技はこういうモノだろうとか、そう思っていた古くて固定されたモノに対して逆らうというか、抗うっていうか…。本当のところはそうじゃないということを身体が知っている。その身体が反応するんだろうと思う。
H―――――現実を生きる「身体」というものが思考に支配されている一方で、支配されていない「身体」自体が反応するってこと?
S―――――そういうことだと思う。それを最初に体験したのが、僕の場合「Nocturnal Architecture」になるってこと。
H―――――「Nocturnal Architecture」の時に具体的には何が起きたの?
S―――――上手く言えないけど、あの時…まさか、僕の「身体」が叫びだすとは思わなかった。
H―――――実際に叫びだしたの?
S―――――うん、声が先に飛び出て、その次に身体が動き始めた。でも僕がそう思って始めたにもかかわらず、僕はそれを後ろで見ている感じ。それはたぶん僕の中にある制約だとか僕の中にある制度、そういうものが「爆発する身体」を後ろで冷静に見ていたということなんだと思う。あの、これは体験の初期で、段階がいくつかあるんだけど…。
H―――――「爆発する身体」。それは思考から解放されるっていうこと?
S―――――そういうふうに捉えていいと思う。まあ「爆発」っていうとマンガっぽいけど、自分の身体の中に起爆装置っていうか、そういうモノがあることを僕は知らなかったわけで、それが突如作動した。想定したものに自分を沿わせて行為するとか、例えば何かの役になりきって叫ぶとかいうのとは全く違うことが、僕の内側で起こり始めた。それは僕がそれまでに観てきた演技や思っていた演技とは全く違うものだった。うーん何だろう…「体験」が先に立って身体がその体験をただただしていく、まあ、そんな感じだった。
この雑誌は「前衛」について考えるっていう新聞なので…、最後に「前衛」について何か聞かせてください。
S―――――うーん(沈黙)。「体験」している時の身体には未知の可能性があるっていうか…。そしてその「体験」っていうのは他者が入れない、数の価値も捨てていける領域という感じ。一人で生きる身体だけが持つ希望というか…。自分の頭の中でこんなふうになりたいと思うことからも離れて、そのスピードは思考よりも速く進むんだよね。そしてその「体験」の一番先にいる身体が「前衛」だって思う。
H―――――「前衛」だとか「芸術」とかいう言葉、それはカテゴリーだけれども、その言葉を意識的に使うことに今は一定の意味があると思う。
現代の作家は「芸術」という公的な態度を回避して、目新しい価値を生産するだけの道を良しとしている。今、「芸術」という言葉はまるで嫌味みたいだよね。現代人がこの現実を「正常」に耐え抜くための処方箋を施すような対処療法的作品が、今は大手を振って評価されている現状。極めて迎合的なものが「芸術」として扱われ、この世界を根本から見つめ直そうとする「芸術」は影のように存在することしかできない。「芸術」という言葉から逃避しても、生きる人間の根本が変わらなければ同じ途を辿る。今、この頽廃した「芸術」の中で闘わなければどこへ逃げても同じことが繰り返されるだけ。 「前衛」であるというのは、作品の雰囲気や手法や能力の優劣の問題でもなくて、そういった挑戦の在り様のことだと思う。
本日はありがとうございました。
|