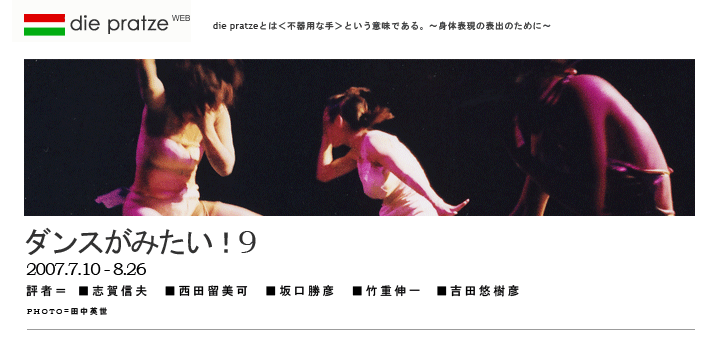
*後日追加で評が加えられる予定です。[最終更新:10月8日]
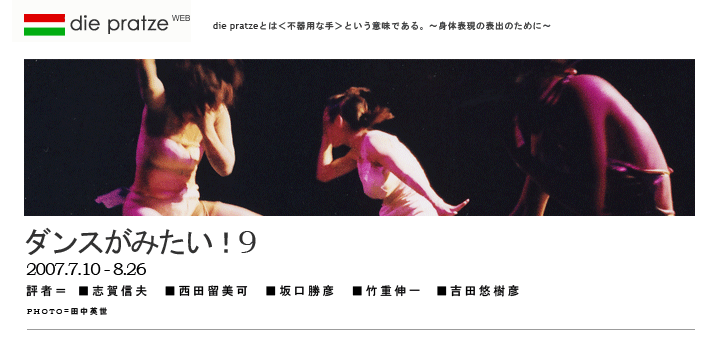
*後日追加で評が加えられる予定です。[最終更新:10月8日]
<京都×東京シリーズ>
|
7/16(月・祝) 14:30/ 18:30、7/17(火) 19:30 音響:長谷川健治朗 照明:田口賢治 ・花嵐『ドリーのダンス 〜肉に内包された夢をひもとく〜』 出演:古川遠、ニイユミコ、伴戸千雅子 振付/構成:花嵐 ・相良ゆみ『サブリミナル』 ■目黒大路×東野祥子 <麻布> 『地平線はたえず逃亡する』 7/21(土) 19:30、7/22(日) 14:30/ 18:30 音:花田真木 照明:三枝淳 舞台監督:魚住和伸 ■ 手塚夏子 <神楽坂> 『人間ラジオ』 7/31(火) & 8/1(水) 19:30 出演:手塚夏子、スズキクリ 照明:中山奈美 ■砂連尾理(砂連尾理+寺田みさこ)(京都) <麻布> 『陰圧 <In-atsu>』 8/4(土) 19:30 8/5(日) 14:30 振付/演出:砂連尾理 出演:佐藤健大郎、三原慶祐 照明:福山和歌子 ■砂山典子(京都) <神楽坂> 『First-Class Barbarian (ファーストクラス・バーバリアン)』 8/6(月) & 8/7(火) 19:30 出演:砂山典子(C. Snatch Z. / dumb type)、松田篤史(大駱駝館) 照明:藤本隆行 音響:岩佐浩樹 ■玉内集子(新人シリーズ5「新人賞」受賞) <神楽坂> 『 Shin 』 8/9(木) & 8/10(金) 19:30 ■shoppin'gocart (新人シリーズ5「オーディエンス賞」受賞) <神楽坂> 『OASIS+sun℃』 8/12(日) 14:30/18:30、8/13(月) 19:30 振付/出演:石和田尚子 出演:長沼陽子、山崎美佳、江角由加、佐藤和央、手代木花野、寺杣彩 ■セレノグラフィカ Selenographica(京都) <麻布> 『待たない人〜樹下の双魚に〜オリエンタル版』 8/22(水) & 8/23(木) 19:30 出演:隅地茉歩、阿比留修一、y-yakk79(塚原悠也) スタッフ:岩村原太、三浦あさ子 |
<インターナショナルシリーズ>
|
『The Canopy』 7/10(火) & 7/11(水) 19:30 出演:エノモトユキ、足立杏(作曲・演奏) 振付け/映像:コリー・ベフォート 照明:中山奈美 ■MayuKan(繭感)+滝田高之(オーストリア+東京) <神楽坂> 7/13(金) & 7/14(土) 19:30 ・MayuKan(繭感) 『Coin of Cabitoh(溶解秘儀)』 振付け/演出/出演:ダニエラ・クロス 出演:カロリーネ・ハイネック ・滝田高之『肛門&シガレッツ』 出演:小倉良博、平地康浩、福原充則(ピチチ5)、宮崎龍一、松本萌(ささらほうさら) 安田理英(ささらほうさら)、滝田高之、他 ■ 財津暁平(舞踏)×Taca(アコーディオン)×大由鬼山(野性尺八)(フランス) 『・・・の無い花』<神楽坂> 8/2(木) & 8/4(土) 19:30 スタッフ:長井健太郎、安田太郎、渡辺真希 ■CHAOS ROYALE(music)+86B210(dance)+松本隆(彫刻) (イギリス+東京) 『「c.o.l.o.r」-colds laboratory of rabbits』<麻布> 7/18(水) & 7/19(木) 15:30/ 19:30 出演:鈴木富美恵、井口桂子、CHAOS ROYALE、松本隆 照明:新村貴樹 ■ VIBE DANCE GROUP(韓国) <麻布> 『接触 (contact)』 8/1(水) & 8/2(木) 19:30 振付/出演:キム・ヒジン(金希眞) 演出:シム・チョルジョン 出演:イ・ミンジョン イ・ウンヨン パク・ジシュク ■加藤文子(シカゴ) <麻布> 『らんど・ざ・らんど9-a peace of idea』『らんど・ざ・らんど-standing point』 8/25(土) 15:30/ 19:30、8/26(日) 14:30 作/出演:加藤文子 出演:村田弘美 舞台監督:金川和彦 照明:三枝淳
|
花嵐
『ドリーのダンス〜肉に内包された夢をひもとく〜』

【西田】
<ブスはオンナの規格外で生きることに絶望するか、それを「キャラクター」として生きるか、顔そのものを変えて「規格内」に無理矢理入るか、もしくはその「規格」を論理で打破して美醜の価値から脱却するか。>北原みのりが『オンナ泣き』という著書でこう書いている(「ブスキャラのパワー」より)。本書でブスキャラが最近個性を発揮し、元気になってきたことにエールを送っているのだが、現実にはコスメ業界不況知らずなのを見ればわかるように、「誰でも美人になれる」という幻想をコスメ業界は女性にかきたてることをやめず、美人は得、という本当かどうかわからぬ言葉は、ブスキャラになる難しさも示している。北原はこうも言う。<お笑いの世界でオンナが生きるには「ブスキャラ」にならざるを得ない。ブスであることでオンナの規格からはずれ、性的対象でなくなることでやっと「芸」を披露することができるのだろう。>と。
花嵐の三人組がくんずほぐれつつかみ合うシーンがある。グラマラスな女性がもう一人に「ブス、負け犬、貧乳」と叫べば、言われた側の女性は、もう一人の妊娠している女性に「産む機械、バツイチ、変態」と叫ぶ。オンナを貶(おとし)める言葉を互いに叫び合い、醜く争いあってブスキャラ度を増大させつつ、女性の評価がその「肉」のありよう(形や機能)にあることに気づかせていく。
パフォーマンス&ダンスで明るく意地悪く笑い飛ばす手法には一種の救いもあるのだが、笑っただけで終わってしまい、その先へ進めていないように思えた。ブスキャラを披露しはするが、披露に留まっていて、もう一つ先へ進めていない感がある。北原の言う「ブスキャラ」を押し進めていくなら、観客に媚びるのでも、自虐でもない表現が見えてくるのではないだろうか。
花嵐のオフィシャルページ(5月10日)には、この作品の創作課程でグラビアを飾るオンナの写真を眺めたと書かれている。「普段は見て見ぬふりをしているグラビア雑誌」を作品作りのために改めて眺め、「こういうのを見るとやっぱ不快感を感じるな、と改めて思う。」一方で「普通の男の子がこういう雑誌を当たり前に見ながら育つことに怖さを感じ」、「ニンゲンどうしのコミュニケーションでは無い。」「市場でまかりとおってるボーリョク」とも語る。
グラビア女性は、オンナ規格の上層部にランクする。美人でグラマラスだ。そしてこちらに向かって魅惑的な笑顔とポーズを見せる。そこに何かわからぬ不快感を感じつつも、ついその美人キャラの姿態をまねてポーズしてしまう。この美人キャラ模倣シーンには、相反する、静かな怒りと憧れのせめぎ合いがあり、「市場でまかりとおってるボーリョク」が半端に女性を傷つけているのではないことにも気づかせられる。花嵐がこのシーンを作るときに感じていた不快感が、まだ何か彼女たちの内側でもやもやと確認されただけに留まっている気がして、惜しく思えた。
北原みのりが同著で、「美人キャラである限り、オトコの視線、性の対象としてどうしても消費されてしまうことを、多くのオンナたちは知っている。そこであえて美人キャラを選択するか、ブスキャラを選択するか、は個人の自由である。」オンナの体、オンナの肉を、スエットスーツのように脱ぎ着自由であれば、もっとオンナは自由を手に入れられるかもしれない。しかしダンスは、ある意味スエットスーツのようなものである。動く体は、生身の肉を引きはがし、オンナを引きはがし、別ものにすることもできる。美人キャラのオンナに固執しさえしなければ、表現の域はかなり広がるだろう。しかしなかなか美人キャラの威力や魅力は輝かしく手放し難い。バレエほど美人キャラを謳歌せずとも、不思議に美しい体を見せたい、という欲の葛藤をどのような方向へ向けていくのか。花嵐の今後の展開が気にかかる。
【竹重】
花嵐と相良ゆみの公演に関しては、私はチラシに協力者という立場で名を連ね、推薦文も書いているということをあらかじめ読者にはお伝えしておきたい。
花嵐は多様な顔を持っているグループで、私が去年観た「箱おんな」は、個の顔を消した様式的に凝縮された舞踏作品だったが、今回はリーダーの伴戸千雅子が妊娠したということもあってか、メンバー3人の個人的な関係をもう一度見詰め直す所から作品創りを始めたようだ。最初に白いスリップ姿の伴戸が上手奥のアルコーブから重々しく這うように現れて始まる舞台は、3人それぞれのソロを見せた後、伴戸の衣装のお腹に詰め込んだ紙を使っての、「産む機械、バツイチ、変態」といったお互いのキャラクターへの辛辣なレッテル張りへと展開する。この後、がに股に沈み込む群舞で一度融和したかに見えた3人は、ラストで再びプロレスのような諍いに陥ってしまう。確かに、3人のダンサーそれぞれの個性ははっきり見えたのだが、演劇的に熾烈な葛藤が繰り広げられながらも、ダンサー同士の間に真の距離感が感じられないため、作品全体としては内向きな印象を受けてしまったのが残念だった。
【志賀】
関西で活動する花嵐は今回女性3人で、泥臭い風味を漂わせながら、互いの女性としての存在を罵倒するような言葉を張り付けたり、争う身振りをし続ける。かつて見た花嵐の構成された展開に舞踏的身体性が垣間見えるという作品よりも、もっとベタに女と体というものと向き合おうとしている。これは1人が妊娠中で自らの女としての体をリアルに自覚しているがゆえかもしれない。タイトルはクローン羊のドリーにちなんでおり、なかなか捩れているところがいい。
相良ゆみ
『サブリミナル』

【竹重】
30分程の作品を暗転で区切り、2景構成にした。舞台中央奥にアルコーブを作り、そこから登場し、また最後はそこに戻っていく。前半は白のスリップ姿で踊り、床に座って痙攣し、上手側奥に置いた椅子と絡み合う。暗転の後の後半は、アルヴォ・ペルトの「タブラ・ラサ」が流れる中、上半身裸になって背中向きに佇むと、両手を頭の上で組み合わせて身体の内側に絞り込むようにしながら上体を床に沈ませていく。その後、前作と違って、観客にも正面の裸身を曝した。相良ゆみは、時代に対する違和感をその硬質なテンションの高い肉体全体に漲らせている稀有な資質のダンサーだが、今回は時間的にやや短過ぎたため踊り急いだのか、大まかなモチーフは示されたものの、踊りの細かい細部のニュアンスに欠けた面があるように思う。もう1景欲しかった。良いものを持っている床の踊りも封印したため、踊りの空間の立体性という点でも物足りなかった。
【志賀】
相良ゆみはクラシックバレエを仕事として教えるほど身体訓練がなされているが、大野一雄と出会い、舞踏を始めて十年以上たつ。また、米国でエイコ&コマに師事した経験がある。相良の身体は、這うなど低い重心を強いて選ぶと、かなりいい舞台を作ることができる。時折「踊る」ことを意識すると、弱くなる。この夏には集団の舞台も振り付けて、美術家作品とのコラボレーションなども積極的に行っており、これからさらに伸びると推測される。だが、タイトルの感性はちょっと不満だ。
目黒大路×東野祥子
『地平線はたえず逃亡する』

【竹重】
デュオだが、目黒大路の振付作品である。最も美しかったのが、冒頭、下手側手前の椅子に腰掛けた東野祥子が、暗闇の中で僅かな光に浮かび上がって、上体の微妙な動きだけで表現した場面。私には、東野は、動きのキレの良いダイナミックな「動」のダンサーだという印象を持っていたので、こうした静謐な表現もできることは、嬉しい誤算だった。しかしその後は、男女の葛藤から和解へというストーリー的な要素に依存した、わかり易いモダンダンス的な作品になってしまっていた。確かに、東野の脚の怪我というハンディはあったかもしれないが、心理的な意味での駆け引きはあっても、肉体と肉体のスリリングな出逢いやすれ違い、葛藤といったものは感じられなかった。舞踏出身の目黒だが、自分の硬質な身体の質を東野にぶつけずに、下手に彼女の流麗な動きに合わせてしまったように思えた。
【志賀】
舞台に椅子を置き、その上で東野祥子がさまざまな身体や表情を作る。それはかなり多様かつ意識の集中が見られて面白い。そこに目黒が白シャツにズボンで登場。髪を伸ばして荒々しい印象で、倒れ、転がり、東野に絡み出す。東野も椅子を離れ転がる。かなり激しい動き。実はひと月前の舞台で、東野は足を故障し、普通には立って歩けない状態。それゆえの椅子という選択だったが、その不自由な雰囲気は、非常に踊れるダンサーである東野に、さらなる動きのきっかけを与えたのではないかと思う。目黒もいつものちょっと粘液質な動きではなくきっぱりとした感触で、双方とも次への展開を感じさせるコラボレーションだった。
手塚夏子
『人間ラジオ』

【西田】
いまどきのラジオは自動で周波数を合わせる機能がついていて、周波数を合わせるのに何の苦労もいらない。だが海外短波放送のラジオを買ったときはちょっと違った。周波数も幅広いし、あちこちチューニングすると、世界中のいろいろな言語が飛び込んでくる。つまみを回していると、どこでチューニングされたのかわからないまま、次のチューニングに向かう。一つの言葉が雑音の渦にかき消されたかと思うと、別の言語が登場し、雑音とともに去っていく。オートマティックな機能をはずし、マニュアル操作しようした途端、雑音がいかに多かったかに驚かされる。考えてみれば、日々の生活や習慣で、条件反射的にオートマティックに作動する事柄は非常に多い。手塚が今まで自分の体との対話の中でやってきたことは、オートマティックに反応できそうにないオーダーばかりだった。だからそこにオートマティックな反応は登場しにくい。だがオートマティックに反応しないと思っていても、繰り返すうちに自動装置は反応してしまうかもしれない。手塚が自らに課す課題に対し、他の人はともあれ、非常にプライベートな個の体の中では、オートメーション化された手塚工場身体が作動していないとも言い切れない。手塚はどこかでそこに気づき、自らの自動装置をはずし、もう一度ゼロに戻してみようとしたのではないだろうか。
自分の体がもし短波ラジオの受信機であるなら、どんな周波数の短波も受け止められるよう、アンテナは四方にたてておくだろう。紙に好き勝手にラクガキしてみたり、突如海は広いな、大きいな、と唱歌を歌ってみたりするのはすべて、どこか何かにチューニングしようとしながら、少しずつチューニングポイントがずれていくさまを見せているように思えた。
ふと日常生活というのは、気づかずにオートマティックなルールにぐるぐる巻きにされている状態を指しているように思えた。何気ないしぐさの癖、いつもの手順。それが身体の感度を鈍くしていることがあるかもしれない。
突然歌い出したり、くるくる踊り出したり、同じ動作を繰り返してみたり。音を出すはずのスズキクリは、音を出さないようにそろりそろりと歩きながら音をだす。いつもの手塚らしからぬこと、いつものスズキクリらしからぬことが多発する。少々つまみを回す加減が違うだけで、違った音が出る。そのちょっとした違いを敏感に嗅ぎ分け、感じ分けるというチューニングの感度を上げるための仕掛け、それが今回の手塚のダンスだった。
【坂口】
止まることなくつねに身体との対話を模索し続けている手塚夏子がまた新たな実験を始めた。身体と何が対話するというのか、それは自分だとしたら身体は自分ではないのか、などという身体/精神という古くからある二元論から始まって、即興/振付、意味/無意味、意図的/偶然、成功/失敗、ダンス/ノンダンスという意味の二項対立を身体レベルで溶かしてしまうような彼女の果敢な挑戦は今に始まったことではないのだが、この作品では〈チューニング〉という不思議な概念によって、さらなる新たな領域に踏み込もうとしているようだ。チューニングというのは、外にあるものと何らかの関係性を持とうとすることなのであろうか。自分でない何かになるのでもなく、何かに合わせるだけでもなく、身体によるその微妙な関係性の可能性に彼女は目を向けている。スズキクリがじゃらじゃらと音の鳴るものを身につけながら、絶対に音を立てないようにとソロリソロリと歩いて行くと、手塚夏子は舞台上で対象の位置を保ちながら、音になり損ねた音を気にしつつなにやら即興的にうごめき出す。鳴らない音が気になるのは観客かもしれないけれど、シンメトリカルな位置にあり続けるふたりは、それだけでもひとつの関係性を持っているのだが、だからといってその関係性が意味を生み出すわけでもなく、失敗した音にチューニングするように、意味にならない動きの破片を彼女はていねいにばらまいて行く。短い一連の振付を彼女がいくども繰り返すときにもまた奇妙なことが起こる。繰り返されるからには振付なのだろうが、同じ場所でくるくるまわりながら幾度も執拗に繰り返されると、個々のフレーズが何かの意味を持っているようなフリを装っていたとしても、残像が重なり合って意味が朦朧として行く感覚に襲われる。振付という行為自体もひとつのチューニング=同調行為であるのかもしれない。ラジオというのは受容体ではあるのだが、精密なシステムを備えて自律してもいる。決して何かにそれが成るわけでもなく、何かの意味を纏うわけでもない。私の身体もラジオのように、外から来るものや内から来る様々なものにチューニングしつつ、刹那刹那に変容し続ける。身体の音に聞き耳を立てる主体としての私も刹那刹那に消えては現れるのかもしれないが。ともあれ、チューニングが完了したところで「う〜み〜は〜ひろい〜な〜お〜き〜い〜な〜」と、ばかでかい声があの小さな身体から吹き出すとき、私たちは彼女が正しくチューニングされたことを確信する。
【竹重】
この作品に対する私の印象は、幾らか複雑である。実際に客席に座って、言わば映画のクローズアップの意識で舞台を観ている時は、手塚夏子の肉体の無表情さに苛々し、どうしようもなく退屈してしまっていた。手塚の踊りを「人間」を超えた不気味なものと感じる人も多いようだが、私には、意識が日常のレベルを右往左往しているだけとしか見えず、表情の多彩さにもかかわらず、トランスフォーメーションが感じられない。それは、彼女が肉体のエロティシズムの領域と向き合っていないからだと思う。ところが、公演後時間が経って、少し引いた意識で作品全体を想い出してみると、意外と堅固な手応えが自分の中に残っているのに驚いた。それは、ダンサーとしては素人なスズキクリを、手塚と常に左右対称的な距離を保って舞台上に存在させ、ラストで手塚が歌い出す場面を除いて、2人のアクティングエリアを舞台裏を含めた舞台の四隅だけに限定したという舞台空間の厳密な幾何学的構造によるものだと思う。
【志賀】
手塚と男スズキクリが奥のアルコーブに貼った紙を剥がして破く。それに続く淡々と歩む動きには手塚の緊張があふれ出して、見事、見応えがある。男は体にいくつか鳴り物をつけて、それが鳴らないように慎重に歩む。意図せず出た音を音楽として、手塚が上手で前に進む身振りと存在はなんともいいようがなく魅力的だ。手塚は身体の中、自分の奥底に入り込んで、体を探りながら動きをつくり出す。それを見て体験すると、奇妙な感覚、自分の身体を虫が這い回っているような感触を抱くことがある。踊りは自分とは外で表現されているものだが、それがなぜか、僕たちの身体に共振してくる。特異な表現者である。
砂連尾理(砂連尾理+寺田みさこ)
『陰圧〈In-atsu〉』

【志賀】
男性2人に振付けた作品。シンプルに踊る作品ながら、砂連尾の動きと振りが2人に移植されて、かなり魅力的。終りで2人が衣装を脱ぎ互いに相手の衣装を着るところも面白い。この日、下着は交換しなかったが、翌日は下着まで脱いで換えたと聞く。そのほうがよりリアルで面白かったかもしれない。寺田みさこはソロで独自の道を歩みつつあるが、砂連尾も自分のリアルな世界を着実に模索し続けている。
砂山典子
『First-Class Barbarian』

【坂口】
ダンスとパフォーマンスと政治的プロパガンダの混淆、あるいはそのいずれでもない特異なものが生まれた。そんじょそこらのダンス作品と違い、ここには明確な主張がある。なんであれ暴力に対する抗議だ。近代化という名をもつ暴力、戦争という暴力、性的な暴力……。暴力を観念的に否定するのでは決してなく、自らの生の経験の場において暴力と面と向きあって思考する。そうして切り分けられた暴力の意味を、ダンス、クラブのショー、そしてパフォーマンスというこれまた彼女の生にとって重要な意味をもっている手段で表現する。表象やらコミュニケーションの不可能性などと悠長なことを言っているヤカラを吹き飛ばすように、それこそ暴力的に暴力の意味が表現される。この世界には確かに暴力が存在するのだ。ただし人間の世界と限定すべきだろう。そして暴力が人間に特有なものであるとしたら、性という、これまた動物にもありながら人間においてはそれがもともとなんであったのかわからなくなるほどに奇妙に歪んだり心地よいものとなったりしているものと繫がりをもったとしても不思議ではない。砂山典子は性的なものへと降り立つことで暴力を体現するのだ。とりわけ最後のシーンでは、戦争へといたる暴力と性的な暴力とがきわどく隣接させられる。アメリカがアフガニスタンやイラクにしかけたごとき戦争とレイプとを、どちらも短絡的な欲望の発現として同じ平面に並べてしまう。さらには、「戦争が終わるなら、あなたの気の済むまで慰めてあげる」と言いながら、「猛り狂うペニス」を慰めることで戦争への欲望を静めようとする。異質なものをないまぜにしていることをいぶかしく思った人もいたかもしれないが、人間にとっては性も暴力もイマジナリーな領野での出来事だとしたら、そしてどちらも社会的に構築された産物だとしたら、彼女が両者を同じ平面で見つめながら暴力が消えることを祈り続けるのは至極正しい行為なのではないか。祈り続けることで争いが終わることを願うのはナイーブだと思われるかもしれないが、「わたしの中にも猛り狂うペニスがあります」と言い、自らのうちにどうしようもなく存在する攻撃性をもしゃぶり尽くそうとする姿の、そのあまりに直截な行為には、作品という狭い枠を揺るがすまでのいさぎよさがある。ダンス作品としてのまとまりを見せる前半、クラブのショーとしての仕上がりを見せる中盤、それに対して後半には、もはや作品としてのまとまりとか完成度などと言われるような狭隘な了見を飛び越えて、捨て身で暴力の現場に切り込む気構えがある。劇場という場で消費されるだけで消えてしまうのではもったいない。
【竹重】
純粋なダンス作品ではなく、砂山典子の胸に貼られた“DON’T SHOOT”というステッカーで終わる、 セクシュアルな反戦パフォーマンス作品なのだが、私にとってこのシリーズで一番刺激を受けた舞台だった。全体は四つのパートから出来ていて、しっかりした構造を持っている。ダンスとして観れば、最初の豚の被り物で踊ったパートが、その意味内容を超えて、その静謐な歩行の繊細さで最も充実していた。しかし舞台はその後、喪服で踊る「お経でサンバ」のパートを挿んで、エロティックなSMショーに移行する。このショーの肝は、逞しい肉体に幼児の格好をした松田篤史を跨いで鞭を打つ砂山の股間にディルド(ペニスの張型)が付けられていることで、これによって、このショーは単なるSMショーではなく、マッチョな男の幼児性と、女性の中にも潜む暴力性、支配性を暴き出すものに変化する。ただこの後、素に戻った松田が逆に砂山に暴力を揮う場面の表現は、手緩かったと思う。やや作品の意図を曖昧にしてしまったのではないか。そしてラストのパート、看護婦の姿をしたマリア様の砂山が、銃の先端に付いたディルドにコンドームを被せて涙を流しながらフェラチオする、この作品の最も象徴的なシーンがやってくる。一見通俗的なイメージのようで、前のパートのSMショーを観ている観客は、このシーンが単純な癒しのシーンではなく、快楽と暴力と祈りが複雑に結び付いた、ギリギリの彼女の内面を曝け出したものであることがわかるのである。
【志賀】
砂山はダムタイプのダンサーだが、黒沢美香ダンサーズにも参加、スナッキーという名でソロ活動もしている。今回は大駱駝艦の松田篤史とのデュオ。スーツを着た松田が脚立を持ち込み背景をかけたりする作業の後に、脱ぐとオムツ姿。砂山はSM女王姿で登場して松田を鞭打ち、模造男根で肛門を犯し、さらに反米、反戦モチーフを導入する。裸身を晒すこの舞台は、エロティシズムが社会モチーフに絡み、奇妙にリアリティを感じさせる。性愛という個的な美意識や身体関係を絡めることで、イデオロギーや社会というストレートな主張を異化し、観客の視点を逸らすことで、作品に強度を与えるとでもいえようか。
【西田】
今年の「ダンスがみたい!」では、反戦・平和に関する作品が二つ(砂山典子と加藤文子作品)あった。いずれも女性による作品であったことが偶然なのかそうでないのか、という議論はさておき、砂山典子は、戦争などに顕現する巨大な暴力性のありかを日常の中にも探ることから出発した。セクシャルな欲望にある暴力性が命を奪うエゴにつながる可能性、それがさらに大量殺戮へと向かう道程をみつめ、それが同じ地平線上にあることを気づかせる作品だった。それゆえに戦争を身近に感じていない人々にも、戦争(につながる暴力性)は自らの内側にも存在しているのだ、ということを気づかせ、ドキリとさせられる構造になっている。身の回りに溢れている暴力と国境を越えた向こう側の世界で行われている戦争が同じ地平線上にあることを知ったとき、そこで生まれてくる反暴力を願う意志は単にイデオロジカルなプロパガンダでも、誰かに向けた一方向のプロテストとも異なるものとなってくる。
タイトルを<第一級野蛮人>と訳してよければ、人間同士が互いに刃を突きつけ合う姿を現代の野蛮人として批判の目を向け、自らの内にある<野蛮人>の性に手を焼きつつも、いとおしみながら見つめる思いがそこに重ねられていることが感じられる。
ラスト近くのシーンで胸元に「Don’t Shoot」という言葉を貼り付け、反戦メッセージを読み上げた。猛り狂う暴力性を自らの内にも見出すからこそ、その暴力に抵抗する術も自らの内に探らねばならない。砂山が見出した、暴力性を鎮め抵抗する方法は、ホスピタリティー精神溢れる<祈り>だった。その祈る姿はセクシャルな行為とダブルイメージになっているために一見挑発的な表現に見えるのだが、それとは裏腹にそこには健気な砂山が見える。組織的構造的な暴力を顕現する場となってしまった現代の戦争に抗するには、もはや祈るしか方法は残されてないのかもしれない。だがその祈りに賭けようと決意することは決して慰めという気休めに留まるものではなく、暴力に抗う確かな力となりうる希望があるように思えた。
セレノグラフィカ
『待たない人〜樹下の双魚に〜オリエンタル版』

【志賀】
京都を基盤に活動するこのグループは隅地茉歩と阿比留修一が中心。今回はこの2人にy-yakk79(塚原悠也)が絡む。舞台の3分の2程度の空間をイメージとして仕切り、上から窓などがぶらさがる。そこで阿比留はダンスのワンセットの動きの組み合せを、ポストモダン的にリフレインしていく。それに対して隅地は日常の動きが中心。導入の挨拶や休憩などの「仕掛け」があるのだが、それ以上に踊りや動きの本体が魅力的であってほしい。2人ともオリジナルな動きを持っているが、提示したアイデアやコンセプトに厚みを持たせるには至っていないように思える。
玉内集子
『Shin』

【竹重】
今年1月の新人シリーズの「新人賞」受賞者。玉内集子は現在の所、その華やかだが、どこかごつごつした身体性の魅力を持ち味にした即興舞踊家である。今回は1時間の長さがあり、「構成」という問題に初めて取り組んだように思える。冒頭から20分程は、上手側奥で両手を左右に大きく広げて前屈する、重力と肉体の物質感を充分に感じさせる姿勢から始まる、彼女ならではのダイナミックで即興的な踊り。1月の時に比べると重心が低いコンパクトにまとまった踊りになっていたが、腕や上体の細かいニュアンスの凹凸に今回は欠けていたように思われる。そこから下手側手前で突然正座すると、ノンダンスのポストモダンダンス的なシーンに移行する。様々な静謐なポーズとそれが醸し出すニュアンスに賭けた表現になっていて、彼女としては新しい試みだったが、まだ頭で創ったような印象は拭えなかった。最後に衣装を着替えて弾けた踊りで終わるのも、動→静→動という予定調和的展開になってしまった。しかし、踊りに対して反対の踊らないという意識と時間を切断するという意識を持っていることには可能性を感じる。
【志賀】
ダンスがみたい新人シリーズの新人賞を獲得して登場。たわめ、歪めた姿勢から丹念にかつ丁寧に作り出すソロは、新人シリーズのときには甘かった部分をより意識的に踊り、玉内独自の舞踊空間を作り出しつつあるように思える。前後して玉内の積極的な舞台をいくつも見たが、その鍛えられつつもどこか怠惰にも見える身体は、何か少しずつ新しい世界を切り開いていく、そんなことを期待させる。
【吉田】
暗闇から女が現れる。オリエンタルな音楽と共に下着のようなエロティックな衣裳を着た女だ。ドレッドヘアに童顔で活動的な小柄なこの女性は体の部位を動かしだし片足を前に大きくつきだしたり、片一方の腕を宙にあげるなど、ポーズのような姿から動き出す。やがて腰をつきだしてかがんだり、片腕のみを宙に動かしながら、意識をこねるようなうごきをしていく。1つ1つの動きから作用・反作用ともいうべき関節から生まれてくる細やかな表情も現れてくる。ドレッドヘアが小柄な身体にパッシヴな雰囲気をあたえていく。時には舞台の上に横になり足先と両腕だけで身体を支えたりする。光の中で倒れると身を床に横たえ、前後に身を捩じらせたりもする。髪型がくずれて童顔の作家の表情がその間から出てくる。呼吸がいつしか無音になった大気中に響き渡る。躍動する身体で空気がいっぱいになる。やがて舞台の上にはトマトがはいったミキサーが置かれる。踊り手が身をくねらせる。ただミキサーは回り続ける。肉体はくねらしたり身を起こしたりと激しく呼吸しながら動いていく。次第にミキサーの中の果実がとける-そして無機的な音が空間内に響き続けている。肉体から生まれる有機的な鼓動が意識の変容のような効果を生み出していく。作家が服を着替えて現れると、今度は水着のようなよりアクティヴな姿勢で動ける衣裳で肉体美をいっぱいに動き出す。四肢を床についたり、寝転がったりしながら、体を大きく反転させていく。東洋的な演出やオリエンタルな動きのシークェンスも登場する。作品を散漫にまとめずじっくりとまとめたという意味で玉内の明確な構成力のある作家といえよう。宇野敦子の照明が冴えており充実した舞台を成功に導いた。
《脱・フレーズ》ともいうべき要素を感じさせる作品だ。ノン・ダンスというよりは、踊りをフレーズに集約しないことから生まれる瞬発の瞬間が見える身体といったほうが良いだろう。作家は発想の原型のような形を形作ったり、内面で遡行を重ねるような動きを見せていく。その辺りが既存のダンスに対するアンチテーゼを打ち出そうとしたポストモダン・ダンス世代との明確なずれであるように感じる。タイトルの「Shin」には『新』、『心』、『真』など様々な意味が込められている。しかし作家はモダンダンスほど概念を単に羅列したり、強く作品や身体の向こうに向けて探求しない。玉内は笠井叡の「冬の旅」で伊藤キムらと活動を共にする畦地亜耶加や創作で活躍し始めている山口華子、そして横田佳奈子と共演をしている。流麗なムーブメントから内面と外面の間を描き出した横田の代表作「彼女的依存のバラード」との共通点があるとすれば自我の境界を狙うようなトーンだろう。一方でこの固有のフレーズにムーブメントを集約させない作風は玉内固有のものだ。おそらくヒップホップやジャズコンテンポラリーのようなフレッシュで新しいPVなどに出てくるような躍動するポップなダンス近いことから若いオーディエンスにも人気があるのだろう。2010年代以後の中核をになうことになるこのジェネレーションのダンスの展開は楽しみだ。
shoppin'gocart
『OASIS+sun℃』

コリー・ベフォート
『The Canopy』

【坂口】
コリー・ベフォート振付、エノモトユキのソロ作品。ギザギザの光の残像のなかにラフな白い服のエノモトユキが立ち現れ、これからの動きの準備をするかのように体を前後にしならせているうちに、スッと前方に押し出されて歩き始める。舞台中央の淡い光のまわりを、両手を左腰の脇にそろえた少々窮屈な姿で歩くその運動が妙に印象に残る。それはダンス作品として見ようとしているところにダンスらしからぬ運動が最初に現れることで生じる印象だろうか。もっともそれ以降もエノモトユキは決していわゆるダンスと言われるようななめらかな運動を繰り出すわけではなく、運動を急速に止めては反発しながら、ギザギザしてギクシャクした動きを繫げて行く。運動の個々のパートはそれなりに美しくしなやかであろうとも、それが切断されて痙攣的に再接続されるとき、そこに「内的葛藤」が表現されていると言われうるのかもしれない。でももちろん、表現されているとかいないとか詮索するのは無意味だろう。それは検証不可能であろうから。むしろ、ダンスと呼ばれうる動きの中に差し挟まれてしまう何らかの違和感、異質感というものをていねいに紡ごうとしているようにも見える。それは内面の表出という不可思議なものと想定される必要はなく、あくまでも身体の運動でありながらも、身体という媒介的な存在を介して他者へとともに自己へも向かうベクトルを紡ぎ出しているのではないか。いまだそれが十分に結晶化されていないかもしれないが、そうした可能性へと思いがいたる。
【志賀】
下手に木の枝と木の葉が壁側から差し延ばされ、全体の3分の2、上手側の空間で日本人ダンサーが、ゆっくりと走り回り、そして踊る。そよぐ木のような映像が時折映し出されるなかで、暗い照明を受けて、ダンサーの動きは日常とダンスの狭間をいく。美術も含めた構成と動きはしっかりしているが、インパクトは感じない。見ていて、振付・演出というより「構成」という文字が浮かぶということは、この枠組から身体がどうはみ出すかを、僕たちが求めてるということなのかもしれない。
MayuKan
『Coin of Cabitoh』

【竹重】
振付/演出/出演のダニエラ・クロスが、昨年のこのシリーズで踊ったソロには強く惹き付けられるものを感じた。今年は女性2人を新たに加えたカンパニーでの公演となったが、全体としては散漫な、不満の残る作品になってしまっていた。これは、一つには新しい2人が舞踏家としてはまだまだ未熟なためもあるが、構成的な失敗もある。冒頭で、どこか山道の途中で3人が踊っている映像が写され、そのシーンがいつの間にか目前の舞台につながっていく仕掛けになっているのだが、この映像が20分程もあり冗長なため、すっかり観客の集中力を削いでしまった。しかし、後半二つ目の映像が写された後、特にダニエラの肉体の、重力感とイマジネーションの幻想性が上手く組み合わさったソロは美しかった。ダニエラは、日本人とは明らかに肌合いの違う濃厚な景色を、舞踏の様式を使って創り出せる稀有な資質の持ち主であり、今後が楽しみである。
【志賀】
ダニエラは9年前に日本で男性ソロの舞踏の舞台を見たことがきっかけで、オーストリアに帰国後、再び日本に来て多くの舞踏家たちに学んだ。昨年初めて日本でソロを「ダンスがみたい8」で踊った。戻ってカンパニー繭感(まゆかん)を立ち上げ、これが最初のカンパニー公演だ。オーストリア山中の映像からダンサーが登場する舞台では、ダニエラの身体は際立って存在感が強く、舞踏家として外国人では初めてと思えるほど、僕らに強く迫ってきた。仮面を使う場面や2人の女性への演出・振付も楽しめ、日本の舞踏グループ以上の力を感じることもしばしばだった。来年もぜひ来日を企画してほしい。
滝田高之
『肛門&シガレッッツ』
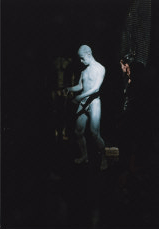
【竹重】
通常のプロセニアム舞台の形式を廃し、客席も舞台空間にして、観客は劇場のあちこちに散らばって、神出鬼没のダンサー達からしばしば逃げ惑いながら観ることになった。冒頭と最後に出てくる、2人の半裸の男に支えられた花札の模様が描かれた凧の真ん中に突き出たお尻の肛門と、紐で結び付けられて胎児のように床に半裸で仰向けに横たわる男のイメージがこの舞台のトーンを決定していて、その間にタイの武術や、5人程で口でゲロを受け渡しするゲロリレー、巨大なぬいぐるみのダンスなど、グロテスクだが楽しめる様々なシーンが登場する。普通の観客の良識を逆なですることを厭わない反俗精神は頼もしいが、観終わった後の印象は茫漠としていて、そこに振付があったかと言えば疑わしい。そろそろ、視覚的なイメージの羅列から脱け出して、踊りを凝縮していく方向へ向かってもいいのではないか。滝田高之のソロの踊りには、充分そういう資質を感じた。
【志賀】
劇団ゴキブリコンビナートの役者で舞踏家滝田高之は、ソロで過激かつ楽しい舞台を作ってきたが、今回は舞踏集団ささらほうさらなどから、9名のメンバーとともに登場。観客は立見で、舞踏手たちが動き回るために、追われるように移動する。中央に絵の描かれた板から尻を出した男、そこから赤い太い腸のようなヒモが出て、それに絡まって倒れている白塗り男のインパクトのある冒頭。赤塗り四人組が口に蝋燭を立てて登場し、祭りのような振りを執拗にリフレインする場面、口移しで液体を垂らしていく場面など、過激かつ破天荒な舞台だ。派手な音楽やバレエ音楽とともに「見たことがない」舞台は素晴らしい。ぜひ集団の舞台にもさらにチャレンジしてほしい。
財津暁平×Taca×大由鬼山
『・・・の無い花』
 -
-
【竹重】
下手側手前にアコーディオンのTaca、上手側奥のアルコーブに野性尺八の大由鬼山が座っている。下手側奥のアルコーブに暗闇の中から浮かび上がると、腕だけが踊り出す。深緑の地味なワンピースに、麦藁帽子という別荘地の女性を想像させるようなキャラクターが創り上げられていて、肉体的にもそのキャラクターに成りきれる、崩れそうな繊細な美しさを持ち合わせている。この身体性の魅力に冒頭から、舞台中央奥で腰を下ろす15分間程は幻惑された。だが、次第に踊りの展開に単調さを感じるようになり始め、終わる頃には私の心の中の熱はすっかり冷めてしまっていた。即興を主体とする舞踏家の宿命か、財津暁平は、まだ一時間程の作品を構成する能力を持ち合わせていないように思われるのが残念だ。踊りの持続していく流れだけでなく、観客の予想を裏切る大胆な切断や視点の転換といったものも必要ではないか。
【吉田】
コンパクトで路上と劇場の中間点と上演空間の意味性を模索しているような舞台だった。尺八とアコーディオンのスタッフが舞台の上に座っている。二人がセッションの様に音を奏ではじめると財津暁平が登場する。帽子をかぶりスカートをはき女装をしている。腰に手をつけてちょっとかがむその姿は「遠野物語」といったフォークロアや水木しげるの漫画に登場する童女のようだ。半陰陽ともいうべき性別を超越した妖しい子どもの傍らからアコーディオンが切ない旋律を奏でたかと思えば、切れ味と野生のある音を尺八が奏でていく。男はゆっくりと身を横たえて、かがんで立っているように見せたりする。遠くをみながら「にかっ」と大きく笑った表情はまるで異星人のようだ。作品タイトルは様々な踊り手の表情の中に宿る《花》という意味合いだろうか。やがて財津は大柄にスピーディーに動き、アコーディオンに沿ってしゃがんだりかがんだりする。構成や設定で工夫をすることも大切だが、この作家は即興舞踊を重んじる作家でもあり、領域や表現手段が近い作家たちと異なるこの作家ならではの表現技法が現在の地平から立ち上がってきてもよいかと思う。ごくごくシンプルな行為が展開されたが、作家が得意とする路上でのパフォーマンスの時に効果を発揮するような表現ともいえ、小劇場での上演をするのであれば構成や演出を通じて、踊り手が演じる場を立ち上げていくことが必要だ。ゼロ次元が活動をさらに活性化させ、神村恵のように路上でのパフォーマンスをする若手ダンス作家もでてきているのであれば、この作家ならではの戦略が見えてきても良いように思う。
CHAOS ROYALE + 86B210+松本隆
『「c.o.l.o.r」- colds laboratory of rabbits』

VIBE DANCE GROUP
『接触(contact)』

【志賀】
韓国のダンスはモダンダンスと韓国舞踊を融合させたり、コンテンポラリーダンス的な新しさを求めたり、前衛パフォーマンス的なものとさまざまだが、大学での舞踊教育が盛んで、教授と学生たちという構造が強く基盤にあるようだ。儒教感覚的ヒエラルヒーの強さも時々目にするが、それゆえかオリジナルなパワーを感じられるものが少ない。今回の舞台自体、面白く見たが、コンタクトインプロをベースに構成した舞踊大学系ダンス以上のものが立ち上がったとは思えなかった。
加藤文子
『らんど・ざ・らんど - standing point』
『らんど・ざ・らんど9 - a peace of idea』
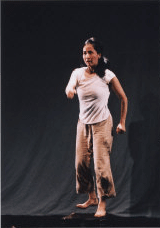
【坂口】
『standing point』の冒頭、椅子に座り足を床に着けずに左右に動かすその足の動きは確かにしなやかで美しい。おずおずと床──というよりも地面に足を着いても、体はすぐには動けない。地に着く前は美しくしなやかに気ままに動かしていられた足は既にそこにはなく、障害物としての地面に妨げられて身動きが取れなくなった足にとまどう体がそこにあるばかりだ。それでもひとは地面を踏みしめながら歩んで行かなくてはならない・・・そこまでしてなぜひとは歩まねばならないのだろう、それは美しさを置き去りにする行為ではないのだろうか、それとも美しさなどは脆弱なものなのだろうか、いや、歩むことはより美しい行為であるはずだ・・・そうした様々な思いを喚起するダンスだった。
『a peace of idea』は、憲法九条を守ろうとする明確な意志のもとで作られたというが、作品の中でそうしたプロパガンダがあからさまに表明されているわけではない。何も知らずに見たら、そうした政治的な訴えがそこにあることなど知らずに作品を受け止めることもできるだろう。加藤文子の狙いは、政治思想の一方的な表明として作品を提示するのではなく、憲法九条に関わる問題、とりわけ、戦争で命が奪われるとはどういうことか、生命の大切さを平和の時にも忘れないでいるにはどうしたらよいのか、そのような戦争と平和に関わる重要な問題をダンス作品を通して考えてみようとしたのだと思う。だから、言葉で直接に思想を語るのではなく、また、あからさまな形として作品の中で現すのでもない。迷彩服で現れる村田弘美を見たり、有刺鉄線が舞台を分断したりするのを見るとき、戦争とまでいわずとも何かしらの暴力的な脅威が迫ってくることを思うだろうが、そこに立ち現れてくる意味は確定したものではなく、それぞれの人が生きてきた歴史や生きている意識に触れてそれぞれの人にとっての意味が生まれてくるのを待っているようなものだ。もちろん加藤文子は、作品それ自体の細部を彼女の身体を美しく使いながら描くのを忘れはしない。あくまでもこれはダンスの作品なのである。その一方で政治思想の真摯な表明でもある。純粋なダンスとして消費されるのでもなく、政治的言明のためだけにダンスが利用されて終わるのでもなく、ダンスと政治に同時に関わろうとする意志のもとで生まれてきた作品なのだ。終幕近くに「たまや〜」となんの障碍もなく声を上げることのできる彼女の声に、平和の理念を言葉であれこれと語る以上の説得力を感じることができたとしたら、それはそこにいたるまでの加藤のダンスが、平和とはどのように体感されるべきものであるのかをていねいに重層的に描いてきたからであろう。
【竹重】
2つの作品が上演されたのだが、今回のメインだったはずの第2部の1時間程の「らんど・ざ・らんど9」よりも、第1部の10分程の「らんど・ざ・らんど」のソロの方に個人的には魅かれた。加藤文子はモダンダンサーだが、舞踏や能の影響も受けているらしく、暗闇の中で肉体の輪郭を見事に浮き上がらせた照明と相俟って、微かな細部の動きに豊かな陰影を籠めることに成功していた。特に腕の表現が美しい。これに比べると、第2部はテーマ主義的に頭で創った印象が否めない。それを証拠に第1部での繊細な身体性は、第2部では全く影を潜めていた。内容的に見ても、政治的な問題をスピリチュアリズムに還元してしまう甘さが感じられ、説得力が弱い。彼女の欠点は、戦争や邪悪な力を外部から自己を脅かすものと考えていて、そういう力が自己の内部にもあるとは全く考えていないように思える点である。その点が砂山典子との大きな違いであろう。肉体に潜む、もっと猥雑な欲望を見詰めることから踊りを創っていって欲しいというのが、私の素直な希望である。
【志賀】
最初の椅子に座って足だけでのソロは見応えがあり、ダンサーとしての実力が感じられた。しかし花火の映像を戦争に見立てながら、軍服や反戦的なものを舞台に載せると、踊りや表現が実に弱くなる。アフタートークでは、日本と米国を行き来するなかで、イラク戦争などからこの作品を作り、米国を回っているという。そういう主張や啓蒙の場では受け入れられるだろうが、ダンスや舞台芸術として置いたときには、作品に対する意識と身体表現の弱さが目立つ。9.11やイラク戦争で目ざめて主張し出す人に共通する、「それまで考えていなかった」甘さも主張のみならず作品に露呈する。舞台表現で反戦やイデオロギーを出すと、タレントがボランティアをするレベルを超えたものを目にすることは稀なのが実に残念だ。
【吉田】
肉体が向かい合う政治、戦争や暴力について表現をする作品は海外では多いが日本ではダンスは視覚的な表現というイメージがあるのかそれほど多くはない。加藤文子の新作は小劇場で踊り手の人数も少なく、ひっそりと世に送り出された。第一部では加藤が手を後ろに動かしたりしてずっと立っている。女は動かない―ひたすらじっとしていて動かない。やがて動き出すと手でフレームを形作ったりする。若干シンプルすぎる件があるのも事実だ。第二部では、冒頭、舞台の上に箱が置かれた島がある。加藤が現れるとこの島の小さな大地を手で丸めてしまったりする。マーチがかかると村田弘美も登場。時折、花火の映像が彼女たちの背景にプロジェクトされる。夏の花火の響きが季節感を立ち上げていく。その一方で花火の音は戦争の火薬の音にも似ているようにも感じさせ湾岸戦争のミサイル攻撃の映像を想いおこさせたりもする。すると、二人は戦争を描写しはじめる。客席前面に痛々しい有刺鉄線が張られる。イデオロギーを主張するプロパガンダ目的で作られたバレエの創作作品のように踊り手たちは具体的なライフルを持って踊ったりするのでもなく、昨年、このフェスティバルでモダン=コンテンポラリーの若手たちを率いて湾岸戦争やジャンヌ・ダルクといったモチーフを描いた古賀豊のようにドラマティックな作品を上演するわけでもない。シンプルで大人が演じているのだが子どもを強調した子どもの身体や動きといった場面が繰り広げられていく。箱庭療法のような世界、コンパクトなイメージによる風景といっても良いだろう。そのため劇場が空間性を感じさせるスペースであったため表現が空間に広がってしまった感覚もあり、作品のコンセプトは興味深くても、上演の完成度を発揮することができず、今一歩な仕上がりだった。
【西田】
花嵐と砂山、加藤の三人は、それぞれ三者三様の作品の中で、自らの性に対する視線を表していた。花嵐は、社会の中での女性の評価のありようを女性同士の争いの中から切り出そうとしていたし、砂山は女性のもつホスピタリティー精神を積極的に評価しその力を信じようとしていた。また加藤は、敢えて兵士も女性に演じさせることで、戦争におけるわかりやすい性の構造が見えてしまうことを回避しようとした。その回避を通じ、また砂山のいくつかの暴力シーンを通じ、戦時下ではいかに多くの女性がレイプされてきたか、ということを思い出させられた。花嵐の女同士の争いを笑って眺めて済ましてしまうだけでは何も見たことにならないと思えたし、同様に砂山のセクシャルなイメージを喚起するパフォーマンスのインパクトにのみ反応していても何も始まらない。
見る側のオンナとしてそこに何を見るのか、生身の体を晒して舞台に立つオンナの生き様をもっと深く汲み取らねばと強く思わせられたのが、今回の「ダンスがみたい9」だった。
批評家 志賀信夫 坂口勝彦 西田留美可 竹重伸一 吉田悠樹彦
彦