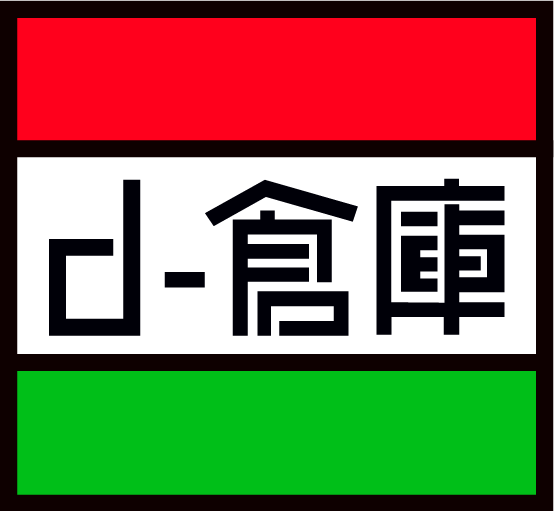ジャンル不問の「ダンスがみたい!新人シリーズ」だが、今回上演された作品は全て「コンテンポラリーダンス」とみなしてよいだろう。コンテンポラリーダンスには、統一的な価値基準も、縁取る枠組みもない。それどころか「ジャンル」という言葉を使うことさえ多くの疑問符がつく。どこまでも広がっていく可能性と多様さこそが魅力であるが、それだけに観る者のそれまでの鑑賞経験や人生経験、知識、文化的背景等によって、何を是とするかは時に大きく分かれる。実際審査員の中でも意見が割れ、自分自身のまなざしのバイアスを省みるとともに、多種多様の作品の中からひとつだけを選出することの困難さを痛感した。
本コンペティションの特徴は、受賞者に対し、受賞作の再演(同年夏)と新作の単独公演(翌年夏)の両方が約束されることにある。2年がかりで支援するこの体制からは、未来を見据え、アーティストの挑戦に伴走しようとする主催側の姿勢がうかがえる。その点、上演時点の完成度を競うタイプのコンクールとは性質を異にしていると言えるだろう。
これを踏まえ、夏開催の「ダンスが見たい!」に選出するという視点から、以下に挙げる項目を評価軸に据えて審査を行った。
(1)動きに必然性と独創性があるか。身体性の選択に、一貫する美学を見て取れるか。
(2)作品の構成力があるか。時間的展開、空間的展開等、ドラマトゥルギーが成立しているか。なかでも重視したのは、関係性の作り方である。音楽、美術といった作品の構成要素とどのような関係を構築しているか。さらに、出演者同士の関係、観客との関係にどのような意識を向けているか。
(3)意外性、裏切りといった驚きがあるかどうか。
今回は作品解説の配布はなく、タイトルのみが手がかりであったため、コンセプト面への注目度は低めに設定した。
他者に見せることを前提としている以上、作品に対して客観的な視点を持つことが求められる。全体を通して気になった点をいくつか挙げておく。
1点目は、無音の使い方である。今回、無音から始まる作品もいくつかあったが、無音も一種の「音楽」であり、ある側面では通常の楽曲使用より強い意味をまとう。効果的に用いれば観客の意識集中を促すが、音楽という一つの求心力を手放すゆえ、散漫になる危険も孕む。その一方で、楽曲が入った途端、その前の無音の場面で保たれていた緊張が緩み、音楽にすっかり乗っかってしまうようなケースも散見された。いずれの場合も、無/音に拮抗できるだけの身体の強度が必要だ。
2点目は、言葉の使い方である。近年ダンサーが舞台上で喋る作品は増えており、それがハイブリッドな新たな表現を生み出していることは確かだ(私自身の研究テーマも「ダンスにおける発話」である)。だが、単に流行に乗るのではなく、なぜ言葉を必要としたのか、ダンス作品であえて喋るのか、ダンスならではの使い方とは、と自らに問うてほしい。実際に演劇の文脈ではすでに多くのことが試みられている。そこに参入する必要も、そこと比す必要もないが、安易に言葉を用いるとダンス自体の力まで失う危険があることは意識する必要があるだろう。
3点目は、既存の“動きの語彙(ボキャブラリー)”の使い方である。なかでも気になったのは、ドラマチックな仕草とダンステクニックとを無批判に用いている作品が多く、さらに、両者がかみ合っていないケースがしばしば見受けられた点である。自らが選び取った動きに反省的なまなざしを向けるとともに、その微細なグラデーションを追求していってほしい。
4点目は、自らを構成する要素への意識である。あらゆる創作は模倣から始まると言われるとおり、先立つものを手本にし、その技を盗むことは、新たな表現創出の土台になる。また、尊敬する振付家や指導者のスタイルを継承することも大事な側面であろう。その上で、何が自らの価値観や表現を形作っているのかという点には自覚的であってほしい。無自覚なまま何かの劣化版コピーになってはいけない。
以上の基準のもと、私が注目したのは、Von・noズ(10日)、砂と水玉(4日)、今枝星菜(10日)の3作品である。このほか、作品と向き合う姿勢が特に印象に残ったものとして、武田摩耶(5日)、高瑞貴(6日)、笠原すみれ(8日)を挙げたい。各作品については、上演順に以下詳述する。
いずれも渾身の作品で、残念ながら受賞を逃した中にも素晴らしいものが数多くあった。道なき道であろうとも、自らのやりたいこと・信じることを徹底的に突き詰めていった作品を、一観客としてこれからも見たいと思う。

1月4日(木)
三谷真保『RED』
赤いリボンを象徴的に用いた作品。背中向きに座った状態から始まり、背面の動きを見せてから振り返るまでの一連の場面を、さらに発展させられるように思う。立ち上がった瞬間にリボンに包まれた椅子が姿を現すのは、視覚的インパクトがある。ひとつひとつのラインが美しいが、少々型にとらわれている印象。
矢島みなみ『composition』
動きを抑制し、非常にミニマルなところを追求した作品。空間を測っていくような無機質な動き、その淡々とした反復からは、なんらかのルールを自らに課しているということがうかがえる。だが、何によるコンポジションなのか、その構成の核やロジックが見えてこない。視線がひとつの鍵である気もするが、それにしては少々意識が弱い。作品後半、加速していくドラムの音の中、正座をし、ゆっくりと背中をまるめていく場面の密度には目を見張った。
砂と水玉『スクラップ・アンド・ビルド』
音楽をうまくつかった緻密な展開で、無音の場面から音楽有の場面への移行が巧み。男性の、一見緩く見えつつも、実は行き届いた身体性が興味深い。なかでも印象的なのは、終盤に一列になってバラバラの動きをする場面。三者三様の身体性ながら、内的に「動きの質」を共有している。構成面では、ユニゾンに頼っている面が否めず、今後さらなる発展を期待。作品中盤、いきなりのテンション変化と子ども性の押し出しは、観客を置き去りにする危険がある。
中村駿『サハラ』
非常に踊れるダンサーだが、動けすぎるという印象が残る。自分で縛りを設けるなど、もう少し身体と動きへの挑戦を見たい。動きの要素をそぎ落とすことで、その作品で追求する身体性が浮き彫りになってくるのではないか。台詞とダンスの併用については練度不足で、特にラストは工夫の余地がある。台詞と連動した具象的な当て振りと抽象的な動きとを接続する技術力は確かなので、そのつなぎの巧みさを活かせるとよいかもしれない。また、時には押し出していくだけでなく「引く」ことで、作品に緩急が生まれ、観客の意識を惹きつけられるようになるだろう。
1月5日(金)
おやすみワンセカンズ『トゥ・マッチ・ペイン』
体操服の女性5人の群舞。タイトルにもある「痛み」の見せ方がかなり直截的なので、工夫がほしい。それぞれが壁に向かって動く場面、5人のユニゾン場面など、各場面におけるダンサー同士の関係をもう少し明示できると、痛みの表象に奥行が出るのではないか。また特定の指示をもとに各人が動いているという風に見えてしまっているので、アイディアを取捨選択する編集作業を行うと、作品としての強度と一貫性が増すだろう。集団制作は難しいが、同じバックグラウンドを持つ5人という特性を活かしつつも、単なる公約数の提示に留まらない作品制作を期待したい。
球磨ユキ『赤いため息 -soft sounds from another planet-』
オイリュトミー由来の呼吸の使い方が面白く、今後さらに深めていける発展可能性を感じた。展開が早くなってきた時に、動きが先走るあまり呼吸のリズムが失われてしまったので、そのバランスをうまく取れるとよいかもしれない。雑誌やチラシで舞台空間を円形に縁取っていたが、その空間構成と道具立ての意味がもう少し見えてくると、作品の意図が明確になるだろう。いまは回収しきれていない印象を覚えた。
樋口聖子 『巡ル』
朧月のような壁当ての照明や繊細な照度変化が印象的な作品。その佇まいとラインのひとつひとつが美しいが、動きが増え流れに乗ってきた時に、型が先行してしまった印象を受けた。誰もが知る名曲(ドビュッシー『月の光』)はことさら訴求力が強いので、動きのドラマを意識的に構築しないと音楽に飲まれる危険がある。また、この作品の神秘的な雰囲気には、日常的な衣装が少々不釣り合いかもしれない。一情景のみで完結した感があり、さらに展開していくのを見たかった。
武田摩耶『record』
冒頭、光の中を客席に向かってゆっくり歩いてくる際の観客をしっかり捉えた眼差しが印象深い。場面の時間的な展開は丹念に作られていたが、ユニゾンに入るきっかけが丸見えであったり、正面性がやや強すぎたりと、個々の場面の構成は改善の余地がある。また、4人の関係性に変化があってもよいのではないか。動きの強度があり、初盤のその場で身体を検分するような振付も魅力的だったので、このような仕草レベルの微細な動きをさらに探ってみてほしい。
1月6日(土)
高瑞貴『くちばしの黄色い女』
光と影の使い方が巧みで、照明が単に空間を区切るだけでなく、ダンサーの意識の広がりを表す役割を果たしているように感じた。照明が直接当たらない空間で、漏れ光を利用しながら踊る姿も美しい。ぶれることなくきっちり静止できる身体で、動きの質が良いが、前半部は豊かな音に対してダンスのリズムがやや平坦。また後半部は急に振付がダンシーになったが、動き数を多くせずとも十分紡げる力量の持ち主と思う。
水中めがね∞『有効射程距離圏外』
舞台に登場し、おもむろに客席に向かって語りかけることで、観客との関係をはじめに設定する。ニコニコとこちらを見ている姿が記憶に残る。しかし、映像を挟んで前半と後半の場面の連結が弱い。作品後半は暗めの舞台空間でプロジェクターの光の中踊るのだが、その「真面目なダンス」が、メタ発言を行う前半や、奔放に屋外に飛び出していく中盤場面とうまく接続していないように感じた。また、バレエから日本舞踊、コンテンポラリーダンス、ヒップホップまで踊れる多才なダンサーだが、本作品ではスタイルの提示のみに留まっていた印象。その複数の身体性を混ぜあわせた姿も見てみたい。
田中朝子『imagination』
雨合羽の形状やテクスチャーをうまく利用した動きの工夫が面白く、ゴミ袋の横にまるで無機物かのように座っている初盤の姿もインパクトがある。技術に長けたダンサーだが、全体を通して、その技術に頼りすぎずに身体を探っていこうとする姿勢がうかがえた。ペットボトルを扱うなど日常的仕草を行う際に少々散漫になるので、今後練度を上げていけるとさらに良いだろう。歩きながら撮影したと思しき映像の「日常性」と、舞台上の非日常的情景の重ね合わせ方には、工夫の余地がある。
鈴木紺菜『向日葵—あなただけを見つめる—』
ひまわりを象徴的モチーフにした、女性5人の叙情的な作品。モチーフの用法をはじめ、物語展開や登場人物間の関係がベタで、最初の段階でオチが読めてしまうのが残念。また、観客を作品世界へと引き込むには少々吸引力が足りなかった。その一方で、コンタクトワークの展開の豊かさは印象に残った。
1月8日(月)
内田しげ美『ブラックホール』
作品冒頭の関節の動きを確かめるような仕草が、謎の生き物のようで引き込まれる。小柄で柔軟な身体を活かして、しゃがんだ姿勢だけで不思議感を出していたのも面白い。ブラックホールたるバケツとの関係は、一層深められそうだ。後半、よくあるダンスシーンになってしまったのが惜しい。また、ボイスパフォーマーとの関係がやや不明瞭に感じた。
美音異星人『スーパー満子』
たとえば鷹の爪団のような、漫画アニメに出てくるへなちょこな悪の組織といった雰囲気。楽器横に控えて舞台上の出来事を静観する女性の存在が効いている。音楽のミックスや、作品終盤の「美音フラッシュ」の場面での光(舞台照明と懐中電灯)の演出が洗練されている。敢えてB級感を狙っているのはわかるのだが、度々の下ネタや妙な絡みには困惑した。
笠原すみれ『箱 to 糸』
丁寧に自分と向き合った作品。耳をつかむ動きや、壁に沿わせた手の動きなど、既存の語彙に頼らない光る振付が随所にあった。ただ、ゆっくりと動いていて急に切り替えるという方法が目立ち、少々単調に感じてしまった。ソロの場合は特に間合いのコントロールが難しく、自らの体感と観客の体感がずれることがしばしばあるので、時間展開を客観的に整理し直す必要がある。また、25分ならばもう少し場面展開がほしい。逆に今の内容ならば10分くらいに凝縮可能であるようにも思った。
梁瀬理加/児島麦穂『手紙』
揃いの格好をした女性2人組が、トイレットペーパー(中国語で「手紙」)を切る/切らないに始まり、じゃんけんやグリコなど、子どもの遊びを繰り広げる。キャラクター設定や関係がシンプルで親しみやすく、子ども向けの出し物に向いているかもしれない。実際客席の子どもが笑っていたことが印象に残っている。もう少し個々のキャラクターが立っていた方が、効果的だったのではないだろうか。
1月9日(火)
イトカズナナエ『Babel』
ミサ曲『キリエ』が流れる中、瀕死の白鳥(不死鳥?)を思わせる動きで立ち上がっていく冒頭部は迫力がある。その後も、倒れては何度も復活し、不敵な眼差しを観客に向けるのだが、その反復が少々過剰な印象を受けた。一種の執着や欲望の体現なのかもしれないが、客観的に場面を整理しないと、独り善がりに見えてしまう危険がある。舞台奥にバベルの塔を思わせる梯子がかかっているが、なぜそこに向かうかの意味合いが作品からは見えてこなかった。
山本裕『モザイク紳士』
冒頭の足指の動きや痙攣的な動きの不可思議さに惹きつけられる。しかし中盤以降、伸びやかに動きすぎていて、作品が描き出す奇妙な怖さと釣り合っていないように思えた。上述のような微細な動きでも十分身体能力はうかがえるので、もう少しそこにこだわっても良かったのではないか。また短くまとまりすぎていたため、長い作品を作るとどうなるのかという可能性が見えてこなかった。
住玲衣奈『←出口A9』
音と動きの連動と非連動のバランスや、場面間のつなぎを溶け合わせていく様が見事で、作品としての完成度が高い。また目づかいも印象的だ。しかし、ダンスシーンの取り入れ方、動き出しの振付、使用音源、ラップとの合わせ方、挙動不審な立居振舞など、多くの要素に川村美紀子に重なるものを感じてしまった。身体・音楽・最小限の小道具で情景を立ち上げる演劇的構成に長けているように思うので、その点をより独自路線で発展させられると、個性が一層際立ってくるのではないか。
大和『東京夢物語』
ミュージカルのようなエンターテイメント色の強いナンバー構成で、ダンスの面でも空間構成の面でも技術があり手馴れている。しかし既視感のある場面が多いことが気になった。とりわけ映像等で広く人口に膾炙している特徴的な振付(たとえばDAZZLE、WORLD ORDERなど)は観客の記憶にも強く残っており、自身にそのつもりがなくてもそれらのコピーと見做されてしまう危険があることは意識した方がよいだろう。
1月10日(水)
Von・noズ『牙のありか』
空間構成が緻密で、特定の場所への移動をきっかけとした場面の切り替えが見事。また、ブツブツ言いながら歩き回る振付を一種のつなぎとして繰り返し用いているが、その喋りのトーンによって場面の雰囲気を変化させている点も面白い。具象的な身振りが元になっている場合も、振付として抽象化されているので、単なる演劇的身振りに留まらない「ダンスの強み」を感じさせる。作品に対するクールな目が随所にうかがえ、2人でひとつのソロを作るという創作方法が功を奏しているように思う。終盤、それまで強迫神経症的な振る舞いを見せていた女性が、リストのピアノ曲『ラ・カンパネッラ』が流れる中、プツーンと何かが切れたようにコケティッシュに変容するところが魅力的であった。
À LA CLAIRE『ゆらぎ ver.K』
スローな時間を生きる浮世離れした姉妹のような佇まいで、独自の世界観がある。特に冒頭、とろんとした目で静かにこちらを見ては、ごろんと体勢を変え背中を向けてしまう2人の姿に引き込まれた。ただ、急に動きが激しくなるあたりはありふれた展開に見えてしまったので、もう少し緩やかにテンションのゲージを上げていくか、いっそ静かな世界を貫くかしてもよかったかもしれない。たとえば中盤以降、バットマンのように脚を上げる動作を何度か行なっていたが、ダイナミズム的に作品世界に合わない印象を覚えた。2人の静と動のコントラストは効いていたので、異なる身体性を活かしながら関係性をさらに作り込むと、より一層意図が明確になるのではないか。
今枝星菜『執行猶予』
ひとつのモチーフにストイックに、徹底的に向き合い、非常に豊かな動きを生み出していた。体幹の強さを感じさせつつも不思議な浮遊感を持ち合わせている点が魅力で、とりわけ作品の冒頭と末尾に出てくる柱を使った場面が印象深い。作品の完成度という点ではまだ不足があるが、伸び代が感じられる。全体的にやや単調に見えたので、場面展開はもう少し大胆でもよかったかもしれない。特に髪の毛を解いてから前半の場面を反復する部分では、前半との差異が明確になると面白いのではないか。
[さかい to しんじ]『KANYUU』
ダンス部への勧誘をテーマに、ハイテンションで押していく男女のデュオ。アニメ『タッチ』の主題歌や松任谷由実といった皆が知っている邦楽の使用、マンガチックな照明の使い方や作品の展開など、幅広い観客を楽しませる間口の広さがある。また2人ともダンスの技術が確かで、サービス精神も旺盛だ。ただ、この作品についてはコンペティション向きではないかもしない。
1月12日(金)
ibis『si-ta-ta』
腕を脈打たせるような動きの反復、足はハイルルベで手は拳を握っての四つん這いなど、随所に特異性の際立つ動きがあった。ある種の不安定さを孕んだ身体性の追求が面白い。後半の針金を使ってのシークエンスはもう少し発展可能だろう。今は前半に比して散漫な印象。一回暗転した後、素の調子で観客に向かって話しかけるのだが、自意識を強く感じてしまい残念。観客に直接向ける言葉は、とりわけ研ぎ澄ませる必要がある。
ザ・プレミアム・ワルツ『サヨナラ!青春』
男子らしさ満載のデュオ。全く異なる身体性を持ちながらも釣り合いが取れていて、それぞれが映えるようになっている。冒頭の首だけクイっと動かして音を拾っていく場面、後半のヲタ芸の場面(特に2人が縦に重なって動くあたり)など、随所に光る画があり、振付的にも構成的にも力があることを感じる。また赤色誘導灯やサイリウムといった小道具を何かに見立てて用途を段々ずらす、何度死んでも生き返る等、舞台が根源的に持つ「遊び」の側面を想起させる。しかし中盤は中だるみした感が拭えない。小芝居に持っていく必要があっただろうか。
小野彩加 中澤陽『共有するビヘイビア』
料理など、異分野における説明の定型文を借用しながら作品制作プロセスを語る、トリオ作品。よく構成された台詞回しとフォーメーションで、演劇の手法にも通じているように感じた。ただ、やや言葉に頼りすぎているゆえ頭でっかちな印象を受けてしまった。発言内容と選び取った動きの関係性も見えない。「ダンスがみたい!」で発表する、つまり「ダンス作品という枠で上演する」ならば、批評的でよいから、もう少しダンスに正面から向き合ってほしいと思う。むしろ既存の動きには意外と無批判であるようにも見えた。
古茂田梨乃『夢から醒める、その前に。』
精神的な強さを感じた女性ソロ。前半部の本を用いたくだりや、四つ這いで再び現れる場面など、焦らずしっかりと観客に向き合う度胸が見える。ただ、日常的な仕草とダンス的な動きの境界線はもう少しぼかせるように思う。本やトランプなど象徴的な小道具を用いているが、特に後半のトランプをばらまくあたりは、少し段取りっぽく見えてしまった。小道具扱いは時に難しく、物に意識を集中するあまり観客への意識が疎かになってしまうことがあり、工夫と練習が求められる。
1月13日(土)
上原香『手紙を書く』
沖縄の民謡など、邦楽を用いた物語仕立てのソロ作品。暗転によって次々に時間がとび、場面が切り替わり、時には走馬灯のように再現される。それらの断片的場面を歌が繋いでいく様は、アニメ的な構成、たとえばジブリ映画のエンディングなどを思わせた。思い描いている情景があるのは感じるが、劇場というブラックボックス内でそれを立ち上げるには至っていない。これは私の妄想だが、現実の風景の中でビデオダンスとして撮影すると映えるかもしれない。また音楽との関係が単調で、カウントがそのまま見えてしまっていた。
三田真央『reincarnation』
ブルーのワンピース、一つ結びの髪型の女性6人の群舞。カノンを用いて作り出される画が美しく、単に幾何学的であるだけでなく微細なニュアンスづけがなされており、視覚的センスを感じる。目で見て合わせている様子や待っている様子など、手の内が観客にも見えてしまっていたため、もっと畳み掛けるようなめくるめく展開にしても良いかもしれない。後半衣装を変えるが、その変化による転調が不明瞭だった。また作品の随所に象徴的な2人組の場面があったが、その差別化の意図が伝わりづらかった。
oblique line『薄明』
親密な男女のデュオ。前半の光の演出や、薄布の使い方、ダンサーの夢見るような目づかいから、幻想的な世界を構築するのが意図かのように思える一方、黒子が丸見えという、相反現象が起きていた。クリティカルに内幕を明かしている風にも見え難いし、かといって「ないもの」とするにはあまりに存在感があるので、無視しているのが奇妙であるように見えてしまう(もしかしたらテクニカル面の限界もあったのかもしれないが)。女性が激しく踊り出すあたりで、それまで濃密だった2人の関係性が曖昧になってしまった。
Future Fighters !『Fighter』
作品前半では、ヴォーギング、パラパラ、エアロビ、アイドルダンス、ボクシングなど、見られる視線を意識して頑張る女子の姿[外側]が、メドレー形式でテンポよく提示される。その構成は巧みで、なかでもユニゾンの作り方にセンスを感じる。ただ、これらの引用を批評的に行なっているのか、純粋に面白いからやってみたのかという点は、作品からはうかがえなかった。いずれにしても、思い切りやり切るか、あえてエセっぽくやるのかというスタンスは明確にした方が、コンセプトが見えてくるように思う。一転して後半は、女の子の心の内[内側]を描くが、その女性性の押し出し方に、男性目線のステレオタイプを感じてしまい、個人的にはあまりのれなかった。
1月14日(日)
MIRA『Re』
ダンサー自身の際立った存在感を活かしたインスタレーション的な作品で、ギャラリー空間などで映えるように思う。上半身の堂々たる佇まいと、わざと足裏を硬直させ不安定にした下肢のコントラストが面白い。身体自体の動きはかなり抑制しつつ、衣装の一部であり美術でもあるビニールの運動や造形をみせていく。光への当たり方を工夫すると、その視覚的効果が一層あがるのではないか。冒頭、1人だと思った人影が実は2人だったという点には驚いた。
pickles『ポケットプラネット』
溌剌とした女性6人による、ちょっとコミカルでちょっと怖いアノニマス集団。勢いのある展開で、群舞として映える作りになっている。録音音声のみで物語を作っているが、言葉のきつさばかりが立ってしまい、上滑りしていた。振付の構成ロジックと物語要素が完全に分離しまっていることも要因かもしれない。ステートメントがあるならダンスで示すことを目指してほしい。ダンサー同士の関係をしっかり構築することで、表したい状況を言葉に頼らず描き出せそうな気もする。また、作品としての強度も上がるだろう。
Mr’Scot『SHIRUKU』
どこかをじっと見る目が印象的な、女性3人の作品。三人三様まったく異なる身体性と温度感は面白くもあるが、時にアンバランスすぎるようにも見えた。持ち味に応じて振付も工夫が必要かもしれない。「シルク」という言葉が繰り返される場面では、声のトーンには様々にバリエーションがあるのに対し、身体にあまり変化が見られず、もっと声と身体を連動させてもよかったのではないか。また、技巧的な動きを行う際につい無意識にとってしまうバレエっぽい身体のラインをどう扱うかも考えてみてほしい。
やまぐちゆうこ『称賛 Accessaries』
アクセサリーを身につける/外すことで様々に変化する女性心理を描くソロ。コンセプトは明確。冒頭部分はもっとハイテンションで押した方が観客をつかめただろうし、中盤以降にアクセサリーを外して行った時との落差も作れる。様々なダンスのスタイルを用いていたが、動きの形式性が立ってしまっており、心理描写にはいまひとつフィットしていなかった印象。場面ごとにガラリと変化させるのでも、特定の動きの質を突き詰めるのでもよいが、なんらかの動きのドラマトゥルギーがほしい。

呉宮百合香 (ダンス研究)
早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍。日本学術振興会特別研究員。パリ第8大学芸術学修士課程修了。2015-2016年度フランス政府給費留学生。Dance New Air(旧ダンストリエンナーレトーキョー)、横浜ダンスコレクション(横浜市芸術文化振興財団)、NPO法人ダンスアーカイヴ構想などにも携わる。
>back
|