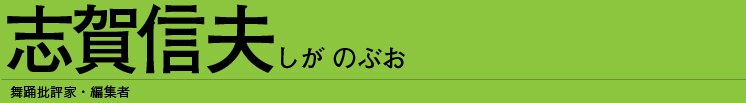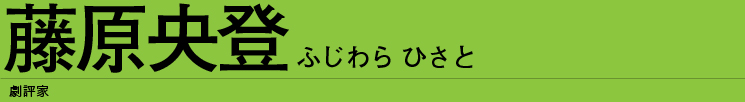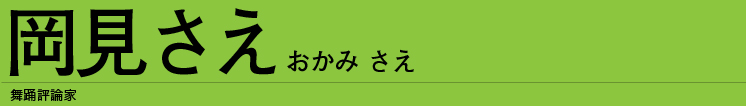総論
コンテンポラリーダンスのレベルは確実に上がっており、日舞、バレエからの挑戦も、以前のようにとってつけたものではなく、十分混ざり合った意味のある作品だった。全体としてオリジナルな発想で見たことのないものを作ろうとする意欲が感じられた。
今回、男性の参加者が多く、32組中9組、28%という状態。舞踏系はそのうち2人だから、男性のコンテンポラリーダンス志向は強まっているといえる。もはや、女子中心だった「コドモ身体」といわれた時代ではない。この舞台の女性デュオも徐々に変わり、しっかり体を絡ませて一体となったフォルムを生んだり、日舞とコンテンポラリーが合体したり、挑戦を続けている。
そんななか、個人的に出色と思われたのが、5日の羽太結子、13日のまさおか式、14日の黒須育海、17日の杉田亜紀だ。詳細は個別評に書いたが、特に黒須は男性中心のグループとして今後が楽しみであり、羽太、まさおか、杉田のソロはさらに新作を見たいし、ぜひみなさんにも見ていただきたいと思う。
舞台のアイデアはちょっとした思いつきから始まる。それが一見、奇妙なものに思えても、本気になってこだわれば実現し、観客に「見たことのない世界」を与えることができる。もちろんその過程でブラッシュアップ、作っては壊す作業の繰り返しが必要だ。ともあれ執念を持って作った作品には、人に何かを感じさせるエネルギーがある。これからも、そういう舞台を楽しみにしている。
1/5
中村理
黒電話を持って立ち、ベルが鳴って受話器を取ると、音楽が流れるという形。時にその音楽に反応して踊る。おそらくかなり以前、モダンダンス初期にも、だれかがやったのではというアイデアだが、緊張と集中感に抑えた照明で、男一人のソロがくっきりと浮かび上がった
いそ+
昨年も出たゆみたろうと2人の女性。女たちが緩い踊りを踊り、下手手前で尺八を吹く男。ゆみたろうも含めて自然体の踊りということなのだろうが、訓練を積んだダンサーでも、コンセプトや貫くべき強い意識がないままでは、単に普通の体がそこにあるだけにしか見えず、尺八の技術があるだけに、それが生きずに残念だった
羽太結子
緩い衣装から体を出すという行為をゆっくりと行う場面はとても引きつけたが、次の景でサティのピアノに朗読が流れたときには、ああ、定型と思った。それでも動きに密度と存在感があり、かつ台詞の最後は凡庸ではなかった。それからキーボード系の多重録音の音で人形的、関節的な動きで踊るのだが、その技術と体そのものが目に残り、印象的な舞台となった。
大東京舞踊団
黒のアクセントでゾンビ的ともいえるおもしろい化粧をした男が十数人、激しいロックで踊る。体操とダンスの間といえるシンプルな動きで、オタ芸とか一世風靡のようなノリだが、時に曲に合わせて歌をわめくなかで、奇妙にそのエネルギーは感じられた
1/6
GRILLED BITCH CONTROL
昨年も出たが、女性性を強調したダンサーと冴えない感じの女性ダンサーが組み合わさり、ショー的パフォーマンスとともに、その差異を強調して踊る。こういうコンセプトの場合は、徹底して笑えるとか、ダンスがメチャ凄いとか、特徴がほしい
藤井友美
脚立でホリゾントの黒い壁に照明を付けて、その下にぶら下がる行為を数回繰り返し、その後、半分闇の中で暴れるように踊る。その激しいリフレインは後半明るみに出るが、同じ動きを執拗に行うことで、空間を変えようとしていた。それが成功したかどうかはわからないが、何かを感じさせる舞台だった
田路紅瑠美
女性が五人、下手奥から観客席に向かって揃って歩いてくる繰り返し、そのなかで、1人ずつ倒れたり、別の動きをしたりするバリエーション。さらに横に向かい同様の隊列ダンスのヴァリアントが、強い現代音楽に乗っていくリフレインは魅力的。そのヴァリアントはしっかり振り付け構成されており、なかなか見応えがあるが、揃い方などは、より訓練を積むともっとかっこいい。中盤で町の騒音の緩い踊りの場面から、再び元の音楽とともに終わりに向かうが、緩い部分はもっと異化するコンセプトが必要だ。全体としてはなかなかの完成度で、もう少し詰めるとレパートリー化できる作品だ
モモ
女性2人がモダンダンス的かつ緩めの衣装で、とても構成された動きだが、全体としてその緩さ、シンプルさ、2人の共感などを強調した踊りで、しっかりと見せた。2人のキャラクター、存在感などもあり、魅力的だった
1/7
石井則仁
白シャツにズボンでうろつくように歩き、時折観客席に向かい、そして暗くなった中で暴れるように踊る。ホリゾント床の蛍光灯がチラチラ点滅して身体は時折見えるのみ。やがて上手手前から下手奥に這っていくなどの動き。上手壁、下手壁下の蛍光灯も同様に点滅して、光で惑わせる。動きはシンプルだが密度もあり、かつ見せ方がうまい。ただ、ホリゾントの蛍光灯はまぶしくて疲労感を感じた
吉川千恵
女性2人、1人は朗読し、横たわったりしながら、時々踊り、もう1はそれをBGMのようにして踊る。このコントラストと緩さを生かしたダンスで、後半揃って踊る部分などで、テクニックはしっかり感じられ、コンセプトも今時だが、中に一つ事件がほしい
すこやかクラブ
オーバーオールの男女と司会者のような長身の男性。男女は元気に踊り、司会者は躁状態のノリで問題を出したりギャグらしき行為。司会の男が女装すると女も赤いドレスで揃ってお色気ダンス。男は脱がされ消えて、女のソロ。それも消えて再びオーバーオールのダンス。たぶんヴォードヴィルをイメージしたような作品だが、古っぽいギャグの重なりは色あせた印象がぬぐえない
熊谷理沙
上手奥から長い白い衣装を引きずり下手手前へ。その衣装で体を隠しながら動く。感情を表現するような激しさを見せ、最後はホリゾント上の空間で1人立つ。シンプルでコンセプトもいいが、そこに身体を強く感じられたかというと、いま一つ。何らかの内包する葛藤が感じられると、もっとよかったかもしれない
1/13
立石裕美
舞台中央に白い巻紙、上手にプロジェクター、下手に携帯とノートパソコンを配置することから始まる舞台。巻紙を広げて横たわり、既にある線の上に自分の身体をマジックで型どり、横たわったまま手を伸ばす、足を上げるなどの動作。携帯を開き歩きながら動作し、アラーム音とともに動く。パソコンを開き震災の場面を流す。紙をセンター奥のポール2本の間に張り、そこに自分の姿のデッサンを投影し、そのポーズを上手で行う。細身の整った身体ゆえに抽象化された動きがよく似合い、パフォーマンスとして見せるが、これはダンサー自身の持つ独特の魅力で見せているようにも思えた
まさおか式
iPodを腕に貼り付けてイヤホンをして、音楽を聴きながら激しく、時には情緒的に踊る。その動きが半端なくエネルギッシュで見せる。かつ背景に流れるプレスリー、モンローなどとは異なる音を聴き踊っており、当然合わないのだけど、時に合いそうにもなる偶然性による微妙な感覚、その差異を浮き彫りにするというアイデアがおもしろい。ダンスの熱が感じられる舞台だ
KEKE
下手奥から両手を上にのばし拝むようなポーズから、片手を上にのばして体を開く。ゆっくりと無音か僅かなノイズのなかで踊る姿は、フォトジェニックに美しい。途中繰り返し倒れるところ、上手で暴れるところがあるが、これらがもっと徹底すると、舞台にアクセントがついたはずだ
仙田麻菜
赤い布で顔を隠して登場し、外すとそれを口にくわえたまま激しく踊る。この場面がとても魅力的。以降も赤い布をモチーフとしながら、いろいろ場面をつくるのだが、ちょっと盛り込みすぎた感がある
1/14
小山晶嗣
車いすを持ってきて踊るという発想は悪くないのだが、そういうモノを登場させるときには、しっかり考えなければいけない。例えば英国にはカンドゥーコという車いす障害者のダンスがあり、コンドルズの近藤良平とも一緒にやっている。車いすを使うことにあらゆる可能性を追求して行わないと、中途半端にしからならない。ただ自分の影絵と踊る場面には、惹かれるところがあった
髙橋和誠
緩い始まりから、照明の中に身体を置くということに徹した舞台。ただ、力あるダンサーが動かないからといって、置いた以上のものになったかは、疑問。意志と意識が徹底しているようには思えなかった
佐々木すーじん
「ダンスが見たくない・というアンチテーゼを冒頭で述べ、「踊らない」といって始めるのだが、その後、「結局踊ってしまいました」というのは、コンセプトとしてお粗末。ただ、彼の動きには魅力があるので、ホリゾントから前面まで繰り返し踊る、ソウルトレイン構造のみを取り出して、両側に動く人形などを多数配置すれば、おもしろいダンスになるのではないか
黒須育海
男性中心、女性が1人混じる群舞が中心の構成で、大の字に横たわったところから始まるが、個々の動きの展開、それぞれの動きが、絡むとなく関わっていくと、その関係性が際立って、見たことのない群舞の世界を作り出しつつある。踊りのコンセプト、動きもそれぞれ考えられており、見せる魅力と新しい世界を感じさせる。個別の力の向上や訓練を重ねるといいカンパニーになるはずだ
1/16
ブラバニ
女性のデュオで主人と奴隷のような構造のなかで、衣装を変えて見せるダンス。トゥで踊る場面もあり、バレエテクニックをそのままでなく、コンテンポラリーな感覚とともに見せる。ただ、最後はエンターテイメントで終わるので、その領域を超えて、もう一つ、強いコンセプトがほしい
尾花藍子
四角く照明の当たった空間の周囲を歩く女性と男性。ノンダンス的なコンセプトで作られており、キャラクター、つまりダンサーの存在感で十分見せるのだが、行われるそれぞれの行為には、形としてのコンセプトとその指示以上の魅力は感じられなかった
ASMR
四つ向かい合わせの椅子にミニのセーラー服で登場して動く。1人を排除して殺し、さらにもう1人も殺すという展開は、なかなかおもしろい。4人のうち2人いなくなるという発想はいいのだが、全体としては何とも弱い。このアイデアからさらに突っ込んだ思考が必要だろう
C×C
冒頭の場面、1人が丸くなっているのかと思わせる、身体のオブジェ化が非常に成功している。そこから2人が絡みつつ踊る展開も悪くはないが、やはり冒頭のインパクトを超えるものではなく、もうひとつ新たな強いポイントがほしかった。
1/17
坂田有妃子
男女4人の群舞で、動きとそれを外す意識とコンセプト、そして書きつける文字など、複雑なものを作りたいという意図は見えており、個別の動きと組合せはおもしろいのだが、しかし、いまひとつ引き込まれなかったのは、個々の表現への徹底の弱さかもしれない
山田花乃
倒立状態から倒立のままの開脚などのコンセプトと場面はとてもインパクトがあり、できればそこをもっと強調して、普通に立つ場面を極力排除すれば、非常に魅力的なダンスになったのではないか。使われる音楽、ボレロも倒立のままで徹底してほしかった。またボレロのラストの破壊的な音楽を敢えて外したのだが、やはりあれを効果的に使わないと、ボレロを使う意味が弱まるのではないか
二瓶野枝(Nect)
女性3人が絡み合うところが多かったが、前日のC×Cの2人の徹底した絡みのイメージが残っていて、ちょっと弱く感じた。ただ赤い靴下が印象的で、後半、胸元から赤い紐を出してまさにからめ取られていくところは、なかなかおもしろかった。
杉田亜紀
正面にしゃがんで観客席に視線を強く向けて、無音で長く動かず、そこから徐々に動くところから、型にはまらない動きをよく考え展開して、ずっと観客の視線を引きつける。去っていくポーズを照明で浮き上がらせて見せるところもカッコイイ。その後のテニスボールと「キャッチして!」という女の子的声やスクール水着に近い衣装は、これまでのコンテンポラリーダンスの「コドモ身体」、少女モードの踏襲だが、それを超えて目に残るものだったのは、しっかりとしたテクニックに加えて、冒頭からの堂々とした存在感と意識ゆえだろう
1/18
横田恵
椅子に体を預けた老婆のようなモードから、文字と自分の言葉を含めて、老いた母とその死を描き出す。とても丁寧で優しい美しさの作品で、特に映し出される青空の写真の中で踊る姿は心にしみる。だが、例えば前半、音はヘビメタにするとか、異なる音で空間をつくると、ストレートな読みを崩すと、その対比によって、切なさ、青い空ももっと生きたのではないか
李真由子
その音楽によって、インド舞踊、ベリーダンスとも見えるような、ちょっとくねった動きで、大きい李とのコントラストをもう1人が出す。ユニゾンや絡みを含めて、テクニックも高く、動きも見たことがない、と思わせるところがしばしばあるのだが、全体的にまとまりすぎた感がある
後藤かおり+安藤暁子
カフェのウェイトレスの白黒衣装のような姿で、1人が日舞の振りを踊り続けて、もう1人がかなり崩したコンテンポラリーの動き。そのコントラストと、2人の戦い、絡みなどがおもしろい。こんな風に日舞の動きを使えるというのは、いい発想だった。さらなる展開に期待したい
スピロ平太
スピロの肛門三部作完結編で、得意のかぶりもので、頭が肛門、股間に人形の頭という逆人間が張り付いた形。冒頭、うんこを口から吐き、生演奏のパーカッションとともに怪しさ抜群。特に、CDでかけるアベマリアのバイオリンとともに、背中に絵とオブジェで全身がバイオリンになった裸の女性が登場して、それを首に抱えて、この逆人間が弾くというパフォーマンスは圧巻。さらに最後は、アベマリアの鳴るCDラジカセを、逆さにブリッジで倒れて頭で壊す!という衝撃的な場面を演出し、喝采を受けた
↑TOP
|