 |
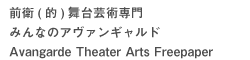 |

![]()
技術と洗練さをともなった「異端」
藤原央登(劇評家)
"異端"×"異端"シリーズ vol.1 川村美紀子『或る女』/ 佐々木敦『paper song』
2017年10月10日(火) & 11日(水) 会場 d-倉庫
パフォーマー・佐々木敦とダンサー・川村美紀子によるソロ作品の連続上演。公演全体が「異端×異端」と冠されている。その名に相応しい2人のパフォーマーは、表現する根拠と独自の世界観を強烈に突きつけた。
異端と聞けば何をイメージするだろうか。個性的なキャラクターが行う特異な表現。感覚的には、ドロドロとした高い情念が発露されたもの、といったところか。パフォーマーの人間性を丸ごと投げ出す表現は、高度な技術や完成度の高さとは別の位相にある。時に理性のタガをはずしてまで全力で己の身体を投企し、その場、1回かぎりにしか成立しない奇跡の異空間を創り出そうとすること。そのような者を、異端のパフォーマーとしてイメージしてしまう。確かに佐々木と川村にも、そういった要素は見受けられる。しかし彼らのパフォーマンスは異形さだけで成立しているのではなく、身体の運びと作品構成を理性的にうまく制御する技術や洗練さにも、しっかりと裏打ちされている。奇異なだけでは、単に観る者の眼の欲望を満たして消費されるだけで終わってしまう。そうさせないための仕掛けをほどこし、何がしかの考える種を観客に与えるためには、技術を用いて完成度を高める必要がある。それでいて彼らは技術や洗練さを、いわゆるハイアートにカテゴライズされるような「オシャレ」なものに仕立てるためには用いない。むしろそこから進んで外れ、別の枠組みで劇を成り立たせるために技術が用いられるのである。そのようにして成立する作品もまた、もうひとつの完成度の在り方である。技術を用いながらも、別の価値を出来させるべくまい進されるパフォーマンスが異端な作品であり、それを遂行する者が異端のパフォーマーと形容されるべきであろう。
彼らのパフォーマンスは、観客が上から目線で見物して消費するものではない。一見したところ独特なパフォーマンスだとしても、観客とまったく別の異形の者としてことさら強調しようとはしない。彼らは他者を求め、作品を通じて観客と対話をしようとしている。彼らの表現する根拠はここにあると感じた。佐々木のパフォーマンスに対峙した私は、ゾワゾワと内奥をかき乱されるような気分を抱かせられた。観る者の潜在意識を体現して暴露するような佐々木の切迫感のあるパフォーマンスが、私にはまったくの他人事だと思えなかったからである。観客の心情をそのように作用させた時、演者と観客との間で対話は成立する。川村はほとんど踊らないパフォーマンスで、全女性の人格をその身に背負ったような作品を提示した。観客に手紙を出す川村は、文字通り、対話を始めようと希求している。自らのパフォーマンスを一方通行で突きつけるのではなく、観客との間をつなごうとする意志に貫かれた2作品であった。その意志が技術に裏付けられた時、独自の異端なパフォーマンスへの道が拓かれる。そしてそこまで劇の思想が深められた時にはじめて、生身の身体を用いる演劇の強度と特性に改めて感じ入ることになるのだ。
©玉内公一
佐々木敦『paper song』は、2010年に初演されたOM-2『作品No.7』(構成・演出=真壁茂夫、日暮里サニーホール)の前半部分に相当するものの抜粋、単独上演である。OM-2は単独の作家がおらず、各パフォーマーが創ったシーンを真壁がまとめあげるスタイルで創作している。したがって、『作品No.7』でのパートも『paper song』も、OM-2に所属する佐々木が主体的に創作した作品である。
うつろな目で雑誌、文庫本が入った紙袋を抱えて、ゆっくりと巨体を揺らしながらやってくる姿からして、不気味で怪しげな危険さを感じる。突き上げてくる内なる衝動に耐えきれず、叫び声を発したり机を激しく叩く。スピーカーから聞こえるエコーがかかった音声は、佐々木の内なる声が立体化されたものか。そして5カウントを唱えながら一心不乱に自分ルールの指運動を繰り返すことで、発作のような行動を抑える。佐々木は、正常と狂気の狭間でなんとか均衡を保とうとしているようだ。コップの水が溢れるように、佐々木はまたいつ突発的な行動に出るか分からない。緊張感を孕んだ佐々木の姿態がそのまま空間全体に伝播する。したがって、観客の身体も緊張感を帯びた空間に同期する。佐々木と共に呼吸し、そして息を詰めながら彼と対峙することになる。
やはりこのパフォーマンスの圧巻は、佐々木が言葉にならない声を上げながら、紙袋から取り出した雑誌、文庫の束を中空に投げ続けるシーンだろう。背表紙が切り落とされているため、ページがバラバラになりながら飛び上がって舞い、そのまま地面に落ちてくる。いつしか床面は紙でびっしりと覆われてしまう。緊張感を一気に打ち破り、動的な開放感へと転じる巧みな構成だ。送風機を手にした佐々木の周りで、紙がものすごい勢いで舞っている光景は美しくすらあった。とにかく圧倒的な量で空間を飲み込むのである。
同じ作品にもかかわらず、7年前に日暮里サニーホールで観た時とは受ける印象が正反対といえるほどに異なる。天井が高く、空間全体が広い日暮里サニーホールで舞ったページは、情報や紙幣に象徴される高度消費社会の謂いとしてあった。それらから逃れようとして紙を放り投げるが、同じ分量が結局は地面に降り落ちてきてしまう。佐々木が背中や腹にいっぱいの紙を詰め込んで肥え太る姿は、資本から逃れることができない人間の孤独さを浮き彫りにさせた。佐々木の危うい人間性は、資本に翻弄され急き立てられる、現代に生きる我々の似姿だったのである。しかし今回は、物理的に空間が狭くなったことと、背景に立ちすくむ女性との関係が加わったことから、ドメスティックな印象を受けた。
©玉内公一
作品が終わりにさしかかる頃からか、いつしか顔を髪で隠して、まるで幽霊のようにじっと佇む着物姿の女性がいた。佐々木が放つ咆哮のような言葉はほとんど聞き取れないが、「いかないで」と何度か繰り返して発語していたことは分かる。女性の存在を併せて考えた時、佐々木の姿が、愛情に飢えた子供が母親を追い求めているように見えた。忌避したい資本の海からは逃れられず、反対に唯一無二の母親の愛情はどれだけ強く求めても手に入らない。極私的な思慕を募らせる一人の男の悲しみが強調された。文脈が違えば受ける印象が180度変わる。これは、生もののパフォーマンスならではの力である。
長めの紐の先に付いた照明を振り回して自身の身体に巻きつけたり、新聞紙で覆った頭の中に入れた後、腹の中にしまい込むシーンがある。一歩間違えば身体を傷つけかねないパフォーマンスにヒヤリとさせられるが、パワフルながらも確実にこなす。この辺りに、パフォーマンスが単なる無茶ではなく、佐々木は理性で自身の身体をコントロールしていることが了解された。
当て所なく母なる幻影を追い求めた末に、紙で埋め尽くされた地面に仰向けに倒れる佐々木。そこに、件の女性が近寄る。実は彼女が、次のパフォーマーの川村美紀子なのであった。2015年に上演されたダンサー・木村愛子とパフォーマー・林慶一による共同企画『身体に対する態度表明』(d-倉庫)では、明確に2人のパフォーマンスは分かれていた。今回はシームレスにつながり、ゆるやかに移行する構成になっていたのである。川村は佐々木の元に近寄り、紙で超え太った腹部に向けてナイフ(かんざしかもしれない)を突き立てる。その先端が佐々木の身体に達しないかが心配になるくらい、川村は力を込めて何度もそれを突き立てる。腹を切り開くようにしてTシャツを捲り上げて、腹部に収められた照明を取り出す。煌々と照らされた照明は、心臓か堕胎児のようにも見える。このシーンだけでも、佐々木とはまた異なる川村の怪しさが示されていた。様々な思念を想起させる佐々木から川村への作品の移行は、非常にスムーズで必然性があった。
©玉内公一
川村美紀子『或る女』の骨格は、時代も人間性も全く正反対な2人の女性による往復書簡である。川村は昭和29年の、雅やかで古風な着物姿の女性と、平成29年の現代を生きる女性を演じる。下手側に前者が、上手側に後者が位置取る。それぞれに出入り口があり、そこを通って裏から移動する間に着物を脱着することで、川村は2人を演じ分ける。療養所に入院している女性は呼吸器の病気に罹患しているらしく、近く大手術を控えている。病弱な点が、この女性のしとやかさをいや増しにしている。女性は死への恐怖を抱いている。しかしその反面、彼女は日々移ろいゆく季節の微妙な変化に敏感である。その様子を歌に詠んで手紙にしたためることで、今を生きていることの喜びと、それが一日でも長く続くことを願う。静かな生への執着をも感じさせるのだ。川村が手紙を朗読すると、背景の壁には手書きで記された文面がゆっくりとスクロールされる。この手紙の受け手が、現代を生きる女性だ。彼女は先の女性とは異なり、性に開放的でかつ自堕落で覇気がない。ダンサーであるらしいが、世の中をかなり斜に見ており、常に世間や自身に対する毒と悪意を吐き出す。メンヘラのような面倒くささを抱えた、すれからしの女性なのに、ラップでの返答は耳心地が良い。加えて、キャッチーな言葉が登場すると、大小のメリハリが付いたゴシック文字として背景に投影される。叩きつけられるように飛び出してくる文字列はデザインアートのようで、これもまた視覚的に良く映える。
『或る女』といえば、有島武郎の同名の小説を思い浮かべてしまう。最初の結婚を2ヶ月で破綻させた後、様々な男と恋愛しながら自由奔放に生きる葉子。彼女は激情に駆られるまま男を手玉に取る。しかし、葉子の男への執着心が反転して、いつしか周りの者への猜疑心と嫉妬・憎悪を膨らませてしまう。そして最後には孤独へと至る様を描いたリアリズム文学である。川村がどれだけ小説の『或る女』を意識したのかは分からない。しかし、劇に登場する2人の女性は、葉子を分裂させて彼女の要素を別々に分け与えられた存在のようにも感じる。劇中、2人の女性が互いを良く似た性格であると評するからだ。2人は相手を補完し合う同一人物=葉子と考えられる。さらにいえば、川村の身体を容器として二人の女性が取り憑き、川村自身が葉子を体現しているように思えてくるのだ。そのことが大正期の葉子、そして昭和期を経て現在に至るまでの近代的な女性像が、川村の身体に流れ込み合一するダイナミズムを感じた。
©玉内公一
川村が唯一ダンスらしい動きを見せたのは、木の実ナナ『うぬぼれワルツ』を歌い踊った所くらいだ。そこではストリートダンス出身の切れのよさを見せてくれる。だがそのことよりも印象深いのは、死の想念と格闘ながらも明日を夢見る病気がちの女性を演じたかと思えば、思い切り良く上半身裸になって性に奔放な現代女性を示す、川村の「演技力」の高さであった。目線の置き方やしなの作り方といった、細かな所作で昭和の女性のか弱さを演じた様には、ダンスを想像して川村の作品に対峙した私の期待を良い意味で裏切り、目を見張る表現を見せてくれた。投影される文字情報の配置の仕方も含め、川村の作品にも周到に練られた企みがある。
川村は最後に、観劇した日付(10月11日)と自身の名前を入れた便箋を読み上げる。『或る女』というパフォーマンス全体が手紙の内容という意味であろう。それは、いわゆるダンスから外れたパフォーマンスを行った人間からのお便り。観客は事前に当日パンフレットと共に、作品解説と白紙の便箋が入った封筒を受け取っている。川村との内的なコミュニケーションが成立した観客は、白紙の手紙をまた誰かに出そうという、パフォーマティブな欲望を喚起されたかもしれない。この劇評は、そのように促された私からの、川村へのささやかな返答である。
INDEXに戻る

