 |
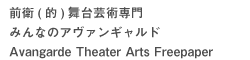 |

![]()
『欲望と誤解の舞踏~フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』の著者=シルヴィア-ヌ・パジェスさんと、表紙の舞踏家=財津暁平さんに特別インタヴュ-(パリ、2017・10・25)+書評をかねた解説
原田広美(舞踊評論家)
*〈その1〉書評をかねた解説 インタヴュ-掲載の前に、未読の読者のために、また本書で考察された時期の舞踏を知らない読者のために、書評をかねた解説を書かせていただく。2017年7月、 シルヴィア-ヌ・パジェス(Sylviane Pagès)著『欲望と誤解の舞踏~フランスが熱狂した日本のアヴァンギャルド』(パトリック・ドゥヴォス=監訳/北原まり子・宮川麻理子=訳)が、慶應義塾大学出版会から出版された。これはパジェス氏が、2009年に「パリ第8大学舞踊学科」で完成させた博士論文を元に研究を継続し、2015年にフランスの国立舞踊センタ-(CND)から刊行した『Le butÔ en France一Malentendus et Fascination』の翻訳である。
博士論文の審査には、他の2人の欧米人の研究者と共に、本書の監訳者であるパトリック・ドゥヴォス氏(東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授)が携わった。また翻訳者両氏の提案に始まり、本書の邦訳が実現したと言う。翻訳者両氏は、パジェス氏の「パリ第8大学舞踊学科」での教え子でもある。また日仏両書の表紙を飾ったパリ在住の舞踏家・財津暁平氏は、パジェス氏の授業で、一週間に渡るワ-クショップを提供したこともあるというほど、パジェス氏との信頼関係は厚いようだ。
そもそもパジェス氏が、「フランスにおける舞踏の受容」という本書の研究テ-マを開始する契機となったのが、2000年ごろに見た財津暁平(敬称・略)の即興舞台と、その後、約2年間にわたり参加したワ-クショップである。パジェス氏は、そこで得た体験・印象と、従来からフランスのマスコミや評論が培って来た舞踏についての言説に、大きなギャップを感じざるを得なかった。
ちなみに、舞踏のフランス上陸の初期について、よく知られたものを大まかに紹介すれば、まずは1978年の、室伏鴻と「アリアド-ネの会」の『最期の楽園』、舞踏の創始者・土方巽の振付で芦川羊子が踊った『闇の舞姫十二態~ル-ヴル宮のための十四晩』、そして1980年の、ナンシ-演劇祭での大野一雄、アヴィニョン演劇祭での「山海塾」などと言うことになる。
そして本書のタイトルについて、かいつまんで解説すれば、「欲望」とは、フランスの戦後において隠蔽されがちだった「ドイツ表現主義舞踊」を見ることへの「欲望」であり、舞踏の中にフランスの観客達が、知らぬ間にそれを見ていたのではないかと言う意味である。また「誤解」とは、舞踏に見られる「硬直し、時に折り畳まれた白塗りの肢体」などが、原爆による被害者の亡骸のイメ-ジと重なり、舞台の暗さも手伝い、とりわけ「核兵器」の犠牲となった最初の被爆地「ヒロシマ」と結びつけて語られて来たという「誤解」を意味する。
確かに、土方も大野もダンスを始めたのは戦後だが、戦前に江口隆哉・宮操子らがドイツから持ち帰り、すでに国内に根づいていた「ドイツ表現主義舞踊」から出発したので、上記の指摘の前者は、的をえたものであるだろう。ちなみに、このノイエ・タンツとも言われた「ドイツ表現主義舞踊」は、20世紀初頭のドイツに生まれた各種の身体療法などと同時期に、興隆した。いわば、「欧州のモダン・ダンス」とも言えるものだ。
また現在は多様化した舞踏だが、発祥国・日本の批評家として、舞踏の形成期の身体性について、いくつか確認をしておきたい。まず室伏鴻や麿赤兒などは、土方を師と仰いだ後に、「大駱駝艦」を旗揚げした。だが、その中心的な存在であった麿は、元は「状況劇場」の怪優と言われ、唐十郎の「特権的肉体論」の体現者でもあった。
そして麿が、さらなる初期を過ごした「ぶどうの会」(主宰=山本安英)の身体トレ-ニングから取り入れたと思われる「野口体操」は、現在の「大駱駝艦」でもトレ-ニングとして用いられているが、本来の趣旨とはだいぶ異なり、ソフトで滑らかな脱力ではなく、力強いイメ-ジを伴う施行法をとっている。これらは、身体性のル-ツとして、「ドイツ表現主義舞踊」と重複的な部分もあろうものの、そこから、はみ出た部分である。
さらに土方や大野より若い世代の、「大駱駝艦」の系列の天児牛大や、カルロッタ池田(「アリアド-ネの会」の初期の振付は室伏鴻)は舞踏以前に、戦後に「アメリカ文化センタ-」が紹介したマ-サ・グレアムの「モダン・ダンス」のメソッドに触れていた。
また土方や大野などの初期の暗黒舞踏には、「アルト-館」の主宰の及川広信が、1950年半ばにパリからバレエと共に持ち帰った、エティエンヌ・ドゥクル-が開発したフランスの近代マイムである「コ-ポラル・マイム」からの影響もある。ちなみに大野が憧れたジャン・ルイ・バロ-も、ドゥクル-にこれを学んだ。そして当時の笠井叡がマイムに触れた際の、師であったジャン(太田)・ヌ-ボの手解きをしたのも、及川である。
ところで日本でも、本書が出るまで、フランスでは歴史的にバレエは盛んだが、戦前のダンスの歴史はないように語られて来た。もちろんのことドイツ占領下の思い出のために、それは隠蔽されたのであろう。だが隠蔽されても、往々にしてフランス文化とは逆の持味を持つドイツのダンスの面影を舞踏-BUTÔ(s)-の中に垣間見ていたという現象は、微笑ましい。
つまり人間には、抑圧されている部分と、表に現れている部分がある。そして、その双方をもって丸ごとの一人だろうが、そもそも往々にして分離しがちな仏独の文化の、フランス側から見て裏側の、加えて隠蔽されていたドイツの舞踊の面影を欲する気持ちが、観客の中にあったことを推察する見解には、大いに興味をそそられた。言い代えれば、正反対に近いほど分離・対立(相手側を隠蔽・抑圧)した構図の下では、実は相互が、相手方が持つ要素を必要とするようになるのではないか、という思いでもある。
またパジェス氏が、本書を貫く論旨として用いた、心理学者の(エドガ-・ルビンらによる)「図と地」の理論は、私が舞踊評論以前に取り組んでいた「ゲシュタルト療法」でも、支柱とされる理論である。その重複した現象は、私が本書に親しみを覚える要因にもなった。その理論では、抑圧されている「地」と、見えている「図」は、時にひるがえる。パジェス氏の論では、隠蔽されていた「ドイツ表現主義舞踊」が形成していたフランスの舞踊界の「地」の部分に、ある時に「舞踏」がピタリとはまり、「地」と「図」が反転したのである。
加えて、本書に親しみを持った一因に、表紙の舞踏家・財津暁平と面識があったということもある。2004年の拙著『舞踏大全~暗黒と光の王国』(現代書館)の刊行後に舞踏家・雪雄子と出かけた2005年の欧州ツア-の際、パリのベルタン・ポワレ文化センタ-で出会っていた。その暁平(ぎょうへい)さんが、表紙に写っていたのには驚いた。今回は別件でのパリ行きに付随しての会見であったから、どこまで出来たかという危惧もないではないが、パジェス氏に並び、財津暁平氏からも、大変に興味深いインタビュ-を得ることができたので、それも掲載する。是非とも最後まで、楽しみに御高覧いただきたい。
ここで、「誤解」の話に戻るが、私が拙著『舞踏大全』を書き終えた時に、思いがけず認めざるを得なかったことがある。それは舞踏の生成と、大戦の記憶の間には多大な関連があるという事実だった。土方巽の1970年代の作品では、幼年期の東北の飢饉、きびしい農作業や独自の生活習慣、あるいは不治の病に冒された身体と関連する「衰弱体」の印象が顕著だが、「バンザイ女」(1959年)や「静かな家」(1973年)という、大戦に関する記憶が明確な作品もある。
いずれにせよ日本が豊かになる過程で、忘れ去られてゆく戦前・戦中・戦後の故郷の人々の労苦を紡ぎ続けることに、土方が自らのアイデンティティを見出そうとしたのが、1970年代以降の作品であったと思う。
土方の夫人の元藤燁子も、戦中・戦後の東京で、亡骸が放置されているのを少なからず目にした思い出を私に話した。加えて、大野一雄には7年にも及ぶ兵役体験があり、「敵味方なく亡者の精霊達と一緒でないと踊れない」という趣旨の言葉を残している。また麿赤兒の戦死した父は、戦艦の副艦長であったし、天児牛大は、戦後に米兵を迎えた横須賀に育った。そして、大須賀勇は「ヒロシマ」の被爆胎児として生まれ、ピカドンの光を逆手にとって1980年代の「明るい時代」に合致させ、「明るい暗黒」を舞台上で目指した。
要するにパジェス氏が指摘した、フランスにおける舞踏の受容に「ヒロシマ」と結び付いた解釈が、執拗につきまとった現象の一因として、上記のような、大戦の記憶と舞踏との関連という現象が付随する可能性を感じた、というのが私の一試論である。各々の現象の詳細については、拙著『舞踏大全』や「現代詩手帖」(思潮社/2005年3月号一「今、舞踏を語ることの意味」)を併読いただければ幸いである。
そして、ここで本書が伝えてくれた「フランスでの舞踏の受容のされ方」についての概要と分析、あるいは翻訳を経なければ読むことは困難だった原書に対して、労力を惜しまず、監訳・翻訳を担って下さった諸氏の仕事と、パジェス氏を含めたチ-ムワ-クに感謝しつつ、どうしても舞踊評論家(研究者)として指摘しなければならない点がある。
それは、くしくも本書1ペ-ジめに記載のある、土方の「舞踏譜」に関する「誤解」である。その部分を引用すると「・・創作ノ-ト(スクラップ・ブック)は、デフォルメされた身体への想像を育んだベ-コン、ダリ、ゴヤ、クリムト、シ-レあるいはリヒタ-の絵画のコピ-によって埋められている。ところが一九六〇年代の終わりになると、土方の探究はしばしば、というよりもほとんど排他的に、東北地方の農民の身振りに代表される日本文化をもとにして行なわれた」、とある。
だが土方の「舞踏譜」は、逆に1960年代の終わりから、1972年の『四季のための二十七晩』に向けて作られ、その後も継続して、弟子達に自らの特殊な振付イメ-ジを伝えるために、あるいはそれを考案するために用いられたものだった。
パジェス氏は本書で、「身ぶりを介した舞踊」という方法の「国際性」についても強調している。土方においても、1968年の『土方巽と日本人~肉体の叛乱』以降は、前述のように、故郷の東北の飢饉、きびしい農作業・独自の生活習慣、あるいは不治の病などに冒された身体を「衰弱体」と名付け、自らの舞踏身体の中心に据えたことに間違いはない。
だが加えて、土方が貪欲な熱意で、国際的な芸術観を維持しつつ、独自の舞踏身体を考案し続けた証として、単に日本文化としての身ぶりには限定せずに、異端的な海外の絵画のイメ-ジを、異端的な日本画・浮世絵および言葉などと共に、ふんだんに融合した振付を継続したことを私がここに明記しておく必要があるだろう。
すでに舞踏の始発から60年近くになろうとする昨今、パジェス氏の本書の冒頭の記述を鵜呑みにする読者も少なくないことを危惧した上での指摘である。ちなみに土方が1970年代の舞台で用いた音楽も、クラシックの他、ジャズや電子音学が多く、決して単に日本風の志向ではなかった。
土方の1970年代と「舞踏譜」の関係は、実はパジェス氏が参考文献で挙げた『土方巽の舞踏』(川崎市岡本太郎美術館、慶應義塾大学ア-ト・センタ-編)にも、記載されている。加えて上記ア-ト・センタ-刊行の、森下隆氏が携わった舞踏関係の他の数冊のブック・レット、三上賀代『器としての身体』(ANZ堂・発行)、『土方巽全集』(河出書房新社)、和栗由起夫のCD-ROM『舞踏花伝』(ジャスト・システム)、そして拙著などを介しても、すでに広く知られている。
パジェス氏の本書に戻ると、「舞踏譜」の年代についての「誤解」は、論全体を揺るがすものではあり得ない。そして日本語の読み書きが可能な研究者ではない以上、致し方のない部分もあるだろう。ただ私が残念に思うのは、日本語の読み書きが可能な舞踏研究者で、博士論文の審査員でもあった本書の監訳者辺りが、この部分についてのサジェスチョンをなし得なかった点である。あるいは今回の「誤解」は、何か中央集権的な、周辺に対する隠蔽体制などと関係があるのだろうか。せっかくの良書の上梓であるのに、日仏両国の読者が、土方の国際感覚について、矮小して理解することを惜しむのである。
このような土方の国際的なア-ト志向については、すでに舞踏陣営に限られたことではなくなっている。たとえば、2013年に東京国立近代美術館で開催された「フランシス・ベ-コン展」では、絵画の展示の後に、「ベ-コンの絵画と〈舞踊〉の関連」として、2枚の大型スクリ-ンによる展示があった。その時、1枚目のスクリ-ンに映されていたのは、1972年の土方の『四季のための二十七晩』の最高傑作「疱瘡譚」のクライマックス・シ-ンの映像で、他方は、1990~2000年代にかけて、コンテンポラリ-・ダンスの寵児であったウィリアム・フォ-サイスに関する映像だった。
また土方の舞踏とフォ-サイスの作品や身体性の関係・類似性については、1990年代から舞踏陣営内でも指摘されていたことであり、昨年の拙著『国際コンテンポラリ-・ダンス~新しい〈身体と舞踊〉の歴史』(現代書館)の、フォ-サイスの項でも触れているので、併せて御高覧いただくことができたら幸いである。そして、上記のベ-コンは、まさに土方が興味を抱き、1970年代の作品における身体性の、参考にした画家であることを付け加えておく。
後述のインタヴュ-記事を御覧いただくと、パジェス氏の開かれた人柄が理解されるだろうが、パジェス氏は、本書執筆のために、多くのフランスのマスコミ関係者、批評家、研究者、思想家の文献およびその人自身に広くあたって分析・研究を進めたようである。
それは、これまで私が少なからずぶつかざるを得ないで来た、アカデミックな人脈の閉鎖性を超えたものであるように感じられる。アカデミックな立場を明確に持ち得ない、あるいは〈周辺と認知された者達〉の研究や調査が、隠蔽・無視されがちな体制があり、もしそれが維持されるのであれば、後から来る研究者達は、知らぬ間に「裸の王様」にされてしまう危険性がある。
今回、パジェス氏と財津暁平氏からいただいた真摯で爽やかな後述のインタヴュ-が、そのような霧を吹き払ってくれることを願い、この文章を終わりたい。(2017・11・23)
INDEXに戻る