 |
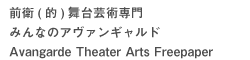 |

![]()
二項対立と両義性の狭間で耐えるということ
藤原央登(劇評家)
DULL-COLORED POP『福島三部作』
2019年8月8日(木)~28日(水) 会場 東京芸術劇場シアターイースト
0
DULL-COLORED POPが渾身の連作を2019年の夏に放った。福島県双葉町を舞台に、福島第一原子力発電所の誘致から東日本大震災における原発事故までを描く、長大な年代記「福島三部作」である。昨年上演された第一部と、新作の第二部と第三部を合わせて一挙に上演した。私は一日に3作をまとめて観た。そのことによって原発政策を巡る戦後史の流れと、原発の是非を巡って揺れ動き、ときに分断される人々の複雑な心情が良く伝わってきた。
谷賢一の両親は、母が福島県出身で父は原発に従事する技術者であり、谷自身も幼い頃は福島で暮らしていたという。谷の家族の肖像と実在する双葉町町長や東電社員、テレビ局員、そして時間をかけた取材で出会った福島県民たち。こういった人々が、様々な登場人物のモデルとして落とし込まれている。そんな彼らが織りなす物語は非常に奥深い。年代記に相応しく、計6時間の上演時間は長尺であった。とはいえ、充実した内容と三作共に異なる作風であるため、飽きることなく見通せた。
1
以下、三部作がいかに練られた作品であるかを詳述する。まずは三部作について概観しておこう。福島県双葉町にある穂積一家の長男、次男、三男が、それぞれの作品の主役となる。第一部『1961年:夜に昇る太陽』は1961年10月、双葉町に原発の誘致が決定する数日前を描く。大学卒業を控え、東京で就職することへの許しを得るべく、穂積孝(内田倭史)は一時帰郷する。孝は上野から乗車した常磐鉄道の車中で、東電の社員・佐伯正治(阿岐之将一)、三上昭子(大内彩加)と乗り合わせる。孝と佐伯は科学の未来などについて語り合いながら、共に双葉町へと向かう。
佐伯と三上の目的は、原発を建設するための用地買収のためであった。彼らは、双葉町町長・田中清太郎(大原研二)と福島県庁職員・酒井信夫(東谷英人)を伴って、穂積家の当主でかつて町議も務めた孝の祖父・正(塚越健一)に、土地の売却をもちかける。原発のエネルギーが産業を興し、工業地帯を形成する。それが東北の中で最も貧しい福島が、仙台のような都市になる術である。彼らはそう正に訴える。広島出身の佐伯が「原子力の平和利用」と原発の安全性を説きつつ、現在の価値として3億円を超える保証金を提示する。最終的に正は、地元の発展のために引き受ける。それに先立って正は、孝に同意を求める。それに対して孝は、「自分には関係のないことだから」と答えて態度を保留する。この台詞は、三部作全体を通して重要な問いを含んでいる。そのことについては、最後にもう一度触れることにしよう。ともかく当時は、原発が「未来のエネルギー」であり、科学が人類の生活を便利に豊かにすることが信じられていた。降って湧いたように東京から福島にもたらされた原発を、良いものだと押し切られて引き受けてしまう、地方の人々の姿が描かれる。
第二部『1986年:メビウスの輪』の舞台は1986年。1971年3月に福島第一原子力発電所が営業運転を開始し、双葉町住民の四分の一が原発関連産業に従事しており、税収の半分も原発によって賄われていた時代。そして何よりも、旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故が起きた年である。第二部は穂積家の次男・忠(岸田研二)が主人公である。第一部で忠は唯一、佐伯に向かって感情的なまでに原発誘致に反対していた。その後、彼は町の青年団から社会党に入党した後、反原発派のリーダーを務めていた。原発廃炉を公約に県議会選挙に一度当選しただけで、その後3回連続で落選。すでに原発の恩恵を受け、それが前提で行政や暮らしが成り立った時、忠の訴えは響かなくなったのだ。そんな彼を、社会党県議会議員・丸富貞二(藤川修二)と自民党町議会議員秘書・吉岡要(古河耕史)が、原発誘致を働きかけた上に数々の汚職で辞職した田中清太郎の後釜に担ぎ上げる。彼らは原発に反対ではなく危険性を訴えることで、結果的に原発を賛成する策略を忠に提案する。
丸富と吉岡による老獪な策略によって、原発反対を隠しながら賛成するという矛盾を抱えた立場で、忠は見事に町長に当選する。しかしチェルノブイリ原発事故が、忠を窮地に追い込む。チェルノブイリの事故を受けて、町長の立場上、日本の原発は安全であることを記者会見で訴えなければならなくなったからだ。日本の原発は耐震性に優れた建築方式を採っており、その上、何重にも安全策を講じている。かつて佐伯がそのように正を説得した際、忠は激しく反発した。今や佐伯と同じ説明を、忠は記者会見対策として何度も練習させられる。最終的に忠は、忌野清志郎のような派手なメイクを施し、RCサクセション『サマータイム・ブルース』の曲に乗せて「日本の原発は安全です♪」と音楽劇調に連呼する。原発反対と賛成のダブルバインドに置かれた、彼の滑稽さがここで描かれる。そんな忠の様子を、死んだ飼い犬のモモ(百花亜希)が俯瞰する格好で舞台が展開される。モモは忠に、原発に反対していた本来の自分に戻るよう、実存主義哲学を用いながら忠告する。しかし死者であるため、忠には届かない。モモは死者の目線で、人間の愚かさを見つめるのだ。
そして、2011年の東日本大震災と福島原発事故後を描く第三部『2011年:語られたがる言葉たち』。第一部で3歳だったため、人形として登場した穂積家の3男・真(井上裕朗)が主人公だ。テレビ局の報道局長となった真をはじめとする局員たちが、年末に放送される震災特番の企画と取材を進める。東京のキー局からの要望も取り入れ、被災者の悲惨な暮らしや家族を亡くした悲しみを強調して、視聴率が取れる派手な映像を撮るべきか。それともじっくりと時間をかけて、分かりやすい悲劇ではなく本音の言葉を被災者から引き出すべきか。「福島県民に、生きる自信と誇りを取り戻す」ための報道とは何かを巡って、彼らは対立する。そこに、取材先で出会う福島県民同士のむき出しの非難が挿入される。さらに原発事故後、精神に異常をきたして入院している忠(山本亘)に、原発推進派だった元双葉町町としての言葉を引き出そうとする真の葛藤も描かれる。
第一部にはプロローグとエピローグがある。真と、忠の妻で元々は孝の恋人であった美弥(都築香弥子)が、防護服姿で一時帰宅をするシーンだ。原発事故により警戒区域となった自宅。そこには、原発建設のために転居を余儀なくされた家から持ってきた、三兄弟が背比べをした大黒柱や、東京の孝から真に送られてきた、当時のジャズやポップスのレコードや家族のアルバムがある。原発誘致前の、貧しいが牧歌的な人のつながりが濃厚だった時代を、立入禁止区域となった双葉町の様子が相対化する。第二部は、死者であるモモが忠の所業を客観的に見つめていた。そして第三部は、原発事故直後の生々しい光景を、それから8年経った時点から観客は観る。原発をフックにした日本の戦後史を、単に過去の出来事ではなく客観的な眼差しで描くよう貫かれている。歴史との距離感を保っているために、三部作を見通した後、2020年以後の日本へと意識を向けさせられるのだ。
2
本作を貫くのは、原発の是非に象徴される大小様々な二項対立と両義性である。例えば第一部における東京と地方、科学と農業、発展と衰退という問題であり、個人の生き方や人生観に関わる問題としてそれが顕れる。第一部の冒頭、常磐鉄道の車内で佐伯と邂逅した孝は、三上から「先生」と呼ばれる彼と、科学談義や室生犀星の詩「小景異情(ふるさとは 遠きにありて 思ふもの)」の解釈について会話を交わす。孝は佐伯に、科学に貢献して日本の発展に寄与したいと述べる。その孝の直情的な心情は、仕事がなく発展の見込みがない故郷への、嫌悪に似た複雑な思いと裏腹である。裏を返せば、孝が東京と科学志向を強くすると同時に、対となる地方(福島)と農業が意識されてしまうのだ。母と祖父、二人の弟と美弥と離れ離れになる寂しさは、孝を二項対立の狭間に立たせる。
同じような問題は福島県庁役人・酒井によって、福島県が置かれた歴史的な積年の恨みとして語られる。戊辰戦争で会津藩が新政府軍に敗れて以来、福島県は開発が後回しにされ何もない県という不遇の扱いを受けてきた。そこから脱却する起死回生の一手として、原発のエネルギーによる町の発展を力強く訴える。同様の趣旨は、第二部で丸富も語る。戦前44人いた歴代の福島県知事の内、福島県出身は二人しかおらず、大半は東京から送り込まれていたこと。明治44年創業の猪苗代水力電気株式会社の電力が、東京に送られるだけで福島の開発には回らなかったこと。自由民権運動の発祥の地のひとつであるにも関わらず、福島県には自由がなかったこと。さらに、そもそも初代征夷大将軍・坂上田村麻呂が東北出身でありながら、朝廷によって蝦夷討伐を命じられ、福島県民をいじめた第一号にならざるを得なかったという伝説まで持ち出す。本作に登場する年長世代の福島県民たちは、東京への尋常ならざる対抗心と恨みを持っているのだ。その対抗が、東京=国策がもたらす原発で果たそうとすることに、坂上田村麻呂伝説に似た悲哀を感じさせる。第一部で双葉町町長・田中清太郎が佐伯の足元を見て、保証金を吊り上げようとするシーンがある。その卑しい心性を佐伯に手厳しく叱責された田中は、原発誘致が頓挫することを恐れて前言を撤回し、卑屈に彼にすがる。その姿には、東京に隷属しなければならなかった福島県の歴史的な経緯が集約されている。
こういった経緯を全て飲み込んだ上で、正は土地の売却を決定するのだ。維新で敗北し、郡山から逃れて入植した者が多いという双葉町。そのため、土地は先祖代々からのものではなく、せいぜい二代三代の歴史しかない。保証金でまた土地を買えば良いと田中は正に告げる。この台詞にも、福島県民は土地を転々とすることが当然であり、あたかも棄民されることを受け入れているような印象を抱かせる。そんな中にあって、原発の受け入れを「決めさせられたんでねぇか」と反発する忠(宮地洸成)の言葉は、胸を突く。福島県民による東京への対抗心が、結局は東京に依存するしかない卑屈さに支えられていることを炙り出す言葉だからである。容易に解消できない矛盾の両義性がここにはある。
とはいえ第一部の時代では、原発は希望を与える科学技術の象徴だった。原発を説明するにあたり、佐伯は幼い真に『鉄腕アトム』を持ち出す。そこからも推察できるように、原発は町に開発と発展という夢をもたらす、外部からやってくる未知なるものであった。だからこそ、原発の是非や東京と地方の格差に翻弄されて思い悩むとはいえ、町の発展と暮らしを良くするためと説得されれば、人々は割と素直に受け入れられたのかもしれない。しかし1986年になると、ある意味でのすっきりとした立場は取れなくなる。
第一部『1961年:夜に昇る太陽』©bozzo
先述したように、44歳になった忠はただ原発に反対することは許されず、賛否を解消することなくその身に抱え込まねばならなくなる。原発が町に根を張った結果、原発関連産業による法人税と国と東電からの補助金で、町の税収の大半が賄われる財政状況になってしまったからだ。その恩恵によって各種のインフラが整備され、公民館や学校なども建設されてある程度の開発が実現した。その事実が忠を、原発反対の旗を降ろしての町長選へと至らせる。なぜ県議選に3回も落選している忠に白羽の矢が立ったのか。利権まみれの典型的な土建屋である田中清太郎と違い、クリーンであることだけが理由ではない。原発によって町が一定の開発を遂げ、今後は建設の仕事が減少して税収減が予想される。それを食い止め、雇用と税収を生み出し続けねばならない。そのためには、原発の危険性を煽って国と東電から原発の補助金を引き出し、さらには改築工事を受注して原発関連産業を維持する必要がある。これまで原発に反対してきた忠は、その役目を担うには打ってつけの人物だったのである。原発から脱却することがもはやできなくなった町は、現状を維持しながら原発産業を加速するしかないところまで来てしまったのだ。
そこにチェルノブイリ原発の事故が起こる。本来は忠が丸富や吉岡に提案したように、この時点で全原発を停止して安全点検を行うべきであった。そして日本における原発政策の是非を、国家的にゼロベースで再検証する奇禍とすべきであった。しかし忠はその機会を逃す。その結果、ソ連と炉心のタイプが違うこと、日本人は真面目だから事故を起こさないなどと、丸富と吉岡による悪魔の論理を信じ込まされる。本来の危険性に目を瞑り、信じたいものだけを信じる呪文として、忠は「日本の原発は安全です♪」と唱えるのだ。
第二部で忠は大きな判断ミスをし、本来の主張である原発反対から賛成へと、180℃の転換を行ったように見える。しかしそんな忠も、東京=国策の論理にやり込まれ、翻弄された被害者であると言える。そのことは第三部において、69歳になった忠が福島原発事故後、精神を病んで入院することに顕れている。原発についての賛成と反対を一身に背負った忠は、その矛盾と二項対立を解消することなく抱え続け、耐え切れず入院した。そのことが、原発事故の爆発と見合っている。そういう意味で忠の人生は、原発の悲劇を体現するものであったのだ。
3
原発が爆発したことによってむき出しの二項対立があちこちに露呈する。第三部で描かれるのは、避難指示を受けた福島県民同士の諍いや差別感情だ。まず双葉町出身で、津波によって妻と娘を失った荒島武(東谷英人)と、富岡町から郡山をへて福島市へ避難してきた飯島貴彦(森準人)、佳織(佐藤千夏)夫妻。妊娠中の佳織は、胎児への放射線の影響を心配しており、食材も福島県産をはじめ東北のものを食べないようにしている。線量に神経質になっている佳織に対し、家族を失って無気力になり、災害義援金でパチンコ三昧の生活を送っている荒島が「うるせえな!」と非難する。貴彦は神経が過敏になっている妻の言動を、荒島に丁寧に謝罪する。しかし、荒島が双葉町出身であることを知ると態度を豹変させる。双葉と大熊の連中が原発を誘致したせいで、原発関連の恩恵を一切受けていないのに、被害が少なかった富岡町から避難させられた。貴彦はそう怒りを荒島にぶつける。子供が生まれることを安心して喜ばせろと言われ、荒島は飯島夫妻に土下座して謝罪する。
高坂美穂(有田あん)による宮永美月(春名風花)への差別も、いじめのように陰湿だ。飯館村から福島市内へ避難してきた美月は、17歳の女子高生。美月は市内の通学路を撮影した動画を、ネットにアップした。皆が放射能の内部被爆を恐れて、マスクをして道路の真ん中を歩いている光景である。福島市内もいかに汚染されているかを世間に知らしめ、「福島県は全滅です」と警告を発する。合わせて、自分が子供の産めない身体になったら誰がその補償をしてくれるのかと訴える。
浪江町出身の20歳の高坂は、その動画を流した美月を「放射能」と呼んで激しく責める。高坂は原発事故後に浪江町からすぐに福島市へと避難した。しかし美月が住む飯館村は、政府からの警告が遅れたため避難まで1ヵ月を要した。多少は放射能が体内に入ったもののすぐに避難したため、1ヵ月間も放射能を浴び続けた美月よりもキレイだ。美月は放射能で汚染されているにも関わらず、同じ場所に避難してきた。しかも美月は自分のことは棚に上げて、福島県全体が放射能で汚染されていると誤った情報を拡散させている。その高坂の怒りが、「放射能が伝染する」「こっち向くな」「汚いから出ていけ」といった露骨な言葉として美月にぶつけられる。
第二部『1986年:メビウスの輪』©白土亮次
注目すべきなのは、高坂も差別される側だったことである。彼女は当初、神奈川県の親戚宅へ避難した。浪江町には半日ほどしかいなかったにも関わらず、高坂も「放射能」と呼ばれて差別された。美月のような者が誤った情報を流すから、自分も差別されると高坂は感じたのだ。そんな高坂に対して美月は、大気中に放射能はほとんどないことなど、誤解されているからこそ情報を正しく伝え続けなければいけないと告げる。しかし高坂にとって美月の行動は、火に油を注いでいるようにしか思えない。高坂も子供が産めなくなることへの不安を抱いている。高坂による美月への攻撃は、「キレイなままの私でいたい」という心情から来ている点において、佳織や美月と根底では同じ不安を共有しているのだ。
畜産農家であり美月の父である宮永壮一(大原研二)も、福島県への風評被害を広めていると娘の行動をいさめる。原発から30キロ以上離れている飯館村だが、事故時の風向きの影響で放射能の被害を受け、全村避難となった。それにより飯館牛の飼育と出荷ができなくなった。酒造業を営む従兄弟は昨年作った酒も、福島県産という理由で大手デパートから取引を停止された。美月の行っていることは、そういった福島の風評被害を拡大させているだけだと壮一は述べる。科学的根拠に基づいた客観的データを用いて福島の現状を訴えようとする美月に、壮一は「おめらは汚れてなんかいね」と、わが娘と牛を無条件で愛そうとする。壮一が、非科学的で何が悪いと悲痛に訴える心情も間違ってはいない。それだけに、真に迫って響く。
原発の是非という両義性、二項対立を突きつけられた福島県が、50年という時間をかけてその矛盾に侵食され、耐えられず爆発すること。これが、三部作を貫く太い幹となっている。25年ごとに時代が下るにつれて矛盾が深刻になる様からは、いかに問題を先送りにしてきたかが看て取れる。三部作には原発の是非について懊悩し、状況に迫られて何がしかの選択をさせられる人々ばかりが登場する。だが既述してきたように、どちらかの主張を声高に唱えることはしない。明確な答えを提示することもない。第三部における、真をはじめとするテレビマンたちの葛藤もそうだ。「福島県民に、生きる自信と誇りを取り戻す」ための報道を巡って、原発誘致の当事者家族である真は難しい立場に置かれる。自身の心情に近い部下である小田真理(柴田美波)からも、原発を推進してきた忠は原発事故について語る責任があるとして、取材するよう要請される。
そういった背景を持つ真が、懊悩の末に番組作りの方針を打ち出す。それは、被災してからの日々や想いをできるだけ聞き出し、淡々と報道し続けるというものである。人によってそれまでの生き方が違うように、被災の仕方も異なる。それを束ねてひとつの大きな答えに導けば、個別具体的な人間の生がかき消されてしまう。そうではなく、被災者の貌が顕現するように一人ひとり丁寧に掘り下げ、それを提示する。ろうそくを一本一本立てるように、被災者の声を並べることが、癒しにつながらないかという仮説に、真は辿り着く。「語られたがる言葉」を時間をかけて引き出すことは、そのまま三部作を創るために谷が行った取材や文献調査に当たった姿勢のことでもあろう。加えて、8年前に演劇人に突きつけられた、「演劇にできることは何か」というテーゼ対する、谷の態度表明でもあるはずだ。
4
作品に胎胚する本質を体現する舞台美術も印象深い。舞台両側には電球をはめ込むための、穴のたくさん開いた巨大なボードがある。そして上手天井にも、電球の束が垂れ下がったような巨大な美術が設えられている。第一部で、高台にある電灯を修理するために、忠がボードにはめ込んだ電球が1個だけ灯る。第二部ではボード全体にはめ込まれた電球が眩しく光る。ボードは原発が二葉町に誘致されてから、原発が稼動して町のインフラが整った様を表現している。したがって第三部では、ボードは震災と原発事故によって破壊されることになる。
天井から吊り下げられた美術も同様の役割を担うが、こちらは両義性と二項対立を示すという意味で、より作品に肉薄する。第二部で勢い良く煌々と灯ることで、原発のエネルギーの強さを感じさせる。第三部でも同様の光を放つが、そこでは原発の爆発の様に見える。と同時に、原発事故後も懸命に生きる生の輝きであり、死者を鎮魂する灯でもあった。
そう、死者の目線と存在が強く作品には注がれている。第二部では忠の飼い犬だったモモが常に舞台上に居て、死者の視点から忠に正しい選択をするよう声を届けていた。地上は生ける命で溢れているが、見えないだけで死者たちも同じく漂っている。そして生者たちに語りかけている。だが死者の声は騒がしい生者たちの営みにかき消されて届かない。生ける者に警句を与える死者たちの声に耳を澄ませてほしいと、モモは誌的に語る。
第三部『2011年:語られたがる言葉たち』©bozzo
残念ながら忠にはモモの声が届かず、町長になって以来、原発推進派として生きざるを得ない立場に追い込まれた。その結果、忠は原発事故後に精神を病んで入院して以来、町長時代の在りし日を幻視したり、19歳と44歳の時の自身と自己対話をする日々を送る。小学校一年生の児童が作った標語「原子力、明るい未来のエネルギー」を職員に発表する朝礼では、福島の未来に夢と希望を抱く児童の期待に応えるべく、後に計画が中止となる原発7、8号機の増設のために日々の業務に邁進しようと職員へ訓示する。かつての自己たちとの対話では、原発が安全ならなぜ第五福竜丸の事故が起こったのか。ヒューマンエラーであるチェルノブイリ事故が日本で起こらないとは限らない。そのように、青年だった19歳と双葉町町になりたての44歳の忠が述べる。だが病床の忠は、広島と長崎を経験して覚えている日本人は核の取り扱いを間違えず、日本とソ連では炉の形式が異なると、佐伯や丸富、吉岡に吹き込まれた説明を繰り返すばかりだ。
そんな忠に真は、ゴミで溢れた部屋を少しずつ片付けるように、心を整理するつもりで語ってほしいと何度も話を聞こうとするが、まともな返答が帰ってこない。そこで美弥は真に、原発事故を目の当たりにして忠は狂気の淵で苦しんでいる。原発について語らないことが本音を語っている、そうは思ってもらえないかと伝える。忠は「語られたがる言葉」を飲み込み背負うことで、贖罪に代えた。その姿は痛ましい。その後、死を迎えた忠をモモが迎えに来る。死ぬことは怖くはないとのモモの言葉は、原発政策を巡って懊悩し続けてきた忠に、ようやく訪れた開放と癒しとして描かれる。忠の最期は、三部作に注がれる人間への眼差しを象徴する。それは、人間の善悪の両義性を描くということである。
双葉町の用地を買収しに来る佐伯は広島出身で原爆を実際に目にしており、それだけに原発の平和利用を実践すべきとの思想を持っていた。酒井、丸富、吉岡も福島を東京に比肩する都市にしたい一身で原発誘致を推し進めた。第一部に声だけで登場する政治家は佐伯に、用地買収に苦戦するようなら「札束で頬を引っ叩いてやればいい」と告げる。これにしても、原発建設は日本が将来的に核を保有する国になるための準備であり、それが対米従属から抜け出して真に自立するために必要であるという理由が一応ある。現時点から振り返れば、人間の過ちを指摘することは可能であろう。だが三部作に登場する人物の誰もが、この国を破壊しようとしたのではなく、それなりに真剣に故郷を想い、国を想って行動している。その時々において、一人ひとりの登場人物の言動に確かなバックボーンがある。それだけに、正否を断罪することが難しい。第三部における、ろうそくの火のように人間の生きた証を記録するという姿勢は、原発を誘致した時代にまで遡って、谷の中であらゆる人々を描く際の大原則となっている。そのことが徹底されているため、単純に善悪が判断できない深みと倫理観を三部作に与えているのである。
5
誰もが原発の誘致や事故後の生き方について真剣に模索し、受動的ではあってもなにがしかの選択をする。それだけに、第一部で採る孝の態度が示唆的なのである。既述したように、祖父の正から用地の売却に同意を求められた際、孝は「関係ない」と返答したのだった。地元を捨てて東京で生きることを選択した孝にすれば、自分にはその決定権がないと思ったのだろう。だが、他の登場人物が痛みを背負って重要な決定を行った。そのことを鑑みれば、孝の返答は態度の保留であり、もっと言えば責任からの逃避である。正が「忘れんでねえぞ。おめは、反対しねがった。いいな」と念を推す様は、選択しなかったことについて後悔する日がきっと来るぞ、という警告に聞こえる。
何が正しい選択なのか、その時代の渦中にいる人はもとより、こうして長大なドラマの中に落とし込まれた人間模様を目の当たりにすれば、簡単には言えない難しさがある。しかしそんな中でも、孝のように「関係ない」と答えを宙吊りにすることはまずいのではないかと思わされる。原発事故とそこに至るまでの責任は、それに関与した福島県民や東電、為政者だけにあるのではない。孝のように日本国民の大半が態度を保留しなし崩し的に問題が先送りされた結果、事故が起こった面も十分にあるからだ。責任を回避して傍観者でいれば、いざ事が起こった際にその事象について真正面から対峙することはできない。忠のように責任を感じて悔やむこともできない。深く考えないで済ませて逃げてしまう態度は、現在に至る多くの日本人の心性なのではないか。したがって孝は、原発に無関心な日本国民の無意識の集合体である。孝は第二部で東大大学院を卒業後、原子力研究所に就職したと忠が語るだけで、それ以降登場することはない。日本人の無意識の集合体であるためには、消える必要があったのだ。そして消えて無対象になることで、空気のように舞台上に偏在して、観る物に自分こそが孝かもしれないと痛感させるのだ。原発事故後も原発政策から転換できない現代において三部作が問いかけているのは、今後何か起きた時に、良くも悪くも自分の問題として考え行動できるよう、せめて「関係ない」という態度をとるべきではないということなのである。
最後に、三部作に認められる演劇的な趣向について触れておこう。死者となったモモが世界を眺めるという、客観的な距離感を持った第二部の劇世界は、猫がナレーションを務める『くろねこちゃんとベージュねこちゃん』(2012)や『夏目漱石と猫』(2015)で試みられた、DULL-COLORED POPではおなじみの手法である。先述したように、振り切ったように忠が原発の安全性を歌うシーンを含め、第二部はファンタジーを基軸にバラエティに富んだ作品である。第一部と第三部もそれぞれ劇のスタイルが異なっている。被災者や死者の声を蘇らせるように、人間のむき出しの対立を生々しく描く第三部は、社会派劇のような重厚さがある。第一部は、かつての日本への郷愁を抱かせる叙情性溢れる創り。等身大の人形を操って表現される3歳の真や近所の子供たちは、愛らしくて楽しませてくれる。折々に流される当時の流行歌や最先端のジャズは、シーンを切り替えるブリッジとして効果的なほか、東京と地方の差異も演出する。音楽をバックに、都会で生きることに決めた孝と、田舎に残る美弥(倉橋愛実)の別れのシーンではあえて力いっぱい、舞台を大きく使って大熱演を繰り広げる。別れなければならない寂しさを押し殺して、わざと悪態をついて強がる。演技のスタイルと、美弥の孝への卑屈さを垣間見せる振る舞いは、『熱海殺人事件』における大山金太郎とアイ子を思わせた。『アクアリウム』(2013)でも木村伝兵衛と熊田留吉を髣髴とさせる人物が登場したことを思い起こすと、谷賢一のつかこうへいへの志向性を改めて感じた。役柄を違えつつ作品を複数兼務する俳優がいたため、大変な労力であったろうが、彼らの奮闘によって「福島三部作」は劇団の代表作になった。
註1 台詞の引用は上演台本より。
註2 三部作を通して出演する忠と美弥は、各作品で演じる俳優が異なる。
INDEXに戻る
韓国社会の「いま」を伝えるパフォーマンスと構成力
藤原央登(劇評家)
劇団新世界『狂人日記』
2019年7月11日(木)~15日(月・祝) 会場 上野ストアハウス
ストアハウスカンパニーが運営する上野ストアハウスでは、主催事業として「ストアハウスコレクション」(2013年~)を年に数回開催している。日本とアジアの集団が、時にテーマを共有しながら競演する催しで、2019年7月時点で15回を数えている。中でも「日韓演劇週間」と題された日韓の企画が最も多い。7回目となった「日韓演劇週間」では、日本のDangerous Boxと韓国の劇団新世界が公演した。テーマは、「食人」を通して儒教社会を批判する魯迅の小説『狂人日記』である。
劇団新世界『狂人日記』(脚色・演出=キム・スジョン)は、9人の俳優が、自らの人間性についての自己紹介をそれぞれに行う作品だ。自虐的に自らを語る基底には、芸術家を志し活動することに対する、社会や家族から負け組・貧困層とみなされていることが貫かれている。そのことを通して、韓国の若者が社会的に置かれた状況を溌剌と、そして切実に訴える作品となっている。物語というよりも、観客に向けたパフォーマンス・プレゼンテーションの体裁を採っている。そのために、俳優たちによって語られる事柄は、どこまでが彼らが実際に経験したことなのかが判然としない。しかし、虚と実の淡いを増幅させる俳優たちの語りは、笑いと共に妙なリアリティを生み出す。そこから韓国社会の「いま」を、俳優の体温と共に観客は受け取るのだ。
同じ国に生きながら、彼らはステータスが高い資本家や旧制度に縛られた家族から虐げられる立場にある。同胞から忌避される様を告白する点において、『狂人日記』で描かれる食人のイメージと通じる。ソウルには演劇街である大学路(テハンノ)があり、私も一度訪れたことがある南山(ナムサン)アートセンターをはじめソウル文化財団が直接運営する劇場が多数ある。大学での演劇教育が盛んであることも知られている。韓国における演劇の地位は、日本よりもずっと公共性を帯びて社会に根付いていると思っていた。そのため、芸術をすることを「狂人」だと自虐的に捉える彼らにいささか驚いた。俳優のパフォーマンス力と劇構造が巧みな本作は、そういったことも含めて非常に興味深かった。そこで本稿では、この作品に絞って詳述することにする。
©宮内勝
本作は、韓国での初演・再演を経ての三演目である。冒頭、舞台上に勢ぞろいした彼らは、初演・再演と常に自分たちと社会情勢とのその都度ビビッドな関係性を描いてきたこと。再演のたびに異なる作品になってきため、今回の日本での公演も全く新たな作品になるだろうとアナウンスされる。そして、何を上演しようかと座組みで相談する、打ち合わせと稽古場風景を思わせるやりとりの後、自己紹介をすることにしますと告げて舞台が始まる。
9人の俳優が、自分は何が好きで何に囚われているのか、何に興味を示しているのかを披露する約1時間の舞台だ。それを、後景に投影される「○○狂人」というお題と共に戯画的に語る。例えば、俳優として痩せなければならないのについつい間食してしまう俳優は「過食狂人」、大企業の社長を親に持ち、その脛をかじりながら俳優をしている者は「影狂人」、母親から働けと言われながらも無職のまま実家に居候しながら俳優をしている者は「ルーザー狂人」。ダメンズばかりを恋人にしてしまい、男にとって都合の良い女に甘んじてきた者は「ガス狂人」と呼ばれる。彼女は男に対するストレスが「ガス」となって、おならとゲップが止まらないのだ。その他、「舞台狂人」「自己愛狂人」「劇的狂人」「フェミニズム狂人」「拘束狂人」とそれぞれにラベリングをして、自分語りをする。
そのことがそのまま、俳優自身の魅力を披露することにつながっている。俳優は皆、キレの良いダンスが踊れるしっかりとした体躯。そして良く通る太くて強い声を持っている。それに加えて、オペラ歌手のように歌える者、ラップができる者がいる。子供の頃に合気道を習っていたという俳優は、カンフー映画のような立ち回りを見せる。おならが出るたびにおばさんのように高らかに笑う「ガス狂人」の俳優は、その様があまりにも自然でほがらかなため、こちらにも笑いが伝播するほどだ。すなわち、皆一芸を持った確かな表現者なのだ。そんな俳優たちの言動は個人的なものだが、例えばそこに現代の奴隷制・階級社会を作り出しているとして、スパイ映画風にサムスン電子を撃とうとする「劇的狂人」が登場する。財閥に就職しなければ勝ち組に入れない韓国社会の「正しさ」と、そこから外れれば「狂人」に見なされてしまう社会構造のいびつさが滲み出る。舞台に登場する「狂人」は、特異な個人ではない。社会構造によって、否応なくそのような立場に置かれた韓国の若者たちの姿なのである。事実、韓国統計庁の発表では、2019年7月の若年層(15~29歳)の失業率は9.8%と、非常に高い数値を示している。
©宮内勝
社会の「正しさ」から外れると「狂人」扱いされ、スポイルされる韓国社会の闇の構造。それを芸術家を志向する演劇人に象徴させることで、彼らは自虐的に語っている。本作はそのことを、俳優たちの魅力で明るく笑いによって表現する。しかし本作の魅力は、そこだけにあるのではない。演劇の趣向を援用する知的な企みが、本作にさらなる奥行きを与えている。そのための重要な存在は、舞台に立つことが大好きで、拍手を観客に何度も求める「舞台狂人」である。彼女は自己紹介が終わった後、黒いマントを羽織れば私は消えることになります。しかし「ここ=舞台上」にはいますと述べる。以後、俳優の自己紹介を舞台にいない体(てい)で見つめる。そして時が経過し、観客も彼女の存在を忘る頃を見計らうかのように、皆さん私のことを忘れないでください、と主張する。その際、言葉を発さずに背景に投影した文字で行うのが笑える。字幕の使い方も凝っている。日本語訳は白字で投影されるのだが、消えたことになって以降の彼女の言葉は、ピンクの字幕になる。そのことで内的な言語をささやくように、そしておずおずと発している様子が上手く表現されるのだ。マントを羽織った姿とピンクの字幕によって、彼女は舞台上から消えて他の登場人物からは見えない透明人間になる。しかし、生身の俳優としてはマントを羽織った姿で、しっかりと舞台奥に座り込んでいる。そのことは、観客からは丸分かりである。
舞台上にいるのに作品上はいないことになるという、演劇の不思議な「お約束」。そのことが社会の役に立たない存在として、"いるのにいない"者として冷遇されている韓国の若者たちに重なるのだ。だからこそ、彼らが自虐的な笑いを用いてそのように自己規定した作品を創らなければならないことに対する怒りや鬱憤、悲しみが強く伝わってくる。演劇趣向を巧みに使うことで、鋭く韓国社会の現状とそこに生きる若者の生態を炙り出す、社会性を孕むに至っているのだ。とはいえ終始、観客を楽しませるユーモアに溢れたエンターテインメントであった。カラフルな照明や自虐的な笑い、歌とダンスで観客を楽しませつつ、そこから人間の生き辛さが透けて見える。だからこそ、かえって胸を打つのだ。それを可能にしているのが、俳優の十分な表現力と巧みな劇構造だ。この2点が合致したことで、俳優たちの不満や情熱をただぶちまけるだけでなく硬軟両面を併せ持つ、全体的に良くできた作品に仕上がっていた。
ラスト、社会に何かを訴えずにはいられない「フェミニズム狂人」が、「狂人」は生まれるのではなく作られるものであること。皆どこかしら狂人であること。加えて、日本の観客は私たちが狂人に見えますか?と尋ねる。彼らの問いかけは、日本で生きる者にとっても切実な問題である。だからこそ観客は、彼らの練られた作品構成と高いパフォーマンスに、最後に熱い拍手で答えたのである。
舞台と観客は少なからず心を寄せて通じた。だが国家のレベルで言えば真逆の事態である。今年7月に日本政府は、半導体材料の韓国への輸出規制を強化した。そして本作を観劇した11日は、韓国・文在寅大統領が大手財閥トップを交えた緊急会合を開いた翌日であった。そこで文大統領は、日本に対し撤回を求める姿勢を初めて明らかにした。そして8月2日に日本政府が、輸出管理手続きを優遇するホワイト国から韓国を除外する閣議決定をした。それにより、戦後最悪の日韓関係が今日まで続いている。
観客が本作に熱い拍手で答えたのは、社会構造からパージされる人間を描いたことに対して、国を越えて共感し連帯の感を寄せたからであろう。そのことと、日韓の政治家や経済人による軋轢とはあまりにも隔たりがある。輸出規制を巡る問題は、いわゆる徴用工問題や自衛隊機への韓国海軍のレーダー照射問題など、昨年来から続く軋轢を踏まえたものである。そういう意味では連続性がある。だが輸出管理の問題は、これまでの歴史認識の齟齬とはフェーズが異なる経済の問題である。そのため、これまでの日韓関係にあった「政経分離」の原則が壊れる懸念がある。日韓の政治家が、互いの政府を非難する声を支持する世論の声も高い。いくつか日韓の姉妹都市の交流事業が中止となり、日本製品の不買運動や韓国から日本への旅行客の減少が報道されている。経済摩擦は国民の諸生活へ、実利的な被害として跳ね返ってくるだけに目に見える影響を与えるのだ。
本作が興味深かっただけに、日韓演劇の交流が阻害されることなく今後も絆を深め続けてほしいと切に感じる。
INDEXに戻る
大竹野正典への実像を体現させた関係者たちの愛
藤原央登(劇評家)
オフィスコットーネプロデュース 大竹野正典没後10年記念公演 第3弾 改訂版『埒もなく汚れなく』&『山の声-ある登山者の追想-』
改訂版『埒もなく汚れなく』
2019年5月9日(木)~19日(日) 会場 シアター711
2019年5月24日(金)~5月27日(月) 会場 アイホール
『山の声-ある登山者の追想-』
2019年5月17日(金)~19日(日) 会場 GEKI地下リバティ
2019年5月24日(金)~5月27日(月) 会場 アイホール
1
大阪で活動した劇作家・演出家の大竹野正典(1960~2009年)。彼の死後、その作品に魅せられたのが、オフィスコットーネのプロデューサー・綿貫凜である。2012年12月に、大竹野作品に魅了されるきっかけとなった遺作『山の声-ある登山者の追想-』(2009年、OMS戯曲賞大賞受賞)を上演。それから足掛け7年、オフィスコットーネは再演を含めて様々な大竹野作品を上演してきた。私はその公演に接するたびに、綿貫の大竹野作品への愛を感じてきた。その愛のひとつの頂点をなすのが『埒もなく汚れなく』(作・演出=瀬戸山美咲、2016年)である。
家族や友人と毎年行っているキャンプで、大竹野は一人で遊泳して水難事故に遭う。その報せを受けて狼狽する家族と友人の姿を起点に、大竹野の高校時代から晩年までの人生が差し挟まれる。大竹野(西尾友樹)と妻・小寿枝(占部房子)、娘・都(さと)(橋爪未萠里)の彼氏・森良太(照井健仁)と大竹野という、2組の関係性が本作では重要となる。これらが、登山家・加藤文太郎と吉田富久の二人芝居である『山の声』と照応する劇構造になっているからである。つまり、槍ヶ岳北鎌尾根の登山中、猛吹雪で遭難死した加藤文太郎に、大竹野を重ね合わせているのだ。それは、表面的な趣向に留まってはいない。加藤文太郎の、遭難という絶体絶命な状況で露になる生への希求。そんな加藤文太郎を、魂の言葉で書き付けた大竹野。両者の人間性が根底で相通じるよう、説得力を持って大竹野の人物像が造形されている。そこにはさらに、『山の声』に魅せられた綿貫の想いも加味されている。だからこそ本作の初演を観て、オフィスコットーネの大竹野作品上演のひとつの集大成だと私は感じたのである。
改訂版『埒もなく汚れなく』©青木司
今年は大竹野正典の没後10年に当たる。「大竹野正典没後10年記念公演」と銘打って、2019年1月~2020年7月19日の命日まで、大阪と東京で様々な団体による公演が予定されている。オフィスコットーネも、2月の『夜が摑む』(作=大竹野正典、演出=詩森ろば)を経て、本稿で触れる改訂版『埒もなく汚れなく』と、くじら企画の初演キャスト・スタッフが参集した『山の声』(作・演出=大竹野正典、協力=くじら企画)のオリジナルバージョンを上演した。8月には『夜、ナク、鳥』(作=大竹野正典)のオマージュ作品『さなぎの教室』(作・演出=松本哲也)が控えている。2002年に実際に起きた、4人の女性看護師による連続保険金殺人事件をモチーフにした作品だ。
大竹野正典という作家がいたこと。彼の作品を少しでも多くの人に知ってもらいたいということ。綿貫はもちろんその想いで大竹野作品の上演に取り組んできたのだろう。しかし、ひとつの区切りとも言える本作を生み出して以降も、一人の作家の作品を上演し続けられるのはなぜか。大竹野作品を上演することが当たり前になるまで初発の熱意を熟し、マンネリや飽きを突き抜けた地平に至っているからだ。そのことは本作に登場する、綿貫をモデルにした演劇プロデューサー・絹川蘭子(柿丸美智恵)によってそう思わされる。
彼女は折に触れてズカズカと大竹野家を訪れ、大竹野夫妻に上演許可を求める。その押しの強さに彼らは面食らう。彼女にそうさせるのは自身で語るように、家族に次いで大竹野のファンであることに尽きるのだろう。そして、惚れ込んだ作家の作品だけを上演していると推察させられる彼女の意志は、劇中「芝居は最高の道楽」と語る大竹野の台詞と響き合う。好きな演劇だけを創ること。その意味で綿貫もまた、大竹野と相通じるのだ。本作には、大小様々な照応関係が多層的に配置されている。この劇構造によって本作は、評伝と創り手の想いの表出が絶妙に交叉する作品たらしめている。私は大阪出身だが、くじら企画の作品は『サヨナフ―ピストル連続射殺魔 ノリオの青春―』(2005年、ウイングフィールド)の再演しか観ていない。しかし本作を観て、大竹野正典という作家はまさにこのような人物だったに違いないという、確かな核心を私に抱かせたのである。
2
大竹野の演劇に対する姿勢で印象的なのは、決してプロの作家にはならず市井の生活者の立場を手放さなかったことにある。大竹野はアルバイトで入社した会社で社員になり、コンクリート技師として生涯勤めた。平行して、1983年に犬の事ム所を旗揚げする(~1996年)。演劇活動に理解を示す社長の計らいにより、公演前に休みが取れるなど融通が利くこと。そして、会社勤めをして子供を育てるという「普通」に暮らす経験の中で感じたことから、創作の糧を得たい。こういった理由から、大竹野は職業作家になることを望まなかった。彼は他人から求められるのではなく、書きたい事があるときに戯曲を生み出す「自己本位」を心情に演劇活動を続けた。そんな夫に対して小寿枝は、大竹野に黙って戯曲を様々な戯曲賞に応募する。『夜が摑む』でテアトロ・イン・キャビン戯曲賞佳作を受賞(1989年)した際に小寿枝は、これを期に東京に進出し劇作家として一本立ちすることを大竹野に勧める。しかし「芝居は最高の道楽」と言い放って、大竹野は妻の要望を拒否。映画監督を夢見て進学した横浜映画専門学校時代を除いて、終生、活動拠点は大阪であった。才能のある夫の作品が、知り合いを中心に100人ほどにしか観てもらえないことに、小寿枝は不満を抱く。一方で小寿枝の要望を、妻自身の欲望を自らに投影したにすぎないと窮屈に感じる大竹野。そんなわけで、事あるごとに二人は激昂し、互いに怒りをぶつけて喧嘩する日々だ。
ところがサラリーマン一家としての大竹野家は、典型的なかかあ天下である。給料日に給料のほとんどをパチンコに費やした大竹野を、小寿枝はこっぴどく叱りつける。以後、大竹野に一日500円と弁当を持参させて財布のひもを握り、自身も内職をしながら家計と劇団活動を維持する。妻の尻に敷かれるダメ亭主の一面は、まさに大竹野が手放さなかった働くお父さんの顔である。どこにでもある夫妻を想像させるボケとツッコミのようなやりとりは、芸術面での大喧嘩とは異なるほほえましいやり取りだ。本作ではこういった、夫妻の愛憎が激しく入り混じる濃密な日々が大部分を占める。
『山の声-ある登山者の追想-』©藍田マリン
ここで先述しておいた、小寿枝とは別に印象深い良太とのエピソードに触れよう。キャンプ前日に大竹野は良太と八幡山(滋賀県)を登山している。その道中、数メートルの滝登りに失敗した大竹野は、膝を強打して負傷。そのことを小寿枝に内緒にしたまま、大竹野はキャンプへ参加した。膝に貼られた絆創膏を見て、遊泳を取りやめるよう忠告する妻をよそに海へと向かう。その背中が、大竹野の最後の姿であった。一連のエピソードは、大竹野の死後に刊行された『大竹野正典劇集成Ⅰ』(松本工房、2012年)の付録「あの日のできごと」における、小寿枝や良太の回顧録が基になっている。良太の回顧では沢登りの詳細な工程と、登山者の先輩である大竹野に認められたいと気負うあまり、自らのリードの失敗によって大竹野にケガをさせたことが記されている。それだけに、大竹野が負傷しなければ事故が起きなかったのではないか、という当然抱く後悔の念が重く響いてくる。
瀬戸山による劇作と演出では、垂直のベクトルを有する沢登りを、舞台空間を水平にらせん状に歩いて表現した。そして、きっと大竹野一人ならケガをすることはなかったはずと気落ちする良太に対し、ここは一人では来れない場所だから二人で登るのだと大竹野は返答する。ここには、冬山で遭難した加藤文太郎と吉田富久のやりとりを思わせる。自ら望んだわけではなく、その個性によって知らず知らずの内に単独登山者となった加藤文太郎。そして劇中、家族から離反する孤独な男を数多く描いてきたと評される大竹野正典。両者は単独、孤独という点でつながる。しかし孤独を選んだとしても、人は必ず他者を必要としそのありがたみに気付くことがある。そのことを男の友情として描く場面は、『山の声』と見事にシンクロする。
3
パートナーとの切っても切れない関係性は、『山の声』の重要なエッセンスである。『埒もなく汚れなく』においても、大竹野と小寿枝の間で加速度的に強まってゆく。そのひとつに、大竹野が同業の作家と浮気をした際のエピソードがある。好きなら一緒に過ごせば良いと、小寿枝は大竹野に告げる。悔しさや悲しみの裏返しか、いずれは自分の元に帰ってくるはずという正妻としての矜持がそう言わせたのか。いずれにせよ小寿枝の複雑な想いに反し、登校する子供のように笑顔で手を振りながら家を出る大竹野は何とも能天気だ。こうして夫妻は別居するのだが、やがて大竹野は家に帰るべく小寿枝に手紙を書く。手紙を介して交わされる夫妻のやりとりにおいて、家に帰る理由に「家族のため」と書かれていたことに対し、誰かのためなら帰ってこなくて良いと、小寿枝はひとり取り乱す。その真意はどこにあるのか。
それは別のシーン、大竹野の遭難の報せを受けて、大竹野の高校時代の先輩・広瀬(福本伸一)と小寿枝の会話が読み解く鍵となる。大竹野作品には、家族から離反し孤独になろうとする男がしばしば登場することは先に触れた。そのことを敏感に察知したのが他ならぬ小寿枝であった。一番身近で深い部分で理解し合えるはずの家族と接することで、かえって孤独さを思い知るという人間の闇。大竹野はそのことを再確認するために結婚生活を送り、その想いを作品に落とし込んでいたのではないか。小寿枝は広瀬にそう打ち明ける。最愛の夫の遭難という弱った心情がそうした想いに囚われた遠因なのかもしれない。大竹野の事故が家族からの永遠の離反、すなわち自殺に近いものとして小寿枝は推察しているとすら受け取れる。小寿枝は大竹野に、自分から離反しようとする不安感を抱いていたのではないか。確かに大竹野は、小寿枝から過度に期待されて彼女の枠に押し込められることを拒否していた。そして大竹野のその想いを、小寿枝も理解していた。大竹野が自己犠牲的に家族の枠に収まろうとすると、今回の浮気のようにまたいずれ自分から離反してしまう。そう考えたからこそ、小寿枝は「家族のため」に戻るという手紙の文言に反発したのだろう。小寿枝は、離れてみて家族が必要だと改めて痛感したという旨の、大竹野の自発的な気付きの言葉が欲しかったのだ。女としての愛の希求と絶望、そして家族としての安定。小寿枝の大竹野への想いの複雑さがうかがえるシーンだけに、非常に重みがあった。
『山の声-ある登山者の追想-』©藍田マリン
確かに大竹野作品には、犯罪加害者を題材にしたものが多い。それだけに、人間の孤独さに焦点が当てられてはいる。だが同時に、それでも他者を求める様も同時に描いてもいる。犬の事ム所を解散した後、プロデュース企画・くじら企画(1997年~)を立ち上げた大竹野が、演劇活動を2年間休止してまで魅せられた登山を題材にした『山の声』。この作品はそれまでのように事件や犯罪ではなく、極限状況下に置かれた人間を描いている。そこには、他者を希求して止まない人間の原基が凝縮している。劇中、彼の才能をいち早く見出し家族に寄り添って応援してきた編集者・小堀純(緒方晋)が述べるように、大竹野の新たな筆致を予感させる作品として位置付けられる。
原稿用紙にガリを切るように、丁寧に鉛筆で『山の声』を書く大竹野。まさに魂を込めて書き上げたばかりの作品を、大竹野と小寿枝が読み上げるシーンがラスト近くに訪れる。しだいに涙を浮かべながら新作を読み上げる夫妻。リーディングで加藤文太郎と吉田富久を体現する彼らの姿を通して、『山の声』へと収斂する劇構造の効果が最大限に際立つ。なぜだか分からないが山へと魅せられる加藤文太郎は、山にいれば里を想い、里にいれば山を想うと語る。この台詞はそのまま、演劇に魅せられた大竹野の、小寿枝や家族との微妙な距離感のことを差している。大竹野は彼なりに全力で演劇と向き合い、そして愛憎の念が入り混じる中でもなくてはならないパートナーとして小寿枝を想っていた。そのことがカタルシス的に了解される場面だった。
『山の声』は猛吹雪のためにビバークした加藤文太郎と吉田富久の会話によって構成されている。しかし、全ては死の直前に加藤が幻視した光景であることが発覚する。最後に加藤が里の家路を説明し、玄関を開けて「少し疲れたから眠らせて欲しい」と述べて幕を閉じることと照応させるべく、『山の声』を読み上げた大竹野が大の字になって横たわる。そして本作で繰り広げられることの一切が、大竹野の行方を坐して待つ小寿枝の回想劇になっているのである。
4
同時期に上演された、くじら企画オリジナルバージョンの『山の声』にも言及しておきたい。オリジナルの『山の声』は、2009年の初演と2011年の大竹野の追悼公演に次いで3演目となる。該当の公演に触れる前に、私が観た『山の声』の上演記録とキャストを整理しておく。
①オフィスコットーネアナザー第1弾(2012年12月、レンタルスペース+カフェ 兎亭)
白井圭太=加藤文太郎
大道達也=吉田富久
②オフィスコットーネアナザー公演第4弾(2013年12月、赤坂CHANCEシアター)
白井圭太=加藤文太郎
飯田太極=吉田富久
③若手演出家コンクー2013 最終審会(2014年3月、「劇」小劇場)
白井圭太=加藤文太郎
いわいのふ健=吉田富久
④劇団チョコレートケーキバージョンプレミアム同時上演(2014年、小劇場B1)
岡本篤=加藤文太郎
浅井伸治=吉田富久
⑤温泉ドラゴン 番外公演(2018年1月、「劇」小劇場)
阪本篤=加藤文太郎
浅倉洋介=吉田富久
⑥オフィスコットーネプロデュース 大竹野正典 没後10年記念公演 第1弾(2018年10月、Space早稲田)
杉木隆幸=加藤文太郎
山田百次=吉田富久
③と⑤を除いて、綿貫がプロデューサーを務めている。温泉ドラゴンのバージョンは大竹野正典没後10年記念公演 参加作品として、本年10月末~11月上旬に兵庫県での再演が予定されている。ちなみに未見の『山の声』に、オフィス3○○プロデュース・鳥ノ巣企画 第一回公演(2010年07月)とカムヰヤッセン(2015年6月)の公演がある。
上演記録を振り返っただけでも、綿貫が『山の声』に賭ける情熱が並大抵ではないことが分かろう。その情熱はプロデュースだけに留まらない。没後10年記念公演では、綿貫自身がオリジナルバージョンを再現するべく、演出も担当している。それを踏まえて、「大竹野正典没後10年記念公演」第3弾として、オリジナルキャストとスタッフによるオリジナルバージョン初の東京公演が行われたのである。
上記の上演では、加藤文太郎を慕う吉田富久を若手俳優が演じることが多かった。登山者としてのキャリアと年齢差の違いを俳優歴のそれに合わせ、両者のコントラストを明確にする配役であった。しかし、オリジナルバージョンの戎屋海老(加藤文太郎)、村尾オサム(吉田富久)は、両者共に野暮ったい中年男である。戎屋が演じる加藤文太郎は、やや枯れた印象の中にも、ひょうきんさと明るさを感じさせる人物だ。白井圭太や杉木隆幸といった、無骨で男気のある人物造形とは対照的だ。むしろその要素は、無精ひげと黒々と焼けた顔が精悍さを感じさせる村尾オサムが演じる吉田富久の方にこそある。加藤と吉田のキャラクターが、綿貫プロデュースとオリジナルでは真逆との言えるほど印象が異なるのだ。吉田富久は決して未熟な登山者ではなく、加藤文太郎が信頼しその実力を認めていたという。村尾が演じる吉田像にはそのことへの説得力が感じられた。
戎屋と村尾のやりとりは、本場の大阪弁であるためかもっちゃりとしている。それを武器に当意即妙のかけあいを行い、おかしみのある場面ではきっちりと笑いを取る。そして雪山での遭難という生死の境目を前にしては、相手を死なせまいと気にかけながら生還を目指し奮闘する。その振れ幅をきちんと表現してみせた。印象深いのは、椅子代わりの登山リュックに座って膝を抱え、会話する2人の姿である。吹雪が止むのを待ちつつも、妙に力の抜けたやりとりを交わす彼らを見て、私は『ゴドーを待ちながら』を想起した。そのような印象は、他の『山の声』で受けたことがない。吹雪によって主体的な行動を奪われたため、待つという受動的な立場に甘んじるしかない2人の男はただただ時間をやり過ごすしかない。加えて加藤文太郎は、単独登山者として認識されていた人物である。そういった事柄が、無為な時間をどうでも良いやりとりで埋める『ゴドー』の浮浪者と、2人の登山者が私の中でつながったのである。
先に紹介した『埒もなく汚れなく』での小堀の言葉や当日パンフレットの文章で、大竹野は『山の声』で新局面を切り開こうとしたと評されている。生や他者を希求する人間が、根本的には孤独であるという複雑さと矛盾。それが切り詰めた劇構造に落とし込まれている。世界演劇史の大転換をなした『ゴドー』と共振する部分が、その理由ではないだろうか。オリジナルバージョンの『山の声』を観ることで、改めてこの作品の射程の深さを思い知らされた。
5
ここまで記してきたことを踏まえ、改めて『埒もなく汚れなく』に戻って考えてみる。大竹野夫妻の、ベクトルを異にする想いが激しくぶつかり合う、愛憎渦巻く濃密な関係性。そのことを、2人の登山者を描いた『山の声』の劇構造の中に落とし込んだ点に、改めて感心する。
そこで描かれる大竹野の姿は、男性なら少なからず思い当たる節があり、共感できるような男の生き様が見出せる。アマチュアに留まろとした大竹野の演劇の向き合い方に、そのことを強く抱かせられる。賞金や名誉、それをフックに権威付こうとうする上昇志向。それらを排して、やりたい事だけやる大竹野の考え方は、頑固一徹で筋が通っている。そんな大竹野の尻を叩き、小寿枝は奮起を促す。その言葉に耳を貸そうとしない大竹野に小寿枝は、彼が憧れている別役実や唐十郎、寺山修司、つかこうへいと同じ土俵で戦っていないと詰め寄る。大竹野はその言葉に敏感に反応する。俺に才能がある、作品が好きだと言いながらそういう言葉を投げかけるということは、やはり特別な才能を持っている彼らには遠く及ばないと感じているからに違いない、と。
小寿枝のこの言葉に反発する大竹野は、痛いところを突かれている。大竹野はきっと自分の才能を自分なりに自覚し、ある手ごたえの下に創作活動を続けていたに違ない。別に仕事を持つ兼業作家だとしても、演劇を「趣味」ではなくアウトロー的に「道楽」と表現する点に、自らを独自に位置付けていることが感得される。とはいえ、賞を狙ったり自分を売り込んで仕事を獲得することはプライドが許さない。淡々と仕事をこなすことで、きっと自分の才能が発見されピックアップされる機会はやってくるはずだ。黙っててもやることをやっていればきっと浮上できる。大竹野にはそのような思いがあったのではないだろうか。その第一人者が大竹野にとっては小寿枝や、大竹野の芝居にしか関わらないと劇中述べられる俳優やスタッフたちだったのだ。
いわば、大竹野は孤独者を装いつつ、身近な人間に甘えていたとは言えまいか。事実、小寿枝が大竹野に黙って戯曲賞に応募したことで、賞をいくつか受賞できたのだ。男にはちっぽけなプライドにしがみついて、それをいつまでも磨くような性がある。そのことを見透かした上で、小寿枝は先の言葉を大竹野に投げつけた。そう考えると、大竹野と小寿枝との関係にも個別の夫妻を越えた、男と女の性すら見出されよう。だからこそ、大竹野夫妻の切っても切れない関係性は、『山の声』の加藤文太郎と吉田富久を下敷きにすることで、他者を希求して止まない人間という普遍性に厚みを与えているのである。
改訂版『埒もなく汚れなく』©青木司
アウトロー的なロマンに固着する大竹野。そんな男ならどこか理解できる人間を、女性が描いた点に、本作のもう一段階の深さがある。そこにもやはり、綿貫の大竹野作品に対する愛を背景に感じる。綿貫をモデルにした絹川は、いかに自分が大竹野のファンであるかを伝えて大竹野家を訪ねることは記した。絹川は小寿枝と知遇を得て、いつしか夫妻と交わした手紙を見せてもらうまでに至る。実際、綿貫は大竹野作品を上演するにあたって、過去の上演作品を観たり小寿枝に何度も会って取材を重ねたりしてきたのだろう。そんな大竹野にまつわる知識をたっぷりの愛情にくるんだ綿貫から、本作の劇作と演出を担った瀬戸山は十分に聞き取ったに違いない。だからこそ、夢見がちで子供っぽい男の微妙な生理を、瀬戸山は生きたものとして掬い取ることができたのだ。もちろん本作に登場する大竹野は、様々なフィルターを通して出来した人物である。したがってフィクショナルな存在だ。しかしだからこそ、男の生き方のひとつのモデルとして共感できるような人物として昇華されているのであり、そこまで出来上がった人物は本人への確かな実像を感得させるには十分なのである。
そのような大竹野像を描いた綿貫と瀬戸山は、本作の制作過程を通して、彼女たち自身もまた大竹野と妻の立場で接していたとすら私には感じられた。大竹野への綿貫の愛の深さを瀬戸山が受け取り、それがまた俳優へと通じた。だからこそ、自然に涙を流しながら大熱演する西尾と占部の演技を引き出したのであろう。小堀純を演じた緒方や広瀬を演じた福本伸一らもしっかりと作品を支えた。大竹野の才能を信じ、彼が遭難した後の小寿枝を励まし支え合う彼らも、人が人に寄り添うことの重要性を側面から体現していた。
大竹野と小寿枝・良太の関係性を『山の声』に重ね合わせる趣向が、まさに『山の声』を生み出すシーンへと至って、最終的に大竹野と小寿枝の関係性の濃密さが倍加する劇構造。『山の声』を蝶番にすることで、大竹野と小寿枝の何度も行き違いながらも交叉する愛憎劇が何重もの厚みを増す。その歪な男女の関係性は、つかこうへい『蒲田行進曲』における銀四郎―小夏―ヤスの三角関係に匹敵する重層的な複雑さと深さがある。大竹野は本作において、つかこうへいと肩を並べたのだ。
綿貫は今後も、深い愛情を持ちながらも大竹野作品を淡々と上演しつづけることだろう。その道行きを、私も観客の一人として随伴したい。
INDEXに戻る






