 |
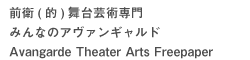 |
「遺稿 アルトー論」
及川廣信
(アルトー館主宰) 資料提供:星野共 編集協力:ホワイトダイス(万城目純.相良ゆみ)
これは及川廣信氏の遺稿で、アントナン・アルトー(Antonin Artaud)に関する興味深い記述が散りばめられています。及川氏のフランス留学から亡くなるまでの期間を通して向き合ってきたアルトー論と言えるでしょう。

かつてアンドレ・ブルトンのシュルレアリスム運動で、その機関誌の編集長として先端を切っていたアントナン・アルトー(Antonin Artaud 1896~1948年)について書くよう依頼されましたが、果たしてアルトーと言っても今の日本人にどれだけ関心を持たれるのか。
しかしフランスの権威ある脳医学者から20世紀において、ニーチェとこのアルトーの二人が最も脳の構造が優れている、と言われたことを知ると、少しは興味を持たれるかもしれません。
ところが20世紀を語る上で、芸術ならびに思想的な観点からこのアルトーを外しては語れない、という事実があるのです。
それは何故か? それは20世紀を指導的なかたちで最後まで思想のレベルを牽引してきたのはドゥルーズ=ガタリの二人の哲学者であるが。その著書『アンチ・オイディプス』(1972年)で、アルトーの晩期に書いた演技論で使用していた「器官なき身体(corps sans organes)という言葉をこの二人の哲学者は、社会と政治を変革するキー概念として使用したのです。
今になって20世紀という前世紀の意味を問題にする場合、この本と対立的なジャン=フランソワ・リオタールの『ポストモダンの条件』との対比が必要だと思うのですが、ここにおいては先のアルトーのことに話を戻しましょう。
この頭脳の人並み以上に優れたアルトーは幼少期に脳膜炎に罹り、それ以降 一生涯、彼は頭痛に悩まされ、それに耐えるため麻薬を使用していた。
その苦しみは他から見ても大変なものだったようで、彼の内部世界は現実世界を超えて他人より明瞭にリアルに感じているようだった。シュルレアリズムのシュルというのは、アルトーにとって決してシュルではなく、日常の現実と並行してリアルに二重性を持って感じ取ることが出来たようで、ブルトンたちが感じていた向こう側のシュルな世界は、アルトーにとってはより現実的な世界だったかもしれません。
そして、その事実をアルトー自身も宣言していたのでした。彼の初期の著作『神経の秤』以来、はっきりと自分の特異性を身に感じ取れるようになったのです。そういう体験が自分だけの特殊なものなのか、あるいは文明人になってはじめて人類の意識の上部に、現在のリアルな文明世界が描かれ現れるようになったのか?
その実験を試みるために、彼はパリ公演が終わった後、直ぐにメキシコのタラフマラに向かったのかもしれない。そして原始人たちに加わり、薬草(麻薬)を使っての秘密の儀式に参加することによって、ヨーロッパ文化を背負った彼にとって、はじめて彼の現実世界を拭いとった思いを経験したのではなかろうか?
その後なぜロンドンに直接船で向かったのか。その理由がわからないのですが、いずれにしろ船上の彼の行為はヨーロッパ人の眼から見ると、異常に見えたのでしょう。それでロンドンに着くなり、精神病院に入れられてしまったのです。入院中のアルトーが書いた文章は、なるほど理解できない部分が多いのですが、それが狂人が書いたものではなく、アルトーだけしか理解できないものであるようです。

私は、このあたりの彼の時期の文章にはついていけないので、以来アルトーの著作よりも、アルトーの身体論から宇宙への彼の思いを知ろうとしています。
そもそもアルトーがバリ島の踊りに感動したのは、パリ万博に参加した催し物を観てのことです。なぜアルトーはその踊りを見て感動したのか、それについてアルトーは、その理由を詳しく分析してはいないのですが、恐らく次のようなことを直感するに感じ取った、と私は推測します。アルトーはその時、バリ島の踊りに、踊りの原点とも言うべきものを直観的に見い出した、と思うのです。すなわちバリ島の踊り手の中に、次なるようなことを感じとったのでしょう。
発生学から言うと、人類はまず頭と胴体が出来て、その後腕と胴部が肩と腰から順を追って発生するのですが。今、肩から腕が発生する場合、まず肩先から掌の部分、次には胴まで、最後に上腕が肩先から生え出すのです。
しかも掌の場合は発生しても最初は指が分離しておらず、袋状になっております。それが発生した後、5指が分離して指先が空中に伸び、その部分が、つまり手頸と指が交感するわけです。次の手頸と肘までが延長する時は、ちょうど胴体の内部で胃腸の器官が形成されたので、踊りの中で、この手頸から肘までの部分が胴体と動きと同調するのです。
そして最後に肘から肩までの上腕の部分が延長されて、はじめて全体の腕の動きによって、今度はからだの外部を取り巻く自空(原稿ママ)へ接触感と、更に宇宙へと広げるのです。そして腰から足までの下部は、腰を下に静めて、しっかりと、自分の人生の場としての地面を踏みしめるのです。アルトーはこれらの踊 りの本質的なものを、バリ島の踊りを見て直接的に感じとったと思うのです。
フランスの最初の住人はケルト人でした。それは紀元前5世紀頃からのことで、それ以前にケルト人はヨーロッパの各地を支配していたのです。
しかし、ケルト人はその後、ゲルマン人の南下とローマ人の南から北からのフランス人の侵入があり、それらに追われるように北西部のブルターニュ半島から、海を渡ってイギリスのウェールズに。また再びアイルランドにまで移った人たちがあり、また、そのままブルターニュの地に踏みとどまった人もいるのです。
ケルト人というのは、それだけローマ人やゲルマン人とは違ってその土地に執着するタイプでなかったようです。
しかし民族の特性としては非常に個性的です。例えば代表的な文学者としてアイルランド人としてはジェイムス・ジョイスとサミュエル・ベケット、ブルターニュからはバルザックが多分そうだと思うし、先に述べたアンドレ・ブルトンがケルト人の血を引いています。
それに対してローマはともかく、ギリシャは植民地だけをマルセーユを中心に地中海の海岸縁に持っていたので、アルトーの母親のギリシャ血統をまず挙げた後に、ヴァレリィやピカソはどう考えてもギリシャ的思考なのです。
ゲルマン人はスカンジナビア半島から先に、このガリアの地に入っていたローマ人を脅かせていたのですが、ローマ人は海に沿って、まず南部のフランスを圧(おさ)え、その後カエサルの指揮のもと、このガリアの地をローマ人のものとしたのです。
そして言語と宗教によって国家形式をとったのです。それは紀元前1世紀の頃であり、その後、紀元476年に西ローマ帝国が崩壊した後、ゲルマンの一部族であるフランク族が他のゲルマン諸族を圧(おさ)え、首領のクロビスプロミスが王位に立って、フランスの国を出発させたのです。
しかしその後、何度か王朝が変わり、最後にブルボン王朝になり、その14世の時代が1番栄え、ベルサイユ宮殿を創設し、そこで華やかな宴を重ねることによって、国内の諸王国を完全に圧(おさ)え、ヨーロッパ第一の威力を示したのです。その上カトリックによって、ローマ法王の結びつきをより深くし、ヨーロッパ全体を支配するかたちとなったのです。
フランスはガリアと言われていた頃はローマの属州とされていて、南仏のニースやアルルなどの町にはローマ時代の建造物がいくつか残存していて、パリ市内のサンミッシェル大通りの浴場跡も、その当時の遺跡です。
紀元800年、シャルルマーニュのカルロス大帝がローマ法王から冠を授けられ、ローマ皇帝として西ヨーロッパの正当性が認められたのですが、フランスのルイ14世の時代になってからは、フランスはヨーロッパ全体の王者としてローマ法王と関わることになったのです。
なぜ以上のようなフランスの歴史的な事にこだわるのか。その目的はシュルレアリズムのアンドレ・ブルトンと アントナン・アルトーの二人の対決の原因を知りたいからです。ブルトンとアルトーは二人とも詩人です。ですがブルトンは詩の次に美術を重要視していて、アルトーは絵は好きなのですが、詩を同等というより演劇を第一としていたのです。ところがフルトンが演劇を最も排除すべきものと思っていたばかりではなく、アルトーの演劇実験の現場に向かって破壊行為にまで及ぶのです。
でもケルト系のアイルランド出身のジョイスにしろ、ベケットにしろ、演劇的な構想の作家です。この事をギリシャとケルトの対立として捕らわれる必要はない。それよりも奥のところで決定的な質の差というものがあるのではなかろうか。それが私のパリ生活での第1の疑問だったのです。
フランスと言っても、特にパリを中心に、ほとんどローマ系の頭で、本来は事務的に処理される。しかし芸術など、心の深部に関わるものはギリシャ系とケルト系では、どのような違いがあるのだろうか。
次はアルトーの私の関心のことですが、これはごく自然な体質的なものだったような気がします。それは別に演劇学のために研究対象とするというものではなく、ただ直感的にもっと知りたい、もっと近寄りたいという思いだったようです。
アルトーという人物を初めて知ったのは、ジャン=ルイ・バローの『Ré flexions sur le théatre(演劇随想)』というフランス語の原書の中でした。この本は第二次世界対戦の終了後、間もなく紀伊国屋を通じてパリの出版社に、スタ二ラフスキー、ジャック・コポー、ルイ・ジューべ、シャルル・デュラン、ジャン=ルイ・バローなどの演出台本の双書と共に注文して購入したもので、これらは渡仏してから驚くほど●●●●●●●●(読みつくしている?)。
これはマルセル・カルネの映画『天井桟敷の人々』は本上映より前のことでしたが、特に前記の『Réflexions sur le théatre(演劇随想)』の中の演出家デュランの教室でのアルトーの行為に驚かされたのです。
フランスの現代演劇はロシアのスタニラフスキーの現代演劇の革新によって、フランスでは最初にアンドレ・ジイッドの友人であるジャック・コポーがルイ・ジューべとシャルル・デュランの二人の俳優がその後、それぞれの劇団を創り活動するのですが、シャルル・デュランはアトリエ座という劇団を始め、また演劇教室も持ってデュランが演劇指導も行なっていました。このデュランという演出家は演技者でもあり、当時の映画によく悪役として出演しており、いかにも悪人の顔で、それにぴったりな演技をするものですから、非常に迫力を感じ、私の好きな俳優でした。ところがデュランの人柄を聞くと、素晴らしい人柄で善人そのものだ、と言われているのです。私は当時、山崎清博士に顔面表情学を学んで、このことを非常に不思議に思っていたのです。
ところが最近デュランの経歴を知ることによって、彼は元悪人だったそうで、それがある時、改心して演劇を始め、それ以来素晴らしい善人になったということです。

さて、そのデュランが教える教室に、しばらく旅に出ていたアルトーが久しぶりに顔を出したのですが、新人のバローにとってはその時が初めての出会いだったのです。
デュランはちょうどある台本に夫々役を降り与えている時でしたので、アルトーにも役を与えて、自習の後それぞれの自由に考えた動きをもとに、演出の側からそれをまとめる段階となり、さてアルトーの役が奥から出場する場面になったとき、なんとアルトーは動物のように四肢で出てきたのです。それを見て全員は笑い、デュランも「それはないだろう」と言ったのです。ところがアルトーは次のように応じたのです。「ムッシュー、デュラン。このことをよく考えてください。四肢で出てくるということは、大きな意味を持っているのですーー」。この後アルトーは『貝殻と僧侶』というシナリオを作るのだが、多分アルトーは旅する間に二本肢と四肢との違いから、身体と精神のつながりについて考え続けていたに違いない。
『貝殻と僧侶』は後に映画化されるのだが、アルトーは僧侶の街中を歩く姿に満足しなかった。しかし、この女流監督が作った実験映画は例の眼球にメスを入れるダリの作品と一緒に傑作として映画史に残ることになる。
私のフランス留学は当時のドル制限の意味から年2回留学のため試験が行われた。美術と音楽が主体で、私のような演劇とバレエを学ぶための者は、その時は私一人だった。しかし私の第1の目的は憧れのアルトーの住んだマルセーユとパリの土を踏みたいという一心でした。それほど当時、1954年に26歳の私はアルトーと一体化しようという一念に燃えていたのです。
結果として私の最初のパリの2年間の留学は大変恵まれていました。まずフランス語は初歩段階でしたが、一応のことには不便を感じなかったこと。そしてITIのメンバーとして、無料で世界演劇祭の2年間は、出品作を観ることができたこと。その中にはブレストの最後の演出作品。ギリシャ劇、京劇など最高の作品ぞろいでした。それに先に申し上げた演劇台本の演出家等の同作品を生で、またはフィルムで並行して学ぶことができたのです。
その上、エチエンヌ・ドゥクルーの現代マイムの研究所に通うことが出来、バレエに関してはパリオペラ座との関係のあるコンセルヴァトワール(ベジャールの出身校)で学ぶことができたのです。
これで午前はバレエ。午後はマイム、夜はバローなどのフランス演劇とオペラを観劇という忙しさで。12時過ぎてからは、アルトーに関する資料に当たるという、睡眠時間が4時間という状態だったのです。しかし残念なことは、パリ全体がアントナン・アルトーのことは既に忘れ去られているようなのです。
しかし、次のような事実が見えてきました。
器官はないのではなく、からだの機能を中心的に動かしている器官(それは現代で五臓)、それを現在までやって来ているのだが、その後は血流とホルモンなどに移動しつつあり、まだ決定的なシステムが見えていない。それが見えてきたならば外部の真のリアリティーを知ることができるだろう、ということです。つまりオルガン対組織が問題なのです。もしこれを社会等と政治当てるとしたら、ドゥルーズ=ガタリよりも同じフランスのブルデューの方がより近いように思います。
またアルターはかつて演劇論として主張した「残酷劇」について次のように説明しています。
それは分子生物学の世界であると同時に、太陽などの宇宙のダンスでもあり、これは正しく人体と人間の思考のシステムを残酷に解剖する「残酷劇」なのです。
アンドレ・ジィッドによるヴィユ・コロンビエ座でのアルトー講演。それは15年ぶりに精神病院から解放されたアルトーを、それぞれの思いを抱いて会場のヴィユ・コロンビエ座に集まった。だがその会は大きな混乱を生じる結果となり、最後にはアルトーは自らの不運を思ってか、泣き叫ぶ状態で立ちすくんだ所に、ジィッ ドが舞台に上がってアルトーを抱きしめる、と言う感動的な場面で終わる。そして客席の中にバローもブルトンも見えていたのです。
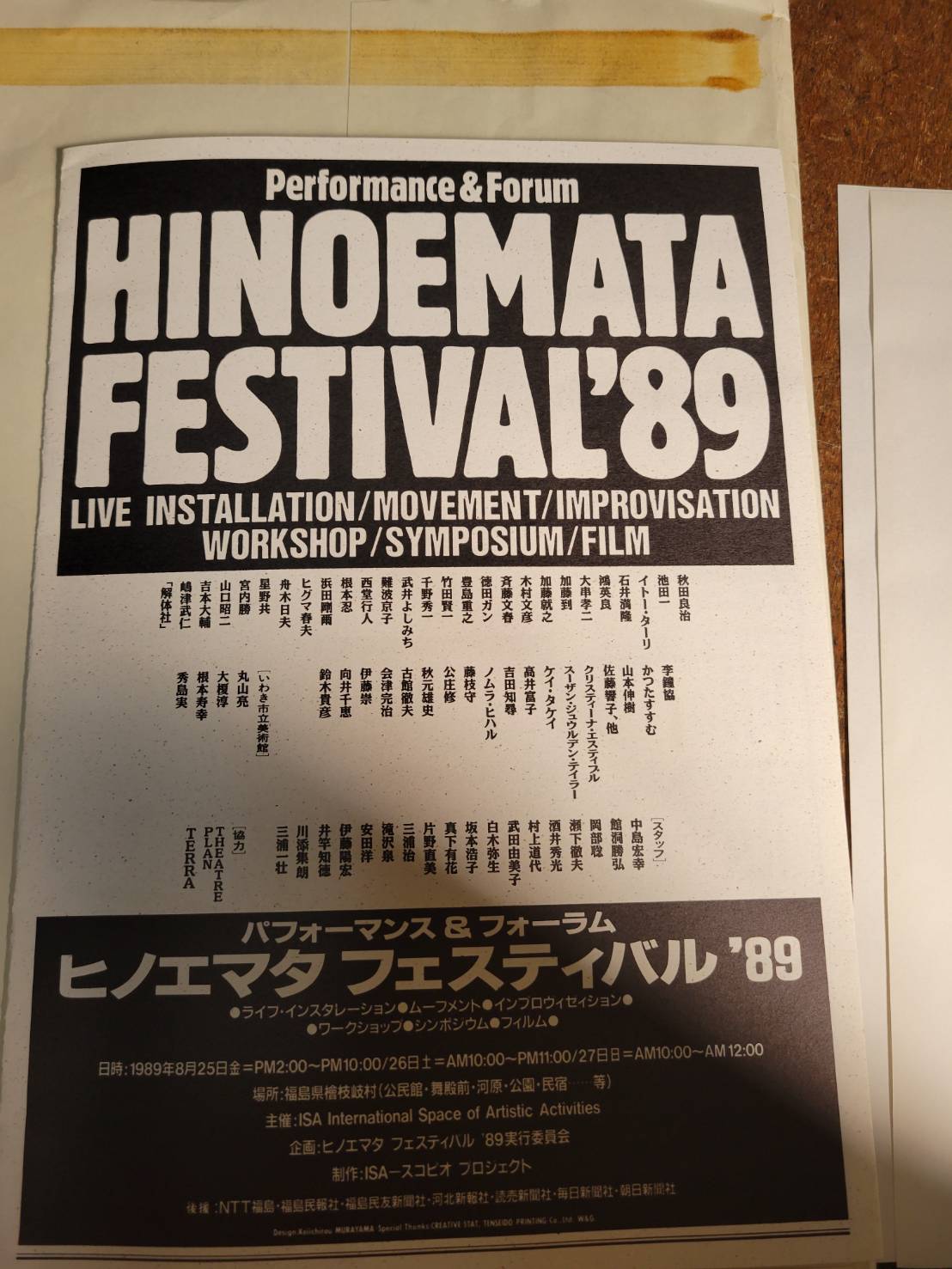
アンドレ・ジィッドは NRF という出版社を仲間と一緒に立ち上げたのですが、それがフランスの知識人の牙城となり、フランスの文化を支えるセンターのようにもなっているのです。
そしてジィッドはアルトーの青年時から、その才能と彼のこの世に生きる態度に感銘しているのです。
ジィッドはフランスを代表する知識人であると同時にアラブに憧れている一面を隠すことがなかった。民族と文化面でアルトーと共通するものを感じていたのでしょうか。
「私たちはこの世に二度と生まれることはない
私たちは死ぬと再びこの世を見ることは出来ないのだ
そして現実世界から引き放たれ
目前の事象を見ることができないため
存在するという理念から失われるのだ」
──アンドレ・ジィッド
私がパリに着いた時には、学生区のカルチェラタンに隣接する、それまで世間に騒がれていたサンジェルマン・デ・プレは静まり、ファッション化されていたが、数年前のこの街の状態が映像化されているものを見たのです。その時の中心メンバーであるサルトル、ボリス・ヴィアン、ジュリエット・グレコたちの活動を紹介した後に、最後のシーンはアントナン・アルトーが車上に立ち上がったまま、両手を天に向かって開き、そのままの姿でサンジェルマンの道を前に進んでくる姿が写されているのですが、その周辺に光を放っている青ざめたアルトーは、正しく民族の犠牲者としての姿を現していたと思うのですが、何故アルトーがこの場面で 引き出されたのが、今でも夢のようにそのビデオを観たことを不思議に思ってい るのです。
ですが、そのキリストのような、その時のアルトーのイメージが強烈に刻みつけられたことが、私にとっての大きな財産なのです。
※原文は手書き。名称、固有名詞、引用文等の表記は原文に依る。
著者プロフィール: 及川廣信(おいかわ・ひろのぶ)
アルトー館主宰。Scorpio Project(現after scorpio)代表。ダンサー。演出家。プロデューサー。
エティエンヌ・ドゥクルー「エコール・ド・ムーブマン」、レオ・スターツ「コンセルヴァトワール・コレオグラフィック・ド・パリ」出身。 ダンス・演劇・マイムの技術と東洋の身体メソッドを横断的研究。日本マイム研究所元所長。

かつてアンドレ・ブルトンのシュルレアリスム運動で、その機関誌の編集長として先端を切っていたアントナン・アルトー(Antonin Artaud 1896~1948年)について書くよう依頼されましたが、果たしてアルトーと言っても今の日本人にどれだけ関心を持たれるのか。
しかしフランスの権威ある脳医学者から20世紀において、ニーチェとこのアルトーの二人が最も脳の構造が優れている、と言われたことを知ると、少しは興味を持たれるかもしれません。
ところが20世紀を語る上で、芸術ならびに思想的な観点からこのアルトーを外しては語れない、という事実があるのです。
それは何故か? それは20世紀を指導的なかたちで最後まで思想のレベルを牽引してきたのはドゥルーズ=ガタリの二人の哲学者であるが。その著書『アンチ・オイディプス』(1972年)で、アルトーの晩期に書いた演技論で使用していた「器官なき身体(corps sans organes)という言葉をこの二人の哲学者は、社会と政治を変革するキー概念として使用したのです。
今になって20世紀という前世紀の意味を問題にする場合、この本と対立的なジャン=フランソワ・リオタールの『ポストモダンの条件』との対比が必要だと思うのですが、ここにおいては先のアルトーのことに話を戻しましょう。
この頭脳の人並み以上に優れたアルトーは幼少期に脳膜炎に罹り、それ以降 一生涯、彼は頭痛に悩まされ、それに耐えるため麻薬を使用していた。
その苦しみは他から見ても大変なものだったようで、彼の内部世界は現実世界を超えて他人より明瞭にリアルに感じているようだった。シュルレアリズムのシュルというのは、アルトーにとって決してシュルではなく、日常の現実と並行してリアルに二重性を持って感じ取ることが出来たようで、ブルトンたちが感じていた向こう側のシュルな世界は、アルトーにとってはより現実的な世界だったかもしれません。
そして、その事実をアルトー自身も宣言していたのでした。彼の初期の著作『神経の秤』以来、はっきりと自分の特異性を身に感じ取れるようになったのです。そういう体験が自分だけの特殊なものなのか、あるいは文明人になってはじめて人類の意識の上部に、現在のリアルな文明世界が描かれ現れるようになったのか?
その実験を試みるために、彼はパリ公演が終わった後、直ぐにメキシコのタラフマラに向かったのかもしれない。そして原始人たちに加わり、薬草(麻薬)を使っての秘密の儀式に参加することによって、ヨーロッパ文化を背負った彼にとって、はじめて彼の現実世界を拭いとった思いを経験したのではなかろうか?
その後なぜロンドンに直接船で向かったのか。その理由がわからないのですが、いずれにしろ船上の彼の行為はヨーロッパ人の眼から見ると、異常に見えたのでしょう。それでロンドンに着くなり、精神病院に入れられてしまったのです。入院中のアルトーが書いた文章は、なるほど理解できない部分が多いのですが、それが狂人が書いたものではなく、アルトーだけしか理解できないものであるようです。

私は、このあたりの彼の時期の文章にはついていけないので、以来アルトーの著作よりも、アルトーの身体論から宇宙への彼の思いを知ろうとしています。
そもそもアルトーがバリ島の踊りに感動したのは、パリ万博に参加した催し物を観てのことです。なぜアルトーはその踊りを見て感動したのか、それについてアルトーは、その理由を詳しく分析してはいないのですが、恐らく次のようなことを直感するに感じ取った、と私は推測します。アルトーはその時、バリ島の踊りに、踊りの原点とも言うべきものを直観的に見い出した、と思うのです。すなわちバリ島の踊り手の中に、次なるようなことを感じとったのでしょう。
発生学から言うと、人類はまず頭と胴体が出来て、その後腕と胴部が肩と腰から順を追って発生するのですが。今、肩から腕が発生する場合、まず肩先から掌の部分、次には胴まで、最後に上腕が肩先から生え出すのです。
しかも掌の場合は発生しても最初は指が分離しておらず、袋状になっております。それが発生した後、5指が分離して指先が空中に伸び、その部分が、つまり手頸と指が交感するわけです。次の手頸と肘までが延長する時は、ちょうど胴体の内部で胃腸の器官が形成されたので、踊りの中で、この手頸から肘までの部分が胴体と動きと同調するのです。
そして最後に肘から肩までの上腕の部分が延長されて、はじめて全体の腕の動きによって、今度はからだの外部を取り巻く自空(原稿ママ)へ接触感と、更に宇宙へと広げるのです。そして腰から足までの下部は、腰を下に静めて、しっかりと、自分の人生の場としての地面を踏みしめるのです。アルトーはこれらの踊 りの本質的なものを、バリ島の踊りを見て直接的に感じとったと思うのです。
フランスの最初の住人はケルト人でした。それは紀元前5世紀頃からのことで、それ以前にケルト人はヨーロッパの各地を支配していたのです。
しかし、ケルト人はその後、ゲルマン人の南下とローマ人の南から北からのフランス人の侵入があり、それらに追われるように北西部のブルターニュ半島から、海を渡ってイギリスのウェールズに。また再びアイルランドにまで移った人たちがあり、また、そのままブルターニュの地に踏みとどまった人もいるのです。
ケルト人というのは、それだけローマ人やゲルマン人とは違ってその土地に執着するタイプでなかったようです。
しかし民族の特性としては非常に個性的です。例えば代表的な文学者としてアイルランド人としてはジェイムス・ジョイスとサミュエル・ベケット、ブルターニュからはバルザックが多分そうだと思うし、先に述べたアンドレ・ブルトンがケルト人の血を引いています。
それに対してローマはともかく、ギリシャは植民地だけをマルセーユを中心に地中海の海岸縁に持っていたので、アルトーの母親のギリシャ血統をまず挙げた後に、ヴァレリィやピカソはどう考えてもギリシャ的思考なのです。
ゲルマン人はスカンジナビア半島から先に、このガリアの地に入っていたローマ人を脅かせていたのですが、ローマ人は海に沿って、まず南部のフランスを圧(おさ)え、その後カエサルの指揮のもと、このガリアの地をローマ人のものとしたのです。
そして言語と宗教によって国家形式をとったのです。それは紀元前1世紀の頃であり、その後、紀元476年に西ローマ帝国が崩壊した後、ゲルマンの一部族であるフランク族が他のゲルマン諸族を圧(おさ)え、首領のクロビスプロミスが王位に立って、フランスの国を出発させたのです。
しかしその後、何度か王朝が変わり、最後にブルボン王朝になり、その14世の時代が1番栄え、ベルサイユ宮殿を創設し、そこで華やかな宴を重ねることによって、国内の諸王国を完全に圧(おさ)え、ヨーロッパ第一の威力を示したのです。その上カトリックによって、ローマ法王の結びつきをより深くし、ヨーロッパ全体を支配するかたちとなったのです。
フランスはガリアと言われていた頃はローマの属州とされていて、南仏のニースやアルルなどの町にはローマ時代の建造物がいくつか残存していて、パリ市内のサンミッシェル大通りの浴場跡も、その当時の遺跡です。
紀元800年、シャルルマーニュのカルロス大帝がローマ法王から冠を授けられ、ローマ皇帝として西ヨーロッパの正当性が認められたのですが、フランスのルイ14世の時代になってからは、フランスはヨーロッパ全体の王者としてローマ法王と関わることになったのです。
なぜ以上のようなフランスの歴史的な事にこだわるのか。その目的はシュルレアリズムのアンドレ・ブルトンと アントナン・アルトーの二人の対決の原因を知りたいからです。ブルトンとアルトーは二人とも詩人です。ですがブルトンは詩の次に美術を重要視していて、アルトーは絵は好きなのですが、詩を同等というより演劇を第一としていたのです。ところがフルトンが演劇を最も排除すべきものと思っていたばかりではなく、アルトーの演劇実験の現場に向かって破壊行為にまで及ぶのです。
でもケルト系のアイルランド出身のジョイスにしろ、ベケットにしろ、演劇的な構想の作家です。この事をギリシャとケルトの対立として捕らわれる必要はない。それよりも奥のところで決定的な質の差というものがあるのではなかろうか。それが私のパリ生活での第1の疑問だったのです。
フランスと言っても、特にパリを中心に、ほとんどローマ系の頭で、本来は事務的に処理される。しかし芸術など、心の深部に関わるものはギリシャ系とケルト系では、どのような違いがあるのだろうか。
次はアルトーの私の関心のことですが、これはごく自然な体質的なものだったような気がします。それは別に演劇学のために研究対象とするというものではなく、ただ直感的にもっと知りたい、もっと近寄りたいという思いだったようです。
アルトーという人物を初めて知ったのは、ジャン=ルイ・バローの『Ré flexions sur le théatre(演劇随想)』というフランス語の原書の中でした。この本は第二次世界対戦の終了後、間もなく紀伊国屋を通じてパリの出版社に、スタ二ラフスキー、ジャック・コポー、ルイ・ジューべ、シャルル・デュラン、ジャン=ルイ・バローなどの演出台本の双書と共に注文して購入したもので、これらは渡仏してから驚くほど●●●●●●●●(読みつくしている?)。
これはマルセル・カルネの映画『天井桟敷の人々』は本上映より前のことでしたが、特に前記の『Réflexions sur le théatre(演劇随想)』の中の演出家デュランの教室でのアルトーの行為に驚かされたのです。
フランスの現代演劇はロシアのスタニラフスキーの現代演劇の革新によって、フランスでは最初にアンドレ・ジイッドの友人であるジャック・コポーがルイ・ジューべとシャルル・デュランの二人の俳優がその後、それぞれの劇団を創り活動するのですが、シャルル・デュランはアトリエ座という劇団を始め、また演劇教室も持ってデュランが演劇指導も行なっていました。このデュランという演出家は演技者でもあり、当時の映画によく悪役として出演しており、いかにも悪人の顔で、それにぴったりな演技をするものですから、非常に迫力を感じ、私の好きな俳優でした。ところがデュランの人柄を聞くと、素晴らしい人柄で善人そのものだ、と言われているのです。私は当時、山崎清博士に顔面表情学を学んで、このことを非常に不思議に思っていたのです。
ところが最近デュランの経歴を知ることによって、彼は元悪人だったそうで、それがある時、改心して演劇を始め、それ以来素晴らしい善人になったということです。

さて、そのデュランが教える教室に、しばらく旅に出ていたアルトーが久しぶりに顔を出したのですが、新人のバローにとってはその時が初めての出会いだったのです。
デュランはちょうどある台本に夫々役を降り与えている時でしたので、アルトーにも役を与えて、自習の後それぞれの自由に考えた動きをもとに、演出の側からそれをまとめる段階となり、さてアルトーの役が奥から出場する場面になったとき、なんとアルトーは動物のように四肢で出てきたのです。それを見て全員は笑い、デュランも「それはないだろう」と言ったのです。ところがアルトーは次のように応じたのです。「ムッシュー、デュラン。このことをよく考えてください。四肢で出てくるということは、大きな意味を持っているのですーー」。この後アルトーは『貝殻と僧侶』というシナリオを作るのだが、多分アルトーは旅する間に二本肢と四肢との違いから、身体と精神のつながりについて考え続けていたに違いない。
『貝殻と僧侶』は後に映画化されるのだが、アルトーは僧侶の街中を歩く姿に満足しなかった。しかし、この女流監督が作った実験映画は例の眼球にメスを入れるダリの作品と一緒に傑作として映画史に残ることになる。
私のフランス留学は当時のドル制限の意味から年2回留学のため試験が行われた。美術と音楽が主体で、私のような演劇とバレエを学ぶための者は、その時は私一人だった。しかし私の第1の目的は憧れのアルトーの住んだマルセーユとパリの土を踏みたいという一心でした。それほど当時、1954年に26歳の私はアルトーと一体化しようという一念に燃えていたのです。
結果として私の最初のパリの2年間の留学は大変恵まれていました。まずフランス語は初歩段階でしたが、一応のことには不便を感じなかったこと。そしてITIのメンバーとして、無料で世界演劇祭の2年間は、出品作を観ることができたこと。その中にはブレストの最後の演出作品。ギリシャ劇、京劇など最高の作品ぞろいでした。それに先に申し上げた演劇台本の演出家等の同作品を生で、またはフィルムで並行して学ぶことができたのです。
その上、エチエンヌ・ドゥクルーの現代マイムの研究所に通うことが出来、バレエに関してはパリオペラ座との関係のあるコンセルヴァトワール(ベジャールの出身校)で学ぶことができたのです。
これで午前はバレエ。午後はマイム、夜はバローなどのフランス演劇とオペラを観劇という忙しさで。12時過ぎてからは、アルトーに関する資料に当たるという、睡眠時間が4時間という状態だったのです。しかし残念なことは、パリ全体がアントナン・アルトーのことは既に忘れ去られているようなのです。
しかし、次のような事実が見えてきました。
「人間の体の真の器官がまだ構造化されて動き出していないので、リアリティなるものが見えていないのだ」──アントナン・アルトー
晩年の理論の中に、上の文章が見出されたのです。これはドゥルーズ=ガタリがキー概念として選んだ「器官なき身体」の解釈とは違っている。器官はないのではなく、からだの機能を中心的に動かしている器官(それは現代で五臓)、それを現在までやって来ているのだが、その後は血流とホルモンなどに移動しつつあり、まだ決定的なシステムが見えていない。それが見えてきたならば外部の真のリアリティーを知ることができるだろう、ということです。つまりオルガン対組織が問題なのです。もしこれを社会等と政治当てるとしたら、ドゥルーズ=ガタリよりも同じフランスのブルデューの方がより近いように思います。
またアルターはかつて演劇論として主張した「残酷劇」について次のように説明しています。
「私のいう残酷演劇というのは、人間の体を全く新しい技法を使って演出されたもので、それはミクロの世界であり、また凝結した虚無の世界でもあるのです」──アントナン・アルトー
これは全く現代物理学と老子のタオを溶け合わせた作品で、しかも俳優ではなくダンサーを使用する。なぜなら身体的な技術の問題は演劇の俳優よりも素材としては都合が良いだけではなく、おそらくアルトーの望んでいることはバリ島の踊りを参考にして、私が先にバリ島のダンスを分析したように、おそらくその方法でからだを徹底的に創り変えること。それは分子生物学の世界であると同時に、太陽などの宇宙のダンスでもあり、これは正しく人体と人間の思考のシステムを残酷に解剖する「残酷劇」なのです。
アンドレ・ジィッドによるヴィユ・コロンビエ座でのアルトー講演。それは15年ぶりに精神病院から解放されたアルトーを、それぞれの思いを抱いて会場のヴィユ・コロンビエ座に集まった。だがその会は大きな混乱を生じる結果となり、最後にはアルトーは自らの不運を思ってか、泣き叫ぶ状態で立ちすくんだ所に、ジィッ ドが舞台に上がってアルトーを抱きしめる、と言う感動的な場面で終わる。そして客席の中にバローもブルトンも見えていたのです。
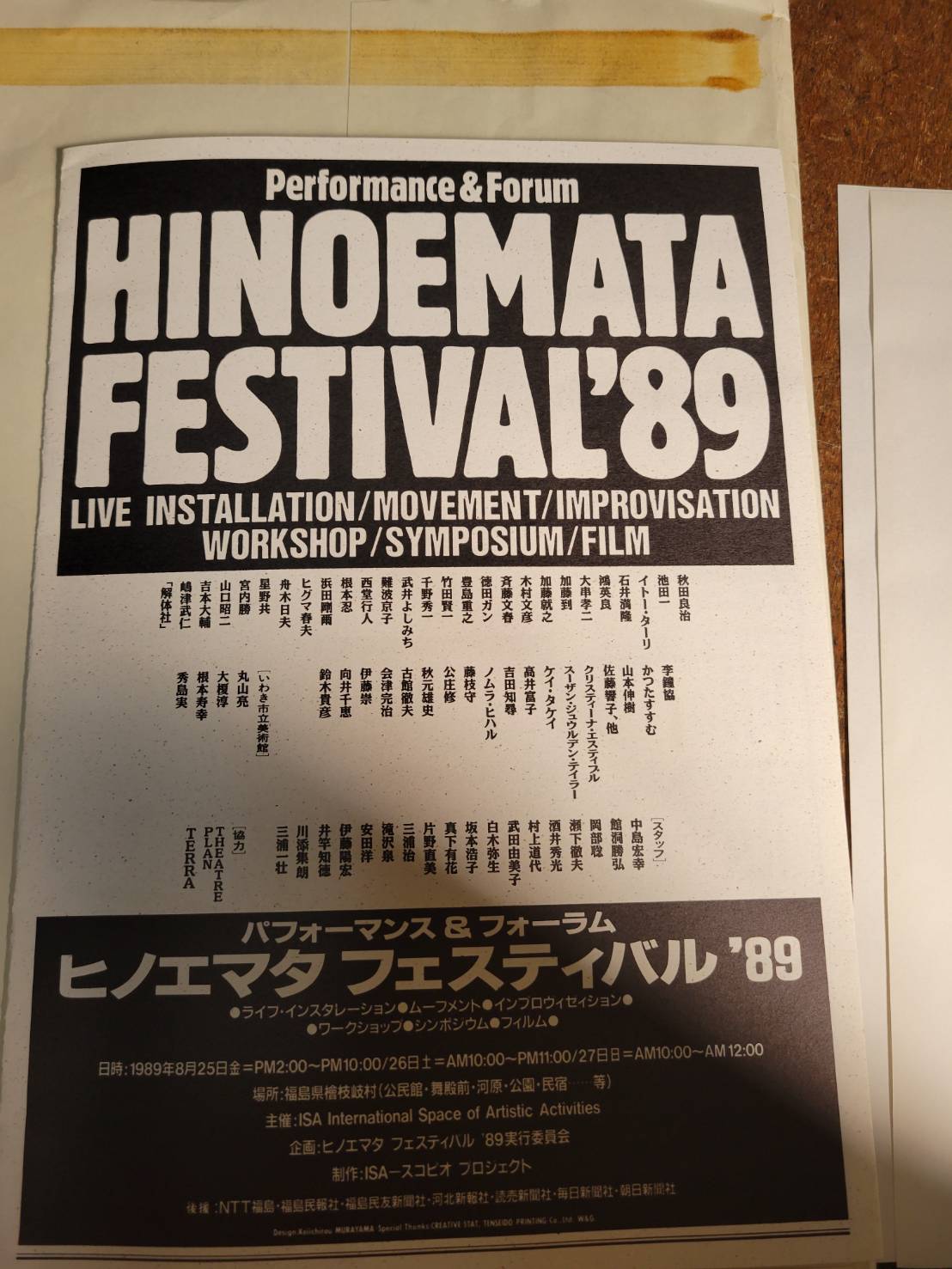
アンドレ・ジィッドは NRF という出版社を仲間と一緒に立ち上げたのですが、それがフランスの知識人の牙城となり、フランスの文化を支えるセンターのようにもなっているのです。
そしてジィッドはアルトーの青年時から、その才能と彼のこの世に生きる態度に感銘しているのです。
ジィッドはフランスを代表する知識人であると同時にアラブに憧れている一面を隠すことがなかった。民族と文化面でアルトーと共通するものを感じていたのでしょうか。
「私たちはこの世に二度と生まれることはない
私たちは死ぬと再びこの世を見ることは出来ないのだ
そして現実世界から引き放たれ
目前の事象を見ることができないため
存在するという理念から失われるのだ」
──アンドレ・ジィッド
ですが、そのキリストのような、その時のアルトーのイメージが強烈に刻みつけられたことが、私にとっての大きな財産なのです。
※原文は手書き。名称、固有名詞、引用文等の表記は原文に依る。
著者プロフィール: 及川廣信(おいかわ・ひろのぶ)
アルトー館主宰。Scorpio Project(現after scorpio)代表。ダンサー。演出家。プロデューサー。
エティエンヌ・ドゥクルー「エコール・ド・ムーブマン」、レオ・スターツ「コンセルヴァトワール・コレオグラフィック・ド・パリ」出身。 ダンス・演劇・マイムの技術と東洋の身体メソッドを横断的研究。日本マイム研究所元所長。
INDEXに戻る