 |
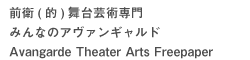 |
「"核"と修羅 宮沢賢治からの視線 - OM-2×柴田恵美×bug-depayse
「M/Mフェスティバル」参加『椅子に座る−Mの心象スケッチ−』」
吉田悠樹彦
(ダンス批評家)
宮沢賢治を描いたOM-2・柴田恵美・bug-depayseのコラボレーション作品が上演された。真壁茂夫と宗方勝、柴田恵美の共同演出の作品だ。「銀河鉄道の夜」、「春と修羅」など宮沢のテキストを用いながら時代背景、作家性などから"異端と生"というテーマを描いたインクルーシブな要素もあるメディア・パフォーマンス作品である。
 © 丸山雄二
© 丸山雄二
冒頭、一人の男が現れ、観客へ「体育」の授業をはじめ作品が始まる。観客たちはラジオ体操をする。先生は学生に成績をつけさせる。続く「国語」になると先生は学生にパンフを朗読させる。先生は教員でもあった賢治自身でもあるが、この作品のナビゲーターでもある。
この文学者が世間に知られるようになったきっかけの一つは、戦前の軍部が「雨にも負けず」の冒頭部分をプロパガンダに利用したことである。この様にさらに知るとこの宮沢賢治の面白さが解ることが語られていく。作家の人生において作品中にでてくるイメージがどの様に派生したかが紹介される。例えば「注文の多い料理店」や「風の又三郎」の一シーン、そして「銀河鉄道の夜」の作中に登場するタイタニック号沈没事故などのエピソードと、宇宙や自然のイメージがお互いにリンクしていく。宮沢賢治の原風景や意識の様相を立ち上げていくような演出だ。宮沢賢治が手がけた歌曲も用いられている。
怪優・佐々木敦が問い描く賢治像は煩悶と慟哭を繰り返す。宮沢賢治を評価したのは文学者でダダイストの辻潤だった事を彷彿とさせる。辻はアナーキストの大杉栄に妻・伊藤野枝を奪われ、「英語、尺八、ヴァイオリンの教授」の看板を掲げるようになり、やがて放浪生活をすることになった浅草を代表するユニークな文学者だ。2022年から1世紀前にあたる1922年ごろに彼や詩人・高橋新吉は自らをダダイストと名乗るようになる。余談となるがこの年にアンナ・パブロワが来日公演を行い、年の瀬に石井漠・小浪は渡欧する。辻は新聞に掲載をしていたエッセイで宮沢の詩集「春と修羅」(1924年)を刊行されたその年に高く評価した。宮沢の作品にでてくる音楽のイメージは彼が当時接触していた浅草オペラからの影響であるという論もある。辻もまた山田耕筰ら当時の先端的な舞台芸術や浅草の演芸と接している。
 © 丸山雄二
© 丸山雄二
賢治は自身の内面を"修羅"(ケダモノ)と描いた。"生きながら地獄に堕ちたこの修羅のからだ、空のみじんにちらばれ"というその言葉は真壁茂夫の演出論ととも舞台のクライマックスの場面となる。宮沢が感じ取っていた生きる根拠、例えば彼がセクシャルマイナリティであることを通じて、さらには異端を排除する日本社会の問題が描きだされる。これが「『核』からの視点」(れんが書房新社、2010)などで語られてきた、個人の「核」をその演出論で重視する真壁茂夫の問題意識と通じる点だ。
真壁は宮沢賢治が圧倒的に孤独を抱えており生きるための「隠れ蓑」をしていたと考察する。そして近年、日本で紹介され話題となった賢治がセクシャルマイナリティであることを示す資料を用いながら賢治にとっての「核」について問いかけがなされる。やがて“わたくしという現象は 仮定された有機交流伝統の ひとつの青い照明です”という言葉で序文が始まる詩集「春と修羅」を用いて、特に妹への感情とされる「永訣の朝」の下りが取り上げられていく。"修羅"(ケダモノ)としての生きる事が描かれ、その意識はメディア・パフォーマンスを交えながら作中のパフォ―マティヴな身体に描かれる。
宮沢賢治にとっての生きる根拠の問題は、出演者一人一人の生きる根拠にも連なることが示される。中でも車いすで登場する障がい者演劇の野澤健が舞台全体に強度を与えている。彼の存在に対して、教師は異端としてより一般性であれと野澤を何度も力強く殴り顔面が赤くなる場面も登場する。
ダンスの場面では柴田恵美が一列に並ぶ椅子と共に、決してムーヴメントとして完成することない同じシークエンスを反復していく。作品「傾斜 -Heaven&Hell」(2020)から躍進を重ねている柴田の振付言語は意味解釈や演出との歩みよりを拒否するような解読不能な文字だ。異端に憧れピエール・クロソウスキーに挑んだ現代舞踊出身の黒沢美香は逆に異端であろうとする姿勢がみえそれが裏目にでることもあった。柴田の作らず客に媚びないその清純派の眼差しはまぶしい限りだ。日本の歴史や伝統との対峙に妙にこだわることなく、しっかりとピュアに自分の思考と身体をこの作品の中へ残そうとしている。
作品のラストには観客にリラックスを勧めるシーンが織り込まれている。同一性を強要するような日本社会の全体主義的な狂気に催眠や教育への懐疑といった面からも踏み込んでいる。作品に登場する映像は宗方勝が手掛けていると考えられる。今野勉の細部を描くテレビ・ドキュメンタリーならではの映像詩の表現と異なり、パフォ―マティブに身体から現代を描こうとしている。
 © 大洞博靖
© 大洞博靖
宮沢賢治をテーマにした作品は近年舞踊界で上演されている。コンテンポラリーダンスの勅使川原三郎もそんな一人だ。勅使川原は長年自分が読み込んでいた宮沢賢治の作品とその解釈からこの文学者の世界や作品をダンス化している。
一方、この作品は若いころからずっと賢治の作品に対して距離を置いていた真壁は演出家・プロデューサー・脚本家で テレビ論の今野勉が演出を手掛けたドキュメンタリー「映像詩 宮沢賢治 銀河への旅~慟哭の愛と祈り~」(2021)や著作「宮沢賢治の真実-修羅を生きた詩人-」(新潮社、2017)と出会う。今野は森鷗外の「舞姫」のモデルとされる美少女エリスの実像に挑んだ「鷗外の恋人:百二十年後の真実」(日本放送出版協会、2010)のような著作があり、資料を駆使した構成をする。日本のテレビ文化を代表する才能の一人だ。書簡など具体的な資料に基づき、セクシャルマイナリティとしての側面に対する考察から賢治像を立ち上げてみせた。その面白さに気がついた真壁はこの作品と取り組んだ。
 © 丸山雄二
© 丸山雄二
真壁は演劇を身体でとらえるとも考えている。その姿勢がダンス界との接点にもつながり、演劇のみならずダンス・フェスティバルを長年開催することへとつながってきた。彼が率いるパフォーマンス集団OM-2は首都圏で活動し、長くいろいろな観客がその仕事をみてきた。
私は真壁についてモレキュラ―・シアターの豊島重之とある面で全く逆であるように感じている。豊島はパフォーマンスとモダンダンスを通じた前衛劇から青森・八戸で活躍し、賢治を作品のイメージに用いることもあった。彼は地方で政治的に立ち回ることで独自の場を構築してみせたが、周囲を権威でかためたが、その後年の活動は限られた関係者しかみとどけていなく、活動の全貌を80年代から長く見てきた人物の評はほぼいない。一見、独自な地平を形成したとはいえるが、後年の彼の作品が本当に独創的かというと、20世紀末の彼らの作風で止まっていたような部分もある。
一方、OM-2の作品は様々な人が接してきており、ポストドラマ演劇のカラーを色濃く持ちながらも柔軟に新時代を吸収しようとしている。さらに障がい者演劇やメディアアートとの接点を考えるbug-depayseのような活動もはじまっている。
真壁はアングラ世代の演劇については、結果としてそれ以前の演劇人と同じようなことに陥ったり、単に経済的に優位であるだけになってしまったと指摘をしている。この姿勢は日本のダンス界にあてはめることも可能だろう。舞踏やコンテンポラリーダンスもすっかり「日本」化し、彼らが長年否定をしてきた洋舞界の大系列を中心とする体制のようになり、中身も空洞化してきている。ダンスでも演劇でも自分の原点に返りながら権力と距離を取りことで、さらなる新しい方向性を歩みと表現をどのようにみせるかが問われている。2020年代は舞踏もコンテンポラリーダンスも歴史的な重々しい概念で、新しいまだ呼び名のわからないような表現が重要となる。2021年にd-倉庫は惜しまれながら閉館となったが、その後の真壁の歩みと「日本」によりかかららない独自な方向性が楽しみだ。
(2022年3月17日、日暮里SUNNY HALL)
著者プロフィール: 吉田悠樹彦(よしだ・ゆきひこ)/ダンス批評家
舞台芸術ではバレエ・ダンスからパフォーマンスに至るまで身体表現に関して評論活動を展開する。舞踊ジャンルではコンクールの審査や芸能賞の選考に携わる。
メディア芸術ではレニ・リーフェンシュタール論を新しい科学と芸術のジャーナル『Technoetic Arts』(ロイ・アスコット編)に発表しPrix Ars Electronicaデジタル・コミュニティ部門国際アドバイザー(2005-2009)を務めた。映像ジャンルでは東京ドキュメンタリー映画祭やドキュメンタリーカルチャーマガジンneoneoで活動する。
共編著のneoneo叢書「ジョナス・メカス論集」(2020)「アニエス・ヴァルダ論集」(2021)、Routledge Companion to Butoh Performance(2019)、20世紀舞踊研究会編「修訂版・20世紀舞踊」(2021)他 著作多数。
 © 丸山雄二
© 丸山雄二 冒頭、一人の男が現れ、観客へ「体育」の授業をはじめ作品が始まる。観客たちはラジオ体操をする。先生は学生に成績をつけさせる。続く「国語」になると先生は学生にパンフを朗読させる。先生は教員でもあった賢治自身でもあるが、この作品のナビゲーターでもある。
この文学者が世間に知られるようになったきっかけの一つは、戦前の軍部が「雨にも負けず」の冒頭部分をプロパガンダに利用したことである。この様にさらに知るとこの宮沢賢治の面白さが解ることが語られていく。作家の人生において作品中にでてくるイメージがどの様に派生したかが紹介される。例えば「注文の多い料理店」や「風の又三郎」の一シーン、そして「銀河鉄道の夜」の作中に登場するタイタニック号沈没事故などのエピソードと、宇宙や自然のイメージがお互いにリンクしていく。宮沢賢治の原風景や意識の様相を立ち上げていくような演出だ。宮沢賢治が手がけた歌曲も用いられている。
怪優・佐々木敦が問い描く賢治像は煩悶と慟哭を繰り返す。宮沢賢治を評価したのは文学者でダダイストの辻潤だった事を彷彿とさせる。辻はアナーキストの大杉栄に妻・伊藤野枝を奪われ、「英語、尺八、ヴァイオリンの教授」の看板を掲げるようになり、やがて放浪生活をすることになった浅草を代表するユニークな文学者だ。2022年から1世紀前にあたる1922年ごろに彼や詩人・高橋新吉は自らをダダイストと名乗るようになる。余談となるがこの年にアンナ・パブロワが来日公演を行い、年の瀬に石井漠・小浪は渡欧する。辻は新聞に掲載をしていたエッセイで宮沢の詩集「春と修羅」(1924年)を刊行されたその年に高く評価した。宮沢の作品にでてくる音楽のイメージは彼が当時接触していた浅草オペラからの影響であるという論もある。辻もまた山田耕筰ら当時の先端的な舞台芸術や浅草の演芸と接している。
 © 丸山雄二
© 丸山雄二 賢治は自身の内面を"修羅"(ケダモノ)と描いた。"生きながら地獄に堕ちたこの修羅のからだ、空のみじんにちらばれ"というその言葉は真壁茂夫の演出論ととも舞台のクライマックスの場面となる。宮沢が感じ取っていた生きる根拠、例えば彼がセクシャルマイナリティであることを通じて、さらには異端を排除する日本社会の問題が描きだされる。これが「『核』からの視点」(れんが書房新社、2010)などで語られてきた、個人の「核」をその演出論で重視する真壁茂夫の問題意識と通じる点だ。
真壁は宮沢賢治が圧倒的に孤独を抱えており生きるための「隠れ蓑」をしていたと考察する。そして近年、日本で紹介され話題となった賢治がセクシャルマイナリティであることを示す資料を用いながら賢治にとっての「核」について問いかけがなされる。やがて“わたくしという現象は 仮定された有機交流伝統の ひとつの青い照明です”という言葉で序文が始まる詩集「春と修羅」を用いて、特に妹への感情とされる「永訣の朝」の下りが取り上げられていく。"修羅"(ケダモノ)としての生きる事が描かれ、その意識はメディア・パフォーマンスを交えながら作中のパフォ―マティヴな身体に描かれる。
宮沢賢治にとっての生きる根拠の問題は、出演者一人一人の生きる根拠にも連なることが示される。中でも車いすで登場する障がい者演劇の野澤健が舞台全体に強度を与えている。彼の存在に対して、教師は異端としてより一般性であれと野澤を何度も力強く殴り顔面が赤くなる場面も登場する。
ダンスの場面では柴田恵美が一列に並ぶ椅子と共に、決してムーヴメントとして完成することない同じシークエンスを反復していく。作品「傾斜 -Heaven&Hell」(2020)から躍進を重ねている柴田の振付言語は意味解釈や演出との歩みよりを拒否するような解読不能な文字だ。異端に憧れピエール・クロソウスキーに挑んだ現代舞踊出身の黒沢美香は逆に異端であろうとする姿勢がみえそれが裏目にでることもあった。柴田の作らず客に媚びないその清純派の眼差しはまぶしい限りだ。日本の歴史や伝統との対峙に妙にこだわることなく、しっかりとピュアに自分の思考と身体をこの作品の中へ残そうとしている。
作品のラストには観客にリラックスを勧めるシーンが織り込まれている。同一性を強要するような日本社会の全体主義的な狂気に催眠や教育への懐疑といった面からも踏み込んでいる。作品に登場する映像は宗方勝が手掛けていると考えられる。今野勉の細部を描くテレビ・ドキュメンタリーならではの映像詩の表現と異なり、パフォ―マティブに身体から現代を描こうとしている。
 © 大洞博靖
© 大洞博靖 宮沢賢治をテーマにした作品は近年舞踊界で上演されている。コンテンポラリーダンスの勅使川原三郎もそんな一人だ。勅使川原は長年自分が読み込んでいた宮沢賢治の作品とその解釈からこの文学者の世界や作品をダンス化している。
一方、この作品は若いころからずっと賢治の作品に対して距離を置いていた真壁は演出家・プロデューサー・脚本家で テレビ論の今野勉が演出を手掛けたドキュメンタリー「映像詩 宮沢賢治 銀河への旅~慟哭の愛と祈り~」(2021)や著作「宮沢賢治の真実-修羅を生きた詩人-」(新潮社、2017)と出会う。今野は森鷗外の「舞姫」のモデルとされる美少女エリスの実像に挑んだ「鷗外の恋人:百二十年後の真実」(日本放送出版協会、2010)のような著作があり、資料を駆使した構成をする。日本のテレビ文化を代表する才能の一人だ。書簡など具体的な資料に基づき、セクシャルマイナリティとしての側面に対する考察から賢治像を立ち上げてみせた。その面白さに気がついた真壁はこの作品と取り組んだ。
 © 丸山雄二
© 丸山雄二 真壁は演劇を身体でとらえるとも考えている。その姿勢がダンス界との接点にもつながり、演劇のみならずダンス・フェスティバルを長年開催することへとつながってきた。彼が率いるパフォーマンス集団OM-2は首都圏で活動し、長くいろいろな観客がその仕事をみてきた。
私は真壁についてモレキュラ―・シアターの豊島重之とある面で全く逆であるように感じている。豊島はパフォーマンスとモダンダンスを通じた前衛劇から青森・八戸で活躍し、賢治を作品のイメージに用いることもあった。彼は地方で政治的に立ち回ることで独自の場を構築してみせたが、周囲を権威でかためたが、その後年の活動は限られた関係者しかみとどけていなく、活動の全貌を80年代から長く見てきた人物の評はほぼいない。一見、独自な地平を形成したとはいえるが、後年の彼の作品が本当に独創的かというと、20世紀末の彼らの作風で止まっていたような部分もある。
一方、OM-2の作品は様々な人が接してきており、ポストドラマ演劇のカラーを色濃く持ちながらも柔軟に新時代を吸収しようとしている。さらに障がい者演劇やメディアアートとの接点を考えるbug-depayseのような活動もはじまっている。
真壁はアングラ世代の演劇については、結果としてそれ以前の演劇人と同じようなことに陥ったり、単に経済的に優位であるだけになってしまったと指摘をしている。この姿勢は日本のダンス界にあてはめることも可能だろう。舞踏やコンテンポラリーダンスもすっかり「日本」化し、彼らが長年否定をしてきた洋舞界の大系列を中心とする体制のようになり、中身も空洞化してきている。ダンスでも演劇でも自分の原点に返りながら権力と距離を取りことで、さらなる新しい方向性を歩みと表現をどのようにみせるかが問われている。2020年代は舞踏もコンテンポラリーダンスも歴史的な重々しい概念で、新しいまだ呼び名のわからないような表現が重要となる。2021年にd-倉庫は惜しまれながら閉館となったが、その後の真壁の歩みと「日本」によりかかららない独自な方向性が楽しみだ。
(2022年3月17日、日暮里SUNNY HALL)
著者プロフィール: 吉田悠樹彦(よしだ・ゆきひこ)/ダンス批評家
舞台芸術ではバレエ・ダンスからパフォーマンスに至るまで身体表現に関して評論活動を展開する。舞踊ジャンルではコンクールの審査や芸能賞の選考に携わる。
メディア芸術ではレニ・リーフェンシュタール論を新しい科学と芸術のジャーナル『Technoetic Arts』(ロイ・アスコット編)に発表しPrix Ars Electronicaデジタル・コミュニティ部門国際アドバイザー(2005-2009)を務めた。映像ジャンルでは東京ドキュメンタリー映画祭やドキュメンタリーカルチャーマガジンneoneoで活動する。
共編著のneoneo叢書「ジョナス・メカス論集」(2020)「アニエス・ヴァルダ論集」(2021)、Routledge Companion to Butoh Performance(2019)、20世紀舞踊研究会編「修訂版・20世紀舞踊」(2021)他 著作多数。
INDEXに戻る