 |
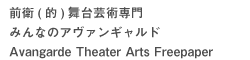 |
前衛芸術のあとにやってくるもの── d-倉庫 閉館に寄せて
北里義之
(舞踊・音楽批評)
その真理とは、人びとによってはじめられ演じられたすべての物語がその本当の意味を明らかにするのは、ようやくそれが終るときであって、行為者ではなく観客だけが、行為と出来事の或る連鎖のなかに実際に起こったことを理解できるように思われるということである。
── ハンナ・アーレント『革命について』
── ハンナ・アーレント『革命について』
私が意識的にダンス公演を観るようになったのはここ10年ばかりのことで、ごくごく近々の出来事に属します。音楽批評はしてきたものの、ダンス批評についてはなにをどうすることなのかについて見当もつかず、ダンスの書籍や記事を読みあさる一方、ステージが腑に落ちるようになるまで現場をできるだけ多く観てまわるという作業をはじめました。最初の数年間は、ライヴハウスや画廊でおこなわれている演奏家とダンサーの即興セッションが中心でした。ダンス誌の記事にも舞踊評論にもけっして登場することのない日常生活とシアターアーツの中間に茫漠と広がるダンスの領域。ダンスを観はじめた当初から、コンテンポラリーダンスはとうに最盛期を過ぎ、いまや衰退しているという話をよく耳にしましたが、新参者の私には、こんなにたくさんのダンスが日々踊られているのに、関係者はいったいどこをどうとらえて衰退というのだろうと不思議でなりませんでした。コンテンポラリーダンスをその誕生期に同時代体験していないせいか、過去の文献をいくら読んでも「衰退」の意味がわからず、トヨタやキリンビールのような企業がスポンサーを降りたり、助成金が取りにくくなったことなどからくる危機感の発露ではないかと思ったりしました。生活の苦しさがダンス活動の足腰を弱くするということは事実としてあるでしょうが。
 あらためてふりかえってみれば、本格的にホール公演に通うようになった時期に知った日暮里d-倉庫の存在は、私にとって、ダンス批評の入口を開いてくれる技能実習校のようなものであり、ダンスフェスティバルの主催を通して、小劇場が公共空間であることを内側から体験させてくれる貴重な場所だったと思います。d-倉庫の観劇歴は、「ダンスがみたい!vol.15:そろそろ、ソロ?」(2013年8月)で川口隆夫『大野一雄について』(2013年8月)を観たのが最初ですが、一般的なダンスシーンの知識に乏しいことが災いして、このとき同時開催された他の公演は観ていません。川口隆夫さんに注目していたための抜き打ち観劇でした。プログラムの全体構成を意識しはじめたのは、翌年夏の「ダンスがみたい!vol.16:新人シリーズ受賞者の現在地」(2014年7月)からで、その翌2015年におこなわれた「ダンスがみたい!新人シリーズ13」は通しで拝見しています。おそらくこのことが機縁となり、日暮里に移転してくる以前から小屋とかかわってこられた批評家/編集者の志賀信夫さんの推薦で、2016年度、2017年度の「ダンスがみたい!新人シリーズ」の審査員を拝命しました。30以上にも昇るエントリー作品から新人賞の1作品を選ぶ作業は、ダンサーにも審査員にも過酷なものだったと思います。受賞者に金一封は出ないものの、継続して公演機会が提供されるという特典は、ダンサーとの長期間にわたる関係性の構築をめざしたものであり、ダンス、演劇の領域における公共空間の創設というミッションを担うものだったと思います。新人シリーズ最終日に設けられた長時間にわたる講評会や、共通テーマとして出された戯曲作品やテクストを複数の劇団(およびダンスカンパニー)が独自の解釈で演出する「現代劇作家シリーズ」における演出家シンポジウムなども、舞踊評、劇評をフィーチャーしつつおこなう言葉の育成というより、そのものズバリ、多種多様な人々が集って言葉を交換しあう公共空間の創設そのものだったといえるでしょう。
あらためてふりかえってみれば、本格的にホール公演に通うようになった時期に知った日暮里d-倉庫の存在は、私にとって、ダンス批評の入口を開いてくれる技能実習校のようなものであり、ダンスフェスティバルの主催を通して、小劇場が公共空間であることを内側から体験させてくれる貴重な場所だったと思います。d-倉庫の観劇歴は、「ダンスがみたい!vol.15:そろそろ、ソロ?」(2013年8月)で川口隆夫『大野一雄について』(2013年8月)を観たのが最初ですが、一般的なダンスシーンの知識に乏しいことが災いして、このとき同時開催された他の公演は観ていません。川口隆夫さんに注目していたための抜き打ち観劇でした。プログラムの全体構成を意識しはじめたのは、翌年夏の「ダンスがみたい!vol.16:新人シリーズ受賞者の現在地」(2014年7月)からで、その翌2015年におこなわれた「ダンスがみたい!新人シリーズ13」は通しで拝見しています。おそらくこのことが機縁となり、日暮里に移転してくる以前から小屋とかかわってこられた批評家/編集者の志賀信夫さんの推薦で、2016年度、2017年度の「ダンスがみたい!新人シリーズ」の審査員を拝命しました。30以上にも昇るエントリー作品から新人賞の1作品を選ぶ作業は、ダンサーにも審査員にも過酷なものだったと思います。受賞者に金一封は出ないものの、継続して公演機会が提供されるという特典は、ダンサーとの長期間にわたる関係性の構築をめざしたものであり、ダンス、演劇の領域における公共空間の創設というミッションを担うものだったと思います。新人シリーズ最終日に設けられた長時間にわたる講評会や、共通テーマとして出された戯曲作品やテクストを複数の劇団(およびダンスカンパニー)が独自の解釈で演出する「現代劇作家シリーズ」における演出家シンポジウムなども、舞踊評、劇評をフィーチャーしつつおこなう言葉の育成というより、そのものズバリ、多種多様な人々が集って言葉を交換しあう公共空間の創設そのものだったといえるでしょう。
 講評会は多くの参加ダンサーを前に、3人の審査員がほぼ全作品について講評するという類例のないスタイルでおこなわれ、本公演で多種多様なダンスを踊ってきたダンサーたちの身体につなげて、通常ならばテクストのうしろに隠れている批評家の身体がステージにあらわれる機会になっていました。授賞式で審査員が登壇するのは一般的なことですが、大学の授業や講演会のような一方通行の関係性をはずれた場所で、講評という批評作業をライヴでおこなうという、いわば言葉が身体化される現場を見せるというのは、やはり稀なことであろうと思います。演劇フェスでの演出家シンポジウムともあわせ、ハンナ・アーレントがいうような意味で、このことは劇場とはアートに特化したひとつの政治的な場であるという、d-倉庫における公共空間の性格を特徴づけていると思います。改憲論議が戦わされるなかの「日本国憲法」特集や、コロナ禍でのカミュ『ペスト』特集──緊急事態宣言が解けずに中止──などは、そのことが直截的にあらわれた事例と思います。
講評会は多くの参加ダンサーを前に、3人の審査員がほぼ全作品について講評するという類例のないスタイルでおこなわれ、本公演で多種多様なダンスを踊ってきたダンサーたちの身体につなげて、通常ならばテクストのうしろに隠れている批評家の身体がステージにあらわれる機会になっていました。授賞式で審査員が登壇するのは一般的なことですが、大学の授業や講演会のような一方通行の関係性をはずれた場所で、講評という批評作業をライヴでおこなうという、いわば言葉が身体化される現場を見せるというのは、やはり稀なことであろうと思います。演劇フェスでの演出家シンポジウムともあわせ、ハンナ・アーレントがいうような意味で、このことは劇場とはアートに特化したひとつの政治的な場であるという、d-倉庫における公共空間の性格を特徴づけていると思います。改憲論議が戦わされるなかの「日本国憲法」特集や、コロナ禍でのカミュ『ペスト』特集──緊急事態宣言が解けずに中止──などは、そのことが直截的にあらわれた事例と思います。
作品講評にあたって興味深かったのは、講評会に臨む審査員が、予想を裏切るような作品の出現によって驚きたいという思いや、一般的なダンスのイメージや習い覚えたテクニックに疑いを持つ姿勢など、感覚に訴えるような“審査基準”を明示したことでした。これはコンテでも舞踏でも今日のダンスがスタイルの多様性に解体している現状に対応したものと思われますが、先に述べたような事情から、審査員であるにもかかわらず、私にはそうした基準はなにもありませんでした。それでも選考会のなかで審査員がそれぞれに候補作をあげていくと、不思議に同じような作品があがってきたのは、ダンスを選択するにあたり、審査員もまた身体的な篩にかけながら言葉にできない領域でなにごとかを受け取っているということがあり、一種の共通感覚が働いているからではないかと想像します。ここにはひとつの希望を見出すことができます。
 ダンスについて本格的に書きはじめたのも同時期で、「動体証明」「極私的ダンス」を掲げて独自のスタイルを築いてきた深谷正子さんの推薦で、「深谷正子─深淵の身体思想」を特集した『ダンスワーク70号』(2015年6月)に参加したのがきっかけとなり、長谷川六編集長からレギュラー執筆陣に加わるよう要請されたのがひとつ。またよく足を運ぶようになっていた中野テルプシコールで、小屋を拠点に活動していた舞踏家・横滑ナナさんの推薦を受け、隔月刊行される『テルプシコール通信no.150』(2015年8月号)から、小屋の公演を中心にしたレポートを毎号掲載するようになりました。翌年には、d-倉庫のスタッフ金原知輝さんの声かけで、『artissue No.007』(2016年8月)に初めて劇評を寄稿しています。
ダンスについて本格的に書きはじめたのも同時期で、「動体証明」「極私的ダンス」を掲げて独自のスタイルを築いてきた深谷正子さんの推薦で、「深谷正子─深淵の身体思想」を特集した『ダンスワーク70号』(2015年6月)に参加したのがきっかけとなり、長谷川六編集長からレギュラー執筆陣に加わるよう要請されたのがひとつ。またよく足を運ぶようになっていた中野テルプシコールで、小屋を拠点に活動していた舞踏家・横滑ナナさんの推薦を受け、隔月刊行される『テルプシコール通信no.150』(2015年8月号)から、小屋の公演を中心にしたレポートを毎号掲載するようになりました。翌年には、d-倉庫のスタッフ金原知輝さんの声かけで、『artissue No.007』(2016年8月)に初めて劇評を寄稿しています。
コンテンポラリーダンスの解説にある「多様性」「なんでもあり」という特徴が、かならずしもダンサーたちの自由に結びつくものではなく、コンテ最盛期にあった社会的な関心が退潮していくなか、生活にも苦慮しながら、容易に方向性を見いだすことのできない解体的現状のなかに放り出され、かえって迷子になるようなダンス情況がすでにあり、いまもあるように思います。こうした情況を前にして、批評にとっても第一の躓きの石となっていた「多様性」や、この時点までに紡がれてきたダンス言説が支える「コンテンポラリーダンス」そのものの存在を疑うため、あるいはそのような疑いをさしはさむことでダンスそのものを根本から考えなおすため、「ダンスがみたい!新人シリーズ」を新人の登竜門としてではなく、ダンス界の全体があらわれる場として扱う方法をとりました。そうすることで「多様性」に枠をはめるといったらいいでしょうか。もちろんこれが仮設的全体であることは重々承知のうえで、新しい年を迎えるたびに新たな仮設的全体を加算することになります。そんなふうにいつまでたっても全体が仮設的であることが、ここでは「多様性」で思考が停止してしまうことの回避につながります。
こんなふうに考えたのは、個々のダンスをファクトとして記録していきながら、一方で全体を想像する(より積極的には「構想する」「構築する」)ことができなければ、現代ダンスへの批評基準を想像することもできないからですが、いまにしてみれば、この背後には、モダンダンス時代にはあり、コンテンポラリーダンス時代になって失われてしまった歴史的な視点を、ダンス批評に回復させるというテーマが横たわっていたことがわかります。換言すれば、コンテの大きな特徴として語られるもうひとつのキーワード「世界性」によって、グローバル時代の空間性のなかに分散する多様性として語られる現代ダンスに、ナショナリズムに絡みとられることなく伝統や記憶などの時間的な厚みを取り戻すこと。このような発想が芽生えたのには、「ダンスがみたい!新人シリーズ」が、他のダンス・コンペティションと違い、エントリーされる「新人」たちがなんの参加条件もない「自称新人」でよかったため、参加ダンサーに大きな年齢幅があったことも影響しているかもしれませんが、やはりなんといっても、劇場とはアートに特化したひとつの政治的な場であるという、前述したようなd-倉庫の場所性が、陰に陽に作用していたためと思います。
スタッフとの雑談のなかで、劇場の運営方針が話題にのぼることはあまりありませんでしたが、2007年に麻布die pratzeを引き払う際に書かれた真壁茂夫さんの「公共劇場への提言」が残されていて、ひとつの判断材料を提供してくれます。「実験的、前衛的な演劇やダンスを応援していく」「人気がなくとも先進的なものを主にラインナップ」というざっくりとした方針は、d-倉庫の運営にも脈々と受け継がれていました。「コンテンポラリーダンス」というよりも既成のダンスを超えていく力を持ったダンスを、また「ポストドラマ演劇」というよりも既成の演劇を超えていく力を持った演劇を求める姿勢は、「ダンスがみたい!」「現代劇作家」の両シリーズにも影を落としていて、日常性の罠に囚われた身体を揺さぶって、ふたつの領域を隔てる境界を乗り越えていくように、それぞれの方向から穴を掘り進めて脱領域的な境域を開き、そこでしか知ることのできない身体存在を獲得することがイメージされていたように思います。
 そのことはこれらのフェスティバルの“外側”に置かれたOM-2の公演──私がこれまで見ることができた公演は、『9/NINE』(2016年9月)、『ハムレットマシーン』(2018年3月)、『Opus No.10』(2019年2月)、OM-2×柴田恵美『傾斜』(2020年2月)の諸作品──に理念的な結実を見せていました。戯曲をリアライズして行為の意味を演劇化する演出というのではなく、ダンサーとアクターの別なく、ステージ上に出現する多様な身体群を平準化してしまうことなく、異質さを異質なままに饗宴させることを内容とする演劇。ステージ上の身体群とその行為を観客に理解させることをめざすのではなく、観客の視線の前に投げ出すような存在の演劇。ダンスでも演劇でもパフォーマンスでもあるOM-2の作品は、それらを部分として加算しただけでは正体をあらわすことはありません。それというのも、OM-2の公演が、舞台空間を身体が存在として立ちあらわれる場所として提示する公共空間=劇場そのものであり、ひとつの理念型として演出されているからだと思います。このことは、より多くの表現者に開放されたd-倉庫との関係で、より明瞭に位置づけられるのではないでしょうか。
そのことはこれらのフェスティバルの“外側”に置かれたOM-2の公演──私がこれまで見ることができた公演は、『9/NINE』(2016年9月)、『ハムレットマシーン』(2018年3月)、『Opus No.10』(2019年2月)、OM-2×柴田恵美『傾斜』(2020年2月)の諸作品──に理念的な結実を見せていました。戯曲をリアライズして行為の意味を演劇化する演出というのではなく、ダンサーとアクターの別なく、ステージ上に出現する多様な身体群を平準化してしまうことなく、異質さを異質なままに饗宴させることを内容とする演劇。ステージ上の身体群とその行為を観客に理解させることをめざすのではなく、観客の視線の前に投げ出すような存在の演劇。ダンスでも演劇でもパフォーマンスでもあるOM-2の作品は、それらを部分として加算しただけでは正体をあらわすことはありません。それというのも、OM-2の公演が、舞台空間を身体が存在として立ちあらわれる場所として提示する公共空間=劇場そのものであり、ひとつの理念型として演出されているからだと思います。このことは、より多くの表現者に開放されたd-倉庫との関係で、より明瞭に位置づけられるのではないでしょうか。
マルチチュードの世界を生きる無名のダンサーから数多の作品を世に送り出してきた実績のあるダンサーまで、たくさんの公演をプロデュースしてきたd-倉庫はすでに跡形もありませんが、建物の撤去とともに小屋が体現していた演劇・ダンスのミッションも終わりを告げたのでしょうか。国破れて山河あり的な感慨がわき起こらないのは、OM-2が健在であるからだけでなく、新人シリーズに登場したダンサーたちが地下茎のようにして根を縦横に張りめぐらせ、ふたたび舞台にその姿をあらわす機会を虎視眈々と狙っているからだと思います。d-倉庫の舞台を通過していったダンサー・演劇人がすべて沈黙でもしないかぎり、ここではじめられたものが終わることはけっしてないでしょう。そこから身体表出や芸術表現のまったく新たな段階が生まれてきたとき、前衛芸術のあとにやってくるものがステージにその姿をあらわしたとき、小屋のミッションはようやくその任を解かれることになるのだと思います。


作品講評にあたって興味深かったのは、講評会に臨む審査員が、予想を裏切るような作品の出現によって驚きたいという思いや、一般的なダンスのイメージや習い覚えたテクニックに疑いを持つ姿勢など、感覚に訴えるような“審査基準”を明示したことでした。これはコンテでも舞踏でも今日のダンスがスタイルの多様性に解体している現状に対応したものと思われますが、先に述べたような事情から、審査員であるにもかかわらず、私にはそうした基準はなにもありませんでした。それでも選考会のなかで審査員がそれぞれに候補作をあげていくと、不思議に同じような作品があがってきたのは、ダンスを選択するにあたり、審査員もまた身体的な篩にかけながら言葉にできない領域でなにごとかを受け取っているということがあり、一種の共通感覚が働いているからではないかと想像します。ここにはひとつの希望を見出すことができます。

コンテンポラリーダンスの解説にある「多様性」「なんでもあり」という特徴が、かならずしもダンサーたちの自由に結びつくものではなく、コンテ最盛期にあった社会的な関心が退潮していくなか、生活にも苦慮しながら、容易に方向性を見いだすことのできない解体的現状のなかに放り出され、かえって迷子になるようなダンス情況がすでにあり、いまもあるように思います。こうした情況を前にして、批評にとっても第一の躓きの石となっていた「多様性」や、この時点までに紡がれてきたダンス言説が支える「コンテンポラリーダンス」そのものの存在を疑うため、あるいはそのような疑いをさしはさむことでダンスそのものを根本から考えなおすため、「ダンスがみたい!新人シリーズ」を新人の登竜門としてではなく、ダンス界の全体があらわれる場として扱う方法をとりました。そうすることで「多様性」に枠をはめるといったらいいでしょうか。もちろんこれが仮設的全体であることは重々承知のうえで、新しい年を迎えるたびに新たな仮設的全体を加算することになります。そんなふうにいつまでたっても全体が仮設的であることが、ここでは「多様性」で思考が停止してしまうことの回避につながります。
こんなふうに考えたのは、個々のダンスをファクトとして記録していきながら、一方で全体を想像する(より積極的には「構想する」「構築する」)ことができなければ、現代ダンスへの批評基準を想像することもできないからですが、いまにしてみれば、この背後には、モダンダンス時代にはあり、コンテンポラリーダンス時代になって失われてしまった歴史的な視点を、ダンス批評に回復させるというテーマが横たわっていたことがわかります。換言すれば、コンテの大きな特徴として語られるもうひとつのキーワード「世界性」によって、グローバル時代の空間性のなかに分散する多様性として語られる現代ダンスに、ナショナリズムに絡みとられることなく伝統や記憶などの時間的な厚みを取り戻すこと。このような発想が芽生えたのには、「ダンスがみたい!新人シリーズ」が、他のダンス・コンペティションと違い、エントリーされる「新人」たちがなんの参加条件もない「自称新人」でよかったため、参加ダンサーに大きな年齢幅があったことも影響しているかもしれませんが、やはりなんといっても、劇場とはアートに特化したひとつの政治的な場であるという、前述したようなd-倉庫の場所性が、陰に陽に作用していたためと思います。
スタッフとの雑談のなかで、劇場の運営方針が話題にのぼることはあまりありませんでしたが、2007年に麻布die pratzeを引き払う際に書かれた真壁茂夫さんの「公共劇場への提言」が残されていて、ひとつの判断材料を提供してくれます。「実験的、前衛的な演劇やダンスを応援していく」「人気がなくとも先進的なものを主にラインナップ」というざっくりとした方針は、d-倉庫の運営にも脈々と受け継がれていました。「コンテンポラリーダンス」というよりも既成のダンスを超えていく力を持ったダンスを、また「ポストドラマ演劇」というよりも既成の演劇を超えていく力を持った演劇を求める姿勢は、「ダンスがみたい!」「現代劇作家」の両シリーズにも影を落としていて、日常性の罠に囚われた身体を揺さぶって、ふたつの領域を隔てる境界を乗り越えていくように、それぞれの方向から穴を掘り進めて脱領域的な境域を開き、そこでしか知ることのできない身体存在を獲得することがイメージされていたように思います。

マルチチュードの世界を生きる無名のダンサーから数多の作品を世に送り出してきた実績のあるダンサーまで、たくさんの公演をプロデュースしてきたd-倉庫はすでに跡形もありませんが、建物の撤去とともに小屋が体現していた演劇・ダンスのミッションも終わりを告げたのでしょうか。国破れて山河あり的な感慨がわき起こらないのは、OM-2が健在であるからだけでなく、新人シリーズに登場したダンサーたちが地下茎のようにして根を縦横に張りめぐらせ、ふたたび舞台にその姿をあらわす機会を虎視眈々と狙っているからだと思います。d-倉庫の舞台を通過していったダンサー・演劇人がすべて沈黙でもしないかぎり、ここではじめられたものが終わることはけっしてないでしょう。そこから身体表出や芸術表現のまったく新たな段階が生まれてきたとき、前衛芸術のあとにやってくるものがステージにその姿をあらわしたとき、小屋のミッションはようやくその任を解かれることになるのだと思います。
INDEXに戻る
